
なぜ、水を飲まないのか?
以前に経営幹部と対峙する際の話法について書いたので、今回は企業組織のマネージャー層(部長職位や課長職位を想定)に変革を働き掛ける際のアプローチについてまとめてみようと思う。
当然ながら、”職位”が異なるからアプローチを変えるわけではない。経営幹部は変革の「オーナー」となるのに対し、マネージャー層は変革の「実務者/実現者」となる、つまり果たす”役割”が異なっている。必達を期すチェンジ・エージェントとしては、異なる役割には、異なる相対の仕方を準備して臨みたい。
そして、これを「実務者/実現者」を動かす為のアプローチと位置付ければ、実はビジネスも越えて、幅広い場面で用いることが出来ると考える。
1.マネージャー VS コンサルタント
何度か書いているが、我々コンサルタントのミッションは依頼受けた組織の変革を実現することにある。分析もするし、立案もする、代行したり、同行したりもするが、全ては変革の為のプロセスであり、部分である。
従い、外部から企業組織に参画して、真のチェンジ・エージェント足らんと考えるなら、組織実務を司るミドルのマネージャー層は変革の本丸である。彼らの認識を変え、号令を変え、ユニットの行動を変えることは、支援目的そのものに当たるのだから。
しかしながら、実際には異分子たるチェンジ・エージェント(コンサルタント等)は、ミドルのマネージャー層から”目的を同じくする同士”というよりは、”無理を強いる走狗”と見られることの方がはるかに多い。少なくとも変革の序盤においては。
当該組織での経験や実際年齢そのものに差があり、実務に関しては軽んじて見られるという、仕方のない要因も無くはないが、多くの場合は(特に若い)コンサルタント側のアプローチミスに起因すると思っている。
2.犯しがちなアプローチミス
これはけして、変革推進の活動に限ったことではないが、”相手の認識も行動も変えられていない1on1ミーテイング”を幾つも観察すると、共通して①インタビュー型、②指示伝達型、③ボイスレコーダー(又はオウム)型とでも例えられる「悪手のパターン」を踏んでいる。以下に特徴をまとめる。
【インタビュー型】
こちらが一方的に情報収集を行うだけのもの。多くの場合、相手は特段に深く思考せず、既に持っている情報や認識を即答で返す。相手に「話したのだから、後はあなたが解決してくれるのでしょう」と思わせてしまい易い。
【指示伝達型】
スケジュールや決定事項、タスクを解説するだけのもの。「このように決まったので」「全社で動いていることですから」「社長(経営幹部)の指示だと思って下さい」等と話す傾向あり。期限を決めるときぐらいにしかオープン型の質問が用いられない。
【ボイスレコーダー(オウム)型】
こちらに、自身で考えた仮説が無く、定型質問を繰り出すだけのもの。「何が問題でしょうか?」「解決策は何でしょうか?」等といった浅いヒアリングが繰り返され、相手が反射的に回答した内容にも、「いいですね、いつまでに?」と飛び付き易い。
容易に想像できるが、このようなアプローチを、年齢も若く、当該組織での経験にも劣る若いコンサルタントが採れば炎上は必至となる。マネージャー層はコンサルタントとの接触に価値を感じなくなり、質問にも木で鼻を括ったような回答で返すばかりとなる。
こういう場合、往々にして更に酷い事態が始まる。コンサルタント側もやり返し始めるのだ。さすがに面と向かっては言わないが、プロジェクトルームに帰ってくる度に、「あのマネージャーは何もわかっていない、意識が低い」から始まり、「変化することを恐れているのだ、外部環境が見えていない」と聞いたような文句を並べ、最後は「抵抗勢力だ、変革に非情はつきもの、幹部に話して外れてもらおう」となる。偉そうに書くが、私自身もこの商売を始めた頃は似たようなものだった。
どうして、こうなってしまうのか? 曲がりなりにも、論理と真摯さで武装した優秀なビジネスパーソンが、斯様に稚拙な衝突を起こしてしまう理由は何であろうか? 私の考えは「なぜと問う訓練が圧倒的に不足しているから」である。より正確に言えば、「競争環境や業務プロセスの中に起こる事象へのなぜは繰り出せても、人間心理の中に起こる感情に対しては、コンサルタントは”なぜ?”と問い掛けないから」である。
3.なぜ水を飲まないのか?
この商売を始めた頃、ファームの先輩より「Desert man(砂漠男)」の話を教わった。こういうものだ。
「あなたは灼熱の砂漠を目の前にしている。刺すような陽が照り付ける広大な砂漠の真ん中には、衰弱し切った一人の男がやっとの思いで立っている。足はふらついており、肌は乾燥し切っており、生命の危険も迫る極度の脱水症状にあるように見える。そして、男の足元には、いっぱいの水をいれて蓋をされたガラス瓶が転がっている」
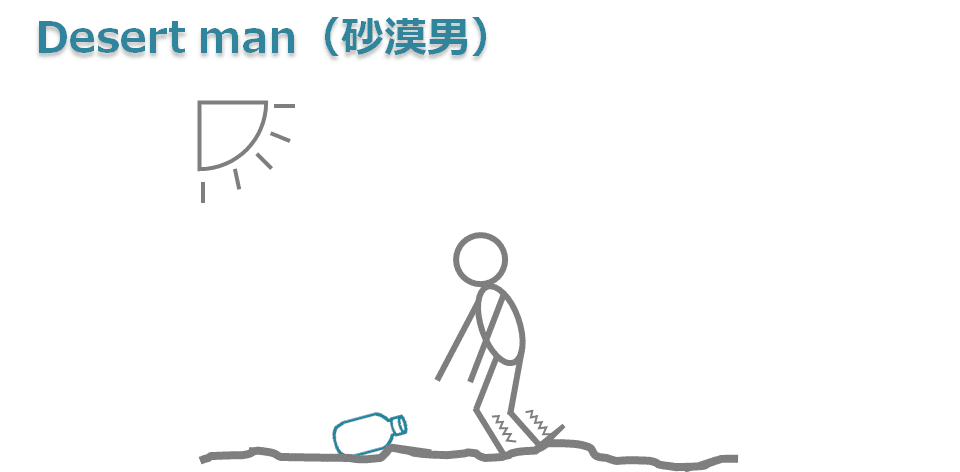
上図のようなイメージを思い浮かべたところで、先輩より質問される。「この男は、なぜ水を飲まないのだろうか? 考えられる理由を述べよ」と。
そう聞かれれば、考えられる”限り”の理由を挙げねばならないことは分かっている。必死で考え、ポストイットに書き出していく。こんな感じだ。
眼が不自由で瓶が見えていない/衰弱しており屈むことができない/自分が脱水症状だと気付いていない/陽に熱された瓶は熱くて触れない/入っているのは水ではなく毒だと思い込んでいる/どうせ、もう助からないと諦めてしまっている/瓶の中の水に高額な値段が付けられていることを知っている/落ちている物を拾ってはいけないという(宗教的?)戒律を守っている/etc.
荒唐無稽なものまで並べ挙げたところでペンを置き、先輩に手伝ってもらいながら分類していく。「Will not(意欲が無い)」と「Can not(能力が無い)」の軸を用いると、考えた全てが綺麗に整理されたように思えた。

そして先輩は、こう締めた。「どの理由が正解か、今はそれは分からない。けれども、水を飲まないのは”意識が低い”からじゃないよね。人が行動を取らないことには、全て理由があるよね」と。私もプロジェクトルームで声高に叫んでいたクチなので、これには恥じ入るばかりだった。
4.8種の「類型要因」
実際には、「Will not」と「Can not」には代表的な類型が4種ずつ存在しており、それぞれに解決アプローチを組み合わせて、下表の様に整理できる。

これは人間が行動を取ることに制約を掛けている代表的な8要因と言える。ビジネスの場で活用することを前提に、3つの要点を補足しておきたい。
先ず、「Will not」の方が発見は難しいということ。ビジネス現場の会話において意欲の不足を示す者はおらず、「~故に、やるべきではない」「他に優先させることがある」等のもっともらしい表現で表出するので、良く見極めることが求められる。
また、多くの場合「Will not」と「Can not」は合併症で発生するということ。例えば「懐疑」が「未熟」を併発して、マネージャー以下が身動きをとれなくなっていたりする。2つのみならず、3つ、4つの要因の合併症となっていることも少なくない。出来ない事実は意欲を低下させるし、意欲の無いところに技量向上はあり得ないと考えれば、これは納得できる。
それを踏まえて3つ目、どんなときも解決は「先ず”Can not”から」行うということ。つい発生した順序や、制約の強さで決めたくなる。しかし、”制約に縛られ苦しんでいる側”の立場にすれば、自責に向き合わねばならない”Will not”よりも、”Can not”の解決支援の方が圧倒的に有難く映る。先ず、相手を少し楽にするアプローチが、認識と行動の変化には近道となる。
5.人を動かす「5Step」
実際の変革プロジェクトにて、マネージャー層に対峙し相手を動かしていく際には、私は以下のような「5Step」でアプローチを設計している。

Step 1: この1on1ミーテイング終了時に、目の前のマネージャーと合意すべき行動は何かを明確にする。
Step 2: 前述の類型要因に基づいて、マネージャーの中で行動に制約を掛けているものを考える。「人が行動を取らないのには理由がある」。
Step 3: 此方が持つ「この行動を取るべき」という考えが正だとすれば、相手が制約を掛けていて行動を取れない状態とは、気付いていないもの/見えていないものが在るということになる。それを突き止める。
Step 4: 相手の”思い込み”を打ち破り、気付きを与える為の「事実(事例・実態・現物など)」を探し出し、用意する。
Step 5: 相手が気付きを得、制約が解けたことを確認する為には、どういう「発言(Verbal)」が出れば良いか、予め設計しておく。実際のミーテイングは、そのVerbalを指針として進めて行くことになる。
以上のような一連のミーティング準備は確かに時間を要する。どんな制約にとらわれているかの洞察には、そもそも絶対的な解が無いので、どこかで決めなければならない。更に、その制約を打ち破るだけのパワーあるFact収集も相応の手間が掛かる。
それでも、この一連の準備が、相手の認識を変え、行動を変え、組織の価値を高めていく仕掛けと考えれば、準備工数は充分に報われる。人を動かす技法の活用局面は無限であり、ここに熟達する価値も計り知れないと考える。
6.「砂漠男」の教え
「砂漠男」のフレームを教わったのは、この商売を始めてスグだったので、もう随分と昔になる。以来、実際のシーンで繰り返し使用して、要因をより詳細に区分したり、準備の為のアプローチStepを定めたりと、手を入れ整備していく過程で、私はこの思考パターンが慣れ親しんだあるものに似ていると考えるようになった。
「他者を動かす」「行動の理由」「相互の信頼関係」・・・・・・これらは、スタニスラフスキー・システムが教える演技術(行動分析のメソッド)とまるで同じものだ。
スタニスラフスキーは、どの場面においても俳優の「演技(Act)」には「目的(Aim)」がなければならない、どの場面においてもそれは、舞台上で相対する他者(他俳優)をどう行動させるかという非常に具体的なものでなければならない、この期待する行動を取らせることを「課題(Object)」と呼び、課題達成の為に他者(他俳優)の「動機(Inner Motive)」を考えねばならない、と著わしている。驚くほどに相似している。

ここで、スタニスラフスキーのメソッド誕生に至る背景に思いを馳せる。スタニスラフスキー登場以前の演劇シーンでは、他者(他俳優)を無視した独りよがりな演説や言い回し、他者をステロタイプに貶める画一的な演技が数多く見られたという。スタニスラフスキー・システムとは目の前の相手を固有の人格として認め、尊重し、交流するためのアプローチだと言える。
あの先輩も「砂漠男」を更なる先達から語り伝えられたと聞く。だとすればファームに連綿と伝えられるこの短い物語が教えようとするものは、要因の詳細分類よりも、準備のフレームよりも、「目の前に座る相手を、よく見て、認識し、尊重せよ」ということに尽きるのかもしれない。
稚拙な苛立ちを感じたら、たった1秒、「これはWill notか? Can notか?」と心の中で問いかけてみてはどうだろうか。目の前の人物に血を通わせ、理解に努めようとする姿勢を取らせてくれる、先達が遺してくれたマジック・クエスチョンかもしれないから。
---
斯様な考え方を、面白がって頂ければ嬉しくございます。よろしければTwitterもフォローをお願いします。
https://twitter.com/NagareKataru
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
