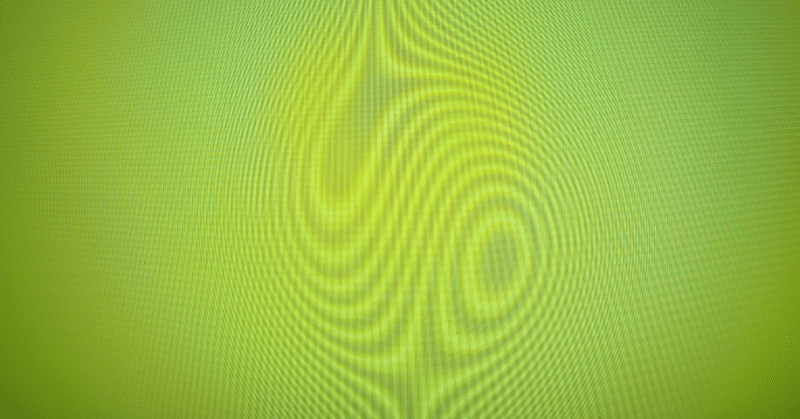
耳ヲ貸スベキ!――日本語ラップ批評の論点――
第二回 リズム/イズム 韻踏み夫
前回、宇多丸=佐々木士郎の日本語ラップ批評を、主に歴史的な観点から見た。「盗みの文化」から「“一人称”の文化」へ。宇多丸=佐々木士郎は日本語ラップの布置をそのように更新したのであった。今回の課題は、その理論的な射程をはかることである。宇多丸の問いの理論的な中心は、なぜかくも単独的であるようなヒップホップが同時に共同的でもあるのか、ということにあった。よって、一つ目の論点はオリジナリティである。いとうは前回引いた対談で、「盗み」から生まれるある種倒錯したオリジナリティということについて言っていた。宇多丸もまたオリジナリティについて考えたわけだが、その内実はいとう的なものとはまったく異なるものとなっている。第二の論点は共同性である。「一人称」は、他の「一人称」を次々と作り出すからこそ重要なのであった。いとうや近田に弱く、宇多丸に強く見られるのが共同性への思考であるように思われる。もちろんそれには、「ヒップホップ・ネーション」というような発想が盛んに言われた時代の宇多丸と、それ以前を活動したいとうとの世代的な相違があるだろうが、同時に共同性への志向はオリジナリティ概念の構成とも関わっていた問題である。
宇多丸にとってのオリジナリティは、RHYMESTER「B-BOYイズム」の有名なフックに示されている。「素晴らしきロクデナシたちに届く轟くベースの果てに/見た揺るぎない俺の美学/ナニモノにも媚びず己を磨く」。彼らは他とのコンペティション(注1)を行っている(「ナニモノにも~」)。それはヒップホップ的リズム/グルーヴのうえで試行錯誤することである(「ベース」)。その「果てに」、「ナニモノにも」比べられないオリジナリティ(「俺の美学」)が見出される。宇多丸のオリジナリティ概念はこのような構成になっている。同じことは、次のMummy-Dのフレーズのなかでも歌われている。
いかにも 俺がB-BOYのなかのB-BOY ただのB-BOY
自分が自分であることを誇る
ただ それだけ 命懸けで守る イビツに歪む俺イズムの
イビツこそが自らと気付く
奴らのカラー分かつこのプリズム 奴らに共通なこのリズム
まず歌われているのは「一人称」性の強調であり、二行目の知られたパンチラインはそれをもっともうまく説明するものとして引用されたKダブシャイン「ラストエンペラー」の一節である。次いで注目したいのは彼らのリズム論である(最終行)(注2)。ここに言われているのはつまり、あらゆる者が肌の色を越えて同一のリズムで踊ることができる場としてのヒップホップ・ネーションの賞揚、ということであろう。リズムによる共同性ということでは、あるいは、「リズム・ネーション」(ジャネット・ジャクソン)や「ワン・ネーション・アンダー・ア・グルーヴ」(ファンカデリック)のようなヴィジョンを想定していたのかもしれない。
つまり、ヒップホップ的リズム/グルーヴの上でなされる他との切磋琢磨において生成される「イビツ」な、差異化された「一人称」こそがオリジナリティであり、それは一見逆説的に思えるが実は、共同性の源泉でもある。ここでは、この宇多丸の問題設定を軸にしながら、しかしそれを一度思い切り外に開いてみたい。
詩人の佐藤雄一の連載「絶対的にHIP HOPであらねばならない」(『現代詩手帖』思潮社,2012~14年)は、いまだ最高の水準を示している日本語ラップ批評として知られているものであるが、それは宇多丸の批評を、さらに精緻に理論化しようとしたものだと位置付けられるように思われる。たとえば、次のような箇所を、前回引用した佐々木の文章と引き比べてみれば、ことは容易に把握されるだろう。Kダブシャインをはじめ、ヒップホップによく見られる特徴は、聞き手を「お前」と呼び引き込む「私信」のような「近しさ」の感触であるとしたうえで、書いている。
人はお前と名指しされたとたん、受け身な聴衆ではいられなくなります。笑いだすかもしれないし、また逆にアクティヴィストになるかもしれない。そこでは、聞き手が買うか買わないかというより当事者になるかならないかが問われます。その押し付けがましさゆえにその賭けは失敗する可能性も高い。しかし、それを受け取って変容した人間が一人でも、受け身なファンでなく、自ら発言しスタイルを作るマスターとなれば、そしてそのスタイルを受け取った誰かがまたマスターとなれば、そしてその連鎖が続けば、流れは確かになります。(注3)
ここから先は
【定期購読】文学+WEB版【全作読放題】
過去作読み放題。前衛的にして終末的な文学とその周辺の批評を毎月4本前後アップしています。文学に限らず批評・創作に関心のある稀有な皆さま、毎…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
