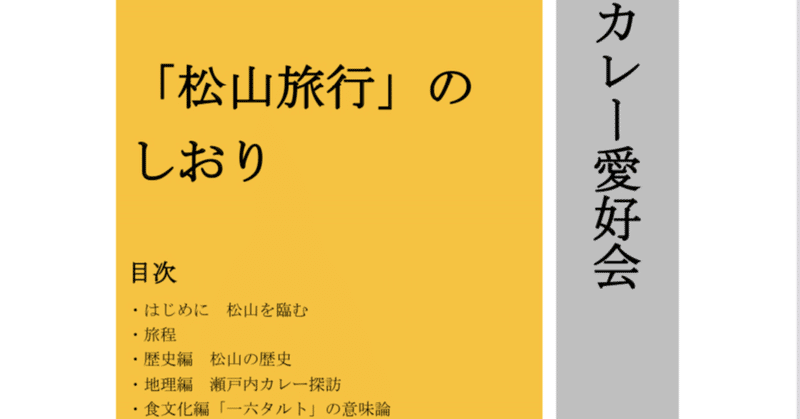
一六タルトはタルトか
この論考は2022年7月に行われた阪大カレー愛好会松山旅行における旅のしおり(食文化編)に掲載したものである。
一六タルトの意味論:「一六タルト」はタルトか
1 松山旅行と一六タルト
弊会の記念すべき松山旅行が令和4年7月16日に催行される意義は極めて大きい。
まず、令和4年の4。これは松山銘菓一六タルトと極めて縁が深い数字である。四を二乗すれば一六になるからだ。(何故二乗するのか,とは決して聞かないこと。)
次に7月の7。これもまた松山銘菓一六タルトと極めて縁深い数字である。一六タルトの一 と六を足せば、七になる。(間違っても,何故足すのかと聞いてはいけない。)
次に16日の16。理由は説明するまでもないだろう。
従って、令和4年7月16日は松山銘菓「一六タルト」の日である。異論の余地はない。
「一六タルト」(いちろくタルト)とは、カステラ生地で、ロールケーキのようにあんこを巻いた、 愛媛の伝統的な和菓子であり、松山土産の定番として多くの人に愛されている。このことに異 論は無い筈だ。しかし、この菓子が「タルト」を銘打っているという点ついては、幾つもの異論 が想定され得る。
カステラ生地にあんこを巻き、ロールケーキのような見た目であり、また、一般に和菓子に 分類されることの多い、その菓子は、明らかに我々が普段考える「タルト」と大きくかけ離れているからだ。
2 一六タルトはタルトか、その歴史
では、一六タルトはなぜ”タルト”と呼ばれているのだろうか。本稿はその背景について歴史 を紐解きたい。
一六タルトの発祥は、愛媛県松山市の「一六本舗」である。創業が明治 16 年だったため、一 六本舗と名がつき、一六タルトはその店名を冠したのである。
肝心の一六タルトが何故タルトと呼ばれるのかについては、一六本舗が創業するよりも前の、 江戸時代初期までさかのぼる。松山藩の藩主、松平定行公が、幕府の命をうけて長崎へ行った 際に、ポルトガル菓子の”タルト”に出会ったことが一六タルトの原型の、その始まりであると言われているからだ。
幕府より長崎探題職兼務の名をうけていた定行公は、正保 4 年(1647)ポルトガル船二隻 が入港したとの知らせで、急遽長崎に向かい、 海上警備にあたった。この時、定行公は南蛮菓 子タルトに接し、その味を賞でて、製法を松山に持ち帰ったのだと言われている。 その南蛮菓子タルトは、カステラの中にジャムが巻かれたものであり、現在の餡入りのタルトは、 定行公が独自に考案したものだと言うのが通説となっている。
3 一六タルトと語の歴史、その多義性
さて、定行公が長崎で耳にしたタルトは、オランダ語でケーキを意味する taart であったと いう説、ポルトガル語でロールケーキを意味する torta であったという説が提唱されている。
ただし、これらどちらか一つに決まる、あるいは、決めるべき問題ではないと言った方が良い というのが私の見解である。というのも、これらの語はすべて「焼き菓子」に相当するラテン語 の tōrta に由来するものだからである。従って、通時的には、taart も torta も同語である。 そしてそう考えるからには、定行公が長崎で耳にし、それを日本語の音韻で書き留めた「たると」も、通時的に見ればラテン語の tōrta に由来する同語たちの一角を成すものとして位置付 けられる。
さて、一六タルトが、我々が普段考える「タルト」とかけ離れていると言ったが、それは、我々 が普段、タルトと言って想定するものが、フランスにおけるケーキのような焼き菓子(tarte)の ことであるからだ。近年流行の洋菓子、タルト・タタン(tarte tatin)におけるタルトもまたフラ ンス語である。勿論、このフランス語のタルトもラテン語の tōrta に由来する。
またもう少し変わり種でいくと、バレンタインの時期に店頭に並ぶザッハトルテ(Sachertorte)。ザッハトルテはチョコレートケーキのことであるが、トルテ(torte)もまたラ テン語 tōrta を由来とするドイツ語である。
タルト、タルト・タタン、ザッハトルテ、一六タルト、普段、それぞれ別の語として扱われるこれ らを本稿ではラテン語の tōrta を由来とする同語であると一つ一つ捉え直しながら、概観してきた。
思えば、普通、一六タルトと所謂タルトの同質性が意識されることは極めて少ない。一六タル トは商品名であって、それ故固有名詞であって、構成要素をなすタルトそのものが独立に反省 的に捉え直される機会が殆ど無いからである。また、別の言い方をするのであれば、タルトの 持つ豊富な多義性が言語の別を超えて意識的に捉え直されることは、殆ど無いであろう。
本稿が確かめてきたように、ある一つ概念の多様な振る舞いを見ていく際には、それを通時的 に捉えていく営みが求められることがある。多義性とは歴史的変化の爪痕であった。
そして、タルトという語の歴史を辿ることでようやく、我々は定行公が長崎で聞いたという 「タルト」の音(ポルトガル語であったかオランダ語であったかはこの際どちらでも良い)を、ここ伊予松山に於いて聞くことができるのではないだろうか。
補遺:カレー愛好会松山合宿に寄せて
以下の文章は松山旅行のしおりの「あとがき」に寄稿したものである
*********************************************
去る 2021年12月末,大阪は中之島,旧ヤム邸(スパイスカレー屋),にてカレー愛好会の今後の活動計画に関する重要な会議 (兼 忘年会)が行われた。議題は「松山旅行」である。
松山は自分の行ったことのない場所に足を運ぶことに拘泥する弊会の旅行奉行(今回の合宿も旅程の計画と宿の予約を担当頂いた),T君の念願の地であった。また,松山旅行は, 2019 年 1 月に実施された学部卒業記念卒業旅行において,K君が部長になった際に昇進祝 いを兼ねて実施するものとして固く約束されていたものである。その約束がいつの間にか「(K君に限らず)誰かが部長になったら」と下方修正されていたわけだが,2021 年末の会議ではこの目標のさらなる下方修正が議題として挙げられたのだった。
これは,決して,弊会員の社会におけるうだつの上がらなさが招いた結果ではない(たぶん)。 おそらく,それぞれ同年代の平均的若者と同じくらいには,平均的に頑張っているはずであろう (たぶん)。しかし,社会人も 4年目にもなれば,わかってくるものである。
「部長になるのって,(なれたとしても)けっこう先じゃね......?」
変化の激しいこの時代において,それ程悠長なことは言ってはられない。 会議の結果「誰かがが部長になったら」という条件は「誰かが係長になったら」という条件にあっさり下方修正された。「課長になったら」がそもそも検討されていないことからも,松山旅行への我々の切実さがお分かりいただけるかと思う。
ただし一つ問題があった。私の務める組織に係長相当の役職が存在しないことである。そこで,私はかねてより取り組んできた現代語「係」助詞の研究に関する論文を公刊することをもって「係」長相当として頂けないか,と提案し,少々強引にその提案をメンバーに認めさせた。すでに,係助詞についての論を用意していた私は,目標の下方修正を受け,2022年3月末の某学会の論文受領締め切り日に向け,年明けより急ピッチで改稿を重ねた。 そして3月末に原稿を投稿,査読の結果「採用」の通知を頂き,晴れて係長相当に昇進。松山旅行が実現することとなったのである。
(私とS君により,2021 年度末まで継続的にPodcastにてレコーディングを行っていたカレーラジオの更新がここ半年間滞っているのは,実は論文の改稿,校正作業に追われていたからである。この点に関しては,本末転倒の極みであることを認め,ここにお詫び申し上げなければならない)
こうして,誰一人として,(いわゆる)係長になることがなく,我々は松山に赴くことになった。
それでよいのか?
と松山は我々に問いかけるだろう。下方修正を重ねてきた我々に対して, 松山を舞台とした小説『坂の上の雲』(あとがき)の次の一節は対照的である。(司馬遼太郎が明治時代の若者たちの精神性を比ゆ的に述べた名文である)。
のぼってゆく坂の上の青い天にもし一朶の雲がかがやいているとすれば,それをのみ見つ めながら坂をのぼってゆくであろう。
テレビドラマ「坂の上の雲」において,主人公の正岡子規,秋山好・真之の 3 人が松山城の坂 を駆け上がっていく映像と合わせて,この一節が読み上げられるシーンは印象深い。
青雲の志を忘れた(?)我々は,松山城の坂を上りながら,いったい何を思うであろうか。
試される地―伊予松山―において我々は,(明治の若者に思いを馳せつつ)次なる目標を策定する必要があるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
