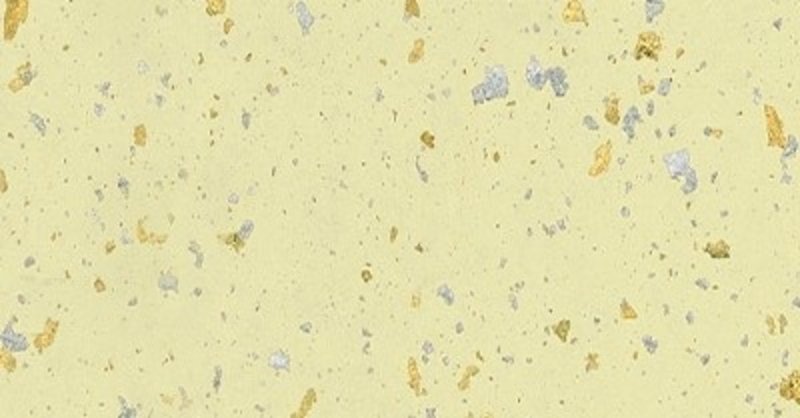
金扇
1-2
田中一村は、五十を超えてから、奄美に移住して、そこで南画に極彩色の花鳥風月を取り入れて、新しい日本画を産み出した画家である。しかし、無名で、染色工として働いて、六十九歳で果てた。
館内は人も疎らで、公武も、弓子も、それぞれ好きな絵の前に立って、眺めていた。公武は、静かに絵を見つめながら、その絵の色のあざやかさが心に迫って、震えるほどだった。このような、美しい不世出の絵を描いても、認められることもなく死んでいくのかと、そういう恐れだった。画家は、人生も後半に差し迫ると、狂う人が多いように思えた。それは、芸術全般に言えることかもしれないけれども、しかし、芸術に携わる公武には、人ごととは思えない。
ゴッホも、ゴヤも、みな狂って、田中一村も、まるでゴーギャンのように、社会から外れて、ただ絵の道を邁進したわけだが、狂いはあったのだろうか。早熟の天才で、七歳の頃から、神童の筆遣いで、『菊図』を描いていた。子供の描いた絵とは、信じられないほどに緻密で、大胆な絵である。絵の神が、彼の指先に纏ったのだろうか。
七歳の画家に妙なシンパシーを抱くことに、公武は、幼い頃から神童と、自身も呼ばれていたことも、関係があるように思えた。
バレエ・リュス、またはロシア・バレエ団の天才、ワツラフ・ニジンスキーの再来だと、そう騒がれたこともある。ニジンスキーは日本人と呼ばれるほどに、東洋の人のような、神秘のある顔立ちで、そういう天才に、自分を重ねられることは、公武の喜びであったけれども、しかし、ニジンスキーは、後年狂っている。精神に異常を来たし、長年のパートナーであった、タマーラ・カルサヴィナと、十数年ぶりに再会したとき、彼女を認知することができなかった。呆けた顔で立ち尽くす、ニジンスキーの写真がある。その横で立ち尽くすタマーラ・カルサヴィナの顔立ちも、どこか呆けている。
ニジンスキーが狂ったのは、バレエ・リュスのボスである、セルゲイ・ディアギレフとの恋と確執が最大の原因だとされているが、彼は、踊ることは神と交信することだと、自分は神に選ばれた者だと、そうも言っていた。自身を神の愛する者と信じて疑わない男は、ディアギレフとの恋のその前から、狂っているのかもしれない。
彼の心の深淵は、彼の手記で垣間見れるけれども、そういう、精神の異常を来すものが、彼の中には最初から宿っていたのかもしれない。
しかし、踊るうちに、公武自身も、ニジンスキーの語るように、恍惚とした喜びが心に浮かんで、自己を寵愛する神の御姿が、目ぶたを包むことがある。それは、公武とニジンスキーとをますます結びつけるようで、そうなると、自分もいつしか狂うときが訪れるのであろうかと、かすかな不安が萌したことがあった。
しかし、一村の描いた絵には、静謐さは感じられても、狂いはないように思えた。芸術家の野心は感じられても、破滅は感じられなかった。
「きれいな絵ね。」
そう言って、弓子は麦わら帽子を押さえながら、公武の隣に来た。館内で、冷房は効いていたけれども、夏の女の装いだった。外は灼熱の地獄である。黄色いワンピースからのぞく二の腕が、清流のように冷たい色である。
「鳥の絵が多いわ。反対に、海の絵は少ないのね。」
「奄美と言うと、晴れ晴れとしたイメージがあったけど、説明文に書いてあるね。年間二百日以上曇りに日だから、それが絵に影響を与えたんだろうと、書いてあるね。」
「沖縄には、一度だけ行った事がありますわ。公演があって、一週間。一日だけ観光が出来たの。首里城や、国際通りに行ったわ。美ら海水族館にも行ったわ。広くて、回りきれないくらいよ。でも、島は行ってないの。公演で、色々な国や場所に行ったけど、北海道はまだないの。」
「なんで北海道なの?」
「蝦夷鹿を見たでしょう。だから、思い出したのよ。」
弓子は、嬉しそうに、今まで訪れた県を指折り呟いて、公武は、それにひとつひとつ頷きながら、静かに絵を見つめ続けた。そうしているうちに、一村のコーナーが終わって、ガラス張りの廊下に出ると、二人をいくつものブロンズ像が待ち構えていた。佐藤忠良の作品で、全て少女たちである。
少女のブロンズ像たちも、夏の装いで、麦わら帽子を被る弓子と重なった。そして、その中のひとつに、金色の人魚がいた。人魚は、『mermaid』と題されていて、ブロンズ像の中で、一体だけ金色である。陽の光を浴びているかのように、黄金である。その黄金は、太腿は女の足のままで、艶めかしい厚みで、肉体の感覚がある。思わず見とれて、弓子が、
「人魚に恋をしているのね。」
「金色の人魚にね。まるで人間だね。」
「人魚姫ね。」
「アンデルセンのね。好きなの?」
「哀しいお話でしょう。人魚は最後には、泡になるでしょう。」
「そうだね。声も失って……。人魚を食べると不老長寿になるって。八百比丘尼って知っている?」
「手塚治虫の漫画で読んだわ。」
「永劫の時間を回転し続けるのなら、僕は不老長寿はごめんだね。」
「そうね。それなら、泡になった方がいいかもしれないわ。」
「『人魚の嘆き』という小説があってね。谷崎潤一郎の……。あらゆる放蕩を尽くした貴公子が、最後に辿り着くのが世にも美しい人魚なんだ。」
「人魚の話って、どの国にもあるわ。人魚はいるのかしら。」
「中国にはね、いそうに思える。木乃伊だって、あるだろう。」
「あれは猿と鮭をくっつけたのよ。ムンクみたいな顔して。」
「鬼の木乃伊も、妖精の木乃伊もある、妖精はいるのかな。」
「私なら妖精にも、人魚にもなれるわ。」
そう言うと、弓子はつま先立ちで、金色の人魚の前で、くるくると回って見せた。ちょうど、館内のガラスに陽が差し込んで、弓子も、白い足も金色のブロンズの輝きになった。人魚と重なるようで、重なりの線が次第に一つに交じって、金色の人魚が踊り出したようにも、公武には思えたものだ。
そうして、目の前の日まわりも、あの日の人魚の金色に重なるように見えるのは、色彩は、音や匂いと同じように、記憶を揺さぶるものだからだろうか。
しかし、泡になった方がいいと言う弓子が、花になることは、不思議なおかしみを公武に感じさせた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
