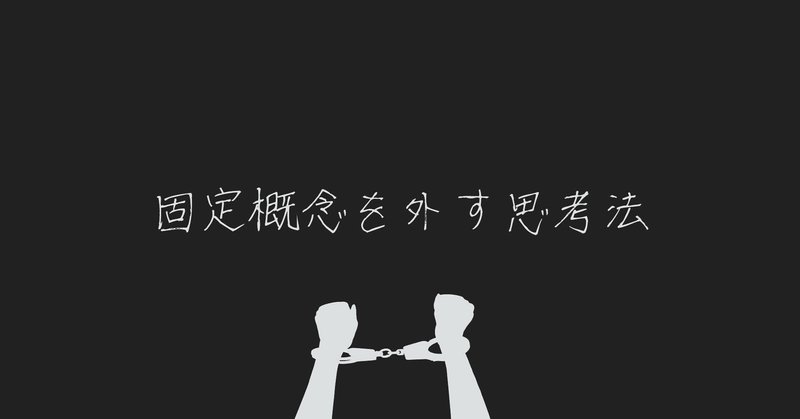
後付けのセンス
僕はみんなと同じ答えだった。
選択問題

学校や塾でこんな場面がよくある。
「この問題の答え、Aやと思った人?Bやと思った人?
手上げてない人は、わからないってことかな?」
「正解は、、」
みたいな場面。
こういう時、
「先生!それどっちも違うんじゃないですか?
答は32やから、選択肢の中に答えないと思います。」
と声を上げる生徒がいた。
あなたの周りにも一人はいたんじゃないだろうか。
僕は嫉妬していた。
アニメや漫画で、主人公だけ俯瞰してみている
あの感じを素でやってのける人が
かっこよく見えて仕方がなかった。
いや、違う、そうじゃない
それだけの理由なら
意見するだけでよかったはずだ。
多分僕は、
みんなと同じ意見が嫌だった。
一緒が嫌だ
僕はすぐ触発されて
人と同じものを好きになるタイプです。
人とすぐに仲良くなれる反面
自分だけの個性、
オリジナルがあまりありませんでした。
そのせいか、中学時代は特に
みんなと違う自分でありたいと
強く思っていました。
だからこそ、
ほとんど同じ意見が出そろう
質問や問題において、
人と同じ解答をするという事が
特に嫌いでした。
答えがない
だいぶそんな感情も薄れてきた
高校3年生の時、ある回答に出会います。
数3の授業でした。
長い記述を書いた後、
答えが出ないという証明に出会ったのです。
模範解答
解なし。
衝撃でした
解がない答えがあるのか。
”かっこいぃ”
それから気づいた僕は
意識して、
人と違う答え
普通じゃない回答を意識してきました。
3択目
アイデアでも、意見でも
普通じゃ無い回答を意識して2年
答えがないことが多い
社会に出ることが多くなり
だいぶ、意識することを忘れていた頃
TRYBEの仲間と参加していた
数十人が参加するビジネスセミナーで
2択の問題が出されました。
そして、いつもの場面です。
「この問題の答え、
1やと思った人?、、、
2やと思った人?、、、」
その時は、
”どっちもやろ”って思っていました。
片方に決めるのが気に食わないのもあったし、
意識高い系ビジネスマンの大勢と
一緒に手を挙げるのも嫌だった。
その他大勢の、
普通の回答が嫌だった
そう、
僕は手を上げませんでした。
”あぁ、答えどっちやねん”
下を向いて、面白くないなと
答を待っていました。
すると、司会者が唸って
「んーーー・・・
どちらもと思う人?」
忘れもしません
聞いた瞬間の衝撃ともに
飛び切りの笑顔で
小学生くらい元気いっぱいに手を挙げていました
しかも、嬉しそうにきょろきょろしながら(笑)
正解はどちらもでした。
ほんの数人が正解でした
うちの代表もあげていました。(さすが)
でもここで大事なのは、
ほんの数人の人は僕が昔、嫉妬していた存在だという事。
元から、本質的思考が得意なタイプだと思います。
でも。僕は?
全くもって違っていた。
僕はいつもみんなと同じ答えで、
誰かと一緒が普通でした。
センスもないし、鋭い指摘もできない。
ただの凡人でした。
実際に、その3択以降
そういった経験が増えました。
なるほど!その手があったか!
いいやんそれ!というセリフをよくもらいます。
普通じゃない回答を意識して、
あの時の憧れ、みんなと違う自分を
手に入れられた気がします。
最後に
よく、既存を疑えと言いますよね
常識をぶっ壊せとか、あれってだいぶ難しくないですか?
だって、まず既存のものって、
当たり前に溶け込んでるせいで
知覚する事自体大変です。
はなからそれをできる人が、
センスいいなとか、人と違うな、
かっこいいなって思う人です。
だから僕が言いたいのは、
とりあえず
提示されてるもの以外を探せという事です。
2択なら、3択目もしくは選ばないという選択肢を、
日常から意識し、習慣にして自分のものにする。
そうすることで段々、
僕が思う、センスあるかっこいい考え方
すなわち、常識を疑う考え方に近づいてきます。
最初は自信がないし、
第三の答えを思い浮かべるだけかもしれません。
でも、それでもやめない事、続ける事ができる人だけが
誰も見ていない答えを見つけることができるのかもしれません。
固定概念に縛られない思考
と
センスは後からつけられる
僕は自分だけの答を持っている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この記事がすごくいいなと思った人に
本を勧められるのが大っ嫌いな僕が
どうしても
絶対に読んで欲しい本があります。
試し読みで
見開き1ページでいいので読んでみて
もし、いいなと思ったら読んで欲しいです
明日明後日は
おそらく
ふぃるむ🌵さぼ10です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
