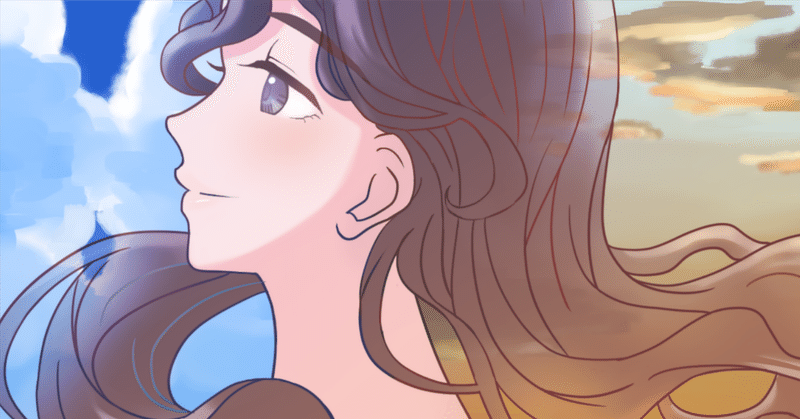
Photo by
kn0623
「そうかしら」と喋る人はいない
小説を書いていて悩むことがあります。そのひとつが、女性の会話文です。
女性の登場人物が話すときに「だわ」や「かしら」を文末につけたくなるときがあります。いわゆる「女性語」です。
原則、女性語をあまり使わないようにしています。だって、現代の女性は、そんな言葉遣いをしないですよね(少なくても、僕の周りの女性は使いません)。
リアリティを追求するなら実際の人が話さない会話文を小説内で使わない方が良い気がします。
だけど、どうしても「女性語」を使いたくなるときがあります。女性語ではない文末だとぶっきらぼうに感じ、男性が喋っている印象になる場合があります。
できるだけ「女性語」を使わなくてもすむように会話文を工夫しますが、それでも、どうしようもなく「女性語」を使う場合もあります。
「女性語」に限らず、「男性語」もあれば、「そうじゃ」みたいな「博士語」もあります。「役割語」と呼ばれるものです。
会話というのは、言葉だけで構成されていません。実際の発話にはイントネーションやアクセント、声質という要素が含まれます。人によって声質は違うし、話し方も異なります。それらの違いは文章では伝わりません。
だから、それらの要素を補うために「役割語」が必要なわけです。「役割語」は夏目漱石の頃からあるわけで、現代にも残っているのはそれだけ意味があることなのだと思いますが、書いていてやっぱりちょっと違和感があります。
だけど、役割語を排除し過ぎると、会話がぶっきらぼうになり、登場人物も冷たくて単調な人ばかりになってしまいがちです。
役割語は薬と同じで、用法・用量を守って正しく使うのが良いのでしょうね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
