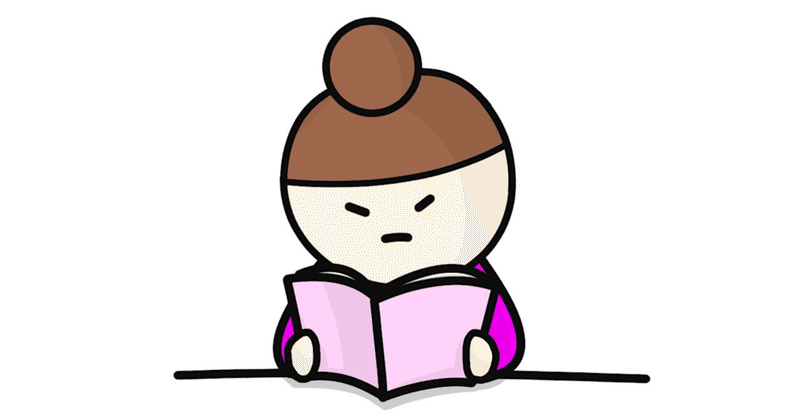
“ゆるーく生きていく系”の本が刺さらない 〜双極性障害だって働きたい 19
みなさん、こんにちは。
双極性障害2型+強迫性パーソナリティ障害のフツーの会社員、パピヨンです。
前回の記事の続き、やっと双極性障害2型の診断がつき、自分から病気について勉強し始めた頃を回顧します。
↓↓
人間ドックの問診、“改ざん”される
『双極性障害』の診断から半年後、年に一度の会社の人間ドックがありました。
問診票の「現在通院中の病気」の欄に、今までは『適応障害』と書いていましたが、その年初めて『双極性障害2型』と記入しました。
ところがいざ医師の問診の際、「精神科に通院中なんですね〜」と医師のほうから確認してきたにも関わらず、何も言わずにさらりとカルテに『適応障害』と書き直して打ち込まれました。
あれれ?
見間違えたのかな?と不思議に思いつつ、後日送られてきた検査結果を精神科の主治医に見せました。
『双極性障害』は軽くない
私は毎回必ず人間ドックの検査結果を主治医に見せています。
一時期激ヤセしていた点と、薬による腎機能の影響をチェックしてもらうためです。
その際、例の“問診票を書き換えられた話”をしてみました。
主治医は冷静に、
「あると思いますよ。『双極性障害』の方がずっと重いですから。会社に見られる可能性を考えて書き直したんでしょう。『双極性障害』は軽い病気では無いですから。」
がーん。
私はあくまで次々に診断名が変わっていった程度の認識で気軽に記入していましたが、どうやら事は私が思っているよりも重大なようでした。
しかも、(転職する場合)会社に見られたらマズい程度にヤバいらしい事を初めて認識したのです。
精神疾患の本を買い漁る
とりあえず、自分の病気にしっかり向き合い、精神疾患について真面目に勉強しようと思いました。
通院7年目にして、やっとです。
まずは精神科関係の本を買い漁りました。
ところが…
精神科の本のコーナーに行くと、
『スーッと心が軽くなる』
『頑張り過ぎてる人へ』
『ゆるーく生きていく』
この手の“優しい”言葉のタイトルがズラリ。
もっとイカつい『双極性障害のメカニズムと対策』みたいな、医学書を探していたのですが見当たらず。
仕方なく5冊ほど上記のゆるゆるタイトル系の本を買い込み読んでみました。
“ゆるーく生きる”が許せない
ここから先は、“歪みきった私見”とお許しください。
どの本も最終的に言いたい事は全て同じ。
突き詰めれば主治医の診察時の言葉の本質ともリンクしていました。
しかーし!
この、“スイーツみたいな”言葉の言い回しが、どうしても私には刺さらなかったのです。
『人と比べなくたっていい』
わかります。
しかし“生きていく”ことは常に比較の嵐です。
『もっと肩のチカラを抜いて』
わかってます。
しかし“働く”とは、常に戦場です。
女がひとりで戦って行くためには、チカラを抜いたら秒でヤラレます。
『自分を許してあげましょう』
周囲みんなのことは全然許せます。
しかし、“頑張ってないジブン”など、もはや処刑案件です。絶対に【脳内ジブン裁判】で私自身が許してくれません。
もはやこの本を途中放棄することを許して欲しい(笑)
無理だ…。
“ゆるく生きていけない”私には冒頭から難易度が高すぎる…。
DSM-5に辿り着く
呆然と本屋をふらふらと探していたら、医学生・看護学生向けのコーナーに『簡易版DSM-5』を見つけました。
『DSM-5』とは、アメリカ精神医学会が発行している精神疾患の診断・統計マニュアルです。
つまり、本当は“お医者さんが読む本”です。
「患者がこんなん読んでいいんかな?」とも思いましたが、本屋に売っている=誰でも読んでいいだろうという解釈により、購入してみることにしました。
これが実に面白い。
あらゆる精神疾患にナンバリングがされていて、疾患ごとに細かな診断基準が記されています。
私は自分とは関係ない疾患まで、がっつり全部読み込みました。
そうすると、「どういう基準で主治医が私を診察しているのか?」がうっすら分かってきました。
あくまで診断のガイドラインなので治療方法は載っていません。
しかし、わたしにはDSM-5の方が遥かに学びがありました。
本には向き不向きがある、らしい
一応「患者が読んでも良いものか」心配だったので、主治医に相談してみました。
「“ゆるゆる系”の本が全然刺さらなかったので、DSM-5読んでみました」と。
主治医いわく、「あの手の啓発本は、ハマる人と向いてない人がいるんですよね〜。勉強するの、良いと思いますよ。“ICD-10”(WHOが出している疾病分類)も面白いんじゃないですか?ネットで無料で見れますよ。英語ですけど翻訳に入れちゃえば大体読めますから」
と、楽しそうに教えてくれました。
以来、時々DSM-5や本やネットで勉強した専門用語を共通言語にして、主治医と病気の診察コミュニケーションを取ることもあります。
それにしても。
精神科の本って、なんで「スピリチュアル」や「宗教」の棚の隣なんですかね??
“偏見の一因”を感じちゃうのは考え過ぎかしら…?
続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
