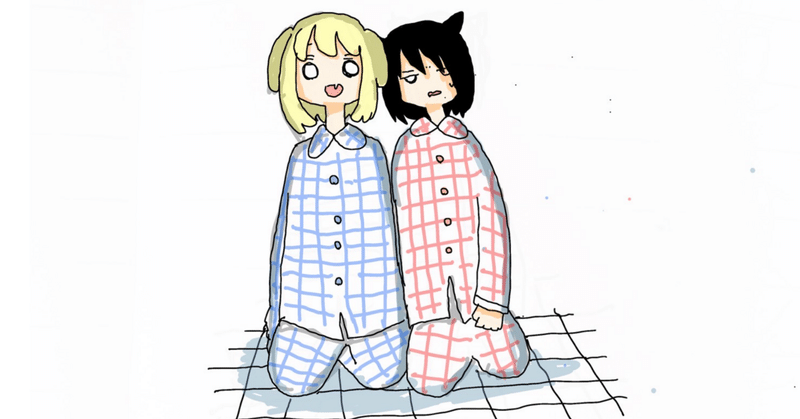
(雑談)良い匂いをたてて、湯気をあげながら皮を剥かれる権利
はじめに言うとこの文章に結論はない。雑談の代わりに書いている。なので雑談してくれる人募集中。
九段理恵の『東京同情塔』には「同情する権利」という概念が出てきた。作中の言葉で言うなら「軽い言葉」としてアイロニカルに使用されていたように思う。最近邦訳されたアミア・スリニヴァサンの本の題名は「セックスする権利」だったし、安楽死の法整備の記事では「死ぬ権利」という言葉が使われていた。
権利という言葉をくっつけて複合名詞にするだけで、いっきに否定しがたい概念に変身するのは面白い。
大江健三郎の『奇妙な仕事』という小説にはもっと刺激的な「権利」概念が出てくる。
「それに、毒を使うとね、死んだ犬が厭な匂いをたてるんだ。犬には良い匂いをたてて、湯気をあげながら皮を剥かれる権利があると思わないか。」
この文章はいろいろな意味で私にとってとても気になる文章だが、今は「権利」という語の強引な使用がすごい。「良い匂いをたてて、湯気をあげながら皮を剥かれる権利」そんなものがあってたまるかという気もするのだけど、「権利」とつけると少なくとも主張することだけはできるようになるらしい。
もともと大江健三郎という人は強引な複合名詞を作る名手(?)だと私は思っている。例えばこのすぐ後の文章にも「犬殺し文化」という言葉が出てくる。まるですでにあるものかのように単語を使うのは哲学者なんかにも見られる特徴で、「哲学とは概念を作ること」と言っていたのはドゥルーズだった。
デリダの『動物を追う、ゆえに私は(動物で)ある』という本に次のことが書いてあった。
「動物に、動物として実在すると言われる猫に、あなたは話すことができるが、猫は応答しない、本当には、けっして。」(太字は傍点)
犬がいったい「良い匂いをたてて、湯気をあげながら皮を剥かれる権利」を望んでいるかどうかは、話しかけることしかできない私たちには決して分からない。そして本来人間同士も実際には何を望んでいるのかは互いに謎なはずだ。そんな中で権利という不可侵領域を作ることはどういうことなのだろう。
「壁の向こうが見えたところでどうにもならないわ、と女学生がいった。
そうなんだ。そのどうにもならない、ということが僕にはやりきれない。どうにもならない立場にいて、しかも尾を振りながら餌を食べているんだ。」
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
