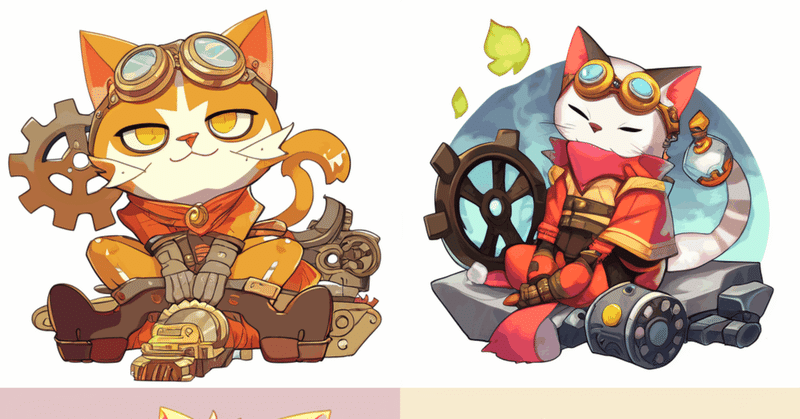
形態模写ならびに文体模写
話している相手の語彙や文構造や統語法や修辞、話題の幅や話題の「飛ばし方」、そして話すテンポの配分や声色などが際立って特徴的なものだと、話しているうちに本人の話し方を覚えてしまって真似できてしまうようになるという能力を幸か不幸か持ってしまっているのだが(本人の口調をそのまま真似して本人に話しかけたりして、顰蹙を買ってしまったことが何度もある。真似せずにはおれなくなるほど面白いのだけど、やはり人間関係を円滑にしようと思ったら本人の面前で真似をすることはなるべく控えるべきだということを、遅まきながらこの20年ばかりで学んだ)、もしかすれば文章についても同じようなことが起きてしまっているのだろう。
ここだけの話、修論を書いていた頃には吉田健一の文章にはまっていたこともあって、修論の本文においても知らぬ間に欧文直訳調のあーでもないこーでもないぐでんぐでんのどろんどろんという感じの文が炸裂してしまった箇所がそれなりにあって、主査を務めて下さった今は亡き某先生から大目玉を喰らってしまった。先生は梅棹忠夫ばりの文章を好まれていたのだが、残念ながらわたしは梅棹忠夫の「開き過ぎた」文体が死ぬほど嫌いで「キモい」とさえ思っていた上に、「分かりやすい」などという言葉を瞬殺してしまう晦渋で派手で饒舌な文体が昔から好みだったのだから、もうどうしようもない。もちろん論文では論旨ならびに文意も明快な文章を書く必要があるのだが、だからと言って修辞を完全に否定してしまったら書く側だけではなく読まされる側も気の毒なことになろう(残念なことに、提示されている情報は正確ではあっても、文章としては読みたくないという、学者による悲惨な文章は掃いて捨てるほどある)。というわけで、わたしは、論文などの文章であっても他人様にわざわざ時間と労力を割いて読んでいただく以上、適度に修辞に凝るべきだと考えている。
それはともかく、あの頃にはまっていた吉田健一ばりの酔っぱらった文体はおそらくカール・ダールハウスの文章を訳す時には大活躍してくれると思う(特に『19世紀の音楽』をあの文体で訳したら抱腹絶倒の名作として読めるようになると思う)。だが、今となってはダールハウスの著作を翻訳しようという気も失せた。だから、彼の文章を本気で訳したいという方がいらっしゃったら、吉田健一の文体をベースにした文体を作るべしというアイディアを喜んで譲ろうと思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
