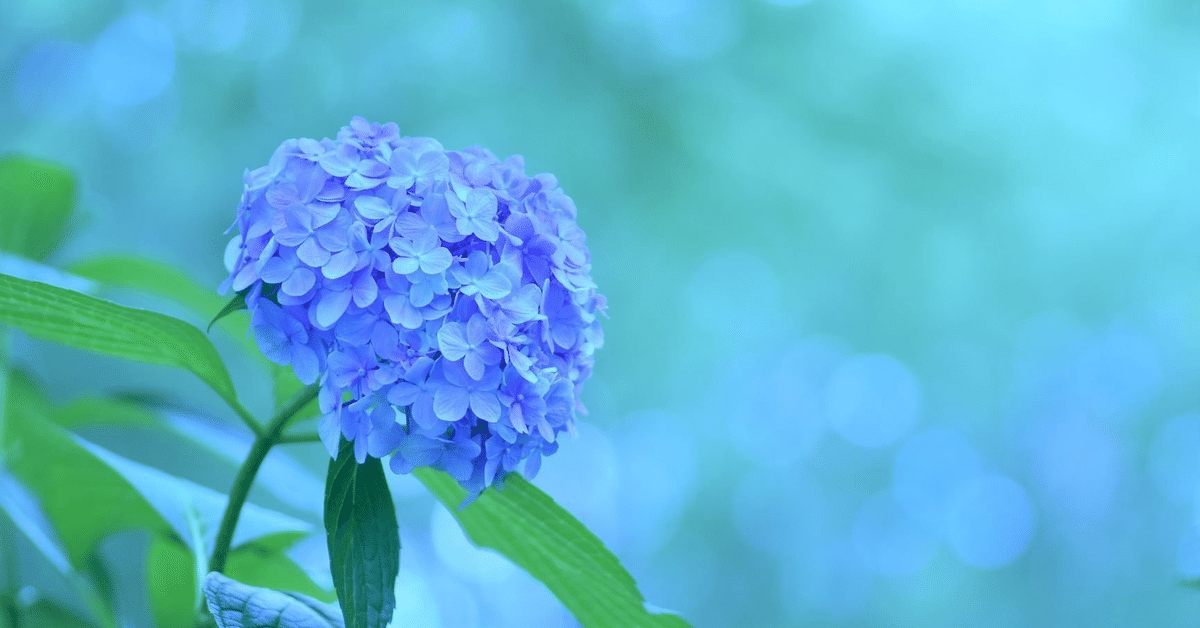
【ショートショート】紫陽花と底
連絡が来た日は気怠い午後の昼下がりだった。さっきまで握っていた手は、もう2度と触れる事ができなくなってしまった。言いたい事が何一つ言えないまま、私は赤子が泣く様に泣き喚き、友人に手を引かれて引き裂かれよる様に離れたのだった。まだ、初夏の暑さと春の涼しさが混在していた、なんとも言えない季節だった。
そこからの日々はうまく覚えていない。すぐに別の男で上書きを済ませてから、魂ごとあなたに持っていかれたように、ただただ時間を流すことしかできなかった。あなたからぽつり、ぽつりとくるメッセージはあまりに薄情で、ああ、ふっと息を吹き掛ければ消えてしまえる様な存在でしかなかったのだと、そこで初めて彼の中での自分の存在価値を知った。それは、あなたがくれた言葉全てを、まるで初恋をした少女の様に鵜呑みにしてしまっていた私にはあまりに残忍で、私はその日からパッタリと食事も喉を通らなくなった。
男に弄ばれる女なんて皆バカなんだ、と思っていた。自分だけは割り切れる事ができると思っていた。セックスの時にかけられる甘い言葉も、その後に撫でてくれる優しい手でさえも、一度も信用したことなんてなかった。むしろそれは寂しく思う事さえなく、夢中で貪るだけの期間限定の甘い蜜でしかなかった。誰一人として、無限に垂れてくる様に思える蜜の中に身を浸すことなんて一度もなかった。
でも、彼だけは違った。
私がバカにしていた女達も、きっとそうなんだろう。自分だけは、と思いながらも気がついたら蜜壺に閉じ込められ、這い上がろうとした時には蓋は閉められていて外に出られない。
壺から出られるのは彼がその蓋を開けたときだけだ。その時だけ、そっと息ができるのだ。食べ尽くした蜜が減った分だけ、また彼はそっと蜜を補充しては私を壺に押し込めるのだった。また罠だと思っていながら、自らも閉じ込められに、弱った羽を精一杯羽ばたかせては蜜がたっぷりと注がれた壺の奥底へと身を沈めるのだった。
そうやって、あなたの蜜で脳の芯まで溶けてしまった私に残されたのは、蜜だと思っていたものが実は毒薬で、目が覚めた時にはもう何もできない体だけだった。
もう蜜の入っていない底の深い壺の中で、開けられっぱなしになった蓋の外に降る雨を、そっと眺めることしかできないのだった。
今はただ、麻痺してしまった体で上手く呼吸ができるまで、じっとしているしかないのだ。狭い入り口から注がれるか細い雨を手のひらに受け、その苦い雫を啜るしかないのだ。紫陽花に滴る朝露を夢見て、真っ暗な底で、私は今日も眠る。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
