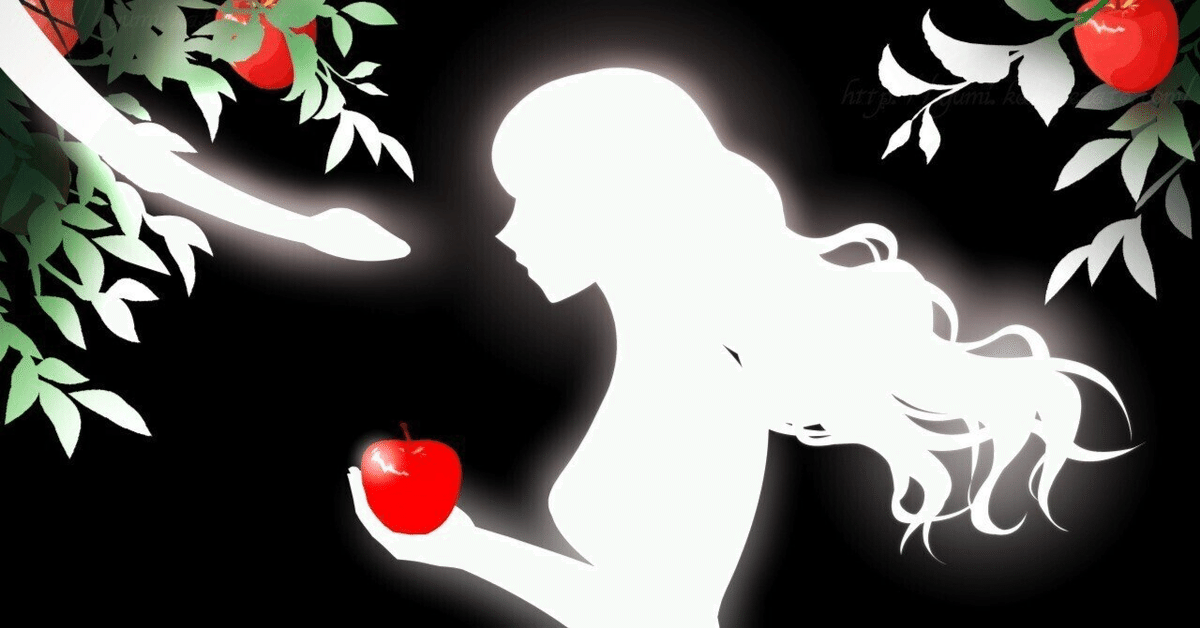
「神様のひとさじ」第十九話
「本当に行くの?足手纏いは嫌だよ」
朝が訪れ、コロニーの出入り口には、出て行く面々が集まった。
土竜と、キボコ、稲子、着いていくときかないバンビの四名が、先発組として移住する事になった。怪我が治り次第、あと六人が加わる。
「まぁ、アダム。そんな事も有ろうかと、ジャーン」
フクロウが、外に置かれている大きな布を引くと、バギーが二台現れた。
「何よ、コレ」
キボコが、足で蹴った。
「ちょ、大事に扱って!人類の遺産を、何とか復活させたんだよ。その後ろのソーラーパネルは特に脆いから、お触り禁止!」
フクロウは、腕を組んで自慢げに説明した。そして、この日のためにアゲハに作って貰ったという、黒いグローブを得意げにはめた。
「一台に三人まで乗れる。俺とフクロウで送っていく」
「僕とラブは、馬で行くよ」
アダムが、指笛を吹くと、山から白馬が現れた。
「アタシは、その機械に乗るわ」
「アタシも、ヘビと乗る!」
稲子が、ヘビの腕に抱きついた。ラブは、目を逸らし白馬に顔を寄せた。
「ちょっと離れて着いてきてね、馬が怖がるから」
ラブとアダムを乗せた白馬が、駆け出し、バギーがその後を追った。
一行は、荒野を抜け、林を慎重に進み、勾配のキツい山を走った。
道になれた馬の足は軽やかだが、バギーは苦戦した。
「おー、ちょっとエネルギーの低下で馬力落ちて来たなぁ」
フクロウは、バギーを停車させた。
森の中は、陰る場所も多く太陽光の充電は減る一方だ。
「アダム、目的地まであとどれくらいだ?」
「もう近いよ。歩いて三十分もしないかな?」
「そいじゃあ、歩いて行くか」
フクロウがバギーから降りて言った。
「そうだな」
ヘビも、エンジンを止めた。
「えー」
稲子は文句を言っているが、キボコに窘められ、渋々荷物を背負った。
持ち出すのは最低限の荷物にと言われたのに、彼女のリュックはパンパンで、入りきらなかった物を手提げに詰めて、ぶら下げている。
「じゃあ、僕たち先に行って、色々準備しているよ」
ラブは、自分の代わりにバンビか、怪我人の土竜が馬に乗ったらどうだろうかと考えたけれど、その発言の暇もなく、馬が駆け出した。
「さて、頑張って歩きますか」
フクロウは、手袋を取って、バギーのハンドルにつけると、いくぞぉ、明るく拳を上げた。その横では、バンビが冷ややかな視線を向けている。
「荷物を持つぞ」
ヘビがバンビに、手を差し出したが、叩き落とされた。
「ヘビ、私の荷物を持ってぇ、重いの」
稲子が甘えた声を出した。
「馬鹿言ってんじゃないわよ、さっさと歩きなさい」
「それにしても、静かだな」
土竜が辺りを見回した。
「そうだな。まだ一羽の鳥すら見ていない」
「車に驚いてるんじゃないの」
「何となく不気味だよね」
フクロウがニヤニヤ笑った。
ざわざわ、と木々の葉が音を立て、通り抜ける風が彼らの心を騒がせた。
何かに――見られている気がする。
「恐ろしい魔物の、掌の上だったりして……」
「おっさん!不吉な発言しないでよ!」
稲子が、荷物でフクロウの背を叩いた。
フクロウは笑いながら謝り、稲子の手提げを持ってあげた。
「行くぞ」
ヘビを先頭に、一行が歩き出した。
「なぁ、俺、トイレに行く」
バンビが声を上げ、皆が足を止めた。
「よし、じゃあ俺と土竜が待ってるぞ。ヘビたちは先に進んでくれ」
フクロウは、怪我をしている土竜を、少し休ませようと提案した。
アダムの言う通りならば、あと少しで目的地に着くはずだ。
土竜も頷いて、木の根に腰を下ろした。
「分かった」
ヘビ達が歩き出し、姿が見えなくなると、バンビが茂みに向かった。
「お、置いて行くなよ!」
「大丈夫、大丈夫。そうだ、聞こえるように歌ってようか?」
「いらねぇよ!」
フクロウは、走り去るバンビの背中を、微笑ましく眺めた。
「なぁ、土竜。この後、どんな悪い事を考えてるんだ?」
「何の話だ?」
「俺は、お前が大人しく外で暮らし始めるとも、砂掛けられたまま、コロニーの奴らを放っておくとも思えないんだなぁ」
フクロウは、コロニーを牛耳っていた時の土竜を覚えている。
彼は、とても楽しそうに住人を支配していた。
「考えすぎだ。俺も歳をとった。自然に囲まれ、自由に暮らしたいだけだ」
土竜は、相変わらず静かに語り、口元だけで笑った。
「あ、そう」
「楽しそうだな」
「そんなことないさ、考えなきゃならないこと一杯だし、人手も少なくなるし、困ったよぉ」
大袈裟に肩をすくめるフクロウを、土竜が探るように見ている。
「そうは、見えないが」
「大変だよ。まぁでも、楽しみもある。これから攻めてくる敵陣営に、どう対応して戦っていくか、戦闘か政治か?ワクワクする」
「お前が、此方に寝返って、俺と、外も中も支配する、そういう道はどうだ?」
「お断りだな。ヘビは敵に回したくないし、アダムは信用出来ないから関わりたくない」
「それは――」
会話の間に、小さな叫び声が聞こえた。二人は、バンビの向かった方へと走り出した。
「バンビ!大丈夫か?」
バンビは、直ぐに見つかった。
彼は、驚いた様子で立ち尽くしていた。
二人は彼の視線の先に目を向けた。
「…蛍」
土竜が、呟くと――女が振り返った。
女、バンビの母親が、彼らに向き合った。
「母さん!」
「おっ、おい!」
バンビが駆け出した。死んだはずの母親に向かって腕を広げ、ついには、抱きついた。
幻覚や、幽霊ではない。
「生きていたのか」
土竜も、彼女へと向かって歩きだした。
「母さん、生きてたの?どうして帰ってこなかったの?迷子だったの?」
バンビは、母親の胸から顔をあげて、矢継ぎ早に尋ねた。
「……」
しかし、彼女は何も答えず、困ったようにバンビを見下ろしている。
「よく似ている別人じゃないのか?だって、獣に首を噛みつかれたと聞いてるぞ」
フクロウが、彼女の首元を指さした。
牧歌的なワンピースにエプロン姿の彼女は、首元が晒されているが、傷一つ無い。
「母さんだよ!間違いないよ。ね、覚えてないの?俺だよ、バンビだよ」
ねぇ、母さん。とびきり優しく語りかけたバンビは、母の手を取った。
彼女の手は、酷く荒れていて――傷口から、藁が飛び出していた。
「か、母さん?どうしたの……手に、いっぱい棘が刺さって、ねぇ、フクロウ、診てあげてよ!」
彼女の手が、フクロウに向けられ、目にしたフクロウは、眉を顰め、腰の銃にそっと手を添えた。
「離れなさいよ!」
突然、響いたキボコの声に、バンビの母は、手を引き抜いて一歩下がった。
「やめろ、キボコ」
銃を構えたキボコが、彼らの方へ足を進めた。
「心配して戻ってみれば、なんでアンタが……死んだはずだろ」
キボコは、銃を下ろさない。数年ぶりに見た、憎い女だ。
唯一、自分の地位を脅かしていた、可哀想な女。
幸の薄い顔をして、誰にでも従順に優しく接する彼女は、男達に絶大な人気だった。
もちろん、土竜にも。
しかし、彼女が選んだ男は、優しいだけの男で、あっさり病で死んだ。
それからも、土竜の視線は、隣に居るキボコではなく、彼女に向けられていた。
やっと、邪魔者が消えたと思ったのに。
「やめてよ!」
バンビが、母を庇い、目の前で腕を広げた。
こんな状況であっても、彼女は心ここにあらず、動揺を見せない。
「ひとまず、落ち着け」
土竜が、キボコに手を伸ばした。しかし、キボコは、その手を避けて、体の位置をずらし発砲した。森の中に、銃声が響き渡った。
「母さん!」
すぐに振り返ったバンビは、言葉を失った。
彼の母は、右腕を撃たれ、風穴が空いていた。切り開かれた藁人形のように。
血は流れていない。
「ひいいい!」
撃ったキボコが、恐怖で尻餅をついた。
「か、母さん……」
彼女は、痛がる様子もなく、撃たれた箇所に手をやり、穴が開いた部分を元に戻すように、抓み解している。そして、治った腕を上げて、指を鳴らした。
すると、うなり声を上げて、茂みを掻き分け、獣が四頭現れた。
「う、うわああ」
「バンビ!」
叫び駆け出したバンビの声を号令に、現れた獣が走り出した。フクロウは、銃を取り出し、走りながら、バンビを追う獣を撃った。
「行くぞ」
土竜がキボコを助け起こし、銃を取り上げ、向かって来た獣を撃った。
「此処が……」
楽園に辿り付いたヘビたちは、言葉を失っていた。
自分たちが想像したよりも、遥かに規模の大きな村が出来ていたからだ。
自然の素材で作られたの家々が並び、手入れのされている畑が広がっている。
川から引き入れた生活用水路、真新しい水車、世話の行き届いた家畜たち。人類が、自然と共に生きていた頃、そのものの風景だ。
楽園の中心には、水路に囲まれ、島のようになった場所に、一際大きな木が生えている。そして、その後ろにも何本かの木が生えて、そちらは実を付けていた。
「すっごいじゃん」
稲子も圧倒され、口が開きっぱなしになっている。
「まぁ、何年もかけて、ラブの為に作ったからね」
アダムが、微笑んだ。稲子は面白く無さそうな顔をして、実のなる木へ向かって歩き出した。
「あの木にお前の実が?」
ヘビが、大きな木を指さした。今は一つも実を付けていないが、その雄大さと存在感に圧倒された。
「うん」
ラブは頷いた。
「そうか……中で育てるには、大き過ぎるな」
「え?」
「いいや、近づいても良いか?」
ヘビが、アダムに尋ねた。
「ぜひ、どうぞ」
アダムの手が、木に向かって広げられた。
稲子の足が、木が生える島への橋に差し掛かったとき、森の方から銃声が聞こえた。
「な、なに⁉」
稲子は、橋から戻り、ヘビの背に抱きついた。
「銃声だ」
「何か有ったのかな?」
ラブは、目の前に立ったアダムの背から顔を出して、森の方を見つめた。
バン、バン、と銃声が近づいてくる。
ヘビは、稲子を引き剥がし、三人の前に出て銃を構えた。
最初に現れたのは、バンビだった。
ヘビに気がつくと必死な形相でやって来た。
「何があった⁉」
「母さんが……獣が」
バンビは、酸欠に喘ぎながら、要領を得ない回答をした。
程なく、キボコとフクロウ、土竜の姿が見えた。
フクロウは、走りながら後ろを振り返り、獣を撃つ機会を窺っている。しかし、木々に阻まれ、斜面に足を取られ、そのタイミングは中々訪れない。
逃げる事が精一杯だった。
「ヘビ、悪い!」
フクロウは叫んだ。結局、最初に倒した一頭以外、数は減らせなかった。三頭の獣を、人里に引き入れてしまう。
一頭でも減らさなければ――フクロウは、歯を剥き出しにして笑い、きびすを返した。
敵を捉え、撃つ。
彼は、堪らなく興奮していた。
大口を開けて喰らいかかってくる獣を、食う。
彼の弾が、獣の体内を爆ぜる。真っ赤に染まる視界。彼の脳内に麻薬物質が大量に放出される。
来い、もっと殺ろう。
フクロウは、次なるターゲットを探すが、一頭はヘビに沈められていた。最後の獲物は森に引き返した。
「ちっ」
「舌打ちをするな」
近づいて来たヘビが、呆れたように言った。
この一見、平和主義者なフクロウは、本当は誰よりも武闘派だった。ヘビは、フクロウに付き合わされ、何度も戦闘訓練をさせられた。様々なシミュレーションの元、戦い、駒を進め気がついた。この男は、戦闘狂だと。
「もー、勘弁してよね。僕らの楽園が血みどろだよ」
「悪い、悪い。色々あってな」
フクロウが頭を掻いた。ラブは、顔色を失って俯いているキボコに寄り添った。
「キボコ、大丈夫?」
キボコは、ラブに視線を向けた。
「此処から逃げた方がいいわよ」
「どういうこと?」
「死んだはずの、バンビの母親が居たのよ!しかも、体が変だったのよ、何なのよ、アレ」
動揺が収まらない様子のキボコの背を、ラブがそっと撫でた。
「……それは、藁がつまった人間か?」
ヘビの問いかけに、キボコが頷いた。
「驢馬と同じだ」
「母さんは、どうなっちゃったの?」
「分からない。ただ、普通じゃない」
「あれは、何かの病か?治るのか?」
土竜を、キボコが睨み付けた。
「殺しなさいよ!驢馬と同じように!」
「やめて、母さんを殺さないで。あっ、思い出した。ねぇ、ラブ。あれが母さんが帰ってくるってこと⁉言ってたよね」
バンビに縋り付かれ、ラブは目を泳がせた。
(そういえば、私、そんな事言った。そうだ、何だっけ?)
知っているけど思い出せない。助けを求めるように、アダムを見上げた。
「偽物の人間は、死んだら生き返るんだよ。楽園の――」
「きゃああ!」
稲子の声が響き渡った。しかし、そこに居たはずの稲子が見当たらない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
