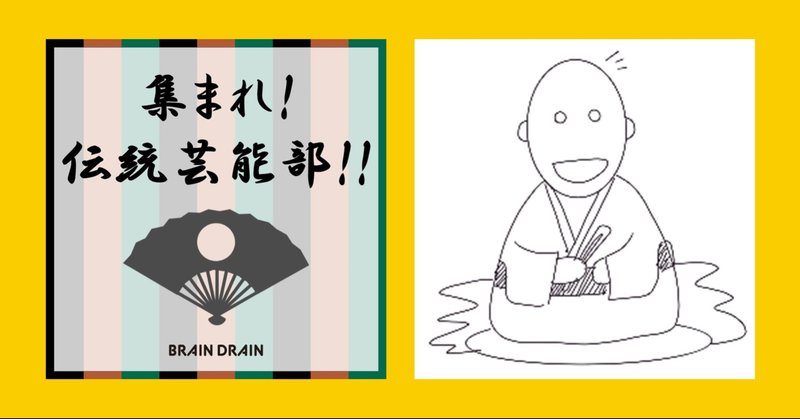
【Podcast書き起こし】落語の沼人:三浦さんに落語鑑賞の楽しみをきいてみた
最近、戦後最大のブーム到来とも言われている
「落語・講談」を中心に演芸全般に渡っていろんなお話をしていきます。落語にはまっていった人たちが語るディープな話を聴いて、
みなさんもこの広大で深淵な「落語・講談」の世界を覗いて見ませんか?そして好きな人同士の新たなコミュニティが生まれる場になるといいなと考えています!
【'20/10/9配信】
「落語の沼人:三浦さんに落語鑑賞の楽しみをきいてみた」より☟☟
【山下】実は三浦さんは私の落語のお師匠さんでもありまして、落語を何回も一緒に見に行って、いろんなことを教えてもらいました。今回大野さんも落語に興味があるということで、今度は大野さんから三浦さんに聞く番組をやってみようと、このPodcastを始めました。
【大野】よろしくお願いします。私は前から興味はあったんですけども、実際にまだ見に行ったことがなくて、どういうところから見に行けばいいのかなっていうのをちょっと教えていただきたくて。そもそも三浦さんは落語をいつ頃から楽しんでいらっしゃるんですか? きっかけとかを。
【三浦】落語っていうのは、子どもの頃から身近にあったなっていう記憶があって。というのは、落語って昔ラジオでずっとかかってたんですよ。NHKとかTBSとか。当時、テレビがない以前から落語ってもちろんあるので、江戸時代ぐらいからあるものなので、落語はだから音声としてラジオから普通に一般の人たちの楽しみで流れていたわけですよね。で、うちの母親が結構ラジオが好きでよくかけてたので、そこでよく落語が流れていたんですよ。それを子どものときに聞いていて、ん? なんかおもしろいじゃん! っていうふうに思ったのが一番最初ですかね、落語を認識した。まあ当然、中学校とか高校とか行くとあまり落語を聞かなくなるんですけど、たぶんそういうものがちょっと好きになるようなタイプの人間だったので、大学ぐらいになるとちょっとまた落語を聞いてみたいなって。もう子どもじゃないので行動が自由になるじゃないですか、そうすると寄席ってやってるんだなって思うわけですね。今でこそ寄席って……。山下さん何カ所でしたっけ? 東京だと4カ所か?
【山下】4カ所ですかね。新宿、池袋、上野……。
※定席は4ヶ所。
新宿末廣亭 http://suehirotei.com/
上野にある鈴本演芸場 http://www.rakugo.or.jp/
池袋の池袋演芸場 http://www.ike-en.com/
浅草演芸ホール https://www.asakusaengei.com/
他に、国立演芸場、江戸味楽茶屋 、そらまち亭、らくごカフェなど。
【三浦】4カ所しかないんですけど、昭和の戦前っていうのはもうそこらじゅう寄席だらけだったんですよ。その話するとまた長くなっちゃうんでちょっと端折りますが、今だから寄席の4つには自由に行っているので、大学ぐらいからなんとなく通い始めて。でもそんなハマっちゃいませんよ、そのときは。落語っていいな、たまに空いた時間に楽しみに行くのには寄席っていいなと思ったのが落語を見るようになった、最初はだから聞いていて、見るようになったのはそういうきっかけですね。そうのうちだんだんハマってくると、落語っていうのは音源がたくさんあるんだな、同じ話で100通り以上のやり手がいて、落語家さんがいて、全然それぞれ違うんだなっていうのがわかり。
【山下】全然違いますよね。
【三浦】そうすると音源を拾うようになってくるんですよ、いろいろ。この人とこの人は全然ここが違うんだっとかっていうのがわかると楽しいんですよ、それが。
【山下】みんな解釈が違うんですよね。
【三浦】そうなんですよね。
【大野】なるほど。
【山下】どういうふうに話を展開するか。
【三浦】っていう辺りから落語を聞くようになって今に至るっていうことですね。
【大野】いろんなところでやっていたという話なんですけど、今例えば落語を見に行こうってなると、どういうところでやってるんですか? 浅草とかのイメージがあるんですけど。
【三浦】そうですね、それは正しいですね。結局コロナの影響でしばらく前まで寄席も閉じてたんですけど、5月いっぱいか6月の上旬は閉じてたんですけど、もう今は各寄席が始まって、おそらくちゃんとソーシャルディスタンスを保ちながら客入れて。
【山下】末広亭も開いてますよ。
【三浦】そうですね、いま新宿1丁目の映像テクノアカデミアですけど、近くですね、末広亭。
【山下】そう、近い。
【大野】新宿ですね。
【三浦】歩いて5分ぐらいで行けますので。
【大野】近いですね。
【三浦】それともう1つは、これは歴史があるんですけど上野の鈴本演芸場。席亭、経営者は鈴木さんっていうんですけど、でも鈴本っていう。
【山下】なるほど。
【三浦】あと浅草の演芸ホール。浅草演芸ホールはおもしろいですよ。はとバスのツアーに入ってますからね。
【大野】演芸観劇。
【三浦】はとバスツアーの中に演芸場が入っていて、アナウンスが流れるんですよ。「はとバスの東京なんとかツアーの皆様、そろそろお時間でございます。」っていうアナウンスが演芸ホールで流れたりする。
【山下】ツアー参加者は途中でみんな出ちゃうの?
【三浦】途中、まあ一応演者の交替のときに出てきます。
【山下】交替のときにですか。そりゃあそうですよね。
【三浦】あともう1個は。ちょっとマニアックなんですけど池袋演芸場っていう。
【山下】池袋演芸場はマニアックな場所にありますよ。とても素敵な場所です。
【三浦】ここ人数が少ないんですけど、もう完全な密状態で落語やってたっていう。
【山下】密な歓楽街で、いろんな夜の街がたくさんあるところです。
【三浦】今はだから寄席は東京で4場あるので、大野さんも興味があったら、パっと行けば必ず入れます。よっぽどのことがない限り。
【大野】新宿と上野と浅草と池袋。
【山下】新宿は風情がありますよ、建物が。
【大野】古い建物?
【三浦】映画で……。なんでしたっけ? 『落語心中』じゃなくて……。※林家しん平監督作『落語物語』、松山ケンイチ主演映画『の・ようなもの のようなもの』など。
【山下】映画? なんだろう?
【三浦】使われてましたよね?
【山下】ロケで?
【三浦】ロケで。寄席でロケしようと思うともうその4つしかないので、別にセットでつくる必要は何もないじゃないですか。
【山下】そうですね。セットつくったら高いからね、本当に。
【三浦】あとちょっと補足すると、寄席っていうのは決して落語だけやってるわけじゃないんですね。
【大野】そうなんですか?
【三浦】最初から最後まで落語家さんが出るわけじゃなくて、落語さんと、あと手品の人とか。
【大野】なんかテレビで見たことあります。
【三浦】曲芸の人。曲芸ってあるじゃないですか? 駒を回したりとか。あと水芸やったりとか。そういう人たちが交互に登場するんですよ。
【大野】手から水が出てくるみたいな?
【三浦】まあ……、そうですね。
【大野】ちょっと違いますね?
【三浦】手品と曲芸の間。あとは漫才師。
【山下】そう、漫才師も出てくるんです。
【大野】浅草漫才協会ありますね。
【三浦】浅草は、いわゆるお笑いの宝庫っていうか元祖ですから。ナイツっているじゃないですか? 結構、売れてる漫才師。ナイツはコンスタントに演芸ホールに出てますよ、ちゃんと忘れずに。普通、漫才師も人気になると寄席とか出なくなるんですけど。
【山下】テレビになっちゃうからね。
【三浦】育ててもらったのが寄席だから、それを忘れずにちゃんと出てる。だから一番最初に開口一番って言って、東京ですけど序列があって、落語家さんの。前座さん、入りたての前座さん。前座さんは何をするかっていうと、楽屋でお茶を出したりとか師匠たちの着物を畳んだりとか、あと師匠たちが話したネタのネタ帳を付けたりするっていうことをするんですよね。ネタ帳ってなんで付けるかっていうと、寄席の出演者って最初から最後まで全員いるわけじゃないから、7番目ぐらいの出演者の人は6番目の人の途中で来たりするわけですね。それでいきなり話に入ると、前の人がやった話をやると「その話は出たよ、もう。」って客から言われるので、ネタ帳っていうのを付けて同じネタが被らないようにしてたっていう。それがとても前座の大切な役割で、その人たちも一応落語はやらせてもらえるので、例えば10時始まりだとすると9時50分ぐらいから上がるんですよ。お客が来てない頃ぐらいから。
【山下】そうなんですよ。やる前から始まってるんですよ、落語って。
【三浦】自分の噺を話して、そこで稽古して。5人ぐらいの観客相手にやってるわけですね。で、開口一番が出て「お客がきたからお前もう引っ込め!」みたいなこと言われつつ引っ込み、次に先輩の二ツ目さん、師匠にいる前の二ツ目さん。
【山下】前座の上ね。
【三浦】上ですね。二ツ目になると羽織が着られるんですね。
【大野】ちょっとずつできることが上がっていくんですね?
【三浦】羽織を着た二ツ目さんが出てきて、3番目に漫才、4番目また二ツ目、5番目曲芸、そのあと真打のまた誰か、また漫才とかそういうふうに。あとギター漫談の人とか。
【山下】それもありましたね。あとこれは? 紙切り。
【三浦】紙切りの人は結構重要な位置にいて。
【山下】そうなんですよね。紙切りは結構意外と重要なんです。
【三浦】寄席ってだいたい2部構成で昼の部と夜の部があるんですけど、最後に話すのはいわゆる主任って呼ばれていて、その人が最後に話をして締めるんだけども、その前に膝っていうんですね、主任の前に上がるのを膝っていうんです。膝で上がる人って結構大事で、そこで満場のウケを取ってしまうと、あとの師匠が困る。だから本当に、ほどほどの芸だけどこれは一流だぞっていうのを披露して。
【山下】難しいよね、これ。独特のポジションですよね。
【大野】一番難しいそうです(笑)。
【三浦】だから落語→落語って最後に並ぶことはないんです。その前は紙切りだったり、それこそ漫談だったり、それこそ小唄・端唄のお姉さんだったり。本当ほどよく寄席の場を温めつつそんなにウケない、でも次に期待させる。まあウケる必要がないってことですよね。っていうとてもとても大事なポジションで。
【大野】そうですね。
【三浦】で、紙切りっていうのは今山下さんが言ったので言うと、本当にもう驚きますよ。その場でネタを募集するんですよ。
【山下】そう。客席から「何がいいですか?」とか言うんです。
【三浦】「何を切りましょうか?」って切りながら言うんですよ。「じゃまず手始めに矢切の渡し切りますのでその間にお客さん何か考えて。」って言って「はい何が?」って言ったら「映像テクノアカデミア!」とか言うと「それなんですかね?」って言いながら映像テクノアカデミア切るんですよ。
【山下】これか? 東北新社の新宿ビルでしょ? みたいな感じで切るんですよ(笑)。
【三浦】そういうちょっとギャグを入れながら。くすぐりを入れながら切っていくという。本当に名人芸ですよ。
【山下】すごい、言った人はそれ切ったやつくれるの。
【三浦】そう、もらえるの。お土産で。
【大野】紙はなんか特殊な? 普通の?
【山下】あれなんの紙ですかね?
【三浦】いや、たぶんコピー用紙みたいな紙だと思うんでけどね。
【大野】その辺のをうまいこと切っちゃう。
【三浦】そんな感じの紙です。そうじゃないと切れないですからね。段ボールだと切りづらいし。
【大野】そうですよね。
【三浦】厚紙だと切りづらいんで。
【山下】普通の紙だと思うな。
【三浦】ホール落語になると最近ちょっと紙切りも進化してて、OHP使って投射したりするんですよ。
【山下】大きく見えるから。
【三浦】みんなに見えるように。
【大野】ちょっとかっこいいですね(笑)。
【山下】広いからね。
【三浦】そういう紙切りの人が出てきたりっていう、その辺はまあ寄席っていうのは開口一番から最後トリを取る主任まで、よく言うのは料亭とかフランス料理屋でフルコース食べるみたいなものだっていうね。
【山下】なるほどね。
【三浦】前菜があって先付があってお造りがあって、ここで箸休めがあってっていうメニューになってるっていうのをよく言いますね。だから寄席は行くと、別に途中でトイレ行ったりすることももちろんいいし、まあ外に出ちゃうと帰ってくるの許してくれる寄席は今あるのかな? 戻ってきていいですか? って言えば大丈夫だと思うんですけど、出入りは自由だし。
【大野】座りっぱなしってわけでもないんですね。
【三浦】それは全然。気楽なところですよ。楽しいですよ。
【大野】行きたいですね。
【三浦】あとビール飲みながらも聞けるし、ぜひ。最近ホール落語はこのコロナの中であまりちょっとやってないですし、もう始まりましたけど、なかなか人気落語家のチケットは取りづらいんで。※新型コロナ感染対策の為、4つ定席の場内でのアルコールはNGになっています。
【山下】取れないんですよ、本当に。
【三浦】あとホール落語は高い。4000円とか普通に取っちゃったりするから。寄席は途中から入ると、半分越えるとちょっと安くなるんですよ。寄席もそこそこ取るんだけど、2800円とか3000円ぐらい。ただ10人出るとして6番目ぐらいから入ると2000円ぐらいで入れたりするんです。
【大野】ちょっと狙って行くみたいなのも。
【三浦】だから、例えば末広亭の夜の部って確か6時かな?
【山下】5時からだね。
【三浦】さすがに5時に僕ら行けないじゃないですか。サラリーマンなんで。6時半に終わって駆け付けて7時に入るとちょっと安いところがあるんです。
【山下】7時になるとね、1500円。
【大野】1500円! 気楽ですね。
【山下】末廣亭。
【三浦】だから、まず気楽に落語に接するのは寄席が一番ですね。私自身もよく寄席に行ってました、本当に。土日とかフラっと。とてもとても。まあ寝ててもいいし、別に。
【大野】とりあえずその場にいて浴びようっていう楽しみ方ですね。
【三浦】眠くなるんですよ、また何人も聞いていると。
【山下】眠くなっちゃう(笑)。
【三浦】おもしろくないなとか思う。それもだからおもしろさなんですよ。おもしろくないのもおもしろいんですよ。
【大野】自由ですね。
【山下】おもしろいのはだいたい起きてるから。おもしろいと絶対に起きるんですよ。不思議ですよ、これ本当に。
【大野】おもしろくないのもおもしろいってすごい言葉ですね。
【三浦】おもしろくないのもそれは一つのメニュー。相変わらずこいつおもしろくねえな~っていうような(笑)。
【山下】あと、昔はね「おもしろくないぞ!」っていう人がいたらしいですね。
【大野】それ感じたいですね、チケットはそこで現場に行って並んで買うんですか。
【三浦】映画館と一緒です。あっ、映画館って今は予約制か。寄席は予約制じゃないですもん。窓口で買うんです。
【山下】コロナでどうなったんですかね?
【三浦】いや、たぶんシールドして売ってると思いますよ。
【山下】普通に予約じゃなくて買うんでしょうね。寄席はだいたいそうだから。
※4つの寄席は基本予約はありません。
【三浦】あのチケット代のことを木戸銭っていうんですよね。
【大野】木戸銭?
【三浦】木戸銭。木(き)に扉(とびら)の銭って。
【大野】あー、木戸銭。入口の。
【山下】あれは、木戸をくぐって入るから。
【三浦】そうですよね、きっと。木戸銭っていって。寄席ぜひ行ってみてください。
【大野】言い方が粋ですね。
【三浦】さっきも話に出てたホール落語の話もちょっとすると、ホール落語っていうのはそもそもやり始めたのってたぶん新聞社主催の落語会とか、あと東横落語会っていって、東横ってデパート知ってる人いないですよね?
【山下】渋谷の東急東横店?
【三浦】そうです。東横劇場ってあってそこで落語会やってて昭和の名人がもう綺羅星のごとく出てたんですけど、そういう何人か出る落語会をそういうスポンサーがついて催してたんですよね。今でも朝日名人会って、これは朝日新聞社だし。
【山下】これ、毎月、やってますよね。
【三浦】毎日落語会は毎日新聞がやってたりとか、それがたぶんホール落語の始まりですね。そこでも同じ構成になってて、いわゆる名前は最初に出てないんですけど、開口一番がやっぱり出て話して、あとはもう事前に発表されている噺家さんの順で4人とか5人とか。
【山下】それはちゃんと出てくる。
【三浦】だからホール落語を見に行くときは、その発表されている噺家さんの名前を見て、じゃあこの人に興味あるなって。まあ最近ワイドショーにいっぱい出てる立川志らくとか。
※立川志らくさんはTBS系列『グッとラック!』や『ひるおび!』などに出演。
【山下】志らく師匠ね。
【三浦】志らくってワイドショーで見るけど、落語は見たことないなとかね(笑)。
【山下】志らくもチケットが取れなくなってきてるから本当に。昔は取れたのに、本当に。
【三浦】あとは『ためしてガッテン』の志の輔さんとか。
※NHK総合の番組『ためしてガッテン』に出演している立川志の輔さん。
【山下】志の輔師匠ね。
【三浦】志の輔さんとか本当にチケット取れないですからね。
【山下】チケット取れないです、本当に。もう全然取れません。
【大野】すごいとはよく聞くんですけど。
【三浦】志の輔さん全国区ですからね。『ためしてガッテン』ですから。っていうふうに立川流の他の噺家がそうやって志の輔をいじったりするのもおもしろいっていう。
【山下】そうそう、同じ流派の家族いじりみたいなものですね。
【三浦】あの人全国区だからさーとかって(笑)。
【大野】あれなんか流派というか?
【三浦】あれは立川流っていうんですね。これはどういうことかっていうと、今でもあるんですけど日本落語協会ってのがあって、今は会長が市馬かな? 柳亭市馬ってのがやってるんですけど、70年代に昭和の大名人の1人の6代目三遊亭圓生って人がいて。この人が協会の会長だったんです。ただ当時落語が少し下火になりつつある頃で、若いやつらをどんどん真打にしてしまおうって動きがあって、
【山下】真打でさっき出てこなかったけど、さっきの前座と。
【三浦】二つ目、最後が師匠と呼ばれる真打。
【山下】それが真打。
【三浦】ゴール。
【大野】待ってました! というような?
【三浦】そうですね。
【山下】真打もたくさんいるんだけどね。
【三浦】売れてない真打とか売れてる真打とか。
【大野】売れてない真打(笑)。
【山下】本当ですね(笑)。
【三浦】でも真打は真打。真打になると師匠って呼ばれる。
【山下】弟子も取れるし。
【三浦】真打をたくさん、そんな実力もないのに上げちゃってた時代があって、圓生はそれに怒って、あんな噺もできないやつをなんで上げるんだ! って言って辞めちゃったんですよ。
【山下】協会をね。
【三浦】それで落語三遊協会ってのをつくって、それがつい最近まであった圓楽党に続いてるんですよね。三遊亭圓楽の。圓楽党にずっと繋がっているんです。三遊亭の。で、やっぱり立川談志は同じような考えを持ってて、立川談志の師匠って5代目柳家小さんっていう。皆さん覚えてるかな? 永谷園で味噌汁を食べてた人。
【山下】剣道をやってたね。
【三浦】あとお墓のCM。今は孫の花緑が出てますけど、他のCMとか出てた人で、本当に好々爺のおじいちゃん。
【山下】髪型は私と同じような髪型で。
【三浦】ニコニコした。剣道が大好きで、さっき言ってた今の落語協会の柳亭市馬がほぼ最後の弟子なんですよね。で、弟子入りして「おい、稽古つけてやるぞ!」って稽古場に行ったら剣道だったていう。
【山下】どっちやねん!? みたいなね、噺の稽古とちゃうんかい! みたいな話ですね。
【三浦】剣道の稽古だったっていう。市馬はこれをネタにしてくすぐりで使うというね。で、その小さんと弟子の立川談志は大げんかしてしまい、とあることで。で、立川談志は立川流をつくり、落語協会を辞めて。
【山下】自ら起業したんですね、新しい流派を。
【三浦】志の輔より上の立川流の噺家たちは寄席を経験してるんですけど、志の輔が入門してすぐ落語協会を出たので、志の輔はたぶんほとんど寄席っていうのは出てないんですよね。ちなみに最近最もチケットが取れない講談師と呼ばれている神田松之丞も落語芸術協会ですよ。今は伯山ですけど。講談師も芸術協会に入れるんですね。で、立川流はそういうかたちで自分たちの一派をつくって、立川流という。で、結局弟子の噺家たちは、寄席っていうのは出ると一応ギャラをもらえるんですよ。前座だと給料が出る。で、ギャラとか出ないじゃないですか、寄席に出ないから。だから自分たちで落語会をつくっていかなきゃいけないっていう、そういう十字架を背負わされて。おまけにもう1個十字架があって。お金を取られるんです、師匠から。
【大野】お金を取られる?
【山下】上納金。
【三浦】上納金っていうのを取られて。「おまえ今月の上納金払えよ。」って言って全員の弟子から取ったんです。「上納金払えないと首にするぞ。」「破門するぞ。」って。
【山下】「働いてこい!」と。
【三浦】結構立川流の噺家たちはみんな築地で修行したりしてるんですよ。バイトで。
【山下】談春さんとかね、築地で働いて。
【三浦】それも芸の肥やしになるという、談志の超一流の弟子の育て方ですよね。
【山下】今の時代だったらね、どんな会社やねん! みたいな話なんですけど、本当に。
【三浦】もうパワハラですよ、完全に。そうやって立川流というのがあり、立川流は今でこそ少し敷居は低くなって、何人かでまとまれば、まとまるっていうのかな? 余一会か。余一会って何かっていうと、寄席って10日替わり興業なんですよ。
【山下】1カ月で10日ずつ、10日ずつ、10日ずつってやるんですよ。
【三浦】1日から10日まで、11日から20日まで、21から30まで。ここで全部顔付けが変わっていくんですよ、出演者が。
【山下】顔付けっていうのは、出演者がどういうのが出るかっていうのを顔付けっていうんです。
【三浦】そう。で、31日って余るじゃないですか。「これ君ら好きに使っていいよ。」って昔は言ってて、若手の勉強会とかに使ったのが31日。だんだんそこがいい日時なので「じゃあちゃんとした落語やろうよ。」って言って、そういう立川流の人たちもそこを借りて、立川流の有名真打も出たり、そういう会になっているっていうことなんですよね。
【大野】なんか今聞いていると、具体的にどの噺家さんから見ようかなとかって思ったりするんですけど、お勧めとか、なんか好きな。
【三浦】それは2つ方法があって、さっきちょっと話に出たやっぱり昭和の名人の音源っていうのがもう膨大な量があるので、それは別に買わなくても図書館に行くといっぱいあるんです。
【山下】図書館で借りられます。
【大野】見たことあります。CDボックスみたいになって。
【三浦】ボックスじゃなくても1枚でもいっぱい出てて。買うと大変なので。それこそこのリモートワークの中、まあ落語を聞いてリモートワークできるかっていうとね、ちょっとまあハテナはハテナだけども(笑)。まあでもいいんじゃない? 別にね。
【山下】ものすごい単純作業でないと無理だね(笑)。
【三浦】音楽を聞きながらリモートワークしている人もいるわけだし。それが落語に変わるだけだから。
【山下】入力とかだとできるかもしれない。
【三浦】落語みたいなね、するって~と、とか入力してたりしてね(笑)。だからそういう音源を図書館で借りて聞くのもよし、あとは今この『東京かわら版』っていう演芸専門誌が出てて、ここに寄席の顔付けとか全部出ているので。
※『東京かわら版』(tokyo-kawaraban.net)
【大野】ガイドですね。
【三浦】これそんなに高くないので、600円なので。これを買っていい落語会あったらこれ行きたいなっていうのを。
【大野】狙って行けるわけですね。
【三浦】行けるわけです。今ね、ただ人気落語家って本当にチケット取れないんですよ。
【山下】そうなんです、本当に大変なんです。
【三浦】ぴあさんとかなら結構売ってるんですけど、例えば立川流だと志の輔はそうだし、立川談春。談春は「下町ロケット」で俳優にもなり。
※TBS系列・池井戸潤原作のドラマ「下町ロケット」に立川談春さんは出演。
【山下】有名でね、本当に。
【三浦】で、談春も取れないですし、志らくもわりかし取れないですけど、まあでも志らくは取ろうと思えば。
【山下】昔は取れたんですけどね、取りにくくなりましたね。
【三浦】今もそうですか?
【山下】うん。
【三浦】あとは柳家でいうと喬太郎っておもしろいですよ。
【山下】喬太郎はおもしろい。女性ファンが多いんですよね、喬太郎はね。
【三浦】多いですね。喬太郎も今なんか配信とか、番組は持ってなかったでしたっけ? 喬太郎は?
【山下】喬太郎はときどき俳優で出てますけどね、映画とかに出たりしてるけど。
※柳家喬太郎さんは映画『落語物語』、テレビドラマ「なつぞら」などに出演。
【三浦】だから、何か1つチケットを買って行ってみるっていうのに、まあ寄席にまず行ってこの噺家さんいいなあと思ったら、その噺家を追いかけるとかね。今回行った寄席の顔付けした人たちにはなんか好きな人いないなと思ったらまたちょっと別の寄席にもう1回行ってみる。そうやって見つけていくんですよね。それは別に前座でもいいんです、二ツ目でも。この人をずっと聞き続けようって、なんか自分でしっくりくるからこの人を聞き続けてみようって。女性ファンはそういう人が多いですよ。
【山下】多いですね。
【三浦】開口一番、前座と若い二ツ目に目をつけて追いかけてる。
【山下】割とちゃんとしたファンになって。すごい。
【三浦】育てるっていう意識ですよね。
【大野】育てるかあ。
【三浦】お姉さんがあんたのこと育ててあげるわよ、ちゃんと見守ってあげるわよっていう感じで。
【山下】歌舞伎とか宝塚と似てますよね、これね。
【三浦】そうそう。タニマチみたいになってるよね。
【山下】タニマチですよね、これね。
【大野】最近だとよくアイドル業界でそういうの聞きますけどね。
【山下】同じ。母性本能が。
【三浦】だから本人のほうもちょっとアイドルみたいにして座って。
【大野】その楽しみ方もありますね。
【三浦】松之丞のファンもそういう人が多いですよ。昔から見てる人は。※神田松之丞さんは襲名して神田伯山さんです。
【山下】そうか、松之丞時代から応援してますよみたいな感じで。
【三浦】そうやって自分の好きな落語家を見つける。見つからない場合は昭和の名人を聞く。昭和の名人を一応覚えてなくてもいいので何人か言っておくと、まずやっぱり古今亭志ん生ですね。
【大野】志ん生ってよく聞きますね。
【山下】僕は最初にCDをこれ聞いたほうがいいよって言われたのが志ん生の『火焔太鼓』。
【三浦】古今亭志ん生の
【大野】演目?
【三浦】『火焔太鼓』おもしろいですよ。
【大野】わかりました。
【山下】古今亭志ん生の『火焔太鼓』のCDがあるからそれを聞いてこいって言ってそれを最初に教えてもらったのが『深夜食堂』を今描いてる安倍さん。あの人は落語が好きで「山下さんそれだったらこれ借りたほうがいいよ」って言って。
※『深夜食堂』の漫画家、安倍夜郎さん。
【三浦】古今亭志ん生は、もう大酒飲みで高座で寝てたって、酔っぱらって。お客が「落語やれ!」って言ったら、他のお客が「まあ寝かしといてやれよ。」って言ったっていう伝説の(笑)。
【山下】すごい有名な話ですよね。
【三浦】借金を背負ってすごい引っ越ししてるんですよ。
【大野】そうなんですか(笑)。
【三浦】志ん生も葛飾北斎みたいにものすごく名前を変えてるんですよ。5代目志ん生に落ち着いたのは最後ですけど、それまでは十何回は名前を変えてるんじゃないかな、確か。ちょっと回数は忘れましたけど。
【大野】結構変えてますね(笑)。
【三浦】それとやっぱり並びを一緒するならさっき出た6代目三遊亭圓生。これはいわゆる長い話とか『牡丹灯籠』とか。
【山下】『牡丹灯籠』は長いんですよ。
【三浦】『真景累ヶ淵』とか。
【山下】あっ! いいですよ、それも。
【三浦】もちろん普通の落語もものすごくおもしろいんですけど、こういう講談話もすごいおもしろいです。
【山下】あれは講談話っていうんですね?
【三浦】ほぼ講談ネタですからね、あれはね。あっ! でもそうか、違うな。ごめんなさい。それは違うわ。三遊亭圓朝作だから、やっぱり落語のほうだ。※三遊亭圓朝は幕末から明治に活躍した落語家。
【山下】圓朝さんは落語のね。三遊亭圓朝という人がいて、これもまたすごいわけですよ。
【三浦】近代落語の始祖みたいな人がいて。
【大野】子孫(笑)。
【三浦】圓に朝って書く、圓朝。
【山下】江戸の落語を現代に変革したイノベーターなわけですよ、圓朝といえば。
【三浦】圓朝はあまりに天才すぎて10代半ばぐらいで真打になってるんですけど、あまりに人気があってウケるから他の噺家さんが意地悪するんですよね。まだ子どもなのに若いのに。あいつの好きな噺を全部やってやろうぜみたいな。ネタ被らないようにするから。で、全部そうやって周りが攻めてくるから「だったらいいよ、俺自分で噺つくってやるから。」っていうのが圓朝が噺をつくるようになったきっかけ。
【山下】『死神』とかですね。
【大野】かっこいい。
【山下】あれもそうでしたっけ? あの……。
【三浦】『文七元結』とか。
【山下】『真景累ヶ淵』もそうだし。
【三浦】『牡丹灯篭』。
【山下】あと、あれか……。
【三浦】『死神』。
【山下】あれもそうでしたっけ? あの年末にやる。
【三浦】『芝浜』もそうですね。『芝浜』は、確か高座で三題噺なんですよね。『芝の浜』と『革財布』となんとかっていうのをテーマをもらって。
【山下】それであれができたんだ。
【三浦】そうなんですよ。お客さんから3つお題をもらって、それで噺をつくったんです。それがその場でつくったか一応前にもらったのかはちょっとわからないですけど。でも、もしかしたらその場でつくってるかもしれないですね。
【山下】圓朝と立川流がおもしろいのは、割と外部の障害が多いじゃん。障害が多い人たちっていうのは天才みたいな人が生まれるのかな? どうなんでしょうか?
【三浦】やっぱり、その与えられたハードルを越えていくんですよね、どんどん。。
【山下】それがすごいですね。それって天才が生まれるあれなのかもしれないね。
【三浦】屈しないっていうかね。あれ? 何の話してたんでしたっけ? そうそう、昭和の
【大野】そうなんですよ、どの方から見ていけばいいかなっていうのを。
【三浦】圓朝はもう置いておいて昭和の落語家で。三遊亭圓生であと8代目桂文楽。これは本当に江戸前落語っぽい人です、8代目桂文楽。それからさっきの5代目の柳家小さん、それから桂三木助とかたくさんいるんですけど、あとは聞いてて一番気持ちいいのは、若くして亡くなって本当に残念なんですけど志ん生の息子、次男の古今亭志ん朝ですね。
【山下】志ん朝も大好きな人がいっぱいいらっしゃいましたよね。
【三浦】本当に声がよくて。
【山下】品がいいというか。
【三浦】聞いてるとこれが落語なんだなあっていう。志ん朝は61ぐらいで死んじゃったんですよね。
【大野】結構早くに。そうですか。
【三浦】そのお兄さんがいて、金原亭馬生っていうんですけど。池波志乃のお父さんですね。
【山下】池波志乃は中尾彬の奥さん。
【三浦】で、10代目かな? 金原亭馬生はどっちかっていうと弟さんの志ん朝が太陽のような明るい芸だとすると、ちょっと陰に籠っているんですけど、ちょっと暗いかな? でもそこは味があるんですよ。
【山下】暗い落語も意外といいですよ。
【大野】暗い落語かあ。
【山下】落語は明るいだけじゃないんですよ。それがいいんです。
【三浦】金原亭馬生のことで志らくと談志でエピソードがあって、志らくは金原亭馬生に入門したかったんですね、実は。ところが金原亭馬生が亡くなってしまったんです。志らくはもうこの人に入門しようって決めてたのに亡くなってしまった。で、亡くなった日に立川談志の高座に見に行ったときに、立川談志が高座でずっと馬生の思い出話をしてるんですね。そのときに客席から「落語をやれ!」って言ったら談志は「いや、今日は俺はもう落語はできねえ馬生師匠が亡くなってこんな日に俺は落語はできねえ。」って言ってやらなかったんですよ。志らくはこの人に入門しようって決めたっていう。
【山下】ええ話やないですか。
【三浦】すごいいい話なんですよ。志らくは今でもワイドショーでよく言ってますけどね。
【山下】いい話ですね、でもね。
【大野】なんかみんな何かしらかっこいいこと言ってますね。
【三浦】落語と講談の話をしたほうがいいですかね?
【大野】そうですね、僕も最後にちょっと聞こうと思ってたんですけど。
【山下】じゃあ、最後にそれだけちょっと。
【三浦】落語と講談っていうのはどう違うかっていうと、基本的に落語っていうのが対話で、会話で、上下を振りながらはっつぁん、熊さんって言って上下を見ながら会話で進めていくのが落語です。で、講談っていうのは地語り。地の語りで進めていくのが講談なんですね。だから地の語りで話すってどういうことかっていうと、例えば長屋のはっつぁんとご隠居さんの話で言うと「八五郎は今朝目が覚めてまっすぐご隠居のところへ飛んで行き、ご隠居の門を叩いた。ご隠居は何事かと思い、起きて八五郎に問いかけるのであった。」みたいなことで進めるのが講談。
【山下】いわゆる地の文ですよね。台詞じゃなくて地の文も……。台詞もしゃべるんですよね?
【三浦】台詞は、どうしてもそれで八五郎とご隠居が会って話し始めたら「はっつぁんも今日は早いね。」みたいなことでやらなきゃいけないですけど、基本的には地の語りで進めていくのが講談っていうふうに思っておけばいいです。落語の場合はそこが、ドンドンドン! 「ご隠居! ご隠居! 起きて下さい! 起きて下さい!」「なんだいはっつぁん、こんな朝早く。」ってやっていくのが落語。落語で地の語りを入れるっていうのはあまりないですね。基本的には上下振りながら進めていくっていうのが落語ですね。そこだけ理解しておくと講談師ってこういうことなんだなって。だから落語家が講談やることも結構ありますけど、基本的には落語風にはやらないです。講談は講談として。
【山下】落語で講談風のやつをやるのがあるから、それを見て興味を持ったら講談も。今日はもう時間があれなんであれですけど、こういうふうに落語も講談も奥がすごく深い。そして実はこの伝統芸能部、落語とか歌舞伎とか、歌舞伎の演目を落語が繋がってたり、いろんなことが繋がっているんですよ。
【三浦】そう、全部繋がってるんですよ。例えば『真景累ヶ浦』は、歌舞伎にも演目ありますよね。『牡丹灯篭』ももちろんあるし。
【山下】『牡丹灯篭』さっき出てましたよね。
【三浦】文楽のほうにいくと、例えば『一谷嫩軍記』みたいなものが、熊谷直実の話は当然歌舞伎にもあるわけだし、全部が繋がっているので。
【大野】そうですか。
【山下】そうすると、このPodcastの伝統芸能部をずっと聞いておくといろんなものが繋がっていく。
【三浦】そう、いろんなところがポッポッと横に繋がっていくっていう。縦割りでない。
【山下】そうです。落語を見ると歌舞伎にいきたくなる。そういうこと。
【三浦】そう、古典芸能を楽しもうと思ったときに、縦割りでやっていくと意外とつまらないんですよね。落語だけ掘っていくと。
【山下】横に広げていく。これめちゃくちゃおもしろいです。
【三浦】なんかどっかであったよな? っていう。そうすると歌舞伎にも能にも狂言にも文楽にも広がっていく。
【山下】あとそれに時代を繋げていくとものすごくおもしろいマップができるんですね。
【大野】確かにすごいですね。
【山下】これからこれを三浦師匠に毎回聞いていくと。
【三浦】いやいや。
【山下】何百回やるねん!? みたいな感じで。
【山下】本当に私たちはたくさん落語会に行かないといけないという使命を得たわけですね。
【三浦】落語会は、今はこういうさなかなのであまり落語会には行けないですけど、本当に音源はたくさん。YouTubeにたくさんありますよ、音源。
【大野】あっ、そうですか。
【三浦】ある、たくさんある。YouTube。
【大野】わかりました。
【三浦】またゆっくり話たくさんしましょう。
【大野】ぜひ。ちょっともうまずこれで行くきっかけができたので、これからいろいろと行ってみたいと思います。
【三浦】ぜひ。
【大野】ありがとうございました。
【山下】では皆さん、今日はいろいろとありがとうございました。また次回よろしくお願いします。
【全員】ありがとうございました。
【'20/10/9配信】「落語の沼人:三浦さんに落語鑑賞の楽しみをきいてみた」より
プロデューサー:山下治城
キャスト:三浦知之、大野洋平、MC山下治城
テキスト起こし@ブラインドライターズ (http://blindwriters.co.jp/)
☟配信はこちら!!☟
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
