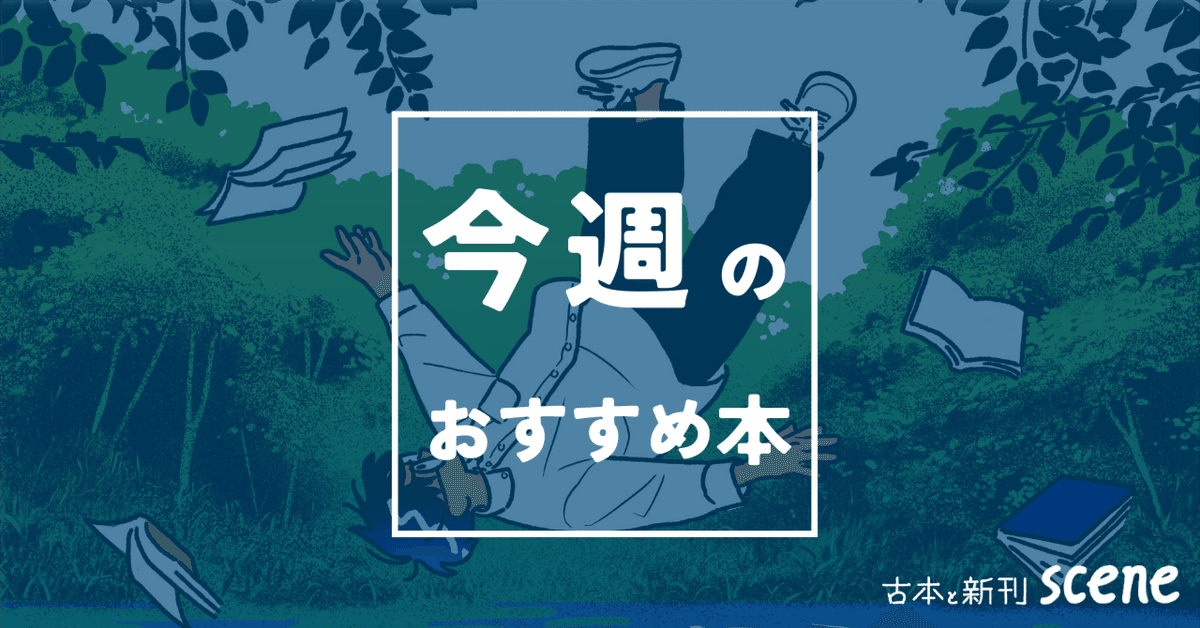
今週のおすすめ本 vol.12
店舗とオンラインストアで取り扱っている本から、おすすめのタイトルを紹介するマガジン「今週のおすすめ本」。
今回取り上げるのは、赤瀬川原平『超芸術トマソン』です。

この記事では、近刊を紹介することが比較的多いのですが、『超芸術トマソン』の初版発行日は1987年。オリジナルの単行本版が出たのはさらにその2年前と、40年近く前に世に出た本です。
毎日多くの本が刷られ、書店の棚に並べられてはまたすぐに別の本に入れ替わっていくという、出版業界の目まぐるしいサイクルの中において、これだけ長い間絶版にならずに刷られ続けている本ですから、その事実だけで「時代を超えて愛されている名著」と言っても過言ではありません。しかし、そのわりにはなんというか、書影から漂うオーラが怪しい(笑)。正直、表紙とタイトルだけではなんのこっちゃわからないこの『超芸術トマソン』を今回はご紹介していきます。
「超芸術トマソン」ってなに?
何はともあれこの疑問に尽きると思うのですが、その答えは意外にもシンプル。こちらの写真をご覧下さい。

六段の短い階段。昇った先には何があるのかというと何もなく、またすぐに下るだけ。
いったいこの階段は何のためにあるのでしょうか。ふつうこういう階段は昇った所に入口があって、ドアがあってそこから建物にはいるわけだけど、これは昇ったところにはドアがない。窓がある。しかし窓にたどり着くためにわざわざ階段を付けるでしょうか。
(中略)これはもう階段の形をした芸術というほかはない。それどころか、これはひょっとして超芸術ではないのだろうか。
現代アートのように何かの意図があって創られたものではなく、元々は機能や役割があったのだけど、改装などによって存在意義を失ってしまったこの階段。しかし、撤去するのもコストがかかってしまうので、無用の長物として、ただそこにあるだけの存在になったのではないかと想像できます。
こういった偶然の産物として生まれた建造物を、芸術を超えた「超芸術」として捉えようというのが、「超芸術トマソン」という概念の始まりです。バカバカしいといえばバカバカしいのですが、「発見」することで初めて姿を表す作品、それが世界中のあらゆるところに潜んでいると思うと、なんだかワクワクしてこないでしょうか。

ちなみに、「トマソン」の由来は、1980年代に巨人に在籍していたものの、助っ人外国人として結果を出せなかった元プロ野球選手、ゲイリー・トマソンから取ったもの。こんなことで名前が知れ渡ってしまうのはトマソン選手には不名誉なことかもしれませんが、語感もどことなくしっくり来るのが不思議です。
かくして生まれた「超芸術トマソン」。その活動はどんどん本格化し、廃業し取り壊された銭湯跡地に佇む煙突の「拓本」を取ったり、トマソンの名所を巡るバスツアーを開催したりと、おもしろスポット探しの域を超えた広がりを見せていきます。
その観測と収集の記録を収めたのが本書、『超芸術トマソン』です。
発想の転換で、世界はいくらでも面白くなる。それも、本気でやればやるほど、楽しいことが次々に起きていく。そんなことを教えてくれた、個人的にもとても影響を受けた1冊です。
今回はここまで。
取り上げた本は、店頭、オンラインストアで販売しています。在庫数は限られているため、売り切れの際はご容赦ください。
本の取り置きや、在庫がない本の取り寄せも承りますので、お気軽にお申し付けください。それではまた次回。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
