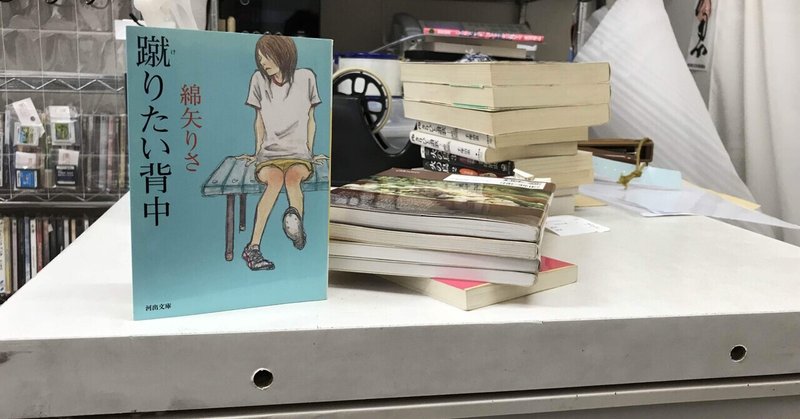
「蹴りたい背中」の意図するところを探り当てる
土曜日だというのにお店はヒマ。そんな日は小説を読むに限ります。今日手に取ったのは第130回芥川賞を受賞された綿矢りささんの「蹴りたい背中」。店主が敬愛する金原ひとみさんの「蛇にピアス」とW受賞された作品です。
読書前の期待値はかなり高め。胸を高鳴らせて本を手にとりました。そして本を開いて読んでみると、すごく読みやすい。砂糖が入ったヨーグルトのように手が止まりません。
先日、店主は職場体験に来た小学生と一緒に芥川龍之介の小説を「暗号を解くみたいだよねー」と解説しながら読みましたが、その記憶が霞んでしまうくらい読みやすい。いい小説だとは思いますが、芥川賞を受賞したと考えると…その受賞情報が読者の心境に微妙な変化を与えます。
レビューを読むと、やはり酷評する人も少なくない。
しかし、店主は悪くないと思います。
小説内の出来事が、全て主人公の目線から語られる作品なので、主人公の心の動きがよくわかる。自分に背を向ける男子、にな川君の背中を蹴りたいという気持ちはわからなくもない。本気ではないけど、なんとなく振り向かせたいのでしょう。「それがこの年代の乙女ごごろじゃ」と言われれば「そうですか」と答えるしかありませんが、その感覚を押し通す感じも読んでいて不快ではない。
また、登場人物の3人のキャラクター設定と描写が見事。その関係性に一点の曇りもない。小説というのは論理的整合性が求められますが、そんな難しい言葉が必要ないくらい、この小説はシンプルな構図とわかりやすい言葉で物語を構築している。
この小説の唯一の問題は、この作品が何のために書かれた小説なのかが読み解くことが難しいところ。ここで店主は考える。深読みする。
主人公の女の子の足がゴボウのようだという表現があった。そこから考えを広げる。この小説は彼女の一人称の物語だ。つまりこの小説の土台は、彼女なのだ。彼女の足なのだ。それは細いゴボウなのだ。細いゴボウに支えられたこの小説は、頑丈な建物は建てられない。壁も間仕切りも無くスカスカであることが求められる。だからより少ない情報で物語を構築しないと、この物語のバランスは崩れてしまう。
主人公の女の子は多感で経験が少なく傷つきやすい女子高生だ。ただ、にな川は少し違う。言葉にしにくいが、少ししっかりしている。少なくとも主人公とは違う。自分が見えている。だからこそ主人公は彼を蹴りたくなる。そして外国人のようなオリチャンが彼ら二人を繋ぐ線だ。それは決して太くはない。しかしそれで絶妙にバランスがとれていた。ところが最後ににな川がそのバランスを壊そうとする。その結果、主人公とにな川の距離も変わる。友人の1人はこのバランス関係には関わらない。
うだうだと書いてしまいましたが、考えれば考えるほど物語の印象が変わって見えてくる。この物語は、全てを細い線で関係性をつくり、物語を構築するということに挑戦した小説かもしれない。だから一見スカスカに見えてしまうのかもしれない。
でも、本当に作者の頭もスカスカであれば、こんなにしっかりお最後までテーマを隠したまま作品を仕上げることはできない。少しぐらい背伸びをしたり、思わせぶりな言葉を残すだろう。それが人間というモノだ。しかし、この作品はそれらしいものがほとんどない。
と、好意的に思考を巡らせてみました。このように、読書後に様々なことを考えさせてくれる小説こそが良い小説だとすれば、この作品の評価は妥当だったのかもしれません。やっぱり読んでよかったと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
