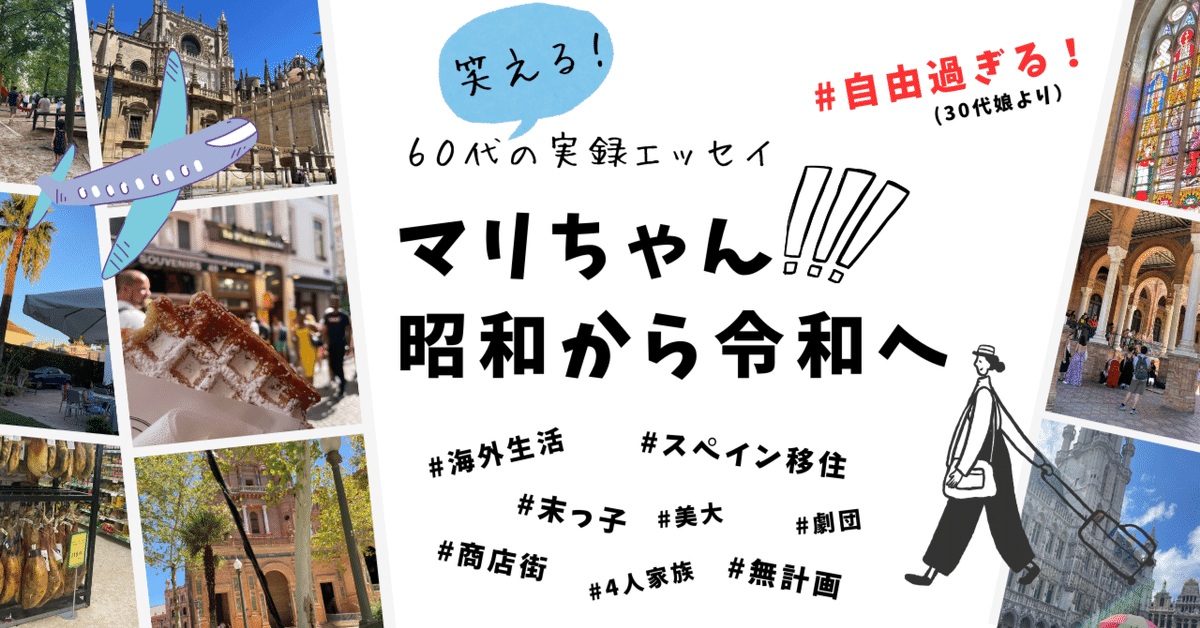
3歳 うまく履かせられなかった白い足袋
私が三歳の時、母方の祖母が五十三歳で亡くなった。
小柄でかなり太っていたから心臓に大きな負担がかかっていた。
祖母の家の土間には、いつもたくさんの酸素ボンベが並んでいて、祖母が発作で苦しくなった時に使っていたそうだ。症状が悪化して病院に入院したが、残念ながら回復しなかった。
母は三歳の私を連れて毎日病院に通っていた。母が何日も風呂に入っていないので、昼の間に銭湯へ行こうと、ちょっと病院を出たその間に亡くなった。
母はいつまでもそのことを悔しそうに話した。
祖母の遺体が病院から家に戻ると親戚中が集まった。
母方の親戚は大体みな半径三キロ以内に住んでいたので、すぐに全員集合できた。葬式に向けて次々と用意が始まった。
白い着物を着たおばあちゃんが布団の上に寝ていた。顔には白い布がかかっていた。
おじさんの一人が
「孫たちに足袋を履かせてもらおうか」と言った。
すると別のおじさんも、
「そうだな。それならおばあちゃんも喜ぶだろう」
そこにいる孫は、姉と私といとこ姉妹の四人だった。
一番大きい孫は七歳で、続いて六歳、四歳、そして三歳の私だった。
おじさんがそう言うのだから、やらなくてはいけない。
お互いに顔を見合わせて、白い足袋を持っておばあちゃんの足に近づく。
足袋を持つのはもちろん七歳と六歳、イヤだの何のと言える雰囲気ではない。
目の前のおばあちゃんが亡くなっていることが分かっているから、何となく怖い。
ところが、なかなか足袋がうまく入らない。
指先は入るが、かかとまできちんと入らない。
足を触りたくないから、全然だめだ。
四人で頑張ったが、左右とも指先だけ入った形までだ。
近くにいたおばさんが、
「いいよ、あとは大人がやるから」と言って、おばあちゃんの足を持って、きちんと履かせ、こはぜもしっかり留めた。
さらに、頭に三角の白い布をつけて、襟元も整えた。
これが私の一番古い記憶だ。
亡くなった後も着物を着たり足袋を履いたり、旅立つ準備もたいへんだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
