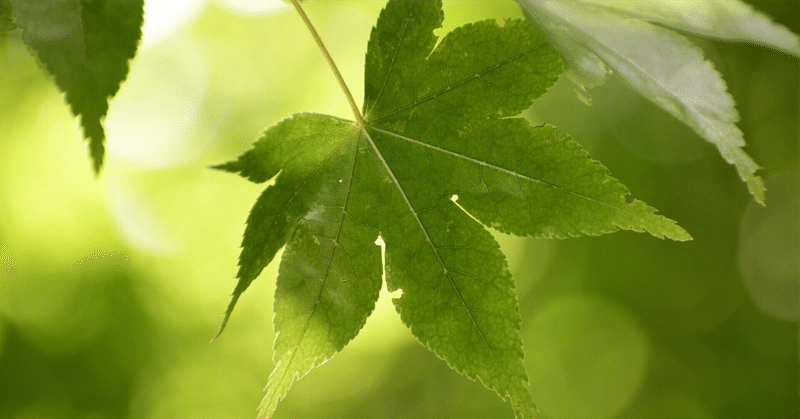
1minute七十二候 蚯蚓出(みみずいずる)
立夏<次候>
5月10日から5月15日頃
春から初夏にかけて、自然界では目に見えない活動が始まり大忙し。特に注目したいのは、地面の下でひっそりと活動するミミズたちの存在です。立夏の次候、「蚯蚓出(みみずいずる)」の時期になると、ミミズが活発に動き出します。ミミズは、腐葉土を食べて栄養豊富な糞を排出し肥沃な土壌を作ってくれています。さらに、ミミズが土中を這うことにより、土に酸素が行き渡り、通気性や透水性を向上させているんですね。そのおかげでふかふかの土が作り出されるのです。
ミミズたちの活躍する地面から目を上げると、この季節は本当に新緑が美しい時期ですね。春の肌寒さも和らぎ、夏の暑さもまだ訪れていないこの時期は、とても過ごしやすく気持ちがいいですよね。
この時期になると、京都では「葵祭」が執り行われます。葵祭は、平安時代に始まり、賀茂の神々の祟りを鎮め、五穀豊穣を祈るために創設されました。葵祭といえば、古式にのっとった華麗な王朝行列がよく知られていますね。多くの人々が平安装束をまとい、京都御所から下鴨神社、さらに上賀茂神社へと進む様は、見る者をタイムスリップさせるかのようです。祭りでは、葵の葉を飾る伝統があり、これは賀茂別雷大神の降臨を祝う象徴とされているそうです。
15日の王朝行列巡行以外にも、1日~15日の間には流鏑馬神事・斎王代禊の儀・賀茂競馬・御蔭祭など見どころがたくさんの葵祭。この時期の京都の街はどこも新緑が美しく巡るだけでも気持ちがリフレッシュします。ぜひぶらり旅にお越しください。
七十二候ってなに?
日本には一年を24に分けた二十四節気(にじゅうしせっき)と、さらにその二十四節気を3つずつ合計72に分けた七十二候(しちじゅうにこう)という季節があります。
七十二候は鳥や虫、植物、天候などの様子で季節を表現しており、細やかな自然の移ろいを感じることができます。 骨董・アンティークバイヤーとして活躍する傍ら「古き良きものの美しさや、ものを大切に使うことの楽しみ」もご紹介中。 ここでは ゆとりある心づくりのヒントとして、季節の話題を記しています。
What is 72 micro seasons?
In Japan, nature's rhythmic seasons are deeply cherished, inspiring a fascination with the mesmerizing 72 micro seasons. Unlike traditional divisions of four or six seasons, these micro seasons paint a vivid picture of nature's transitions with astonishing precision. Imagine the thrill of witnessing the delicate blooming of specific flowers, the graceful arrival of migratory birds, the tantalizing ripening of certain fruits, or even the intriguing behaviors of animals. This admiration cultivates heightened awareness of the surrounding world, immersing individuals in the mesmerizing beauty and rhythmic harmony of nature's ever-changing tapestry.
written by Yuuki Usami-Nakamoto © antique blue Parrot Co.,Ltd.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
