
ファンダムは◯◯を超える|対談・山下正太郎 ×若林恵 【『ファンダムエコノミー入門』より】
【ウェブ特別公開!】 話題のビジネスムック『ファンダムエコノミー入門:BTSから、クリエイターエコノミー、メタバースまで』は、そもそもなぜ生まれたのか。「ファンダム」がもつ可能性はいったいどこにあり、それをドライバーとする経済はどのようなものとなるのか。企業によるオープンイノベーションから、K-POP、オードリー・タン、中国のスーパーアプリ、贈与経済、UX、アレッポのスーク、NFT、メタバースまで縦横無尽に語りながら、ファンダムの可能性を「消費者」「利己的人間」「資本主義」「国家」の超克に見いだす。『ファンダムエコノミー入門』の編者、〈コクヨ野外学習センター〉の山下正太郎と若林恵による、文明を超えた(?)壮大なるファンダム試論。
【トップ画像|KISSのファンダム。ファン組織の名は「KISS Army」。1980年。Russell McPhederan/Fairfax Media via Getty Images 】
* * *

David Becker/Getty Images
若林(以下 W) そもそも、なんで「ファンダム」をテーマに1冊つくろうということになったんでしたっけ?
山下(以下 Y) ビジネスのなかで「顧客との共創」や「オープンイノベーション」といったことばをもって、会社の枠を超えたある種のコミュニティをつくって価値を創造していくということの重要性が長らく言われてきたわけですが、理屈では理解できても、いざ実現しようと思うと非常に難しいわけですね。そうした困難をひとつ乗り越えるモデルとして「ファンダム」というものを考えてみようということだったのだと思います。
W 「共創」や「オープンイノベーション」といったことばは、この10年くらいずっと聞いてきた気がしますが、これはいつ頃から言われてるんですかね。
Y ステークホルダーとの共創を説いた「サービスデザイン」が提唱されたのが1990年代初頭とされています。その後、インターネットが浸透していくなかで、こうした考えや理論がさまざまな分野で一般化されていきますが、経営学の分野ではヘンリー・チェスブロウさんが「オープンイノベーション」という概念を発表したのが2003年。マーケティングの分野ではロバート・F・ラッシュさんとスティーブン・L・バーゴさんによる「サービス・ドミナント・ロジック」が2004年でした。自社のスタンスを維持しながら知財の利活用に注目したオープンイノベーションは人気を博しますが、提供者と受容者を分けずに、お互いが共創する関係性にあるということを謳ったサービス・ドミナント・ロジックはそこまで浸透しなかったように思います。まさに言うは易しで、思うような実践には至っていないという感じなんですね。

ロバート・F.ラッシュ/スティーブン・L.バーゴ
井上 崇通/庄司 真人/田口 尚史・訳|同文舘出版
Photographed by Kaori Nishida
W わかります。つくり手、もしくは生産者というものの特権性・優位性を堅持したいという気持ちは、自分などはかなり強固にありますからね。つくり手至上主義といいますか。つくるのはこっちにまかせとけと。買い手がつべこべ言うな、という。
Y 権威主義(笑)。わたしもメーカーに勤めているので、その感覚はよくわかります。企画、設計、製造、デリバリー、とバリューチェーンが長い分、プロセスのなかからなるべく不確定要素を省きたいというメンタリティは根強い。
W それは実際かなり抜き難くありまして、この10〜15年くらいを振り返ってみても、インターネットやソーシャルメディアが普及し、誰もがブログを書いたり発信することができるようになっていくなかで、それまでのプロがプロとして特権的に発信が許されるという環境は、ビジネス的にもずっと切り崩されてきたわけでして、そのことに対して、特にわたしのような権威主義者は、ずっと警戒感を抱いてきたんですよね。
Y とはいえ、そんなふうに、自分たちのなかだけでプロダクトやサービス開発を後生大事に抱えていたところで、優れたものはつくれなくなっている状況ではあるわけですよね。自動車の大量生産に世界で初めて成功したヘンリー・フォードのかの「もし顧客に、彼らの望むものを聞いていたら、彼らは『もっと速い馬が欲しい』と答えていただろう」ということばに感心はするけれども、普通の企業にそんなカリスマは、まぁいないわけです。
W 自分の感覚では、おそらくもう1980年代くらいにはすでに、プロダクトやサービスの質では競合と差別化ができないような環境にはなっていて、であればこそ、その頃から企業は本格的にマーケティング戦略やコミュニケーション戦略でもって差別化をはかることになったのだと思いますが、「共創」や「オープン」といったことがマーケティングの世界において語られるようになっていった背景には、マーケティングやコミュニケーションによる差異化も飽和しちゃったことがあるのかもしれませんね。
Y ものづくりやサービス提供をしている会社はどこも、物質的な欲求が飽和されていない時期までは、どれだけ均一に効率よくサービスやものを提供するかということを第一義に、生産・流通システムを構築してきたわけです。一度組まれたシステムは強固で、サイロ化された各部門の目標のもち方も、昨年と比べて数%改善するというものになっていますし、全体最適という観点はもちづらい。つくり手側だけの想像力ではもはや限界に達してしまっているという実感は、企業に勤めている者としてはありますね。微細な違いをあぶり出すための他社比較表に無意味さを感じる人は少なくないでしょう。
W そういうなかで、もう一度、「生産者/消費者」という静的で固定化された関係性においてではなく、そのあり方を見つめ直そうというのが、おそらく「ファンダム」というものに対する興味につながっているのだと思います。面白いのは「ファンダム研究」というものが、ちょうど80年代終盤から90年代にかけて勃興しているところで、わたしの理解ではこれは社会学やメディア学の分野において始まったものなのですが、ちょうどビジネスが飽和しつつあったところで「ファン」というものの存在が改めて検討されるようになったのは、いまから振り返ってみるとですが、必然性があったのかもしれません。
Y 「ファン」は、つくり手側からするともちろん大事な存在ではあるものの、その人たちの考えや行動の動態をビジネスの中心に置いて考えようという発想は、これまでずっとなかったですよね。それよりも拡大志向のなかでは新規ユーザーを増やすことに重きが置かれていた。むしろある種の熱狂的なファンは、離れない程度にケアしておけばいい。ことばは悪いですが「外れ値」として扱われてきたのだろうと思います。

BTSから、クリエイターエコノミー、メタバースまで』
編者:コクヨ野外学習センター
編集:山下正太郎(コクヨ ワークスタイル研究所)+若林恵(黒鳥社)
発売日:2022年6月15日|定価:1980円(1800円+税)
Photographed by Hironori Kim
書籍の購入はこちらから
「消費者」を超える
W 本書の最後に掲載したジョン・フィスクさんというメディア批評家の論考は1992年に執筆されたもので、ファンダム研究の嚆矢とされるテキストのひとつですが、これが面白いのは、ピエール・ブルデューが定式化した「文化資本」のフレームを用いながらも、ブルデューの考察の外側にあって顧みられることのなかった「ファン」の存在に光を当て、その人たちが社会的にも経済的にも抑圧されてきた存在であったことに着目した点で、言うなれば「ファン」は文化的にも社会的にも経済的にも周縁化されてきたわけですね。ですから「ファンダム」に光を当てること自体が、一種の政治的な意味をもっていたということにもなるかと思います。
Y ファンダムは、90年代においてはいわゆる「カルチュラル・スタディーズ」のなかで語られていたそうですが、そうだとするならそれを研究すること自体が「公式」な文化というものに対するアンチテーゼだったのでしょうし、日本でいえば東浩紀さんのオタク論に代表されるような表象文化研究の台頭とも対応しているといえそうですね。
W このフィスクさんの論文や、本書の冒頭でインタビューを行ったヘンリー・ジェンキンズさんの研究は、現在でもBTSのファンダムに関するアカデミックな研究などで参照されていますが、フィスクさんの分析をそのまま援用するなら、BTSが世界中でブレイクするにあたって、彼らがグローバル・エンタテインメントの非主流であった韓国/アジアから出てきたことは、それ自体が非常に大きな意味をもっているといえるのかもしれません。
Y 世界中が韓国のアイドルグループに熱狂するなんていう状況は、おそらく誰も想像していなかったと思いますし、しかもそれが重要な存在でありながらマージナライズされてきた「ファン」というものをビジネスの中心に置くことで巨大ビジネスをつくり上げたことは、やはり革命的なことですね。
W とはいえ、そうやってファンを巻き込んでエンゲージメントを高めていく手法は、自分が見たところ日本でも同じように80年代末期から90年代にかけて発生していまして、要はこれって、おニャン子クラブからモーニング娘。からAKB48へと続く流れのなかで開発・洗練されてきた手法だといえばそうなんですよね。
Y CDやレコードを消費するだけでは物足りなくなったファンが「参加」を求めるようになったことと、音楽についていえば、CD消費がデータ消費へと移り変わっていくなかでプロダクトが意味を失っていく流れが、そこでは同時に起きていたように思えますよね。
W 実際CDは、ある時期から「握手券」のチケットになっていったわけですから、ある意味それってNFTを先取りしていたようなものなんですよね。
Y たしかに。それが希少性の高い音源や画像であると同時に、握手会やファンミーティングへの参加権の役割も果たすという使われ方は、NFT所有者がDiscordや特典へのアクセス権を得られるというのとまさしく同じですね。その先に得られるベネフィットが、ファン以外からはなかなか理解しがたいものだということも。
W そうやって「ファン」と呼ばれる人たちの動きが一気に社会のなかで可視化され、その存在の価値が発見されるということが起きたわけですが、それでもやっぱり相変わらず「消費者」は「消費者」のままではあったと思うんです。もちろん、それが多様なマイクロな活動を生み出して、それなりの経済圏を形成していたのだとは思いますが、やっぱりどこまでいっても「消費者」のポジションからは脱せずにいたんだと思います。
Y メンバーの構成まで一部コントロールできるとはいえ、山ほどCDを買わされるというのは、本人にとってはコミットメントの証しなのかもしれませんが、はたからは、事業者にある意味「搾取」されてしまっているようにも見えてしまう。
W そうしたなかで、自分がある意味強く衝撃を受けたのは、K-POPファンによる、いわゆる「ファン広告」でして、自分はそれがどれほど大規模なものになっているのかを田中絵里菜さんの『K-POPはなぜ世界を熱くするのか』という本を読むまで知らなかったのですが、それこそファンのカンパによってタイムズスクエアに広告が掲出されたり飛行機がラッピングされたりといったことが日常的に起きていることを知って、「なるほどそういうことか」と思ったんですよね。

Photographed by Yujiro Tokushige
Y それって、「握手券」ビジネスとどこが根本的に違っているんでしょう?
W 田中さんの本は、K-POPのビジネスが、いかにしてファンの「やりたい」ことを叶えてきたかということを詳細に論じているのですが、ここで重要なのは、K-POPにおいて「ファン」は受け取るだけの静的な「消費者」ではなく、身銭を切って推しの広報をしグッズや動画や字幕をつくったりする「行動」を起こす人たちと考えられていることではないかと思います。
Y 単に「買う」だけではなく、むしろ生産者でもある、と。
W そうですね。かつて台湾のIT担当大臣のオードリー・タンさんにインタビューした際に、彼女は彼女が主導するデジタル民主主義において、「デジタルリテラシー/メディアリテラシー」といったことばは使わず、代わりに「デジタルコンピテンシー/メディアコンピテンシー」ということばを使うと語っていまして、それを聞いたときは正直あまりピンとこなかったのですが、田中さんの本を読んで思ったのは、K-POPはファンの「リテラシー」の開発ではなく「コンピテンシー」の開発をビジネスの中心に置いているんだな、ということだったんです。
Y コンピテンシーは組織内の個人がもつ「能力」の総体という意味だと思いますが、それこそ動画をつくったり翻訳をしたりグッズをつくったりといった個々のファンがそれぞれもっている能力を、自由に発動できる空間をつくっていったということですね。近代民主主義が市民としての政治リテラシーの重要性を強調していたように、知識レベルを問われるハードルの高そうな旧来のファンコミュニティのあり方とは隔世の感があります。
W これは、それこそ台湾の市民主導のデジタル政策と同じ話でして、誰かが「こんなアプリのアイデアあるんだけど」と発案したものを、コードを書ける人がコードを書き、デザインをやれる人がデザインをやり、外国語ができる人が多言語化するといったやり方で、個々人の「能力」をつむぎ合わせていくことで新しい価値を創出していくというアイデアと同じなんですね。

田中絵里菜|朝日出版社
Photographed by Kaori Nishida
「利己的人間」を超える
Y 面白いですよね。とはいえ政治参画みたいな文脈ですと「社会をよくしていこう」といったある種の大義名分が立つので、そこに参画しやすいプラットフォームをつくろうという理屈が通るのはわかるのですが、ファンダムには、必ずしもそういった大義がないわけですよね。そこに「参加」という行動が生まれるのは不思議といえば不思議です。
W そこなんですよね。これまでの経済の考え方に立つと、人間というのは「利己的」な存在として定義されてきたと思うんです。
Y 私利私欲のために活動するものだという前提ですね。
W それってある程度は当たっているかもしれませんが、最初にお話しした「飽和」って結局は、そうした利己的な満足が飽和したということでもあると思うんです。そうしたなかでファンダムというものを見てみると、利己的な消費が極まって、自分でつくり始めちゃうわけですね。
Y 思い余って絵を描いたり、物語をつくってしまったり。
W そうですそうです。いてもたってもいられなくなって、とにかく名前を書いてみたり。自分も子どもの頃、中森明菜が好きでよく名前書いてましたが(笑)、そういう思い余った部分が生産へと人を駆り立てるわけですね。気分的には、仏像を彫るような行為に近い衝動なのではないかと思っていますが。
Y 運慶・快慶も仏師である前に熱心な阿弥陀信仰者であったとされていますし、まさに信仰と祈りですね。わたしは、広末涼子の名前を机に彫っていた気が……(笑)。最近の考古学の世界では、人は、便益のために道具をつくり出すよりも前に、装飾などの意味のために石器をつくっていたとも聞きますし、人間の根源的なモチベーションなのかもしれません。
W アイドルというものを字義通りにとれば、まさに偶像ですからね。何にせよ、そういった余剰な衝動の発露みたいなことがあり、かつその余剰が、同じような「祈り」で結ばれた同士たちの間で流通価値をもつようなことも起きるわけです。わたしは時折公式のマーチャンダイズではない「ファンマーチ」を買ったりするのですが、やはりファン同士ですと「好きなヤツがつくってるんだなあ」と一種の連帯感を抱いたりするわけです。おそらくつくった側も、自分の同士が買ってくれたといったような満足感もあるんだと思うんです。つまり、そこには、これまでの極めて物質的に理解されてきた「利己的な消費」というものとはまったく違う経済の動きがあり、ヘンリー・ジェンキンズさんは、ファンダムエコノミーのなかには、「伝統的な経済システム」のほかに、モラルエコノミー、ソーシャルエコノミー、ギフトエコノミー(贈与経済)が入り混じっていると語っておられますが、そこにファンダムエコノミーというもののひとつの大きな可能性があるように感じています。
Y 経済的な行為が単に経済行為として終わるのではなく、利他的な行動も含めた、もっと広い社会的な行為でもあるようなイメージですよね。伝統的な経済学ではうまく説明できなかった社会現象や経済行動を、心理学的な観点から読み解こうとした行動経済学的な視点の転換にも似ていますね。
W これはあるゲームジャーナリストがメタバースに関連して語っていたことなのですが、「没入感は、自分がどれだけコミュニティに貢献したかで決まる」というんですね。人が徹頭徹尾利己的なもので、結局は自分の利益や満足を最大化したいと思っていたとしても、そこにはおそらく他人に与えることで得られる満足や人に喜んでもらうことで得られる満足、あるいは自分が成長していくことで感じる満足といったこともあるわけでして、そうした部分を促進していくことで新しい経済モデルを構想しうるのではないか、というのがファンダムエコノミーの面白いところだと思うんです。ファンコミュニティ内部における、そうした「贈与」の循環がどのようにダイナミクスを生み出しているのかについては、ファンダムをフィールドに研究されている認知科学者の岡部大介先生が3章で詳細に語ってくださっています。
Y これまでの経済や消費の考え方とは異なる観点から新しい経済モデルの構想として「クリエイターエコノミー」と呼ばれるものがあるのだと思いますが、それはファンダムエコノミーとある意味表裏一体となったものだといえそうですね。
W そうですね。少なくともEpic Games、Roblox、Decentralandといった現状メタバースに近いといわれている企業がイメージしているのは、プラットフォーム上で消費されるコンテンツを参加者がつくっていくというモデルのはずでして、プラットフォームサイドにとっては、参加者がそのなかで「生産者」になるための機能やツールをどれだけ提供しうるかというところがキモになってくるのだと思います。
Y メタバースビジネスの本丸は、コンテンツ制作を可能にするレンダリングエンジンなどのデファクトの争いですもんね。こんなものをつくりたい、という欲求をどう叶えていくかという生産手段の民主化の意味では、ファンダムエコノミーは「広義のメイカームーブメント」ともいえそうです。それまでただのDIYとして趣味的な文脈で回収されてきたものが、ユニークなプロダクトをつくる製造業者として立ち現れた流れとも重なります。

PictureLux/The Hollywood Archive/Alamy Stock Photo
W そうした機能開発において一日の長があるのが、それこそK-POPのプラットフォームですし、中国のスーパーアプリだったりするわけですね。これは4章で陳暁夏代さんが詳細に語ってくださっていますが、やはり大事なのは、ユーザーのコンピテンシーの開発・発動をどれくらいダイナミックにできるかということなのだと思います。
Y そうなってくると、事業主体はもはや、ある価値を自分たちだけのものとして囲い込むことは不可能になりますよね。ファンに向けて素材を提供して、いかにそこにコミットしてもらうか、もっと言うと、いかに遊んでもらうかといった考え方へと転換しないといけないということになりますね。
W 最近とみに感じるのは、プロダクトというのはもはや目的ではなく、むしろきっかけに過ぎなくなっているということです。これはおそらくどんな人でも実感があると思いますが、わたしたちはもはや、一つひとつのプロダクトを見ているのではなく、どちらかというとそれをつくっている会社を見ているんだと思うんです。つまり、いま会社というものの最も重要な売り物は「会社そのもの」なんだと思うんです。それはビジネスにおいて株価こそが最重要であるという意味でもそうなのですが、一方のユーザー側からしても、それこそ社長や社員の一挙手一投足がソーシャルメディアで炎上してしまうように、会社の思想信条や社会的なスタンスやセンスといったことのほうを、新商品の良し悪しよりも重視するようになっているわけで、その観点からすると、商品は会社のファンになってもらう「きっかけ」でしかない、という状況が起きているのだと思います。そういう意味でも、プロダクト至上主義という考え方は、どこかで手放さなくてはならなくなっているように感じます。
Y 「UX」(ユーザーエクスペリエンス)ということばが象徴しているのは、まさにビジネスのキモが、商品そのものではなく、それを通して得られる「体験」へと移行しているということで、これはまさに「サービス・ドミナント・ロジック」において語られていることです。プロダクトやサービスそのものに絶対的な価値があるという思想でこれまでやってきたところから、むしろそれらはただのコミュニケーションツールであって、それを介して価値を共創していく関係をどうつくることができるかというところへの移行が語られるのですが、本来的にはこれこそが「UX」の話なんですね。
W 特にデジタルサービスでいいますと、そこで重要になるのはユーザーの「属性データ」ではなく、むしろ「行動データ」でして、「体験」というものは実際のアクションを伴うものですから、それが「行動データ」として事業主体側に返ってくることが重要で、そのフィードバックを受けながら新しい機能やユーザビリティの開発を事業側が行っていくことになるわけですが、個人的には、ユーザー個人を「属性データ」から「行動データ」において認識・理解するということは、実は大きなパラダイムシフトであるような気がしています。
Y 「わたし」というものを、静的な情報の羅列から、動的な行動の軌跡において捉えるようになるということですもんね。コクヨ野外学習センターとして一緒に制作した『働くことの人類学』という本のなかで、文化人類学者の小川さやかさんがしてくださった、「社会情勢が不安定なアフリカにおける個人信用の概念は、職業や資産という固有のもので規定されるのではなく、状況によって揺れ動いている」という話を思い出します。
W 時間のなかで人は変化するといったことを静的な「属性データ」は捉えられなかったわけですが、ある人が朝と夜とではまったく違う傾向をもっていたとしても、「行動データ」としてみれば一貫性がなくても一向に構わないわけですし、むしろ、人は常に動いていて一貫性なんてないのが当たり前ということが明らかになるのであれば、それは、いわゆる近代個人主義が前提としてきた「個人」というものの認識を変えてしまうような気さえします。
Y ファン経済のなかにおいては、同じ人のなかで、消費者であることと生産者であることが時に応じてクルクルと変わって多義的になっていき、その時々で見え隠れする個人のもつキャラクターが「分人的」になっていくわけですね。
W そうやって考えていくと逆に、個人は一貫性がないといけないとか、つくる人とユーザーは明確に分かれていないといけないといった、これまでわたしたちが当たり前だと思ってきたことが、むしろ「なんでそうなってたんだっけ?」と思えてもくるんですね。例えばビジネスにおいても、価格を決めるのは一元的に生産者であって、消費者は言われるがままにそれを買うしかなく、しかも、生産者が決めた通りのやり方でしか消費もできなかったわけですが、それっていったいいつから当たり前なのかなと考えると、おそらく結構最近のことなんだと思うんです。
Y そうですね。価格を値切ったりするような空間はいまやほとんどないですし、つくったものを好き勝手に改造したりする自由も、どんどん失われてきましたよね。著作権を戦略的にコントロールして円滑な流通をサポートするクリエイティブ・コモンズも、そうした問題意識からのように思います。最近ようやく欧州を中心に、サステナビリティの文脈からフィジカルなものについても「修理する権利」といった考え方がクローズアップされるようになりましたが、ファンダムという観点からも影響は大きそうです。
「資本主義」を超える
W これは人に教えてもらったことですが、ファンダムエコノミーを考える上で「コミケ」というもののありようは極めて示唆に富んでいるというんですね。わたしが聞いたところ、コミケという空間においては、生産者と消費者という区分はなく、また「販売」ということばではなく「頒布」ということばが使用されるそうなのですが、その背景にあるのは「ものに価値が発生するためには、ものをつくる人と、そこに価値を見いだす人が必要だ」という発想なのだそうです。
Y つまり「価値」というものは、ものをつくる人とその価値を発見する人との相補的な関係性があって初めて成立する、と。確かに自分でつくったものに値段をつけたところで、買い手がいなければ価値があることにはなりませんよね。
W まさにそうなんです。つまりそこでは、「価値を発見する人」が「ものをつくる人」と対等な関係性にあるということで、そこではお互いが等しく「商人」であると見なされることになっているそうです。
Y まさにマーケットの原初的な姿ですね。
W このことを教えてくれた知人は、そうしたマーケットの原初的な姿はシリアのアレッポに見ることができると、黒田美代子さんという研究者が書かれた『商人たちの共和国:世界最古のスーク、アレッポ』を教えてくれたのですが、この本で面白いなと思ったのは、アレッポの商人たちは「定価」という概念を非常に強く警戒し、それが「専制」をもたらすものと見なしているということです。

DE AGOSTINI PICTURE LIBRARY via Getty Images
Y 面白いですね。価格が一種のヒエラルキーを生み出すと。
W ここでの論点は、「一物一価」、同じものが同じ値段で売られることによって「貨幣による専制」が起きるということでして、「定価」の概念が取引を効率化し経済活動を増大させたとはいえ、その一方で、「定価」と「ものの価値」の間にギャップが生まれていくことにもなり、さらに問題なのは、そこから「人」が排除されていくというところだとされています。
Y 「誰が売っているか」は問題ではなくなり、商取引が、ただ「もの」と「お金」だけの関係性になっていくということですね。
W そうなんです。シリアのバザールにおいては、基本単位が商人という「人」であることがとても重要で、いったんバザールのなかに入ると、そこでは資本の多い少ないは関係なく対等の存在として扱われることが原則なのだそうです。それを「定価」という考え方は、資本が多い商人に有利なように変えてしまうわけですね。
Y それこそ『働くことの人類学』で文化人類学者の中川理さんが、南フランスの小規模のズッキーニ農家の人たちの間では市場というものと資本主義というものが明確に線引きされていて、彼らにとって市場はいいものとして考えられているというお話をされていました。「市場は小さきものの味方だ」と彼らは感じているとおっしゃっていましたが、まさに市場/マーケット/バザールにおいては、すべての商人が対等の立場であることがとても重要で、逆に資本主義、あるいは「定価」に基づいた経済は、その原則を破壊してしまうんですね。
W わたしも中川さんのそのエピソードは大好きなのですが、その話に照らして考えていくと、クリエイターエコノミー/ファンダムエコノミーにおいて最も重要なのは、そこにいかに活気のある「市場」と「商人世界」を再興できるのか、というところであるように感じるんです。
Y インターネットが本来可能にするはずだったのは、そうした活気と弾力性のある「マーケットプレイス」だったわけですよね。ピア・ツー・ピアで直接取引ができて、ショバ代は払うにしても、大きな企業が担ってきた中抜きをするミドルマンが要らなくなるという。
W そうなんです。それがなぜここまで実現されてこなかったのかは、本書の2章でクリエイターエコノミーの主導者のひとりであるベンチャーキャピタリストのリ・ジンさんが語られていますが、彼女が構想するWeb3の経済モデルは、まさに「原初のマーケット」がブロックチェーンによって下支えされたようなイメージなんですね。
Y メルカリやヤフオクといった中古マーケットプレイスでは、そうした「市場」性が強く発動しているように思いますが、ファンダムの二次創作市場なども、今後はそれこそNFTといった新技術を用いて発展していくことにもなりそうです。
W それこそaespaやNCTといったグループを抱えることで知られるK-POPの雄、SMエンターテインメントは、NFTを用いた二次創作流通を手がけるべくブロックチェーン企業と提携したそうですが、今後どんどんそういうものが出てきそうです。
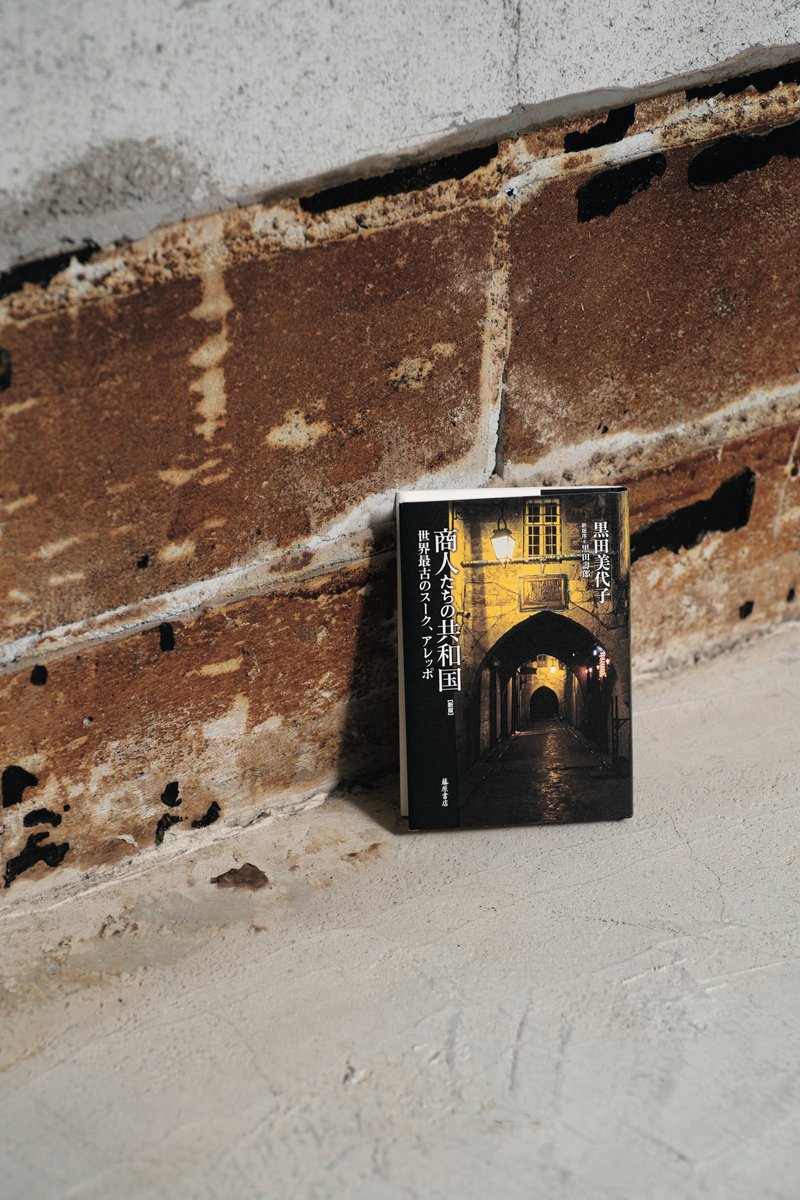
黒田美代子|藤原書店
Photographed by Kaori Nishida
「国家」を超える?
Y そうやってあらゆる領域において、それぞれのコミュニティ内で小規模な流通が加速していき、個人が商人として遊動するというイメージはワクワクするところはあるものの、とはいえ、それがどんどん社会を分断し細切れにしてしまうということも起きそうですね。
W そうなんですよね。BTSのファンダムがいかに巨大なものであっても、それを知らずに生きていくことはおそらくできるはずですし、わたしはアニメやゲームにはまったく疎いのですが、そこに超巨大なファンダムがあったとしても、その存在を知ることもなく過ごすことはできてしまうわけです。また一方で、例えば白人至上主義の過激派やQAnonのような組織でも、その動員や活動のやり方においてはそれこそBTSのファンダムとまったく同じ手法が使われていたりしますので、テクノロジーの民主化が、そのまま自明のものとして民主主義的な価値観に紐づくわけでもありません。政治運動などがファンダムによって推進されるのは、グレタ・トゥーンベリさんの活動やBTS Armyによるアメリカ大統領選への介入からトランプ大統領の選挙戦やアメリカの連邦議会議事堂の襲撃などでも見た通りですので、局地的なファンダムが無数にある状態が、そのまま社会の分断の反映にもなるということは、十分に想定されることかと思います。
Y なかなか悩ましい。どちらに転ぶにしても、ある先鋭的な価値に従って活動がアクセラレートされるわけですね。そうした分断は乗り越えられるんでしょうかね?
W どうでしょうね。逆に、分断がないように見えていた状態が何によってもたらされていたかといえば、テレビやラジオ、新聞といったマスメディアによってだったと思いますし、それが「国民」という概念を強固に束ねていたわけですが、マスメディアというものが今後どのように存続しうるのかはよくわからないものの、かつてのように「みんな」を一元的に束ねることができなくなっていくことは確実でしょうから、このまま一種の「中世化」が進むのか、それとも、いま一度国家が「ナショナル」なものを束ねるべくデジタルメディアをマスメディア的に管理するようになるのか、あるいはそうではない別の道があるのか、かなり大きな分岐点にあることは間違いないように感じます。
Y 難しいですね。『儀式は何の役に立つか:ゲーム理論のレッスン』のなかでゲーム理論の研究者マイケル・S-Y・チウェさんは、「人々がある事実を知る」という情報を共有することと、「『人々がその事実を知っている』ということを皆が知っている」という「共通知識」をもつことは、まったく別のことだと指摘しています。反戦デモのように、他の人びとも同じく行動するときに限って自分も行動したいと思うようないわゆる「協調問題」を解決するには、この共通知識がどれだけ流通するかが重要であり、マスメディアが担っていたことの社会的な再設計がまさに求められています。

マイケル・S-Y.チウェ|安田雪・訳|新曜社
Photographed by Kaori Nishida
W 『商人たちの共和国』の著者の黒田さんは、アレッポの市場のなかに「醜い過度の集中を抑制する、節度ある叡智」があったと語られていまして、政治人類学者のピエール・クラストルのことばを引用して、そこに「国家に抗する社会」を見ることができる、と希望を込めて語っています。ジョン・フィスクさんが語っているように、ファンダムの本質が「産業の言いなりにはならない」ところにあったのだとすると、それはマスメディアがもたらすコンテンツを利用しながらも、メディア産業による集中管理に、ある意味抗う運動だったともいえるわけでして、それはおそらく「国家」というものに対しても、同じ構え/スタンスを取るものでもありそうです。
Y ファンダムの対義語は「国家」であると。中森明菜からついにここまで議論が来ました(笑)。
W いや、適当に言ってますが(笑)。ただ、それこそ、メディア論の大家であるピエール・レヴィが『ポストメディア人類学に向けて:集合的知性』という本のなかで語っているように、デジタル技術のなかにあらゆるメディアが融合(コンヴァージェンス)していく環境が「文書」に基づいた文明社会のあり方を決定的に変えてしまうのだとすれば、わたしたちが「文書」に基づいた世界観のなかでものごとを考えているうちは、何をどう考えたところで未来の姿を描くことはできないような気がします。メタバースなんていうのはそうしたコンヴァージェンスの最たるもので、まさに「ドキュメント」ベースの世界からの離脱を意味するのでしょうけれど、それが本当に何をもたらすのかは、わたしたちが文書的に考えているうちは思い描けないのではないかと思うんです。
Y そうですね。文書の終焉は、まさにリテラシーの終焉なのでしょうし、近代的な個人というものの終焉をも意味しそうですが、それが何を意味するかは、まるで想像できないですね。
W 話がでかすぎますよね(笑)。というわけで、本書は、そこに行く手前の話として、今後の社会における経済活動の新しいモデルというところに話を限定して「ファンダムエコノミー」をお題としたわけです。
Y それはもうすでに起きている話ですしね。
W はい。というわけで。
Y どうぞ本書をお楽しみください。

Vinnie Zuffante/Michael Ochs Archives/Getty Images
* * *
山下正太郎|Shotaro Yamashita
コクヨ野外学習センター センター長/コクヨ ワークスタイル研究所所長。コクヨ株式会社に入社後、コンサルティング業務に従事。2011 年、グローバルな働き方とオフィス環境のメディア『WORKSIGHT』を創刊。同年、未来の働き方を考える研究機関「WORKSIGHT LAB.」(現ワークスタイル研究所)を立ち上げる。2019年より、京都工芸繊維大学特任准教授を兼任。2020年、キュレーションニュースレター『MeThreee』創刊。2022 年、コクヨヨコク研究所を開設。主著に『WORKSIGHT 2011-2021: Way of Work, Spaces for Work』(2021)。
若林恵|Kei Wakabayashi
コクヨ野外学習センター・キャプテン/黒鳥社コンテンツディレクター。平凡社『月刊太陽』編集部を経て 2000年にフリー編集者として独立。2012年に『WIRED』日本版編集長就任、2017年退任。2018年、黒鳥社設立。著書『さよなら未来』(岩 波書店・2018年4月刊行)、責任編集『次世代ガバメント 小さくて大きい政府のつくり方』、『週刊だえん問答』など。「こんにちは未来」「blkswn jukebox」「音読ブラックスワン」などのポッドキャストの企画制作でも知られる。
* * *
『ファンダムエコノミー入門
BTSから、クリエイターエコノミー、メタバースまで』

『ファンダムエコノミー入門
BTSから、クリエイターエコノミー、メタバースまで』
ファンダム研究の第一人者からシリコンバレーのトップVC、認知科学者、中国エンタメビジネスやUXのエキスパートなどを迎え、トレッキー、デッドヘッズ、BTS Armyから、クリエイターエコノミー、Web3、NFT、メタバースまでを縦横無尽に読み解く全ビジネスパーソン必読の入門書。
◉書籍の購入はこちらから
【目次】
#0 ファンダムは◯◯を超える|対談 山下正太郎+若林恵
#1 ファンダムエコノミー入門|ヘンリー・ジェンキンズとの対話
#2 Web3ルネッサンスとクリエイター/ファンダムの経済|リ・ジン
#3 ファンダム経済は「ギブ」でまわる|岡部大介
#4 中国の音楽アプリにみるクリエイターエコノミーのつくりかた|陳暁夏代
#bookguide ファンダムを読む
#5 贈与経済のためのUX|藤井保文との対話
#6 メタバースのなかのリテール|ダグ・スティーブンス
#7 ファンダムの文化経済|ジョン・フィスク
【書籍情報】
書名:ファンダムエコノミー入門 BTS から、クリエイターエコノミー、メタバースまで
編者:コクヨ野外学習センター
編集:山下正太郎(コクヨ ワークスタイル研究所)、若林恵(黒鳥社)
アートディレクション・デザイン:藤田裕美
定価:1980円
発売日:2022年6月15日(水)
発行:黒鳥社
発売:プレジデント社
◉書籍の購入はこちらから






