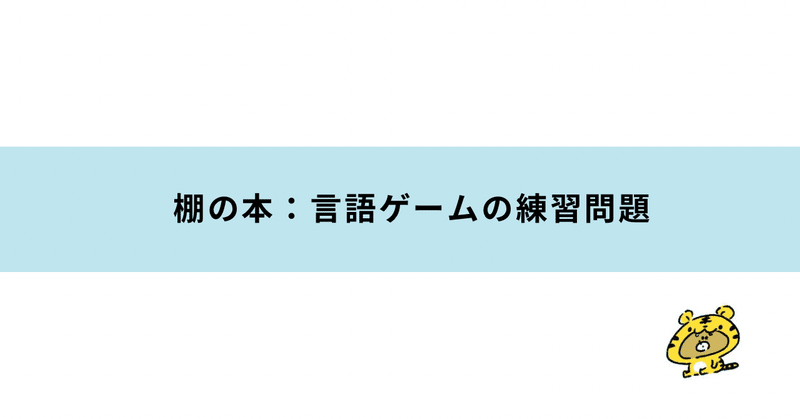
棚の本:言語ゲームの練習問題
ヴィトゲンシュタインの哲学を、36の練習問題を通して考えます。
くまとら便り
本書は、東工大の学部4年生向けの「理論社会学」の配布原稿が元になっています(「おわりに」参照)。
平易な言葉と練習問題で、言葉とは、言語ゲームとは何かが明かされます。
1.1 言葉が平易だからといって、内容が平易だとは限らない。
前半には、地球人のなかに宇宙人が紛れている場合、見分けることができるか、という変な問題が出てきます(宇宙人は外見やふるまいも変わらず、言葉も通じます)。
この問題は、正直、よく意味が分からず、若干スルー気味でしたが、1週間程して、ひゃっとなりました。
バーチャル空間にいる人びとのなかにAIが紛れ込んでいたら、見分けることができるのか、という問題と同じ?と。
もしや、これは今どきの重要問題ではないかしら。
哲学は、当たり前を疑う学問ですので、本書では椅子とは何か、普通名詞とは何か、も考えます。
少数の椅子を見せて、イスという言葉を教えるとき、子どもは、次のことを理解します。
(1)この世界のモノは、椅子であるか、椅子でないか、どちらかである。 (2)自分は、それを識別できる。
(3)イスという言葉は、すべての椅子をよぶことができる。すべての椅子でないものは、よぶことができない。
ごく僅かな有限の事例から、際限のない事例にあてはまるルールを学ぶ。不思議な知能の本質です。
それから、固有名、人称詞も考えます。
固有名を用いるとき、人びとが知っているのは、その個物がどのように固有であるかの詳細(確定記述のたぐい)ではない。その個物が、ほかのものと置き換えがきかないことだけである。
人称詞を用いて表現できるのは、たとえば、意思である。
人称詞には、話し手からみた世界を表現するという利点がある。
ローランドの「俺か、俺以外か」という言葉も、深淵に思えてきます。
世界は、ローランドか、ローランドでないかのどちらかであり、ローランドについて詳しいことは知らないけれど、彼は置き換えがきかない。
ローランドが「俺か、俺以外か」と言うとき、彼から見た世界には、おそらく対象の女性がおり、彼女に向けられた意思が存在する。
椅子とローランドで、どこまでも深淵になれます。
後半は、言語ゲームの世界が広がっていきます。
言語ゲームとは、人々の一致したふるまいのこと。
本書によれば、私たちは、社会に順番に生まれてやってきて、始まりも終わりもない言語ゲームをするのだそうです。
どこから読むのがよさそうか
3「宇宙人を見分ける」の「なぜ、言語ゲームか」、後半の7「ゲームとルール」から14「確実性について」までを先に読んでもいいかもしれません。
ヴィトゲンシュタインの言語ゲームの面白さが濃縮されていました。
言語ゲームのルールはどこに存在するのか、私的言語、自己言及、相対主義や懐疑論など、盛りだくさんです。
本書とは、ほぼ無関係なこと
「ポスター貼るな」というポスターや、「この命題は嘘である」という命題、「私は嘘つき」という発言、「この文は偽物である」という文は、自己言及のパラドックスといわれます。
私は嘘つきという発言が真だとすると、その発言も嘘、つまり私は正直だという結論になり、私は嘘つきという前提と矛盾します。
私は嘘つきという発言が偽だとすると、私は正直であり、その発言も本当であり、私は嘘つきという結論になり、やはり前提と結論が矛盾します。
この発言は、真であるとも偽であるとも言うことができません。
自己言及的な命題は、真でもなく偽でもないのです。
真偽が判定不能の命題があるというのは、数学の不完全性定理でも証明されているそうです(文系のため、伝聞調です)。
時折インタビューなどで、小説家が「ほんとうのことを書きたい」と発言されることがあります。
真実、真理、美を表現したい。
芸術を志す人であれば、おそらく誰しも一度ならず思うことです。
ただ、考えてみれば、小説は、作家が構想し、想像し、創作した物語です。読者も、小説を創作された物語だと分かって読んでいます。
小説家を名乗ることは「私は嘘つき」だと言うことと同じような性質を帯びており、小説もまた「この文は偽物である」という文と同じような性質を帯びている、とも言えそうです。
自己言及のパラドックス。真偽が判定不能の命題。
哲学と数学が明らかにした限界です。
小説家の「ほんとうのことを書きたい」という発言は、その明らかな限界を超えたいという、想像を絶するほどの、切実な心の叫び、なのかもしれません。※
それでは、また。
『語りえぬことについては、沈黙しなければならぬ。』
※もう少し妄想してみると、自己言及的な命題は、同時に真でも偽でもあり、可能性にみちている、とはいえないのでしょうか。
そして、読者が、小説の可能性を観測してはじめてその真偽が決まり、「ほんとうのことを書きたい」という小説家の意図は、幾分かは観測結果に影響するのではないかな、と思うのです。
ーと、語りえないことを、語ってしまいました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
