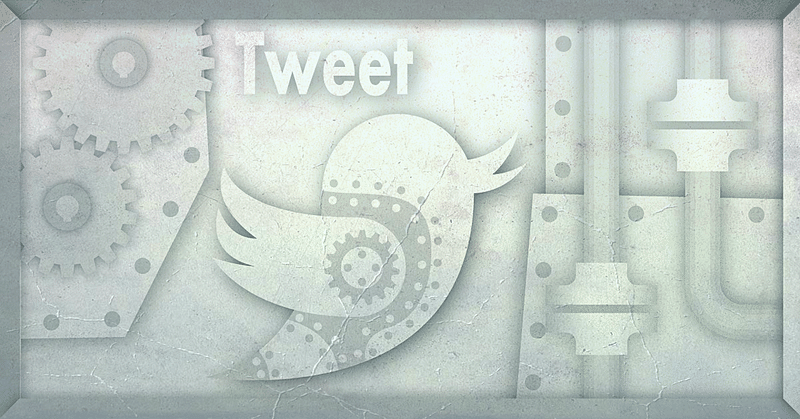
Twitterをやめたこと
きょう、夏に書いた短編の改稿を終えた。世に出すあてはなくて、友だち数人に読んでもらうだけかもしれない。それで構わない、と今年ぼくはおもうことにした。この小説を書いているときに考えていたのはそれだ。物書きとして生きようとする努力と、生涯にわたって小説を考え続けることは根本的にちがっていて、ぼくはいま、なにをおもいなにを考えて小説を続けているのか。この小説は50枚程度しかない短編だけど、生きようとするほどにズレていく小説との関わりかたを見つめ直すためにもきっと時間をかけなければならなかった。そんな気がする。
小説を書きはじめた10年前から、考えかたはかなり変わった。
小説投稿サイトで短編を公開していた当時、「ウケる」ことがぼくにとって大切だった。読んでもらって、おもしろいといってもらって、それからぼくやぼくじゃないひとの小説についてあれこれいったりするのがたのしかった。友だちとのやりとりをかさね、多くの作品を読み、小説のことを知っていくなかで、表現的な目的を持つようになった。それまでは主題やメッセージのような、「意味」を伝えることがすべての文章表現の絶対的なルールだとおもっていたけれど、ことばはもっと絵の具のように使ってもいいんだと知った。意味を伝えるために整備された起承転結などの構造や、文法を踏み越えた文章表現が機能しうる場所がある。その場所がどういうところで、どうすればそれを見つけ出せるのか。
ぼくの興味はそこへと移っていった。一定の長さを持つ散文表現が、それの内部だけで駆動する特有の因果律を持つとき、ぼくはもっとも詩情をかんじる。この詩情について考えると、それまで大学で研究していた自然科学について漠然と抱いていたこととの一致が見えた。このころあたりから、自作のなかで積極的に数学や物理のことを書くようになった。読み手は離れた。しかし、新たな読み手ができて、それがいまでも仲良くしている友だちになっている。
会社を辞めて仕事として文章をするようになり、複数の幸運によって「大滝瓶太」として賞を貰ったり寄稿機会をいただいたりするなか、いつも抱いていたのは「今月はどうやって稼げばいいんだろう」という現実的な問題だった。生活をするために書いている文章は「大滝瓶太」として求められる文章とはまったくちがっていて、じゃあ「大滝瓶太」がWEBメディアや文芸誌に求められているかといわれればそれもちがう。ライターとしての生活のしんどさについては別の記事でも書いたけれど、このしんどさは「大滝瓶太」としてやっていることを全否定する感情を自身のなかに芽生えさせる程度には精神的につらい。「大滝瓶太」に仕事がないことはひとえにぼくの力不足でしかないのだけれど、膨大な時間と労力を注ぎ込んで書いたものが内職として書いたものの数十分の一程度のお金にしかなっていないことに無神経でいられるほど、世間離れをしていなかった。
Twitterは、すこしでも「大滝瓶太」の名前を知ってもらうためにやろうとおもった。もともとTwitterでボケをかましたりするのは好きだった。読んだ小説の感想をいってみたりもした。じっさいにそれによってぼくのことを知ってくれたというひともいて、これは素直にうれしかった。今年は特に、出かけるたびにぼくのことを知っているというひとに出会えた。みんな、「Twitterでよく見ます」といってくれた。
しかし、いま問題におもっているのはこのことだった。
ぼくはTwitterをやることで「Twitterのひと」になってしまっている。ぼくは出会うひとたちから、「大滝瓶太の小説を読んだ」といわれたことがなかった。トークイベントでも、ぼくがおなじく登壇するひとたちの書いたものについて話すことはあっても、ほかのひとがぼくの書いたものについてなにかを言ってくれることはない。ぼくが生活のために「大滝瓶太」の名前を売ろうとするほど「大滝瓶太の文章」は読まれなくなる。
この一年、一番苦しかったのはそれだ。
ぼくがいま辞めなければならないのは、生活のために「大滝瓶太」をすることだ。接する必要のないひとやことばをきちんと拒否することだ。仕事の件数や収入、どれくらいのひとがぼくの文章を読んでくれるかに関係なく、ぼくはきっと小説を書き続けるだろう。たとえ今後一作も世に出せなくても、ぼくは小説を書き続ける。それを受け入れたいとおもった。今後二度と小説を世に出せないという絶望を受け入れ、それでもなお小説を書き続けるという自信がほしい。そこで、それを脅かす最大の要素だったTwitterをやめることにした。文章表現をおこなう人間が、表現ではない文章でひとと出会うのはあまり良いことではない気がする。
頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。
