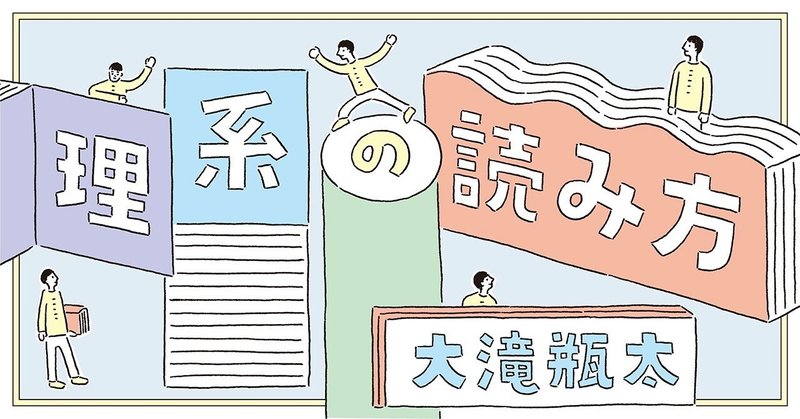
【#理系の読み方 第1回】小説を「解く」──カフカ作品をどう読むか? 前編
第1回で取り上げるのはフランツ・カフカです。
小説全般の話をするとき、ぼくは決まってカフカを最初に挙げるのですが理由はたくさんあります。まずカフカら現在活躍している世界中の小説家に影響を与えていますし、『変身』¹⁾はおそらく世界で最も有名な短編小説のひとつと言えます。さらに文章は平易で読みやすく、物語の筋は明瞭で、なによりとてもおもしろい。あまりにも有名な作家ゆえに敷居の高さを感じて敬遠しているひとも多いかもしれませんが、そういうひとはぜひ『変身』や『流刑地にて』という短編から読んでみてください。
ただ、「理系の読み方」を銘打った本連載で最初に取り上げるのには相応の理由があります。もちろんカフカ作品が理系と相性が良いという主張になるわけですが、その論点として今回は「小説を解く」ということを考えてみたいと思います。結論を言えば、カフカの小説は「解ける」ように書かれています。
1) 筆者が読んだのは高橋義孝訳の新潮文庫版である。
「小説を解く」とは?
そもそも「小説を解く」という概念はぼくの知る限りありません。
「読解」という言葉がありますが、これは「作者の意図を読み取る」ということを指していて、今回持ち出した「解く」とは異なります。小説に「答え」があるみたいな言い方をするとめちゃくちゃ怒られそうなのですが、まず準備したいのは「小説を解く」という概念の定義です。以降の連載でもこの概念を基礎に話を進めていきます。
「解く」という行為ですが、奇妙にこんがらがったなにかをスッキリさせるみたいなニュアンスを含みます。「問題を解く」にしても、与えられた問題のなかで複雑に絡み合った情報をほどいていった結果「解答」が得られるわけです。ここで大事なのは「解く」という行為で必要なのは「問題」ではないということです。より本質的²⁾なのは奇妙にこんがらがったものであり、それがときどき「問題」という実にわかりやすいかたちでぼくたちの目の前に差し出されているだけです。だいたいのことは複雑なかたちでそこらへんに転がっていますが、ぼくらはふだんそれを特に注意深く見たりはしません。視界に入ってはいても、それを「問題」として認識することはあまりありません。
「小説を解く」を定義する上で大事なのはここです。小説でもミステリなど特殊な分野では「謎(=問題)」がはっきりと提示されるものもありますが、そうでない他の多くの小説では読者に対する「出題」は行われません。ただ、そのように明示されはしなくても、読み応えのあるフィクションにはなんらかのかたちで異質と呼んで差し支えない複雑さが存在しています。
あえて少々乱暴に言いますが、すでに問題化された対象に解答を与えるのはただの作業でしかありません。問題なんて解けて当たり前なわけです。研究や表現では問題が明確になったあとは常套手段を駆使して時間と手間さえかければ何か出てきますが、肝心の「問題」は都合よく誰かが恵んでくれたりしないので大変です。
しかし、ある状況を与え、その中で登場人物を動かしていくと、見たことのない奇妙なことが起こります。「小説を解く」とは、この奇妙なことを発見し、視野に納め、ピントを合わせ、解像度を高めていく行為です。言い換えると、「問題未満」だった物事を「問題化」するために想像力をついやす行為です。そしておもしろいことに、これは作品に対して作者からだけでなく読者からも働きかけることができ、その場合は特に「批評」と呼ばれたりします。
2)この言葉ほど胡散臭いものはない。
シミュレーションとしてのカフカ作品
つまり「カフカは小説のなかに生じる奇妙な物事を問題化するのが異様にうまい作家」というのがぼくの主張です。あるいは読者に「問題化」させるのがうまいとも言えます。その具体的な話については、作品を実際に取り上げるのがいちばんわかりやすいでしょう。
そこで『変身』です。グレーゴル・ザムザが朝目覚めると自分が虫になっているのに気づいたという書き出しから、家族に厄介者扱いされ、部屋を出ることなく死に、その後彼の家族は幸せに暮らす……というのが超ざっくりした筋書きです。超現実的なシチュエーションから始まりますが、作品世界のリアリティに即した思考や行動が積み重ねられ、主人公は終始部屋のなかにいますが物語はテンポよく動いていきます。
ぼくがこの小説をはじめて読んだのは大学院生のときなのですが、「なんだか分子シミュレーション³⁾みたいな小説だな」というのが最初に出てきた感想でした。
この「分子シミュレーションみたい」というのが実はぼくにとってめちゃくちゃ重要で、もしカフカを読んでこんな感想を持てなかったら小説なんてさっさとやめていたかもしれません。それはさておき、当時ぼくが所属していた研究室では分子動力学シミュレーションというものをよく使っていました。これは数千個とか数万個とかそれなりにたくさんの分子を用意して、そのひとつひとつの運動方程式をコンピュータでガシガシ解くという数値シミュレーションです。量子効果を考慮しないケース⁴⁾では最もメジャーな分子シミュレーション手法のひとつです。
たとえばこんな状況を考えてみましょう。無限に広い空間⁵⁾にたくさんの気体分子を用意します。それらは空間中に一様に分布し平衡状態にありますが、ある時刻にある位置に特定の分子群を系外部から仕事をしてピンポイントで加熱するとします。その後、空間中の分子はどのような挙動を見せるでしょう?
外部からの加熱を受け、分子集団全体のエネルギーは上がりました。しかし加熱直後は特定の分子のみがエネルギーを注入された状態ですので、速度分布は平衡状態からズレていて、この状態を「非平衡」と言います。このズレの度合いが大きければ「強い非平衡」と言ったりもします。分子たちは周囲の分子とたくさん衝突してエネルギーを交換するのですが、その繰り返しを経て一部の分子だけが得たエネルギーは分子集団全体に広がり、やがて速度分布⁶⁾は平衡状態に収束します⁷⁾。これを「緩和」と言いますが、以上を考えるのがなんだかダルいなっていうひとは「雨降って地固まる」という言葉をとりあえず思い浮かべてください。
さて、上記の単純な分子シミュレーションと比べると『変身』はどんな小説に見えるでしょうか?
まず最初の「平凡な青年がある日突然虫になる」というのは日常から比べて「強い非平衡状態」に相当します。それから人間から虫になったグレーゴルがなんやかんやして家族との「衝突」があり、最終的に家族はグレーゴルがいない新たなかたちでの日常(=平衡状態)を獲得します。つまり、「強い非平衡状態から無数の衝突を経て平衡状態に遷移する」という緩和現象そのままに小説が進行していると読むことができます。
3) ある数式でモデル化された系について、逐次数値解を得ることで系の変化を仮想的に観察する研究手法を数値シミュレーションという。分子シミュレーションはその仲間で、所属していた研究室では分子動力学(MD:Molecular Dynamics)シミュレーションをよく使っていた。他の数値シミュレーション手法は数値流体力学(CFD:Computational Fluid Dynamics)シミュレーション、有限要素法(FEM:Finite Element Method)などがあり、森博嗣ミステリが好きな方はこのへんの名前は見たことがあるはず。
4) ニュートンの運動方程式を支配方程式とした物理学を古典物理学という。しかし、系のスケールがものすごく小さくなると物体の位置や運動量が確率的なものになる。これを不確定性原理といい、位置と運動量を運動方程式で一意的に求められるという理念を持つ古典物理学とは大きく性格が違うものとなっている。
5)しばしば宇宙は「無限に広い閉じた系」として解釈されるが、これは「外部とのエネルギーのやりとりを考慮しない」ためである。空間的に一様で無限に広い系は周期境界条件で表現される。
6)分子集団の速度の確率密度関数は速度分布と呼ばれ、平衡状態ではマクスウェル分布に収束する。
7)非平衡状態から平衡状態に戻るまでの時間を「緩和時間」と言い、物性値の近似などで用いる重要な値である。
「問題化」の技巧
ずいぶんと長い前置きになりましたが、熱力学や統計力学のシミュレーションでよくある問題と『変身』の感覚的な類似点を見つけ出すことができました。ここからは「それのなにがうれしいのか?⁸⁾」という話になります。ここでは前節の最後に提示した表を詳しく見ていきます。
先にも詳しく書きましたが、作品内で発生する奇妙なことや複雑なことはあくまでその世界の現実そのものであり、そのままの状態ではまだ問題化されていません。そしてその問題化は、小説を語る〈わたし〉なる概念⁹⁾や小説本文とまさに対面している読者の想像力と作用することで起こります。結晶化みたいなものでしょうか。なんかよくわからないドロっとしたものに一手間加えることでカチッとかたちを持つようになる。かたちになるとぼくらはなんとなくわかった気になりますが、このかたちが「意味」というやつです。
せっかくアナロジーが見つかったのですから、それにならって「グレーゴル・ザムザが虫になった」という物語を整理してみましょう。

まず最初にすべきは「系」の設定です。自然科学で頻繁に用いられる「系」という言葉は、ざっくりいうと考察対象を指し、英語では「system」です。ここではざっくりと「箱」のようなものがそれだとイメージしてください。
この箱を考えるとき、以下の3つに注意しましょう。
①蓋は閉じている?
②箱の中身は落ち着いている?
③箱の中身は時間変化する?
これによって目の前がどのような問題になりうるのかがより具体的になります。
①は「系外部との物質量やエネルギーのやりとりの有無」を問うていて、それぞれ「閉じた系/開いた系」と呼ばれます。これによって質量保存やエネルギー保存の扱いが変わってきますが、一般に「閉じた系」の方が単純な問題とされています¹⁰⁾。
②は平衡状態か非平衡状態かです。
例えば「温度」ですが、これは分子集団が平衡状態であることを仮定した状態量です。熱力学では温度の変化や熱エネルギーの移動を対象とすることが多いのですが、温度が定義できないのはかなり厄介なので、部分的に平衡状態を仮定して解くということも行われます。
対象の空間・時間のスケールや非平衡の度合いによりこうした仮定もうまくいかないこともあるのですが、このあたりの現象を詳しく調べるには
より微視的なアプローチ¹¹⁾が必要になります。
③は時間の扱いです。自然現象では時間によらず一定の状態が観測されることを「定常」と言い、そうでないときを「非定常」と言います。対象が定常であれば方程式から時間依存の項が落とせるのですが、これがかなりうれしい。たとえば流体力学ではナビエ–ストークス方程式¹²⁾を用いて流体がどんな運動をしているのかを分析しますが、時間によらず一定の流れをしている場合は時間で微分した項がゼロになります。するとバサバサと方程式を簡略化でき、単純なものだと手計算で解ける¹³⁾ようになります。
8)理系といえばこの一言である。
9)これは一人称小説の登場人物の〈わたし〉とはまったく異なる。詳細については『ことばとvol.5』(書肆侃侃房)掲載の拙論「『幽体離脱する「私」──「拡張された私小説」としての滝口悠生」を参照。
10)系の境界の扱いをどうするか問題はかなり重要で、どんな自然現象を扱うのかの解釈による。たとえば一様で無限に広い空間を想定している場合「右(上)に出て行った奴は左(下)から入ってくる」という周期的な処理をし、有限の大きさの閉じた箱を想定しているなら「壁に対して対称な速度に更新する」など粒子の反射を表現した処理をする。このように系の端っこをどう処理するかを事前に決めておく必要があるのだが、これが森博嗣ミステリの愛読者にはお馴染みの「境界条件」というやつである。
11)系の温度分布を計算するときに用いられる「熱拡散方程式」というものがある。これは局所平衡というものが仮定されており、具体的には系を構成する分子が瞬間的(=ゼロ時間で)にたくさん(=無限回)衝突することが前提になっていることに注意が必要だ。熱拡散方程式を数値的に解く際、系を小さなセルに分割して局所的なエネルギーの収支を計算するのだが、一般にセルは細かく切るほどシミュレーションの解像度は上昇する。しかし、セル分割を細かくするほど、「系を構成する分子が瞬間的にたくさん衝突する」という仮定が成立しなくなることがある。その目安となるのが「平均自由行程」と「セル分割サイズ」の比だ。平均自由行程とは、ある分子が別の分子と衝突してからまた別の分子と衝突するまでに移動できる距離を指すのだが、この距離を分子の平均速度で割ると「分子衝突の時間間隔」が得られる。「平均自由行程/セル分割サイズ」がゼロに近い場合、この時間をゼロと近似できるため局所平衡の仮定が破綻しない。まとめると、計算系を細かく切りすぎると「君が計算したものってそもそも〝温度〟と呼んでよいのですか?」といった質問が発生しうる。
12)巷でかわいいと噂されるコイツ(v⋅∇)vが出てくるのはあまりにも有名。元は流体に関する運動量保存則で、質量保存則である「連続の式」と合わせて与えられた初期条件・境界条件のもと数値的に解かれる。非常に複雑な方程式であり、その特徴的な解の振る舞いはいわゆる「カオス現象」の題材のひとつとして多くの数学者の興味を惹いている。なお「3次元ナビエ–ストークス方程式の解の存在と滑らかさ」についてはアメリカのクレイ数学研究所が2000年に設定したミレニアム懸賞問題のひとつにあげられている。
13) 進んだ注:大学院生のとき、よくかんたんな数理モデルを作って思考実験をしていた。ある日、指導教員のM先生が覗き込んできて「大滝くん、なんかおもしろそうだねぇ」と言って去っていったのだが、その翌日、筆者のデスクには「手計算で解けます」と付箋を貼られた先生の署名入りレポートが置かれていたのだった。
『変身』を解く
これを踏まえると、カフカの『変身』は、
①閉じた系
②非平衡
③非定常
の問題を扱った小説と読めそうです。家族という密室、なんの前触れもなく人間から虫に変身するという非現実的な事件、時事刻々と変わり続ける状況──ここまで整理ができて重要なのは「近似」という考え方です。
小説は原則的には有限の文字数で書かれていますので、有限の情報量しか扱えません。すべてを小説に書くことはできず、大なり小なり取捨選択されているのですが、これは近似に他なりません。それは単に「計算量を減らす」だけの行為ではありません。
なにかを切り落とすとは別のなにかを注視するということですので、そこには解釈が含まれています。それは非言語的でありながら、思想と呼んで差し支えない豊かな意味を持った表現です。小説であれば物語の設定だけでなく人称などの語りの形式もこれとまったく同じことが言えます。題材・設定・技法の選択は、世界を近似的に表現する行為ですが、それによって世界の解像度が落ちるわけじゃない。むしろ「なにを見ているか」「なにが見えないか」が顕在化され、世界をその作品固有の濃度で実感できます。この濃度こそがフィクション特有のリアリティだとぼくは思っています。
物語の中ではちょいちょい家の外のひとが見切れていますが、基本的に系が「家族」という箱に限定されているゆえに、『変身』は一風変わってはいても「家族小説」と読むことができます。そして「虫になった」という強い非平衡性により人間にとっての「当たり前」を前提とした記述が破綻します。
これは熱力学的巨視量を定義できない──局所平衡が仮定できない──のと同じではないかとぼくは考えています。
このせいでグレーゴルはどんな姿をしていて、体調はどんな感じで、なにをどう食べるのか? などをいちいち詳細に描写する必要が生まれたのですが、それはまぎれもなくこの小説だけで成立するリアリティです。なんでこんな気持ち悪い虫の相手をしなければならないのか? そもそもこいつはグレーゴルなのか? といったような嫌悪感は、細部の描写によって説得力が担保されています。常識的なものとしてあえて書く必要がなかったものを詳細に書いていかねばならないからこそ、その積み重ねによって異質さがどんどん強調されていき、家族との関係の変化──非定常な現象──がこの作品ならではのものになる。虫になったグレーゴルの生活のディテールがなければ、こうした家族像が結ばれるのは不可能だったのではないでしょうか。
この物語は、グレーゴルが虫になってから死ぬまでの物語であり、大切な家族の一員だったグレーゴルが疎ましい闖入者に「変身」する物語であり、ある家族が最初とは異なる家族に「変身」する物語です。このような読みかたは「グレーゴル・ザムザが虫になった」という奇妙で複雑な現象をどのようにモデル化するか──どのような近似を仮定するか──によって立ち上がります。
今回のテーマである「小説を解く」とは、ひとことで言えば読書感想文の書き方のようなものですが、もちろんそれは得られた解の唯一性を主張することではありません。注目しているのは「わたしはなぜこう読んだか」の「なぜ」の部分で、たぶんここはみんなちがっているほどおもしろい。おもしろい部分だからこそ、ここがよりクリアに見える読み方を習得できれば、より読書が楽しくなるのではないでしょうか?
ところで最初にカフカの小説は「解ける」ように書かれていると書きましたが、これは彼の作品は寓話的な想像力が軸になっているからではないかと考えています。
寓話を「世界のある一面をフィクションの力でモデリングしたもの」だと解釈すれば、まさに今回のようなアプローチで読みやすい作品になります。またカフカのおもしろいところは、こうした寓話的な隠喩を使うけれども、一定の結論に落とし込むような──つまりなにか特定の意味を主張するような──書き方がされていない点だと思っています。これは想像でしかないのですが、カフカは『変身』をほとんどなにも考えずに書いたのではないでしょうか? たしか一晩で書き上げて、翌朝興奮とともに妹に読み聞かせたという逸話があった気がしますが、カフカの小説にあるのは「現実」だけです。
ということで作家の意図と読み手の解釈の問題については次回、おなじくカフカの作品『城』を題材に考えてみましょう。
(第1回 終わり)
頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。
