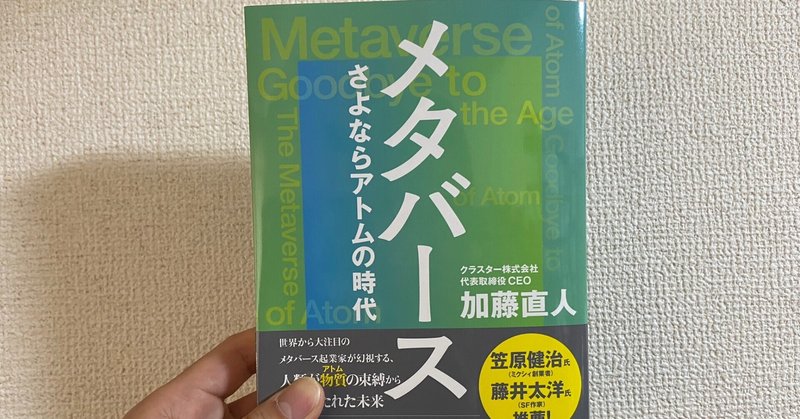
「身体性」と自己組織化/加藤直人『メタバース さよならアトムの時代』書評
SFの想像力とは、われわれが身をおく〝現実〟という世界で〝不可能〟とされる物事を科学技術によって実現可能なものにしてしまう力なのではないか。ぼくはそう考えている。そして作家はまず〝不可能〟へと思考を伸ばしていく──それは宇宙でありこの世界のなりたちであり、われわれ人間というものがどういう存在なのかであったりと、大きなテーマに行き着くことを余儀なくされる。
〝不可能〟が〝不可能〟であるゆえんは、対象の巨大さや抽象性ゆえかどうかはわからないけれど、そもそもまともに考えることじたいが〝不可能〟と思しきものへ向かう様は、それじたいがSFと呼びる行為に等しい。思考がなされる場を〝現実〟とするなら、究極的にはわれわれがそこに身をおいているかどうかは大した問題にならない。かつてSFと呼ばれた現実として生活する現在のわれわれは、過去のわれわれの想像力のなかに生きているのだとしたら、すべての時間を俯瞰する視点から眺めみれば〝拡張された現実〟に他ならない。いま、ここからの脱出が現実の射程を広げるのだ。
加藤直人『メタバース さよならアトムの時代』が扱うのは、そうした広義の現実世界だ。IT技術の発展とともに生活への寄与を大きくしつつあるヴァーチャル・リアリティの社会的実装についての本である、と紹介すると昨今書店でよく見かける本のなかに紛れてしまいそうだが、著者が提示する超域的な世界〈メタバース〉とそのなかに生まれうるエコシステムのありかたが、著者自身のバックグラウンドである物理学の感性に由来している点で個性的だ。メタバースを主軸としたビジネスシーンの解説から人類史におけるヴァーチャル・リアリティの位置づけに至る幅広い議題を、一貫した自然科学的思想でまとめた骨太な内容となっている。
本書で展開される議論の根幹となるのは、「身体性」と「自己組織化」だ。
「身体性」とは言わばわれわれの活動のメインフィールドがどこかという問題だ。現実世界とメタバースでは物理的身体の有無が大きな差異としてまず認識される。そして現在の一般的な価値観では物理的肉体ベースで判断され、メタバースをはじめとするヴァーチャル・リアリティは現実世界に従属するかたちになってしまう。物理的身体を有する現実世界の生活のためにメタバースがあるなら、そこに革命的な変化は訪れない。メタバース産業が目指すのは現実世界とヴァーチャル・リアリティの主従関係の逆転であり、ヴァーチャル・リアリティ固有の価値を創出することだと本書は説く。
「身体性」は人文学で頻繁に使用される言葉だが、本書ではその由来が自然化学的な文脈によって説明づけられ、そのために人類の科学史が簡潔に紹介されている。産業革命以降の200年は「モビリティ」の時代だったと著者は言う。物理学とは、いつどこにどんな状態でモノが存在しているかを計算する学問だ。そしてモノの移動の計算により、人類の生活様式は劇的に変化し、ひとやモノが世界を巡るようになった。その最小単位、つまり「原子(アトム)」が支配していた時代だった。
タイトルにもある「さよならアトム」とは、こうした物理的な拘束条件からの解放である。モビリティの時代ではどれだけ速く大量にモノを地点Aから地点Bに移動させるかが基本となる戦略で、それには同時に限界が避けがたく存在する。そしてその限界点で発想の転換が必要になってくる──モノが瞬時に移動できる世界という極限、つまり完全に情報化された空間での固有の体験やエコシステムがさらなる進化のために不可欠だ。この物理的な拘束条件から端を発する一連の問題が「身体性」である。
対して「自己組織化」とは20世紀後半に提唱された自然科学の概念で、全体を構成する個々が勝手気ままな振る舞いを見せながらも、結果として全体は秩序だった構造を持つという現象である。
全体として認識されうる構造は、それがどのように形成されたかによって意味が大きく異なってくる。たとえば建築物などは設計図が用意され、それに基づいて作られるのに対し、氷の結晶などは構成分子が集団として最もエネルギー的に安定となる状態として自発的に形成される。自己組織化の例として挙げられるのは後者であり、そこには設計図のようなものはなく、個体間に働く相互作用によっていわば〝勝手に〟形成される。
本書ではヴァーチャル・リアリティ産業における両者の違いを、MMORPGと比較することで明快に述べている。MMORPGでは、ゲーム内における人の集まりやイベントをサービス運営者が中央管理することで人為的に作っている。つまり管理側が想定していないことは起こり得ず、起こったとしたらそれはバグとして認識される。
一方で著者が構想するメタバースは、クリエイター・エコノミーの自己組織化に主眼をおいている。自己組織化の鍵となるのは自律的に活動する個体間の相互作用、つまり物理学でいうところの〝場〟の設計である。ある特定の集団やタイミングを選び施策を打つことでユーザーの活発化を促すのが方程式に補正項を加えることだとしたら、場の設計は支配方程式そのもののデザインで、似ているようでいて発想が大きく異なっているのがわかる。
「身体性」と「自己組織化」という2つのテーマに共通して見られるのは、著者の物理学的な感性だ。モビリティという産業特性の極限から「動かない」という時代を想起する着想、構造形成プロセスからユーザーのクリエイティビティに思考のメスを入れるその手つきはロジカルでスマートだ。
冒頭でぼくはSFの想像力を〝不可能〟という言葉を軸に説明をしたが、はたして〝不可能〟とはなんだろうか? 宇宙のはるか果てへと足を踏み入れること、生まれ持った身体とはまったくちがう身体を手に入れること、時間を超えた旅をすること──SFではさまざまな物理的拘束を超えた事象が扱われ続けてきた。いま一度この〝不可能〟を考えるなら、それは〝不可能〟とされるものを高い解像度で見つめる必要がある。それはこの先に行けばなにが起こるかという極限として現れ、時にそれは特異点と呼ばれる。SFの想像力は、そうした極限や特異点への対応として現れ、その方法にフィクション的な解決や現実的解決が含まれるだけで、その差というのは思っているほど重要なものではないかもしれないとさえぼくは思えてくる。現実に実装可能なものが実装され、実装不可能なものはフィクションという別空間に実装される。それはむかしのSFを時を経て現実が追い越しても依然としてセンス・オブ・ワンダーを失わない所以でもあるだろう。
本書は徹底して現実のことが書かれている。そして同時にSF的なセンス・オブ・ワンダーにも満ちている。この両義性が著者の描くメタバース世界を〝仮想現実〟ではない〝広義の現実〟としているのだ。
頂いたご支援は、コラムや実作・翻訳の執筆のための書籍費や取材・打ち合わせなどの経費として使わせていただきます。
