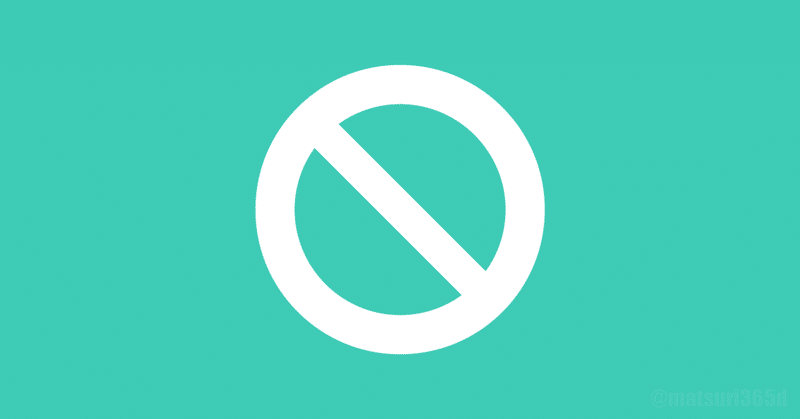
画像の二次利用に配慮を求める美術館 美術と著作権について知っておきたいこと(3)
黄色い《モナ・リザ》問題?
レオナルドの《モナ・リザ》には複数のバージョンがあるのをご存じだろうか。もちろん現実に存在するあの《モナ・リザ》はこの世に一枚しかない。しかし、それをデジタル化した複製画像には、これまでルーヴル美術館が公開してきた画像でも少なくとも3つある(実際にはもっとあるだろう)。

左が2010年の時点でルーブルが公開していた高精細な複製、 真ん中が少なくとも2017年から現在までルーブルが公開中の高精細な複製、右がコレクションページで現在公開しており、ダウンロード可能になっている中サイズ程度の複製画像だ。
見比べてみると、色の鮮やかさや画面の明るさなど、同じ絵画であっても印象がかなり異なっていることがわかる。
ルーヴルが公開したこれらの画像でさえ品質にばらつきがあるのだから、ネット上に溢れている《モナ・リザ》の画像には膨大なヴァリエーションがあり、品質も低いであろうことは想像がつく。たとえばフリー百科事典のWikipediaでは、先ほどの3つの画像とはまた違った画像が採用されている。
おそらく《モナ・リザ》のデジタル画像として世界で一番知られているのはこの画像の方ではないかと思う(Googleで「モナ・リザ」と検索すると、この画像が先頭に出てくる)。


この画像は、実はフランス美術館修復研究センター(C2RMF)が2011年時点で公開していた高精細な画像を、有志のユーザーが画像編集ソフトで色調補正したものだ。つまり公的機関が公開したデータをもとにしてはいるが、それを一般人が加工したものであり、データの信頼性は低いと言わざるを得ない(そもそも元のデータが全体的に暗すぎて鑑賞に堪えないのだが)。
私は《モナ・リザ》の実物を見たことはないが、先ほどの3つの画像と比べるとウィキペディアの画像は全体的に黄色が強すぎるような感じがする。
そこで、おそらくルーヴルが公開している画像のほうが実際の色に近いだろうと思い、日本語版の記事はルーヴルが公開した画像(3つのうち左)に私が差えておいた。差し替えにいまのところ反対する人がいないので、このまま変化がなければ日本のネット空間における《モナ・リザ》は差し替えたルーブルの画像のほうが今後主流になっていくはずだ。
影響力をもつWikimedia Commons
ここ20年ほどでネット環境が普及し誰でもいろんな情報に手軽にアクセスできるようになってから、デジタル画像を通して芸術作品に触れる機会も格段に増えてきている。だが《モナ・リザ》の例のように実物の色味をちゃんと再現できているのか怪しい画像を通してその作品に触れてしまう機会もまた多い。
ネット上で流通している芸術作品の低品質な複製画像に対策をしなければならないと提起するのは、欧州各国の文化施設が参加するデジタルプラットフォームのヨーロピアナ(Europeana)だ。
2011年に公開した白書「黄色い《牛乳を注ぐ女》問題(The Problem of the Yellow Milkmaid)」は、そのタイトルがネット上の低品質な画像の流通によって作品のイメージが損なわれてしまった事件をもとにしている。そのような事態を避けるためには作品の正確な複製データの積極的なオープンアクセス化が有効な対策だと主張している。
Wikipediaの黄色い《モナ・リザ》の例からさらに付け加えるとすれば、WikipediaやGoogle、TwitterといったSNSなどネット上で情報の流通を担っている大手サイトにおいて、ユーザーが所蔵館によってオープン化されたデータをちゃんと利用することで芸術作品とその正確な複製とを関連付けて流通させる努力も必要になってくるということも言えるのではないか。
ところでWikipediaの記事で使用されている画像や音声ファイルなどのデータは、Wikimedia Commonsというサイトにアップロードされたものを転載するかたちをとっている。
Wikimedia Commonsは「誰でも自由に利用できる画像・音声・動画、その他あらゆる情報を包括し供給する」ことを目的に2004年から始まったWikipediaの姉妹プロジェクトだ(Wikipediaは2001年から開始)。たまにどちらもWikipediaのサービスと思っている人がいて画像の出典をWikipediaと書いてしまっているのを見るが、両者は相互補完的ではあってもあくまで別のプロジェクトだ。
Wikimedia Commonsの方針によればファイルのアップロードは教育的に利用できないプライベートな写真や宣伝目的の写真などの適切でない画像ファイルを除いて各国の著作権法等の法律に違反しない限りで認められている。そのルールさえ守っていればファイルが削除されることはない。画像をアップロードする際には適切なライセンスの設定が求められ、その範囲であらゆる人々が画像を自由に利用することができる。
最近ではWikimedia Commonsから画像を転載している書籍もよく見かけるようになってきた。今年刊行された『「山田五郎 オトナの教養講座」 世界一やばい西洋絵画の見方入門』(宝島社、2022年)は、画像の出典は書かれていないがあきらかにWikimedia Commonsから転載した画像をカラー図版で大きく掲載している。
この本は「山田五郎オトナの教養講座」という現在約47万人の登録者がいる人気のYouTubeチャンネルを書籍化したものだ。書籍の冒頭を飾る《モナ・リザ》の解説には、先ほど示したWikipediaの画像を動画と書籍の両方で使用している。Wikimedia Commonsの画像を使って動画を作成するのと同じ要領で書籍にも画像を使用したのだろう。なお同チャンネルでピカソや藤田嗣治など著作権がまだ有効な作家を取り上げた動画では、スパチャ(投げ銭)をライセンス料の支払いに充てていることを明記している。
この本以外にも、Wikimedia Commonsの画像を利用している書籍には、最近刊行されたものでも清水晶子『フェミニズムってなんですか?』 (文春新書、2021年)や今野元『ドイツ・ナショナリズム』(中公新書、2022年)があった。今後もこうした書籍は増えていくだろう。

画像利用をめぐる混乱
書籍でも利用されるような大きな影響力をもつWikimedia Commonsは、まだまだ品質向上の余地がある。
そして、品質向上のためには図録や画集などからスキャンした画像や素人による写真などの低品質な画像から、美術館などの公的機関が公開している画像へと更新していく必要があるのだが、話はそれほど単純ではない。美術館の中には、画像利用に様々な制限を加えることでその流通をコントロールしようとしている施設もあるからだ。
美術品の複製画像には様々な権利関係がある。わたしたちのような一般人はひとまず著作権法だけ気にして画像を利用すればいいわけだが、著作権に限らずもっと広い意味合いで作品の所有者や複製作成者の権利意識のようなものもあるため、美術品のデジタル画像の取り扱いにはいまだに混乱がみられる。
Wikimedia Commonsに美術品の複製画像をアップロードする行為やアップロードされたものを使用する行為は、たとえ著作権法などに照らして問題がなかったとしても、かならずしも歓迎されているわけではないかもしれないのだ。ときには所蔵品の画像データの流通をコントロールしたいと考える美術館と、パブリックドメインとなった芸術作品は誰もが自由に利用できるようになるべきだと考えるWikimedia Commonsの理念が衝突してしまうこともある。
2009年にイギリスの国立肖像画美術館(ナショナル・ポートレート・ギャラリー)がウィキメディア財団に対し、ユーザーによってWikimedia Commonsにアップロードされた3,300枚におよぶ所蔵品の画像を削除するように警告した。画像には撮影者の著作権が存在するため、それをアップロードする行為は権利侵害であるというのが主な主張だった。
この主張にはイギリス特有の事情がある。島田真琴『アート・ロー入門:美術品にかかわる法律の知識』(慶應義塾大学出版会、2021)によれば、イギリスでは日本やアメリカとは違って平面作品を正面から撮影した画像にも著作権を認める判例があり、国立肖像画美術館もこの見解に従って著作権侵害を主張したという。ややこしいのは、画像をアップロードしたのがアメリカ在住のユーザーであり、アメリカに住む人間をイギリスの法律で裁くことは難しかったことだ。
最終的に国立肖像画美術館とウィキメディア財団は和解に至り、訴訟にまで発展することはなかった。ウィキメディア財団は画像ファイルを削除せず、画像ファイルの詳細に「所蔵者が著作権を主張しており、国や地域によっては著作権によって保護されている可能性がある」といった旨の注意書きを掲載する対応をとることでこの事件は終息した。
現在では国立肖像画美術館は、低解像度の画像に限って非営利での利用を認め、営利目的などで高解像度の画像の利用するにはライセンス料を取っている。前々回の記事でも紹介したが、イギリスではテート美術館も同様のビジネスモデルで画像を公開している。
なお、国立肖像画美術館が提供している低解像度の画像サイズは長辺800ピクセル、テート美術館の場合は長辺1536ピクセルだ。このサイズあたりがこのビジネスモデルにおいて妥協できる範囲といったところか。私のようなユーザーにとっては、テート美術館くらいの解像度は最低限ほしいし、できれば2K画質の長辺2048ピクセルはあってもいいのではないかと思う(2K画質はスマホのTwitterアプリで無劣化で閲覧可能なサイズ)。
利用を規制しようとする日本の美術館
では日本の美術館の場合はどうだろう。日本の施設が所蔵品の画像を無許諾で利用した者を訴えた事例としては、1984年の顔真卿自書建中告身帖事件が知られている。
この事件は、中国の書家である顔真卿の《顔真卿自書建中告身帖》の写真図版が出版物に現所有者の許諾なく使用されたことに対して、現所有者の財団法人書道博物館が所有権(使用収益権)侵害を主張し、出版の差し止めを求めた裁判である。
最高裁まで争われた結果、パブリックドメインとなった作品の画像利用は所有権侵害とは認められず、営利目的での利用も知的財産権など著作権の侵害にはならないという判決が下された。最高裁は、「著作権の消滅後に第三者が有体物としての美術の著作物の原作品に対する排他的支配権能をおかすことなく原作品の著作物の面を利用したとしても、右行為は、原作品の所有権を侵害するものではない」と判示して、物理的に存在する原作品を支配する所有権などの権利と、作品に備わる概念的な部分を支配する著作権とを区別した。つまり著作権のない作品の所有者が作品の複製を利用する第三者の行為を妨げることはできないということだ。
しかし、にもかかわらず日本の美術館では画像の利用を許諾制にして制限を設けていることが多い。
そういう意味では国立肖像画美術館やテート美術館のように非営利での利用を認めて、営利目的で高画質な画像を利用したい場合だけライセンス料を取ることを明確にしているビジネスモデルのほうがはるかにユーザーフレンドリーであるとさえ言える。
日本の国立施設では、東京国立博物館が「研究情報アーカイブス」にあるコンテンツについては出典を明記するなどの条件を満たせば利用を認めており、国立館の中ではいまのところ一番寛容な規定を設けている。
それ以外のほとんどの施設では、たとえ非営利での利用であっても教育目的、私的使用、引用など法律で認められている利用法以外は許諾を求め、画像の利用料を取っている。これは著作権がまだ有効である作品の場合は適法な対応ではある。
しかし、それらの施設で共通しているのは、作品の著作権保護期間が満了している場合の画像の取り扱いについて説明をしないことで、著作権に関する知識のない者にどのような作品の画像であっても原則として利用はできないと思わせるようなミスリードを誘う書き方になっていることである。
著作権法についての知識があればこれらの文章を「正確に」理解して、誤解をすることなく画像を二次利用することができるだろうが、そうした知識を持ち合わせている人はごくわずかだろう。それに知識があったとしても面倒なことになるかもしれないと少しでも思えば、利用は控えざるを得なくなる。
画像利用に規定を設けている国立館のなかでも特筆すべきは、奈良国立博物館だ。同館が公開している収蔵品データベースでは、高品質な収蔵品の画像をダウンロード可能にしている。ただし利用に際して厳しい制約を設けており、ダウンロードページに進むと次のようなテキストが表示される。

奈良国立博物館では、非商業目的の以下に示す範囲と条件での利用について、収蔵品の画像を無償提供いたします。
・公刊しない個人の研究資料(レポートやパワーポイント、口頭発表資料を含む)。
・学校の授業や事前学習などのために教員や生徒が作成するスライドやプリント。
・学校や地域のサークル、NPOなどの団体が作成するイベント告知やチラシ。
・販売を目的としない模刻や模写制作の参考資料。
(以上の場合は、利用した画像が奈良国立博物館のものであることを明示すること)
・私的な閲覧や印刷、コンピュータやスマートフォンの壁紙等への利用。
・第三者への提供や再頒布をしないこと。
なお、印刷物やDVD、インターネットサイトなどに利用する場合は、あらためて特別観覧の申請が必要です。
ダウンロードするなら、これらの条件に同意したとみなすかのような仕様になっている。他の国立施設の場合、個別の作品にこうした同意画面のようなものを表示したりはしないため、著作権が切れた作品の取り扱いについてはボカされているが、奈良国立博物館の場合は明確に著作権が主張できないものにまで権利を主張しているようにみえる。画像がダウンロードできるようにデータベースを公開していること自体は評価できるが、こうした画像利用の規制の仕方には問題があるのではないか。
条件はおおよそ教育目的、私的利用のみに限定するというもので、昔の絵画など著作権がないものにまでここまで厳しい規定を設けるのはやりすぎと思える。著作権がない作品なら営利で使ってもいいはずだし、非営利でも許諾を求めるというのは厳しすぎる。高画質な画像をむやみに営利目的で使われたりネットで再配布されたりしたくないということであれば、高画質の画像とは別にそこそこの画質のものを指定して利用を許可するなど柔軟な対応をしてほしいと思う。
東京国立近代美術館 https://www.momat.go.jp/ge/sitepolicy/
画像利用に配慮するネットメディア
以上のような作品の所有者や複製の作成者が抱いている著作権の範囲を超えた権利意識(もしくはリスク回避意識)のようなものに対して、ウェブメディアなどが配慮して自主規制することもある。
美術専門誌の『美術手帖』が運営する「美術手帖 ウェブ版」は、2022年8月27日に伊藤若冲による代表的な連作「動植綵絵」についての解説記事をウェブサイトで公開した。「動植綵絵」は昨年の2021年に国宝に指定されたばかりで、東京芸術大学大学美術館で今年2022年8月から9月まで開催された特別展「日本美術をひも解く―皇室、美の玉手箱」に全30幅のうち10幅が展示された。昨今、話題性のあるホットな作品だ。
記事では現在、当該作品の図版として所蔵館である宮内庁三の丸尚蔵館で過去に行われた展覧会の図録からスキャンして得た画像を使用している。
しかし、公開当初はそうではなかった。
最初、この記事が使用していたのはWikimedia Commonsにアップロードされている画像で、そのことを出典としてURLで示していた。それが後になって現在のものに差し替えられたのだ。Wikimedia Commonsの画像は、所蔵館のウェブサイトで公開されている画像を転載したものだ。


伊藤若冲の作品の著作権保護期間は終了しており、絵画を正面から撮影した写真に著作権は発生しないので、本来断りなく使用しても違法性はない。それなのになぜ画像を差し替える必要があったのだろうか。それは三の丸尚蔵館が所蔵品の画像利用に条件を設けているからだろう。
三の丸尚蔵館は画像利用を「 原則として,その公共性・学術性の高い目的,もしくはそれに準ずると判断されるもの」に限って使用申請を求め、「営利目的の販売品や広告,また個人的な目的等で使用すること」は禁止している。そして、例外として「既刊書等からの複写転載」であれば、営利目的や個人的な利用も認めるという独自の規定を定めている。(これは私の読み間違い)
https://shozokan.kunaicho.go.jp/media/images/image-use-policy.pdf
おそらく記事の作成者は、著作権保護が終了している作品の画像はパブリックドメインであるから自由に利用できると当初は判断したが、所蔵館の規定に後から気づき、それに従って画像を差し替えることにしたのだろう。記事は有料で公開されており、仮に学術性が認められるとしても営利目的の利用といえるため、規定に従うなら許諾を得る必要がある。その必要のない複写転載のほうが所蔵館との関係を損なうことなくノーリスクという判断になったのだと思われる。なお私は有料会員に登録しているので記事を最後まで読んでみたが、差し替えについては触れられていなかった。
もちろん利用する者が善意で所蔵館の規定を守るのは自由だ。だが、差し替え後の画像のように作品の色合いがあまり正確に再現できていない低品質な画像がネット上に出回ることはあまり良いこととはいえない。差し替えの前後を見比べて、その違いは明らかだろう。
差し替えた後の画像に若冲が描いた色鮮やかな紫陽花の美しさは感じられるだろうか。この作品のすばらしさを論じるならなおさら品質の良い画像を使うのがベストだし、それを所蔵館の一存で妨げてよいのだろうか。
入館料問題との共通点
収蔵品のイメージの流通をコントロールしようとする美術館と、そのために低品質な画像を利用するのが合理的と判断するメディア、それらから情報を得る人々、そしてその結果として人々に記憶されていく作品。それぞれが不利益を被らずに済む方法はないのだろうか。
それを考えるためにはまず作品のデータを公開することで得られるであろうメリットと、生じてしまうかもしれないリスクとは何かを整理することが必要だろう。先ほど紹介したヨーロピアナの白書「黄色い《牛乳を注ぐ女》問題」では、データのオープン化に伴うメリットとリスクを精査しており、それぞれ10項目が挙げられている。以下に引用するが、全訳すると長くなるのでかなり意訳した。
オープン化のメリット
①データ提供する機関は、デジタル社会とのつながりを維持できる。
②ネットユーザーがデータやコンテンツにふれる機会を増やせる。
③データが充実することでデータが相互に関連付けられる。
④オープン化に前向きな姿勢がブランド価値(名声、信頼性、革新性)になる。
⑤オープン化を推進する政府から資金調達がしやすくなる。
⑥ネット上でデータがみつけやすくなることでウェブサイトへのアクセスが増える。
⑦新たな顧客を獲得できる。
⑧文化遺産への幅広いアクセスを可能にするという公共的使命を実現できる。
➈専門性が強化される。
⑩新しいビジネスを喚起でき、知識の価値も上がる。
オープン化のリスク
①データが第三者によって情報元から切り離され、品質が劣化する。
②誰もがデータを利用できると、機関がデータをコントロールできなくなる。
③本来、一つのコンテクストでまとまっているべきデータが統一性を失う。
④機関が望まない利用者とデータが関連付けられ、ブランド価値が損失
する。
⑤オープンライセンスでデータ公開すると、機関は情報源/所有者としてクレジットされなくなる。
⑥データから現在得ている収入を他の収入源に置き換えられるかわからない。
⑦将来的に得られる潜在的収入が、他の誰かのものになってしまうかもしれない。
⑧自分たちが提供したデータで他者が利益を得ることを不公平と感じる。
➈データがオープンになれば、顧客は探している情報を得るために他の場所に行くだろう。
⑩データによってはプライバシーによる制限がある。
博物館・美術館は画像利用に制限を課すことで、上記のようなデータを公開することで得られるメリットと生じ得るリスクの回避を両立させたがっている。
しかし、規定をどのように設定しても法的な根拠がなければ流通をコントロールすることはやはり困難であると思われる。著作権保護期間が終了した作品の画像利用を本来的に制限することはできないからだ。その場合、どのような規定もお願いベースにならざるを得ないが、それがあまりに厳しすぎれば配慮を求めるというレベルを超えて存在しない権利を主張しているとみなされて利用者に不満を持たれてしまうだろう。
そして、たとえお願いベースであってもなぜそのお願いが必要なのか、その妥当性が検証される必要も当然ある。ヨーロピアナの白書にもあるように、データのオープン化は文化遺産への幅広いアクセスを可能にするという公共的使命の実現に寄与する。アクセスに制限を加えることは、その施設が自分たちの公共性に対する責任をどのように考えているかを示すことにもなる。
先ほどイギリスと日本の施設で定めている画像データ利用の指針を比較し、著作権法の在り方に違いはあるものの、日本の施設のほうが非営利であっても利用を原則認めず、許諾制と利用料の徴収など厳しい制限を課す傾向にあることを示した。
この問題には、利用者にどのような負担を強いるかという点で入館料問題とも重なる部分があるように思う。
2020年に国立博物館が値上げに踏み切ったと話題となったことは記憶に新しい。その際、「公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。 但し、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。」とする博物館法第23条が有名無実化していることが改めて指摘され、海外の大手施設が一定の条件で入館料を無料にしていることなどと比較して、日本の場合、公的な使命の実現よりも収益の改善が優先していることが指摘された。
そもそも入館料を原則無料とした博物館法の制定において、その文言の挿入は日本の側が能動的に採用したものではないとする指摘もなされている。博物館法制定過程の議論を追った瀧端真理子「日本の博物館はなぜ無料でないのか? 博物館法制定時までの議論を中心に」によれば、無料制という発想は直接的には戦後になってアメリカ占領軍によってもたらされた。
博物館法に先立って1950年に制定された図書館法では占領軍の意向が強く反映された結果、第17条「公立図書館は、入館料その他の図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない」という文言に結実し、実効性の高い無料閲覧制が実現した。そして、それが翌1951年制定の博物館法にも影響を与えた。しかし、日本の施設関係者側の意識としては図書館法・博物館法ともにむしろ入館料が浮浪者など施設の意図しない利用者を排除したり、労働者の休息所として使うような目的外での利用をさせないようにしたりする「入場制限」としての効果を積極的に認める考えが根強くあり、英米のように博物館の無料化が格差是正という公共的な使命を果たすという発想は希薄だった。
日本の美術館がイギリスと異なり画像利用に厳しい規定を設けるのは、入館料問題と同様の態度が作用しているからではないだろうか。
入館料問題とオープンデータの利用制限は、利用者に制限を課すことで施設の利益を最大化させようとする点で似ているが、入館料が利用者に強制できるだけの実効性があるのに対して、収蔵品のデータ利用に規定を設けて制限するのは限界がある点で異なっている。来館者が料金を支払わないなら物理的に入館を阻止することができるが、公開しているデータの利用についてはそうした対処が困難である。
しかし、だからといって著作権に関する取扱いを曖昧にしたり、過大な配慮を要求するような対処が適切とは言い難い。美術館と利用者が相互に良好な関係性を築けるような利用規定が望ましいということは、内閣府が主催するデジタルアーカイブジャパン推進委員会の資料「デジタルアーカイブにおける望ましい二次利用条件表示の在り方について(2019 年版)」が以下のように指針を示しているとおりである。
著作権法による保護の対象とならないデータであっても、そのデータの活用においては、 作品や作者への配慮や敬意を示すと共に、データ提供元の各アーカイブ機関やデータ作成者等の貢献について社会的に広く認知してもらうため、また、データの信頼性を担保するため、活用者に対して、二次利用に際し出典や所蔵館等の表記を正確な形で行ってもらえるよう、更には、民族・宗教等に対する文化的配慮に留意してもらえるよう、望ましい表記事項や留意事項等のお願いをアーカイブ機関がウェブ上に分かりやすく掲載することが望まれる。また、そのような掲載を行う場合は、当該お願いが法的拘束力を持たないものであることを明記することが望ましい。
美術館の所蔵品のなかでもとくに著作権の保護期間が終了しパブリックドメインとなっている作品は、概念的な権利の側面において名実ともに公共の財産として扱われるものだ。そして、作品のデータへのアクセスを容易にしていくことはその作品が様々な人々に記憶され、新しい文化を生む原動力になっていくことが期待されている。
そうしたポジティブな側面を美術館と利用者とで形作っていけるような利用環境のために、データを公開する側は法律に則って権利を主張し、利用する側の権利もちゃんと認めてほしいと思う。
ここから先は
¥ 100
Twitterで日本美術史について呟くbotをやっています。こっちのフォローもよろしくね! https://twitter.com/NihonBijutsushi
