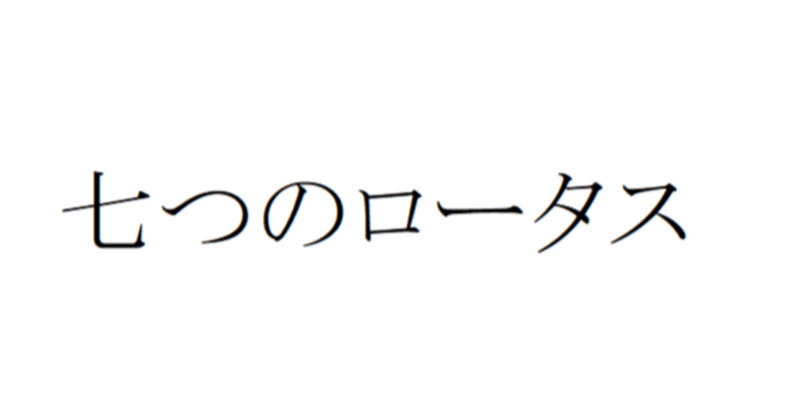
七つのロータス第60章 オランエIV
人々が薄暗い部屋から解放されたざわめきが周囲を包んでいる中、オランエはゆっくりと立ちあがった。帝都をめぐる城壁のすぐ外側で戦いがあったばかりだというのに、会議会議と時間を無駄にさせる。体にのしかかってくるような疲労を感じながら、オランエは思う。今は会議よりも危急の用件に当たるべき時ではないのか。兵力の再編成、スカンダルの討伐、投降したスカンダル側兵士の処分。大人数で話し合うより、責任者が処断するべき物だろう。参議の資格を持つ貴族や書記が議場から出て行く流れを摺り抜けるようにして、苛立ちも露わに歩み去ろうとするオランエを遮るように、サイスが近づいてきた。
「摂政殿下、失礼ながら」
驚いて足を止めたオランエも、その口調には安堵を覚えた。未だ不機嫌な様子であったが、付き合いの長い身には、その怒りが収まりかけていることが見て取れる。
「スカンダルが占領していた鎮北軍の駐屯地で、マライ将軍が見つかりました。スカンダルへの帰順を拒んだ兵らとともに、捕らえられていたとのことです。今グプタに向かっています」
了解の言葉とともに頷いて見せる。
「怪我などはしていないのか」
「手荒に扱われたりもしたようですが、酷い怪我はないようです。皆、馬か徒歩で向かっているとのこと」
「それならば、すぐに会ってねぎらわねばなるまいね。彼らが戻る時に、市門の前で出迎えよう」
サイスが一礼して引き下がると、マライ将軍らのことも頭の中で片隅に追いやられる。オランエの頭の中を占めているのは、戦力の再編成だ。まず現有戦力としては、近衛兵が五千、うち四千が長槍歩兵、近衛兵以外の長槍歩兵は二千、水軍が二千。これらの兵はスカンダルとの戦いでほとんど消耗しなかった部隊。し かし一万五千いた新兵は大損害を出し、無傷の者は約三千、軽傷で近く復帰できそうな者が四千あまり。半数以上は死ぬか重傷を負った。これらの兵をいかに編成して、スカンダルを追撃するか。すぐに使えるのは合計で一万二千だが、帝都の守りも必要だ。
反逆者のスカンダルも、グプタに攻め寄せた兵を全て捨てて逃げた以上、残るのはプハラとバグダに三千ずつ。もしパーバティが敵側についていたとしたら更に三千。今回の敗北で統率には苦労しているだろうが、それをあてに軽々に攻めこむマネはできない。スカンダルに対して個別の判断で攻撃するよう命じる使者はパーバティに出してあるが、征北軍の女将軍もまた、パーラに対する忠誠の宣言をしてはいない。
歩きながら考え込むオランエに、今度はティビュブロスが声をかけてくる。二人は誰にも話を立ち聞きされることのない、内宮の一室に移動した。
「どうやらウルウの目的がはっきりしたな」
先生の目は敗走した賊軍よりも、帝都での勢力争いに向いている。
「勢力を失いかけている旧ジャイヌ派を糾合して、自分がその領袖になろうというのでしょうね」
ティビュブロスが頷く。
「対策を話し合わねばならない問題ではあります。ですが今は傷ついた兵力を立てなおし、スカンダルを討伐する方が優先です」
ティビュブロスは軽く頷く。
「わかった。そっちはお前が将軍たちとやっていけばいい。宮廷の中はわたしが引きうける」
オランエはお願いしますと言いかけて、口ごもった。ティビュブロスの事は全面的に信頼している。なのに何かがオランエに即答を躊躇わせた。
「ところでネ・ピアとハジャルゴがサイスを弁護したのは、何故でしょうね?」
返答をせずに話を変える。相手によってはこれで言質を与えぬまま、同意したように思いこませることもできるかもしれないが、先生には通用しないだろう。
「わたしが買収しておいた」
ティビュブロスは表情も変えずに言い放つ。
「そういうことですか」
オランエの胸に不快感が込み上げてくる。気持ちが落ち着くのを待ったので、次の言葉が出るまで時間がかかる。
「そういうことは、僕にも一言教えて欲しかったですね」
「今朝、戦いに勝ったことで、話を聞いてもらえる立場になったのだ。それまでなら、いかに高価な餌をちらつかせても、連中は用心してのってはこなかっただろう」
それは答えになっていない!勝ってからでなくては動けなかったにしろ、二人を買収しようという考え自体はそれ以前からあった筈だ。
今まで敬愛の念を抱き頼りにしていた相手が、自分を意に反して摂政に祭上げた張本人だと、オランエは今更ながら気づいた。ただでさえ信じられるものの少ない皇宮で、先生まで信じられないとしたら、いったいどうしてやっていけばいいだろう。
「今日の会議でラジの姿が見えなかったのも、何かお考えがあってのことなのですか?」
「ああ、あいつはなにやらへそを曲げて田舎にある荘園に引っ込んでしまったよ。困ったものだ」
オランエは静かに息を吐き出す。これ以上ティビュブロスを追究する意思の力が残っていなかった。
「買収やら多数派工作やらは、事後でもいいですから、せめて何をしているかくらいは教えて下さい」
やっとの思いでそう言うと、オランエはティビュブロスを下がらせた。
極秘の話し合いにも使えるように造られた小部屋は、その用途には似つかわしくないほど開放的だ。部屋の二面は土壁に塗りこめられているが、一面は隣の部屋とほとんど仕切なくつながっており、もう一面はこの部屋を通らねば出入りのできない小さな庭に面している。庭は三方を別の棟の壁で遮られ、正午を挟んだ僅かな時間だけ、部屋に日が射しこむ。周囲を遮断するのではなく、人が隠れる事のできる場所が存在しないように造られた部屋。
小部屋の中に一人残ったオランエの胸には、憤りと無力感が渦巻いていた。僕はいったい何をしているのだろう。先生を悪意ある者とは考えたくない。先生は 帝国全体のためを考えて動いているのだと信じたい。だけれどそうだとしても、自分は先生から信頼されていないようだ。かつて自分は望んではいなくとも、必要ならば摂政だろうと帝位だろうと見事に勤めを果たす自信を持っていた。その矜持も今は失われようとしている。これならば何の為に自分は本来の望みを捨ててまで、忌んでいた皇宮に戻って摂政になったのか。ただパーラのご機嫌を取るためか!
ソウ、ソノトオリ!
オランエはいつしかうなだれていた顔を、跳ね上げた。時に去来する心の声が、いつになくはっきりと、まるで現実に呼びかけるように聞こえた。
てぃびゅぶろすハ、ぱーらガヤケヲオコシテ、タイヘンナコトヲシデカサナイヨウ、ぱーらヲナダメルヒツヨウガアッタノサ。オマエニキタイシテイルノハ、ソレダケノコト。
「うるさい、黙れっ!」
オランエには自分が心の中で叫んだのか、口に出して叫んだのかわからなかった。気がつけば正午をいくらも回っていない太陽が、鮮やかに庭を照らし出している。オランエは荒い息の中で、胸と瞼が震えているのを感じた。
なぜ自分はこんな目にあわねばならないのだろう。一度は全て捨て去った筈だった宮中のしがらみの中に舞い戻り、苦しみにのたうちまわっている。瞑想者の 森に帰りたい。全ての不安と不満を捨てて、自分を常に高い段階の意識に置くことのできた場所へ。瞑想者の森へ戻りたい。人として最も意義ある生活へ。
どれだけそうしていたか。誰も訪れる気遣いのない部屋で、うずくまっていたオランエは、ようやく顔を上げた。太陽は未だ、南の空高くに輝いている。
「半日がなんて長いんだ」
オランエは呟き、次いで叫び声とともに立ちあがった。仕事だ。仕事がまだ幾つも残っている。まずは賊軍の中にあって、忠誠を守りぬいた人々を迎えてやらなくては。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
