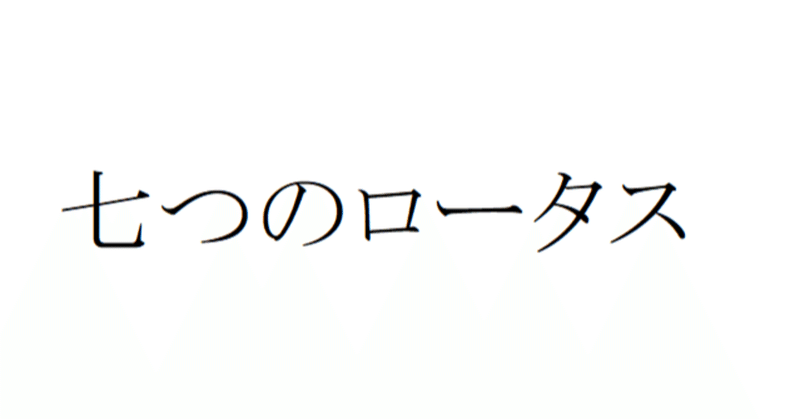
七つのロータス 第1章 アルタス
七つのロータスと、第1章について(作者自身の解説が不要な方は直接本編をお読みください)
地平線まで小石と礫の転がる平らな大地が続いている。まばらに半ば枯れたような短い草が見える以外、生き物の気配は感じられない。いっとき、風が止んだ。今まで吹き流されていた汗の匂いが、アルタスの鼻腔にまで立ち昇ってきた。匂いの源は少年自身の体ばかりではない。
「白銀、休憩は終わりだ。そろそろ帰ろう」
少年の体の下で、短い草に唇を伸ばしていた芦毛が、まっすぐに首をもたげた。
「いい子だ」
少年は目を細めながら、愛馬の首筋を二度叩いた。手綱を取るまでもなく、白銀号はゆっくりと体の向きを変え、ねぐらの方向へと首を向けた。
悠々とした足取りで自ら家路を辿る愛馬の上、遠乗りの間にかいた汗を風がさらってゆく。真昼の陽射しが落ちついてから出発したとは言え、この遠出は少々きつかった。やはり馬の鍛錬は、朝霧のなかでするに如くは無い。愛馬も水を欲しがっているだろうが、そんな様子はまるで見せない。ただ悠然と歩を進めるのみである。
「おい」
アルタスは軽く左の手綱を引いた。それで充分だった。白銀は変わらぬ足取りで、僅かに向きを変えた。
白銀の柔らかな歩調に身を任せていると、うっかり眠りの中に滑りこんでいきそうになる。この白銀は名馬中の名馬だ。アルタスの胸中が、強い感情で満たされて溢れそうになる。生まれた時、平凡な母馬の毛色を受け継いでいるから駄馬に違いないなどと言われて、手放したりしなくて良かった。
やがてなだらかな丘の上に辿り着くと、その下に小さな泉が見える。見渡す限りの荒地の中で、そこだけが緑に包まれている。わずかな潅木と丈の低い草ばかりとは言え、鮮やかな色彩が目に嬉しかった。小石で滑りやすい斜面を慎重に下る愛馬の背で視線をめぐらすと、遥か彼方には城壁を巡らした街。アルタスの生まれ育ったオアシス都市・サッラである。帰るべき家のある都市は、すぐに砂丘の影に隠れて見えなくなった。アルタスは泉に視線を戻した。小さな泉だからまわりに畑を作ろうとする者もなく、他の街への道からも外れているので商売をしようとする者もない。ただ馬を育てる者だけが、ひとときの憩いを求めて立ち寄るだけの場所。衣の内側まで汗に絡め取られた砂埃に覆われた体を、冷たい水で洗い清める事を思えば自然と気ははやるが、愛馬はまったく歩調を崩さなかった。
突然の冷たい刺激に、細かい砂で目詰まりをおこした全身の毛穴が歓声をあげる。顔の、腕の、胴の、脚の肌が、それ自身で水を吸い込んでいるような気がする。口と鼻から盛大に泡を噴き出した後で、派手な水飛沫を飛び散らせながら、水面を貫いて立ち上がる。水を吸った長い黒髪が躍って、その先から滴った水が背骨に沿って細い流れをつくった。泉のほとりでは、白銀がしなやかな首を水面に伸ばしている。両手で顔に垂れかかる髪を押しのけ、手足から力を抜いてそっと水面に身を横たえてみる。暖かな光が心地よい。耳を塞ぐ水が、微かな唸りを伝える。力を抜いた四肢が、柔らかく弄ばれているように感じる。アルタスは暫くよく澄んだ泉水に身を任せた後、ようやく立ちあがって濡れた髪を手でかき上げた。
白銀の待つ岸へ向かって泳ぎだそうとしながら、一瞬背後を振り返る。そこに女がいた。アルタスは動作を止め女を見た。お互い言葉もなく見詰め合う。女にしては背が高い。姿勢良く真っ直ぐに立っているので、なおさら高く見える。首から足元までを包むゆったりとした茶色の衣を着て、両腕もその長衣に包まれて見えない。日に焼けた小さな顔に大きな目が、真っ直ぐにアルタスを見つめている。十六、七と見えるその美しい顔には、全く見覚えが無かった。
「君は…?」
言いながら、腰布まで外してしまわなくて良かった、という考えが頭をよぎった。途端に顔が熱くなった。無言で立ち尽くす女から顔を背け、白銀めがけて泳ぐ。取りあえず、水から上がってしまいたかった。
体を拭い衣服を着込む間、女は泉のほとりに腰をかけ、静かに待っていた。自然にとった姿勢が実に優雅で、平民の出ではないことは明らかだ。身支度を整え、堂々と見えるようゆっくりとした歩調で近づくと、女は静かに立ちあがった。
「おくつろぎのところ失礼致しました。お許し下さい。サッラの高貴な方とお見受けします」
女は用意していたと思しき口上を述べた。
「私はサッラの族長ゾラの長子、アルタスと申す。失礼ながら、あなたも粗末な身なりをされているが、高貴な生まれでありましょう?」
「あたしはタラスの族長リャマの娘です」
アルタスは思わず帯に挟んだ短剣に手をやっていた。タラスは広大なステップを隔てた隣のオアシス都市であり、サッラとは幾度となく戦いを交えてきた相手である。初代皇帝の乗馬であった月光の血を引く大柄な軍馬が騎兵に行き渡ってからは、サッラが敗れる事はなくなったとは言え、タラスの名は未だ年若いアルタスにとっても、油断ならぬ敵として特別な意味を持っていたのだった。
「あたしたちが敵だと思われていることはわかっています。ですが慈悲を給わりにまいった女を、なにとぞ哀れに思し召して下さい」
言いながら女は地に両膝をついてアルタスを見上げた。話しているうちに気が昂ぶったのか、その大きな目は潤んでいる。アルタスはタラスの名に、つい身構えた事を恥じた。
「そのようなことはなさらないで。事情を説明して下さい。力になれることならなりましょう」
アルタスは片膝を落として、相手と視線の高さを揃えた。楽にするよう促すと、女は草の上に腰を降ろしたので、アルタスも泉の岸に置かれた石に座った。
「十日前のことです。タラスは敵に襲撃され、攻め落とされました」
アルタスは突然の言葉に、小さな叫びをあげた。族長の娘は一瞬目をアルタスに向けたが、再び視線を水面に落とした。
「得体の知れない大軍がやって来たということで城門を閉ざしたのですが、行商人や旅芸人を装った敵が街の中に忍びこんでいました。城壁の内側で奇襲され、門を開かれてしまい。後は…、あっという間でした」
娘の頬を一条の涙が伝った。
「兵士達が決死の働きで敵の囲みを抜いて、あたしを逃がしてくれました。追っ手にかからぬよう街道を避けて、荒れ野を歩いてここまで来ました」
女はまたアルタスの顔を見た。その顔は悲痛に歪んでいる。
「そんなに驚いていらっしゃる、ということは、こちらまで逃げてきた者は他にいないのですね」
アルタスは頷いた。少なくとも午後に街を出た頃には、そんな話はなにも無かった。
娘が嗚咽を洩らした。両手で顔を覆って、丸めた背を震わせた。
「あたしは本当は一人で逃げてはいけなかった。街にはやるべき事がいくらでもあったのに、おそろしいばっかりでそんな事思いもしなかった。兵士達に言われるまま逃げ出して、夜通し歩き続けてようやくその事に思い至ったんです」
「そんなに自分を責めないで」
アルタスは思わず女に歩み寄って、その両肩に両手を置いた。女は涙を湛えた目でアルタスを見上げ、僅かな動きで身を振りほどいた。アルタスは慌てて両手を引っ込めた。
「取り乱して申し訳ありませんでした」
「いや」
娘は涙を掌で拭うと、もう一度アルタスに向き直った。アルタスの目は強く引き結ばれた小さな唇に吸い寄せられた。
「どうか、お助け下さい。タラスの民を」
娘は言葉を詰まらせた。
名を呼ばれると、白銀は悠然とした足取りで主の元へ近づいてきた。アルタスは立ちあがり、女の手を取って立ちあがるように促す。
「あなたも草原の民なら、馬は大丈夫ですね」
女は白銀の頭から尻へと視線を滑らせる。
「こんな大きな馬はタラスにはおりません」
「なに、同じことですよ」
言いながら、片膝をつきその上で両手を組み合わせる。
「そんな馬丁のような真似をさせるわけにはいきません!」
「そんなことを言っている場合じゃないでしょう。さあ」
女はせめてもの配慮にと、サンダルを脱ぎ素足でアルタスの手を踏んで、軍馬の背に跨った。
「白銀、重いだろうがこらえてくれよ」
言って、女の前に座り、手綱を取る。頑丈な芦毛は速足でサッラへの道を取った。
「取りあえず、私が助けてさしあげられるのは、あなた一人です。だけど、できるだけの事はしましょう」
二人乗っていても、白銀の滑らかな歩調は全く変わりが無い。砂丘の連なる道のりを滑る様に進んで行く。
「そうだ、あなたの名前を伺っていなかったと思うけれど…?」
「ネム」
砂漠の巨大な太陽は砂丘の稜線にかかり、鮮やかな紅色の光を投げかけている。東の空にはかすかな紺色の闇が忍び込みつつある。やがて砂漠の澄んだ空に、星が輝き出すだろう。
もしサポートいただけたら、創作のモチベーションになります。 よろしくお願いいたします。
