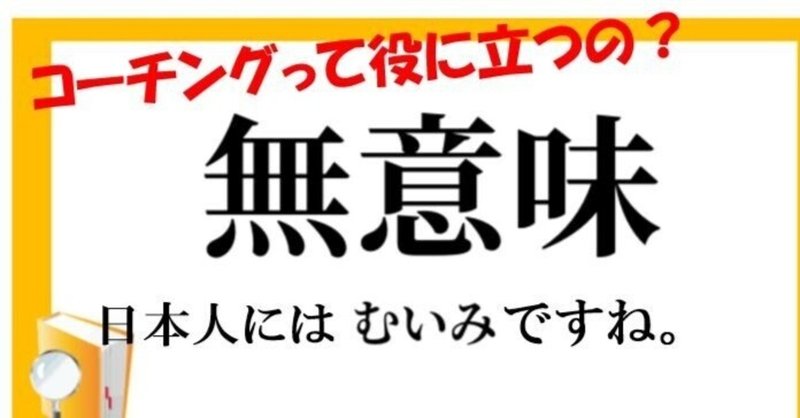
コーチングなんて日本人には機能しない
■過激なタイトルで釣りました。ごめんなさいm(__)m
かくいう筆者も、某スクールでコーチング学び、認定資格を取りました。今もなお、脳科学コーチとして活動を続けていますので、「どの口で言うか!」と叱られるかもしれません。
意図としましては、コーチングは素晴らしいコミュニケーションツールであることを前提に、アメリカ人と日本人の気質に言及しつつ、より多くの日本人を成功に導く「日本型コーチング」の在り方を考察しようというものでございます。
日本人は、なんでも受け入れてしまう懐の深さを持ち合わせている民族です。マック(マクド)も、ドミノピザも、スタバもなんでもOK。これらのアメリカ発の外食チェーンは、もはや日本の食文化になっています。

ですが、アメリカ生まれのものばかり食べていたら、どうなるでしょうか? あまりいい結果は期待できなさそうですよね?
そうです。日本人はやっぱりお米を食べましょう!
■閑話休題。話をコーチングに戻します。
じゃなくて、コーチングの話です。
日本で流行っているビジネス寄りのコーチングも、もともとはアメリカで生まれたものです。マクドとかスタバと同郷です。
アメリカでは、1950年代から偉い先生がビジネスコーチングを取り上げはじめ、80年代から出版物が増え、セミナーなども開催され始めたようです。
■デフレ元年、コーチングが日本に輸入された
輸入という言い方が正しいのかどうかわかりませんが、日本でコーチングスキルの普及が始まったのは1997年。コーチ・トゥエンティワン(当時)が、トレーニング・プ ログラムの提供を始めました。
1997年は、日本にとって重要な位置づけとなっています。規制緩和が加速する中で消費増税が行われ、デフレの元凶となった年です。グローバリズムが加速したのもこのあたりだと認識しています。
つまり、コーチングの日本上陸は、グローバリズムの一環なのかもしれません。年代が符合しすぎてますし。
■おいしいけど体に悪い?
そんな歴史はつゆ知らず、筆者がコーチングを学び始めたのは2014年。第二次安倍内閣の頃です。アメリカの元首はオバマさん。岸田さんは外務大臣でしたね。
また話が逸れましたが、コーチングって、つまるところお喋りじゃないですか。そこにスキルをのっけて、クライアントをその気させるのが目的ですよね。
美味しいんですよ、食べてるときは。マクドと一緒で。でもどこか罪悪感がある。
「なんかスッキリしました~」とか多いんですよね、感想として。本来の目的は、今スッキリすることじゃなくて、長期的に成果を出し続けること。食べたときは苦くても、将来にわたって健康を維持していくためのきっかけになればいいんです。
■ナショナリズム VS グローバリズム
日本はもともとナショナリズムで成り立ってきた国です。ナショナリズムとは、共同体を大切にする国家観です。
グローバリズムはその逆で、国境をぶっ壊して、ルールなんて無視して、「みんなで自由に戦えー!!」という価値観です。

日本は元来ナショナリズム、アメリカはグローバリズムで出来上がった国です。アメリカで生まれたコーチングは、グローバリズムの産物です。
だから日本人がそのまま使うのは危険なんですよ。毎日マックとスタバとドミノピザを食べ続けるようなもんです。割と早めに死ねそうです。
■「コーチングマインド」は日本人はもともと持っていた
コーチングスクールに行くと、「コーチングマインド」を教えられます。コーチングの大原則は、クライアントが主役であり、クライアントのためのお喋りです。
「コーチングマインド」とは、クライアントの可能性を100%信じ、その意思を最大限に尊重することです。
冷静に考えれば、ナショナリズム=共同体意識の中で生きてきた日本人は、もともと「コーチングマインド」を持ち合わせていたはずです。
■コーチングなんて日本人にはいらなかった
釣りタイトルから始まった記事ですが、書いているうちに思わぬところにたどり着きました。
「コーチングは日本人に機能しない」のではなく、グローバリズムをベースとしたアメリカだからこそコーチングが必要だったわけで、国家主義の日本にコーチングなんて必要なかった。

ただ、急進的なグローバリズムの波に飲まれ、共同体意識が薄れてしまい、コーチングが必要だと多くの日本人が思わされてしまった。
本来はお米を中心とした食文化の日本が、ハンバーガーを必要としないように、国家主義に基づく精神を持つ日本人に、コーチングなんていらなかったということです。
■で、お前はどうする?
思いのままにツラツラと書いているうちに、自分のやってきたセッションは、まさに「日本型コーチング」であると確信しました。
「日本型コーチング」とは、新しい価値観や考え方を植え付けるものではなくて、日本人が本来持っている精神性を思い出してもらうことです。
そこにはもう、「コーチング」という概念すら存在しません。
ですから筆者は、これからも脳科学コーチとして、活動を続けようと決意を新たにしたのでした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
