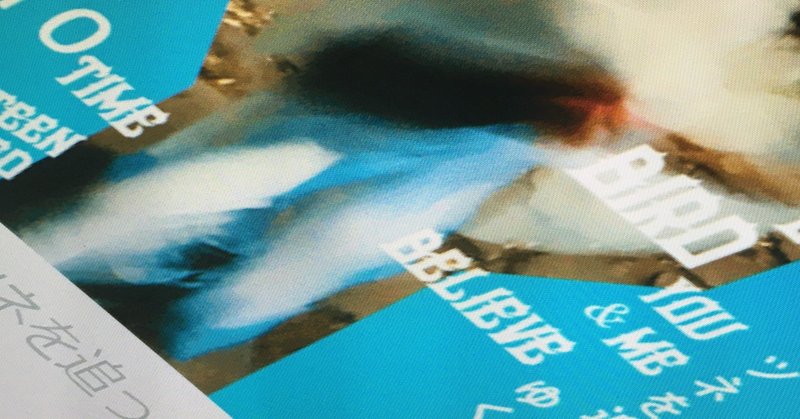
03号販売日記 1122-1128
1122
「レターパックライト」を使えば、01.02号セットでも03号のみでも同じ封筒に入れるだけで済むと気が付いた。今までは細かく計算して普通の封筒に切手を貼っていたが、これなら手間がかからずほぼ一律に対応できる。3冊セットでも多分同じ。
1123
昨日は文学フリマ東京の開催日だった。
朝9時頃に家を出て、文フリが始まったのが正午。消毒の徹底や、一時的に入場制限タイムが入るなど、感染対策がかなり行われていた。駅が混雑しそうなので終了時間の少し前に退出して、数時間を大過なく終えることができた。
帰宅して夜、お礼を兼ねたあいさつを書く。
今朝はもう次の号のための下準備と、03号のネット販売の作業を開始している。10時くらいから注文を受け付けると、待ってましたという勢いで何件か。
すでに01.02号を持っているので03号のみを購入する方がほんの少々、あとは01-03号のまとめ買い。発送のために郵便局に行って、戻ってくるとまた注文が何件か来ていた。
1124
次回のポストカードの絵はこういう風にしようというアイディアを得たので、これはぜひ実現したい。
今日もまた01.02.03号の三冊セットがササーッと売れて、全国へ送った。レターパックライトはとても助かる。03号だけの人と、三冊セットの人と、いずれもレターパックライトで送れる。
01号の販売時はまだ02.03号の構成、執筆ほかで頭が一杯だったので、販売にまで気が回せなかった。それどころか「宣伝しなくていい」「知り合いにだけ勧めて、あとは静かにさせておいて」と周囲に頼んでいたくらいである。
03号まで行ったらきちんと宣伝するつもりだったので、後でBNを読む人が増えてくれればそれでいいと考えていた。
だから、03号が出て一気にまとめ買いが増えるのは理想「的」というより、理想「そのもの」が実現したのだ。理想がイメージ通りに現実になり過ぎていて、ピンと来ない。
金銭的な収支でいうと、Zineの製作販売はなかなか大幅なプラスまでは行かないと思う。といって、大損もしていない。
そもそも本づくりに関する時間や手間や労力をマイナスと見做すのであれば、かなりの損をしている。
しかしこの部分がストレスでなければ、精神面での大損はまずない。Zineをやっている人の多くは楽しさと喜びと充実感と面白さを感じているだろうから、作り終えた時点でそれなりに得るものがある筈である。
自分の場合は、製本にかかる費用(先払い)と、売り上げ(後から入ってくる)の関係がまあまあ良好になってきて、先の見通しもそこそこ立っている。6月頃から売り始めて、01号の分は半年弱で回収できた。もともと支出が数万円ほどだから、どこかに貸したお金が戻ってきたような感覚に近い。
数万円で本を作って、多少の部数が売れるとその数万円がほぼ戻る。それに加えて新しい人間関係が増えて「次の号も買う」と考えてくれる読者が付く。さらにBNを買ってみたいと考える読者や新しい書き手がそこそこ付いてくれれば、次の号の製作までは何とかやっていける。
金銭以外に得るものがあるかどうか?となると自分は結構ある方ではないかと思っている。文フリでは、販売する側と買う側というより、ファン同士の交流の要素が強かった。自分の名前が30年前のファンジンに載っているのを見せてもらったり、前々からお会いしたかった方に出会えたり、「今度こういうことをしましょう」という計画が複数進んだり。
文フリで店番を交代して、休みがてらあちこち流して見ていると、やはり立ち止まらせる力のあるブースとそうでないブースがある。私が立ち止まる要素はまず面白いタイトル、魅力的なコンセプト。それに値段がわかりやすい(見えやすい)こと。
100円のコピー誌は「買ってもいいかな」と思わせるし、話がしやすく、気軽に購入できる。いくら表紙が美麗でも、中身がよく分からない本に千円以上はちょっと出せない。中身の説明が足りない本は、わざわざ訊く気にならない。
妙に売り子が慣れた感じで立っているだけでは、かえって誰も寄り付かない。ある程度、プロとして名の通った人でも、そう売れているように見えないのは悲しい。
文フリに参加する大きなメリットは、臆面もなく毎日のように宣伝できること。文フリなしで自作の宣伝を毎日するのは恥ずかしい。だが、そもそも音楽系の本は売れる見込みがほとんど立たない。宣伝や告知のきっかけになるイベントとして文フリは貴重である。
「ネットで買うのはつまらないが、文フリに行くのは好き」という層を少し取り込めれば良いのだが、そうするには別の何かが必要になる。となると100円の「コピー+ホチキス止め」くらいの本なら作ってみたい気がする。01-03号のダイジェストならすぐできるし、他にも短歌集や回文集など、書けそうなことは多い。
1125
前日の夜10時から11時半までの予定だった配信イベント「キツネを追ってゆくんだよ」の終了が延びて、深夜0時20分くらいまで。どういう風に終わるんだろうと思いつつ見て聴いていた。文脈や誤解の話、肉食と草食、それに伴う文化的な違いやキツネとネズミの話、未来世界の科学と倫理の話など。
配信、あと28時間ほど見られます。「新釈・ドラえもん」「正岡”Shake it”子規」「繊細な君よ」「透明な幕」そして最後の手紙など、アーカイブで飛ばし飛ばし、どうぞ。https://t.co/UGixgmA0t4
— Ozawa Kenji 小沢健二 (@iamOzawaKenji) November 25, 2020
面白かったという人はRT願います笑。最後の手紙は形容詞1つ以外、編集なしで書いたものです!
珍しくFGの頃の歌詞にもサラッと言及されていた。「罠を破る側より、仕掛ける方がよほど悪い」かどうか、先住民と開拓者の関係、他の話題もあれこれ含めてやはり「火星年代記」を連想する。
某SE氏の聞き手兼解説者ぶりが見事で、別の話題とうまく繋げたり、整理したり、例をうまく出してくれたり。編集やDJというよりほとんど現場監督のような采配ぶりだった。
ライブのリハーサルの映像がなかなか出ず、それがスタッフの手違いによるものかどうか、何か別の原因があったのかはっきりしない。自分もつい最近、仕事で似たようなことがあった。お客様と約束している時間が迫っているのに、スタッフAがスタッフBに取り次ぐ簡単な過程で止まってしまい、Bにもあれこれあって予定よりかなり遅れた。そういう時にあまり怒る訳にもいかないし、お客様にも都合があるはずなので板挟みになる。
配信イベントの視聴者数がどのくらいなのかは不明だが、いつでも誰もが視聴できるような「ユーチューバーとしての小沢健二」にはならない、そうはしない、という強い意志を感じる。
私でさえ数千から数万人に読まれるかもしれないブログよりは、読まれてせいぜい数百部単位のZINEを選ぶくらいなので、この傾向はますます強まるだろう。単に利益を生むための商品として提示するのではなくて、読んでくれる人たちへの贈り物のような意識が少なからずある。文フリの出店者は(一見したところ不愛想な人も含めて)皆そういう思いで準備して販売して帰途につくのだ。
1126
昨年11月頃の日記を読み返すと、01号のためのメモや構想が書いてあって面白い。これこそ小冊子にして付録にすると良いかもしれない。
記録によれば「ベレー帽とカメラと引用」というタイトルを思いついたのは11月30日である。思いついて以来、別の案を一つも思いつかないし、少しも揺るがない。
自分でも忘れているような考察がチラホラある。「小沢健二は予言者である、頭が良い、すごい、さすが!」という文脈で何かを書くのは簡単だが、その反対のことも書いてある。これらはチラッと残しておきたい。もちろん皮肉や嫌味が目的ではなくて、物事を相対化するためというか。あまり奉りすぎるのもナニなので、そういう距離の置き方をしながら。カレーにおける福神漬みたいなものとして。
「01-03号制作日記 2019.11.-2019.08.(抜粋)」といった線でまとめれば、まあまあ読み物として面白いかもしれない。ノーカット版はちょっと無理かもしれない。
「報告書の印刷」として考えると、50ページくらい×少部数でも一部あたり数百円でできそう。
N4書房刊「ベレー帽とカメラと引用」のオリジナルグッズを作ってみた。
紺のロゴはチラシを元にしており、「03」や文フリのブース番号が入っていて、やや高め。
赤いロゴはタイトルだけで、利益を薄く設定したのでその分だけ安い。
帽子やスマホケース、その他の商品もリクエストがあれば作ります。
ロゴの色と位置をリクエストしてくれれば、Tシャツやパーカーなら調整もできます。
1127
「キツネを~」の途中で黒ひげの話題が出た。このとき「首チョンパ」という表現が繰り返されたので「そういうゲームだったっけ?」というツイートをいくつか目にした。
自分の感覚では、あのゲームは樽に入っている罪人を面白半分にナイフで刺して、グサッと刺して殺してしまったら負けという不謹慎なゲームである。チキンレースだか何だか分からないが、いじめを助長しているどころではない意味を読み取れそうなシロモノである。確かそういう認識が広く行き渡っていて、メーカー側が修正を加えたのだ。「縛られている仲間の綱を切って、助けてあげるゲームである」といったように。
しかしこの改変は微妙に、不謹慎さが消しきれていない、いかにも後付けの理屈である。のび太を甘やかしすぎでは、という教育方面からの批判に対して「くろうみそ」のようなエピソードを作ったりするのと似た不自然さを感じる。
「ダメでないのび太と頼りないドラえもん」のペアであるような「キテレツ大百科」を描いたところで、それは結局、どこか整理されすぎていて、何かが欠けていて、広い筈の世界が狭くなっている。
ちょうどこの日記の何回か前に電グルの「誰だ!」について書いた際にも思ったことだが、誰かを攻撃しようとすると、その攻撃が自らに跳ね返ってくる、という構造的なスリルが「黒ひげ」にも「誰だ!」にもツイッターにも内包されていて、そこに妙味がある。
世界や人間の本質には、どこかしら「毒」や「自業自得」や「自己欺瞞」や「矛盾」が含まれざるを得ないので、それを潔癖な誰かが排してしまうと、また別の大きな歪みが生じる。もともとあった歪みよりも、それは悪い歪みではないか。
1128
「書かれていないこと」から何かを推測するタイプの批評があって、過去の日記の中にそれを見つけた。これと似たような角度からちょっと言いたいのは「カメラ・トーク」の歌詞には不思議なほどホニャララの話題が出てこないということ。出てきて当然なのに出てこない。おそらく一か所も言及されていないのではないか。平凡な作詞家であればこのように書くはずだという例も示して検討してみたい。04号のどこかで触れたいと思うのでご期待ください。
一年前の日記を読み進めていくと、「この人は書きたいことが多すぎて大変だな」という感想を持つ。つい2,3日前に書いたのと同じようなことが書いてあった。
↓
「特定の歌詞について考えてみたい人」に対して、こういう解釈があるよとか、この本を読んでみたらとか、仮説としてこういう風に見えるけどその先はわからないやとか、有益な情報のつなげ方をしてくれるサービスはまだない。グーグルもアマゾンもまだできていない。だから本を出す必要がある。
ブログやツイッターで数万人、数十万人、数百万人に考えを読ませることはおそらく簡単にできるだろう。
ブログで月に何百万アクセスの大人気ブロガーが本を出しました、でもタダで読める人気ブロガーの本は、なぜか発売と同時に色あせてしまう。しおれて本棚の隅で小さくなっている。
そしてそう遠くない将来、売れても売れなくても同じようにブックオフの100円均一コーナーへ収監されてしまう。あるいはnoteで「ここから先は300円お支払いください」として小銭を稼いで、それで嬉しいのかどうか。
それは薄く広く変な方向へ伝わるだけであって、花火のように表面的な野次馬を一瞬だけ集めて散る、本当にそれだけ。告知や広告には向いているけれども。
では、一体どうやって「心ある人」にだけ伝えたいことを届けられるのだろうか。一種のフィルターをかけるにはどうしたらよいか。
それなら、同人誌(ほとんど個人誌)を作って、ただタイトルだけで購入を決めてくれるような人を無言で勧誘した方がいい。
ほぼ何も言わなくても通じる人たち。
おそらくわかってくれる人たち。
きっとその人たちなら、また別の「心ある人」に伝えてくれるだろうし、伝わってくれるだろう。
時々「アパートの鍵貸します」を思い出す。「僕は人間になるんだ」。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
