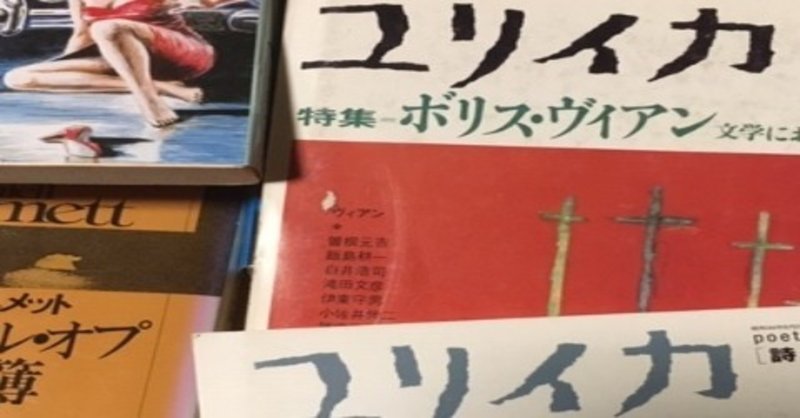
03号編集日記 0914-0920
11月販売予定の「ベレー帽とカメラと引用」03号の製作・編集・進行具合などをメモした日記です。毎週日曜日に更新する予定です。
↓
0914
チャンドラーは「長いお別れ」「さらば愛しき人よ」「可愛い女」しか読んでいないので、この機会に短編全集くらいは読むべきかと思い、本屋で眺めているうちに自宅にあったことを思い出した。
本棚を見てみると創元版の短編全集の1~3巻があり、4巻だけをどこかで買えばよい。長編は図書館に行けば村上春樹の訳したものがあるはず。
話の要約だけでは足りないので「注釈としては長い短文集」というタイトルにでもして、付帯する短い文章をいくつか書かないとうまくまとまらない。どちらも本文で、どちらも補足になるような構成にしたい。先に短文を置いた方がいいかもしれない。
目次を考えるとこうなる。
↓
その3:言葉と考察(前置き)
注釈としては長い短文集 中村四郎
A:「ピクニックには早すぎる」に始まるひとつの傾向
B:「恋とマシンガン」への複数のアプローチ
C:「カメラ!カメラ!カメラ!」に含まれる悲しさ
D:「少しだけシャイなふりをした変な角度のウインク」とは何か
FGの時代と「ことば」 中村四郎
フリッパーズ・ギターの雑誌での発言ベスト10 御野洲皆斎
ときどきポカをする王子様 小川こねり
ビーチ・ボーイズとコーネリアスに挟まれて圧死してしまいたくなる午後のひととき 桐山もげる
「ドゥワッチャライク」を概観する 犬棒先わん子
普通の人の音楽遍歴:第三回 エコロさん
編集後記
「ドゥワッチャライク」の記事のためにもう一つペンネームが必要だ。ただでさえペンネームが多いのだが、実質ほぼ一名なので仕方がない。とりあえず犬棒先わん子としておく。
03号は本誌に加えて、おまけとして「BCQ新聞」とポストカードもつける予定。
0915
チャンドラーの短編全集の4巻を買う。
ボリス・ヴィアンについてちょっと考えてみると、やはり代表作は「うたかたの日々」になる。この小説は「そうはいっても~」と結末に共通する点がある(関連づけられそうなサリンジャーの有名な小説も)し、岡崎京子が後に漫画化してもいる。古典新訳文庫で「うたかたの日々」が出た時の対談↓
https://www.youtube.com/watch?v=3WVVyhcb0SA
「野崎歓 × 菊地成孔 /東京大学のボリス・ヴィアン―「うたかたの日々」を読む -」を見ていたら「サン=ジェルマン=デ=プレ入門」という著書(生前は出なかった)の話題が出てきた。
某さんの語る渋谷の歴史の話題でよく出てくる場所なので、ここで繋がるとは思わなかった。よい店が沢山出て、文化人が沢山集まる、今で言うクラブカルチャーの人だ、と菊池成孔が言っている。
ボリス・ヴィアンで一冊だけ読むとしたら「サン=ジェルマン=デ=プレ入門」ですよと強調されているので、これは読むしかない。
0916
FGの頃の小沢健二はイーサン・ケイニンの短編集を愛読書に挙げているので、これもこの機会に読んでみることにする。近所の図書館にはないので、アマゾンで見ると2200円の一冊しかない。「日本の古本屋」で調べると800円くらいで買えた。
「ほぼ日」で矢野顕子と漫画家の松本大洋の連載が始まった。もしかすると小沢健二の話が出るかもしれない。
チャンドラーの短編全集の4が届いた。パルプ・マガジンっぽいレトロなイラストで4冊が揃った。きっと若き日のオザケンもこの表紙の創元推理文庫で読んだに違いない、と勝手に思い込みながら読むことにしたい。ハードボイルドは苦手だがハメットも読み直すべきか。
0917
斉藤環と福山哲郎による「フェイクの時代に隠されていることと」を読んでいて「オープン・ダイアローグ」という精神科の療法を知った。医者と患者という狭い上下関係を脱するために、治療法に関する対話を本人の前で行うという。また評価や説得をしないという原則もある。
評価しない、説得しない、議論しないというスタイルは、一般に考えられている「批評」と正反対だ。批評とは何かと問われたら、通常それは「何かにつけて無理にでも評価し、説得し、議論しようとする」行いのことを指している。
しかし音楽の場合、たとえば「A」という曲が好きな人、「B」が好きな人、「C」が好きな人がいたとしてもそれは当たり前のことで、まあまあそれで喧嘩にもならず、違いや多様性を認め合っている。ジャンルも同じ。そのせいで平和にやっていけるのだし、批評が進歩しないのもそのためかもしれない。
「カメラ・トーク」のレコーディングに関する印象的な記事を雑誌に書いていたライターがいて、この方はいったい2020年の今、どこで何をされているのだろうかと急に気になったので、犬の散歩中に検索してみた。
すると何と、音楽評論の単著を出しているし、ミステリ関連の翻訳をしているし、さらに調べるとツイッターをやっていて、次回の文学フリマ東京がどうしたというツイートまで発見。さらに調べると本業は歯科医らしい……。
と喜んでいたのもつかの間、よくよく見ると同姓同名の別人だった。本当のその人も二つの顔を持っていてややこしい。ひとときの夢をありがとう!!
雑誌の記事は、時期別に仕分けした方がいい。混ざっているといつまで経っても未整理のままと大差がない。
1.ロリポップ・ソニック名義
2.1stが出て5人の時代
3.2人になって「フレンズ・アゲイン」まで
この1~3を初期とすると、手持ちの記事を合わせても総数は10くらいでは。
4.「カメラ・トーク」レコーディングから発売後まで
5.「ファブ・ギア」~シングル
中期は数が多い。「時期別」「雑誌別(ページの大きさが雑誌ごとに異なるし、連載はまとめたい)」にそれぞれまとめる利点があるし、難しい。カラーコピーして両方とも作るべきか。
6.「ヘッド博士」関連
7.突然の解散関連
大まかに考えて7期ある。6-7期はやや多い。比率でいうと初期1:中期5:終期4くらいになりそう。
ボリス・ヴィアンの本が何冊か届いた。詩を読むとややFGを感じさせる(~だろうの連続など)が、関連性は薄い。
ツイッターでは「LIFE」の頃のオザケンの歌詞にボリス・ヴィアンを感じるという人がいた。「スケートリンク」など。
「 小沢健二 ボリス・ヴィアン」で検索してみたら「墓につばをかけろ」にも言及していたようなので、その線で調べてみたらラジオの書きおこしがあった。「日々の泡」を20年前に読んだとのこと(岡崎京子の漫画版も読んでいるはずと思うが、これもポカだろうか)。
そういえば某さんも「日々のたこ揚げ何々」を書いていたし、皆がこの小説のタイトルを「日々の泡」として捉えているのだろうか。自分は早川書房派なので「うたかたの日々」に愛着が深い。
0918
日々といえばブローティガンの「西瓜糖の日々」の方こそ小沢健二的な小説に思えたものだ(確かFAKEの2号にそう書いたはず)。「アクアマリン」に「西瓜の中の毎日」という歌詞があったので。
ボリス・ヴィアンの小説に出てくる過激なカップルなら、「僕らは古い墓をあばく夜の間に」の「僕ら」であっても不思議ではない。
仕事の帰りに図書館で本を借りる。柴田元幸とか音楽関係の本。「ミュージック・マガジン」を買う。
0919
「大いなる眠り」の冒頭からすでにチャンドラーでありマーロウなので、引き込まれる。
ハードボイルドとは何か、どういう点に魅力があるのか、を知らない人に説明するのは難しい。ミステリ内ジャンルというよりは時代劇や西部劇に似た感触がある。「薄汚れた街をゆく現代の孤独な騎士」といった、中世の騎士道物語の現代版ともいえる。「男の読むハーレクイン・ロマンス」という批判も当たっている。
分かりやすい例として、手塚治虫の「ブラック・ジャック」みたいな話という説明はどうか。クールでニヒルな主人公だが、意外と弱者に優しくて、無垢な存在に弱くて、不正を許さないし権力におもねらない。ドライな面とウェットな面が両方ある。「レオン」もいいかもしれない。
0920
急に寒くなった。イーサン・ケイニンはANNでも言及されていたらしい。しかし文庫になったのは一冊だけで、古本屋でもあまり見ない。
ユリイカのボリス・ヴィアン特集が過去に二回あって、注文した新しい方が届く。
↓
続きはこちら。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
