
【「嗜む」のすすめ】編集技法の作法に焦がれ本を嗜む

私達が密かに大切にしているものたち。
確かにあるのに。
指差すことができない。
それらは、目に見えるものばかりではなくて。
それらを、ひとつずつ読み解き。
それらを、丁寧に表わしていく。
そうして出来た言葉の集積を嗜む。
・
・
・
■テキスト
「[増補版]知の編集工学」(朝日文庫)松岡正剛(著)

本書刊行時の時代背景と執筆時の思い、そして、今回、増補した制作経緯を明かし、あらためて「知の編集工学」で問おうとしたメッセージを、以下の5つの視点で解説しています。
1.「世界」と「自己」をつなげる
2.さまざまな編集技法を駆使する
3.編集的世界観をもちつづける
4.世の中の価値観を相対的に編み直す
5.物語編集力を活用する
これらの視点の大元には、「生命に学ぶ」「歴史を展く」「文化と遊ぶ」という基本姿勢があることも、AI時代の今こそ見直すべきかもしれません。
■読書感想文(教訓)
「知の編集術 発想・思考を生み出す技法」(講談社現代新書)松岡正剛(著)

入門書の体裁をとる割に、懇切丁寧な説明は少ない。
だが、編集とは、何かについて、考えたことのある人なら、深めるヒント、素材に満ち溢れている本だと思う。
編集について冒頭でこんな定義をしている。
1.編集は遊びから生まれる
2.編集は対話から生まれる
3.編集は不足から生まれる。
と生まれる場所をまず並べ、その特徴として、
(1)編集は「文化」と「文脈」をたいせつにする
(2)編集はつねに「情報の様子」に目をつける
(3)編集は日々の会話のように「相互共振」をする
を挙げる。
編集とは、照合であり、連想であり、冒険であるという。
この本のいう編集とは、編集者の仕事だけではなく、旅行の計画を立てることや、デザインをすることや、対話をすること、あるいは生きること、そのものを含めた、大きな意味での編集行為である。
短い言葉だが、深さを感じる要約だ。
著者によれば、生まれる場所として、最初に出てきた「遊び」こそ、編集の本質である。
遊びには、
「自己編集性」
と
「相互編集性」
があるからだ。
非常に興味深い、カイヨワの4分類が紹介されている。
世界中の遊びの要素を、4つに分類したもの。
・カイヨワの遊びの4分類
(1)アゴーン 競争
(2)アレア 運と戯れる
(3)ミミクリー ごっこ遊び
(4)イリンクス 眩暈、痙攣、トランス状態
こうしたやり方で、自分や、他社と戯れることに、編集の基本があるのだと説明されている。
この本の面白さは、箇条書きになっている、こうしたリストにあると思う。
例えば、情報を要約編集するモードには、以下の6つがある。
・エディティングモード
重点化モード ダイジェスト
輪郭化モード アウトライン
図解化モード 2,3枚の図
構造化モード 考え方の関係
脚本化モード 別のメディアに変換
報道化モード ニュースとして伝える
「らしさ」を伝える略図的原型には、
ステレオタイプ(典型性)
プロトタイプ(類型性)
アーキタイプ(原型性)
の3タイプがある。
これも深い。
プレゼンのスタイルには、
言明型のプレゼンテーション・スタイル
暗示型のプレゼンテーション・スタイル
という2種類があるし、
ジョージ・ルーカスの定番プロットは、結局、
原郷からの旅立ち
困難との遭遇
目的の察知
彼方での闘争
彼方からの帰還
なのだと看過する。
圧巻は、「編集8段錦」、「12の編集用法」に続く「64の編集技法の作法」。
この64項目に及ぶ編集技法は、およそ、情報に対して、人間が行える操作のすべてを網羅していると思った。
ちょっと感動して長時間眺めていた。
こうしたリストも、つまりは、遊びなのかもしれないが、何かを生み出すための知識として、貴重だと思う。
この本は、あまりに多い情報量を、新書の紙幅で提示したため、編集の神様の仕事とはいえ、理解しやすい教科書としては、完璧とは言いがたい気はする。
だが、懇切丁寧に教わるより、ヒント、素材を受け取って、あとは、自分で考える方が、実りが多いということ、なのかもしれない。
そうか、これは問題集なのだと、途中で気がついた。
課題提示も多い。
各章で気づきがあり、結局、30枚以上のポストイットでマーキングだらけにしてしまった。
編集や企画で悩んだことのある人ならば、ピンとくる内容が散りばめられていると思う。
緻密で、大きな編集工学の体系を、そのまま受け取るのではなく。
自分なりに編集して、学ぶことができるように、著者が、深い配慮で編集した、なんていうのは、ちょっと傾倒、深読みしすぎであろうか。
【参照図書】
「才能をひらく編集工学 世界の見方を変える10 の思考法」安藤昭子(著)

「編集とは何か。」(星海社 e-SHINSHO)奥野武範(編)

「編集の提案」津野海太郎(著)宮田文久(編)川谷光平(写真)

「編集者、それはペンを持たない作家である 私は人間記録として、自分の感動を多くの読者に伝えたかった。神吉晴夫(著)

「みんなのフィードバック大全」三村真宗(著)

「千夜千冊エディション 編集力」(角川ソフィア文庫)松岡正剛(著)

「「アタマのやわらかさ」の原理。 クリエイティブな人たちは実は編集している」松永光弘(著)

「編集と表現」(はじめて学ぶ芸術の教科書)川﨑昌平(著)

「6つの思考スキルが最高評価をつくる 脳内編集力 正解がない世界で自分らしく生きる思考法」北村嘉崇(著)

■23夜230冊目
2024年4月18日から、適宜、1夜10冊の本を選別して、その本達に肖り、倣うことで、知文(考えや事柄を他に知らせるための書面)を実践するための参考図書として、紹介させて頂きますね(^^)
みなさんにとっても、それぞれが恋い焦がれ、貪り、血肉とした夜があると思います。
どんな夜を持ち込んで、その中から、どんな夜を選んだのか。
そして、私達は、何に、肖り、倣おうととしているのか。
その様な稽古の稽古たる所以となり得る本に出会うことは、とても面白い夜を体験させてくれると、そう考えています。
さてと、今日は、どれを読もうかなんて。
武道や茶道の稽古のように装いを整えて。
振る舞いを変え。
居ずまいから見直して。
好きなことに没入する「読書の稽古」。
稽古の字義は、古に稽えること。
古典に還れという意味ではなくて、「古」そのものに学び、そのプロセスを習熟することを指す。
西平直著「世阿弥の稽古哲学」
自分と向き合う時間に浸る「ヒタ活」(^^)
さて、今宵のお稽古で、嗜む本のお品書きは・・・
【「嗜む」のすすめ】編集技法の作法に焦がれ本を嗜む
「あずきがゆばあさんととら」パク・ユンギュ(著)ペク・ヒナ(イラスト)かみやにじ(訳)

「あいうえおえほん」とだ こうしろう(著)
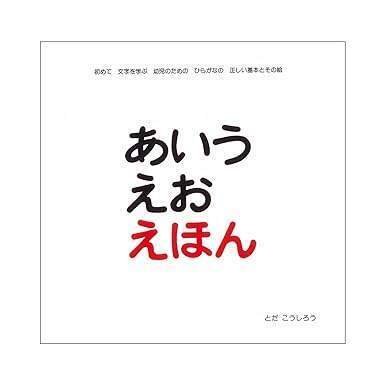
「おばけパ-ティ」ジャック デュケノワ(著)おおさわ あきら(訳)

「私はそうは思わない(ちくま文庫)佐野洋子(著)

「残りものには、過去がある」(新潮文庫)中江有里(著)

「子どものことを子どもにきく 「うちの子」へのインタビュー 8年間の記録」(ちくま文庫)杉山亮(著)

「私の好きなタイプ 話したくなるフォントの話」サイモン・ガーフィールド(著)田代眞理/山崎秀貴(訳)

「えーえんとくちから」(ちくま文庫)笹井宏之(著)

「声をたどれば」若松真平(著)

「毎日あほうだんす 横浜寿町の日雇い哲学者 西川紀光の世界」トム・ギル(著)

■(参考記事)松岡正剛の千夜千冊
・才事記
・バックナンバーINDEX 全読譜
・テーマINDEX 総覧帖MENU
・膨大な知層が織りなす文庫編成組曲
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
