
【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】リベラリズム
西欧近代の価値の普遍性という意識は、西欧の啓蒙主義思想によって生み出されたものだということが分かる。
西欧近代の価値観が世界化するかは分からない。
しかし、自由や平等といった抽象的価値の内容を決めるのは、社会独特の文化や、歴史や、伝統的規範意識であるということは言える。
このことは、伝統的価値や規範から開放され、それを打破して「近代」が出現するという「進歩主義」の図式で事態を理解してはならないということである。
また、近代の企ては、西欧でもうまくいってない。
自由や民主主義が実現した時代は、非常に退屈でつまらない時代であり、ニヒリズムをもたらしたからである。
リベラリズムの基礎づけがうまくいってないのもこれが原因だ。
【参考図書①】
「リベラリズムへの不満」フランシス・フクヤマ(著)会田弘継(訳)

「ハロルド・ラスキの政治学 公共的知識人の政治参加とリベラリズムの再定義」大井赤亥(著)

「政治的リベラリズム 増補版」ジョン・ロールズ(著)神島裕子/福間聡(訳)

「経済成長がすべてか?―デモクラシーが人文学を必要とする理由」マーサ・C.ヌスバウム(著)小沢自然/小野正嗣(訳)

「確実性の探求」を目指した西洋近代は、進展すればするほど生や世界観の「確かさ」を失わせていく。
ニーチェの予言したとおり、現在、我々は、ニヒリズムの時代にある。
つまり、西欧近代の行き着いた先である現在は、ニヒリズムだ、ということになる。
何ともやりきれない結論だ。
以前にも書いた通り、夏目漱石は、西欧進歩主義に疑問を呈したように、当時の開化が必ずしも人間の心理的苦痛を減じないと論じ、これを「開化のパラドクス」と呼んだ。
具体的には、かつては、
「生きるか死ぬか」
で、悩んでいたのが、今日は、
「いかに生きるか」
で、悩むようになり、開化によっても悩みは無くなっていないというのだ。
これは、不確定性、ニヒリズムの問題である。
【参考図書②】
「正義の教室 善く生きるための哲学入門」飲茶(著)
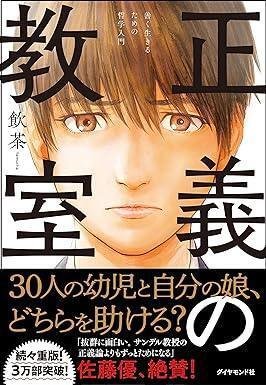
「3種の正義を追い求めようとしたとき、人間の思考は次のような主義に行きつく」
(1)「平等の正義」を実現するには → 功利主義(幸福を重視せよ!)
(2)「自由の正義」を実現するには → 自由主義(自由を重視せよ!)
(3)「宗教の正義」を実現するには → 直観主義(道徳を重視せよ!)
夏目漱石の「現代日本の開化」もそうだったが、「進歩主義」や「文明化」というものの限界を的確に指摘し、警鐘をならしている点だ。
リベラリズム陣営に顕著であるが、冷戦後の混迷の世界で、さらに西欧進歩主義を推し進めようとする動きが見られた。
「自由」や「民主主義」の無理な適用がその好例だ。
しかし、そのような「自由」や「民主主義」の表層的拡大は、成功しないし、そもそも、「自由」や「民主主義」自体が、ニヒリズムを生むと、佐伯啓思さんは指摘していた。
「自由」や「平等」といった抽象的価値の内容を決めるのは、社会独特の文化や歴史や伝統的規範意識であるからであり、それにもかかわらず、「自由」や「平等」は、歴史や伝統を掘り崩してしまうからだ。
これは形は異なるが、夏目漱石の「開化のパラドクス」と似ている。
【関連記事】
【読書メモ(その1)】「人間は進歩してきたのか―現代文明論〈上〉「西欧近代」再考」佐伯啓思(著)(PHP新書)
https://note.com/bax36410/n/nefe30662846e
【選書探訪:有難い本より、面白い本の方が、有難い本だと思う。】「集中講義!アメリカ現代思想 リベラリズムの冒険」仲正昌樹(著)(NHKブックス)
https://note.com/bax36410/n/ne6c2e038cf5f
【短評】欲望の資本主義の行き着く先
https://note.com/bax36410/n/nbd72e02c7b08
今日の政治体制は、近代政治哲学が構想したものである。
【参考図書③】
「近代政治哲学 自然・主権・行政」(ちくま新書)國分功一郎(著)

「はじめての政治哲学」(岩波現代文庫 学術)デイヴィッド・ミラー(著)山岡 龍一/森達也(訳)

「よくわかる政治思想」(やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ)野口雅弘/山本圭/髙山裕二(編)

ならば、その基本概念を再確認すれば、いま私達の体制が抱える欠点についても把握できるはず。
グローバル化のなかの共生倫理を考える指標として、以下の政治哲学に関して、
■功利主義
■プラグマティズム
■リベラリズム
■リバタリアニズム
■コミュニタリアニズム
その当時に発刊されていた新書をテキストにして、今回は、「リベラリズム」について省みたい。
【テキスト①】「アメリカ保守革命」中岡望(著)(中公新書ラクレ)

[ 内容 ]
アメリカで始まり、「アメリカ化」という形で世界を席巻する保守革命。
リベラリズムと対峙しながら思想運動として起こり、やがて現実の政策へと影響力を拡大していく発展過程を詳述する。
[ 目次 ]
第1章 戦後の保守主義のルネッサンス(アメリカのリベラリズムと保守主義思想;二人の保守主義思想のゴッドファーザー ほか)
第2章 保守主義思想とレーガン革命(思想運動から政治運動へ;保守主義思想の政治の代弁者たち ほか)
第3章 レーガン革命と冷戦後の保守主義運動(未完のレーガン革命;一九九〇年代の保守主義の思想闘争 ほか)
第4章 新しいエスタブリッシュメント―ネオコンの群像(ネオコンの創始者たち;ネオコンたちの思想的変遷 ほか)
第5章 ブッシュ政権と二一世紀の保守主義(ブッシュ政権の樹立と政策;ブッシュの経済政策―レーガノミックスの再現 ほか)
[ 発見(気づき) ]
世界を覆うアメリカ化、そして、その流れを汲んだ保守化の流れは、リベラリズムへの反対運動から始まった。
そして、次第に理論化、組織化され、まず伝統的な保守主義運動がウィーバー、カークらによって一定の完成を見る。
ベースは、伝統的価値の尊重、そして、人間は不完全な存在である、という認識、さらにキリスト教・ユダヤ教的価値観の尊重にあった。
その後、ヨーロッパの共産化の魔の手から逃れた亡命リバタリアンによって、ケインズ革命(政府が市場をコントロールする。国家や一部エリートの判断は市場の判断より勝る)への反対運動と古典派の復興が始まる。
当時、ケインズ主義者(今のアメリカでは社会主義者に近い扱い)のニューディール政策が経済学の世界を覆いつくしていた頃である。
この2つの運動は当初、互いに別々のものだったがメイヤーというジャーナリスト出身の学者が結び付けて、1つになったアメリカ保守主義大きな流れはやがて、レーガン革命へと昇華して行った。
[ 教訓 ]
レバタリアンやネオコンの経済政策について的確な分析がなされており、さらに、レーガノミクス(レーガンの経済政策)やブッシュ、クリントン経済政策についての分析も本書が一番分かりやすく、的確にまとまっている気がする。
アメリカの政治について知っておくことは、日本の将来を考える前提知識として絶対に欠かせないと思う。
[ 一言 ]
日本のジャーナリズムの中では、アメリカの保守は新世界のゼロから作り上げられた地域の保守であり、しかもヨーロッパ保守の亜流だ。
日本には伝統も地域社会もあるのだから、ヨーロッパ型の保守を目指すべきであるという意見に人気がある。
ただ、現実問題、世界のある程度政治的に影響力のある勢力はほとんど一神教がらみである。
マルクス主義もキリスト教のカウンターパワーとしての宗教と考えるのが合理的。
この種の保守思想について理解し、それを軸に動いている現実の世界を認識してその中を周囲を見つめて泳いでいくことが日本人には求められている。
現実は日本人の願望とは離れたところにあるが、私たちのアイデンティティは守れる&守るべき部分については守りたいものである。
[ 補足 ]
一般的に保守主義の思想的な特徴としては次の点が指摘される。
第一に、神の前において人間の賢しらを戒め、進歩主義的な観念論を偽りごととして批判する。
それは、戦後政治においては反共・反リベラルとして特徴付けられる。
第二に、政府機能は縮小させ、かわって各人の家族や共同体への帰属意識を重視する。
第三に、経済的な自由競争、自己責任原則を主張する。
ただし、これらが一律に主張されるわけではなく、宗教的倫理重視の伝統主義者と経済的自由重視のリバタリアンとが絡み合っている。
アメリカでは、F・D・ローズヴェルト政権のいわゆるニューディール政策によってリベラルが政治の主流となりつつあった。
そうした趨勢に対して戦後、保守主義思想は自前の立場を主張し始める。
いわゆる保守主義革命は三段階に分けられ、第一段階は1950年代、理論構築の時期。
第二段階は1960年代半ばからで、保守主義者は共和党に入って政治活動を開始した。
そして、1981年に誕生したレーガン政権への参加が第三段階となる。
しかし、レーガン政権への参加に伴う人事抗争、さらにはソ連という共通の敵が消滅したことにより、保守主義者内部の争いが表面化した。
具体的には、キリスト教右派などポピュリスティックな人々を中心とするペイリオコン(Paleo-Conservatism=旧保守)と、インテリ中心のネオコン(Neo-Conservatism=新保守)とに分裂したのである。
両者は次の点で相違する。
第一に、ペイリオコンとは異なり、ネオコンは宗教的倫理観を最優先課題とは考えない。
たとえば、ネオコンの中に同性愛者がいたらしいが問題にもならなかったという。
ペイリオコンには生まれながらの伝統主義者が多いのに対し、ネオコンには左翼からの転向者が多いという出自の違いもある。
第二に、ペイリオコンの主張が極めて情緒的であるのに対し、ネオコンは政策科学的な理論武装をもとに論陣を張った。
たとえば、ペイリオコンは福祉国家を悪しきものとして一方的に排斥するだけである。
しかし、ネオコンは統計データを分析して比較考量し、福祉政策によって依存者が増えるというマイナスよりも、福祉政策を撤廃したときの生活困窮者の問題の方が深刻であるならば、福祉政策路線を継続させるというリアルな対応を取る。
こうした政策ブレーンとしての有用性がレーガン政権以降ネオコンが重用された理由である。
第三に、国際政治への対応として、ペイリオコンは伝統的な孤立主義を主張する。
共産主義は倒れたのだからこれ以上アメリカは世界にしゃしゃり出てゆく必要はない。
これに対してネオコンは、国際秩序の形成にアメリカは責任を持つべきであり、そのためには軍事介入も躊躇してはならないと考えている。
ネオコンにはユダヤ人やカトリックが多く、その世界観には一神教的・十字軍的な使命感が垣間見られると指摘される。
イラク戦争の理由を石油利権等の分かりやすいファクターで説明しようとする議論がたまに見られるが、そんな単純な問題ではない。
アーヴィング・クリストル(Irving Kristol)がネオコンの理論的なキーパーソンとなるらしい。
しかし、彼も含めてネオコンのスタンスを一貫的に主張した理論書はないという。
ちなみに息子のウィリアム・クリストル(William Kristol)はホワイトハウス入りして政策立案で大きな役割を果たした。
独善的な理念の暴走を戒めるというのが保守主義思想の真髄であったはずだ。
そこから考えると、ネオコンというのは、まとっている衣は保守主義であっても、根本的にどこか異質な部分がある。
【テキスト②】「世界共和国へ 資本=ネーション=国家を超えて」(岩波新書)柄谷行人(著)

[ 内容 ]
「資本=ネーション=国家」という接合体に覆われた現在の世界からは、それを超えるための理念も想像力も失われてしまった。
資本制とネーションと国家の起源をそれぞれ三つの基礎的な交換様式から解明し、その接合体から抜け出す方法を「世界共和国」への道すじの中に探ってゆく。
二一世紀の世界を変える大胆な社会構想。
[ 目次 ]
序 資本=ネーション=国家について(理念と想像力なき時代 一九世紀から見た現在)第1部 交換様式(「生産」から「交換」へ 「交換」の今日的意味 ほか)
第2部 世界帝国(共同体と国家 貨幣と市場 ほか)
第3部 世界経済(国家 産業資本主義 ほか)
第4部 世界共和国(主権国家と帝国主義 「帝国」と広域国家 ほか)
[ 発見(気づき) ]
「私が本書で考えたいのは、資本=ネーション=国家を超える道筋、いいかえれば「世界共和国」に至る道筋です。」
資本主義と国民国家というスキームでは、主役が資本であって肝心の人間が疎外されている。
著者はこのスキームを超える世界観として、カントが提唱した世界共和国の概念にポストモダンの理想を追求している。
資本=ネーション=国家の基盤は貨幣を仲立ちにした交換様式である。
この交換には非対称性が伴う。
貨幣には商品と無条件に交換する権利があるが、商品には貨幣と交換する権利がない。
商品は売れなければ価値がないからである。
この非対称性が、資本の支配をもたらしている。
[ 教訓 ]
福祉国家資本主義、国家社会主義、リベラリズムという、既存の国家の形態に加えて4つめに、平等と自由を原理とする新しい交換原理を基盤とした「世界共和国」があるという。
チョムスキーは、この第4の形態の例として、アナキズムや評議会コミュニズムを入れているが、これらはこれまでのところ、現実には存在しない「統整的理念」に終わってきた。
「むろんカントは、こうした「世界市民的な道徳共同体」は政治的、経済的な基盤が根底になければ成立しないと考えていました。
しかも、彼はそれをきわめて具体的に考えていた。
たとえば、カントのいう「他者を手段としてのみならず同時に目的として扱う」という道徳法則は、資本主義においては実現できません。
貨幣と商品(資本と賃労働)の非対称性があるかぎり、そこにおかれた個人は他者を手段としてのみ扱うことを余儀なくされるのです。
もちろん、国家による統制や富の再分配によって、資本主義のもたらす階級格差を解消しようとすることは可能です。
しかし、階級格差をもたらすシステムそのものを変えるべきなのです。」
「目的として扱う」とは自由な存在として扱うということ。
自分が自由な存在であることが他者を手段にしてしまうことではならないとし、自由の相互性の実現こそカントの見出した道徳法則であった。
著者は再分配、互酬、商品交換という既存国家の交換原理に代わる新しい交換原理Xを世界共和国の基盤として見出す。
カントはその世界を小生産者(かつての多数であった職人的労働者)たちのアソシエーションと、「神の国」の実現のために諸国家がその主権を譲渡する世界共和制として考えた。
著者はその考えを現代的に読み替えて、共同体の想像的回復(普遍宗教的な運動)によるアソシエーションと、各国が軍事的主権と国際連合へ譲渡し、それによって国際連合を強化再編する道筋に、世界共和国実現の可能性があると結論している。
難しい本なのだが、ひらたくいえば、自由や平等や友愛という崇高な理念にひとりひとりが共鳴するなら、相互の自由を尊重する交換原理による、新しい社会主義的な世界共和国は理論的には実現できるはずだという思想家の意見表明である。
[ 一言 ]
今日、世界の運営方法を個人が直接に話し合う場として、インターネットがあると思う。
オンラインで小さなネットワークや共同体は無数に生まれているが、国家に対抗する力にまでは育っていない。
ネットで理想を唱えても、各人の足場は国家にあるからだ。
著者は「下から」の運動は「上から」封じ込めることによってのみ、分断をまぬかれ、徐々に新交換原理にもとづくグローバルコミュニティは実現に向かうと書いている。
何が足りないのだろうか。
やはりリーダーなのだろうな。
【テキスト③】「アメリカ外交 苦悩と希望」(講談社現代新書)村田晃嗣(著)

[ 内容 ]
「ブッシュ外交」への感情論、アメリカ「帝国」論議を超える外交・国際問題を学ぶための最良の教科書。
[ 目次 ]
第1章 アメリカ外交を見る眼
第2章 建国から大国へ
第3章 二つの世界大戦―内向的な大国
第4章 冷戦の起源と本格化―超大国の自覚化
第5章 冷戦の変容―ベトナム戦争とデタント、多極化
第6章 新冷戦から冷戦の終焉へ―カーターとレーガン
第7章 ポスト冷戦期―G.H.ブッシュとクリントン
第8章 九・一一からイラク戦争へ―G.W.ブッシュ外交
終章 これからのアメリカ外交と日本
[ 発見(気づき) ]
アメリカの外交史について書かれた本。
たとえば「デモクラシーの帝国」では、アメリカを圧倒的な軍事力を持つ「帝国」として描いている。
「デモクラシーの帝国 アメリカ・戦争・現代世界」(岩波新書)藤原帰一(著)

しかし本書で筆者は、「アメリカを「帝国」と呼ぶことは、アメリカのパワーに対する過大評価であり、アメリカと国際社会双方の複雑性と多様性に対する過小評価」と述べている。
というのは、軍事力だけが「力」の源泉ではないからである。
それに、世界が一極構造になっている、ということは、一極支配とイコールではないのである。
本書ではパワーを、軍事力、経済力、価値(情報、文化、規範)の3つの観点から分析している。
それだけでなく、分析のレベルを、国際システム、国内レベル、個人レベルの3つにわけるなどして、より丁寧に状況を記述し分析しようとしているのである。
このような分析概念が提示した上で、本書ではアメリカの外交史を、建国から現在までを分析されている。
それも、典型的な方向性として、ハミルトニアン(海洋国家)、ジェファソニアン(大陸国家)、ウィルソニアン(理念追求)、ジャクソニアン(国威高揚重視)の4つの方向性を提示し、それらの出方の違いとして各時代の外交を記述しているのである。
ちなみにブッシュ政権は、ジャクソニアン(チェイニーとラムズフェルド)やジェファソニアン(パウエル)などの様々な勢力が合従連衡する混成チームだったのだが、9.11とアフガニスタン攻撃の頃から、自由や民主主義といった理念を強調するウィルソニアン敵色彩を強めていった、というように分析されているわけである。
[ 教訓 ]
国際政治学の基本的な見取り図の作り方としてはリアリズムとリベラリズムの二つが代表的なものと言えよう。
リアリズムは国家間の対立関係を不可避なものと考え、パワー・バランスによって紛争の回避を目指す。
リベラリズムは国際社会の相互依存関係に着目し、協調の可能性を模索する。
近年、もう一つの考え方としてコンストラクティヴィズム(構成主義)も有力となってきた。
人間同士にしても、国家間関係にしても、目の前にいる奴は友好的なのか敵対的なのか、相手をどう捉えるかによっておのずと態度は違うし、そしてこちらの態度に応じて相手の反応も変わってくる。
つまり、相互の関係性も、認識のあり方によって後から構築されていくという側面がある。
そのように、外在的な環境要因ばかりでなく、国際政治におけるアクター自身の内在的な要因から組み立てられた自己イメージ、他者イメージのあり方に応じて外交関係も大きく変化し得ることを重視する観点がコンストラクティヴィズムと呼ばれる。
9.11以降、アメリカ外交におけるユニラテラリズムが際立ち、これを“帝国”とみなす議論が盛んになっている。
だが、コンストラクティヴィズムの立場からすると、“帝国”アメリカというイメージばかりが一人歩きを始めてしまうと、ヒョウタンから駒と言おうか、アメリカ自身もまたそうしたイメージ規定に絡め取られてますます極端な振舞いへと暴走してしまうおそれすら考えられる。
いずれにせよ、国際政治はほんの些細なきっかけでも事態が大きく変わってしまうデリケートな性質がある。
そこには表面からはうかがい知れぬ微妙な伏線が縦横に張り巡らされており、一面的なキーワードで決めつけてしまう見方は慎むべきであろう。
ステレオタイプなアメリカ“帝国”論、ブッシュ悪玉論はまったく無意味である。
アメリカ外交を動かす要因として本書はハミルトニアン・ジェファソニアン・ウィルソニアン・ジャクソニアンという4つのキーワードを挙げている。
それぞれ過去の大統領の名前に由来する。
対外的な関与の方向を軸に取ると、ハミルトニアンは積極的で海洋国家志向を持つ。
これに対してジェファソニアンは国内的な安定と繁栄が最優先で、内にこもった孤立主義の傾向がある。
対外関与の態度のあり方を軸に取ると、ウィルソニアンは民主主義を世界に広げなければならないという理想主義的な使命感を持っている。
これに対してジャクソニアンはアメリカの安全と繁栄のためには実力行使も辞さずというユニラテラリズムの傾向がある。
本書はこうした4つの傾向が絡み合ってアメリカの政治・外交が織り成されてきた姿を描き出しており、建国から現在に至るまでのコンパクトな通史として読みやすい。
外部との相互作用によって、アメリカ自身が抱えている内在的な要因の、あるものは表面に出て目を引き、別のあるものは沈潜して見えなくなり、また複数が組み合わさることでもアメリカの顔の見え方は大きく変わってくる。
そうした複層的なアメリカの姿を本書はきめ細かく描き出しており、肯定するにせよ否定するにせよ、ともすると一面的に陥りがちなアメリカ認識を解きほぐしてくれる。
[ 一言 ]
本書は、外交という観点から、ある程度の視点を持ってアメリカを捉えなおすことができるという点では、興味深い本であった。
ただし、各時代にみられるそれぞれの傾向が基本的に記述されているだけである部分が多いのは、私としてはちょっと残念に思った。
ここの部分が単なる記述だけでなく、大きな意味での「流れ」なり、変遷の背景にまで踏み込んでくれるといいのになあ、という感じである。
もっともこれは、政治オンチの私の私見であって、そういうことが可能なのかどうかはわからないのだが。
【テキスト④】「「資本」論 取引する身体/取引される身体」(ちくま新書)稲葉振一郎(著)
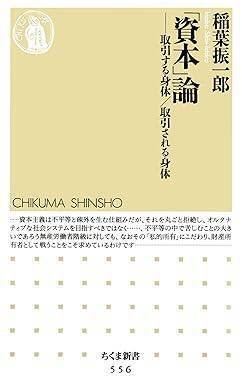
[ 内容 ]
「私的所有」が制度化され、市場経済が発展し、資本主義の秩序が支配する世界は、それ以前の「自然」な状態よりも、おおむね有益である。
だがそうした世界は不平等や労働疎外をも生みだす。
それでもなお、私たちはこの世界に踏みとどまるべきであり、所有も市場も捨て去ってはならない。
本書はその根拠を示し、無産者であれ難民であれ「持たざる者=剥き出しの生」として扱われることがないよう、「労働力=人的資本」の所有者として見なすべきことを提唱する。
「所有」「市場」「資本」等の重要概念を根本から考察した末に示されるこうした論点は、これからの社会を考える上で示唆に富む。
[ 目次 ]
プロローグ 自然状態からの社会契約
1 「所有」論
2 「市場」論
3 「資本」論
4 「人的資本」論
エピローグ 法人、ロボット、サイボーグ―資本主義の未来
[ 問題提起 ]
リベラリズムとは、他者への寛容を旨として、市場経済のもとで所得の再分配を広く認める考え方だ。
個人的にはほかに社会がうまくいくあり方はないだろうと思うのだが、一方には新保守主義(≒ネオリベラリズム)とよばれる市場原理主義的な考え方があり、他方には市場経済に代わるしくみを模索する共産主義的な考え方もある。
リベラリズムは中庸ともいえるのだけど、なぜ再分配が認められるのかという問いに対して十分答えきれてないような気がしていた。
[ 結論 ]
それに対してはホッブズやロック(そしてヒューム)が唱えた社会契約説が回答としてあげられるのだけど、伝統的な社会契約説は資産をもつ市民が対象で、何ら財産を持たない労働者階級(ぼく自身もここに属することになる)の人々は埒外におかれている。
もちろん国民国家というものの形成によって、これらの人々も国家の内部に取り込まれたのだけど、論理的には国家に寄宿している形になり、実際「国家以外に貧しい庶民を守ってくれる者はない」わけで、過度に国家に依存することになり排他的なナショナリズムを生み出しやすい。
また、逆に国家の側からみると、資産というものを仲介せず彼らの「剥き出しの生」と相対するので、守ってやる代わりに戦時には命を差し出せという要求が暗黙裏に可能になってしまう。
本書では、労働者の人々が「労働力=人的資本」という資産をもっていると位置づけたらどうかという、提案をしている。
土地を所有している人がその所有の権利のうち幾分かを国家に譲り渡す代わりに国家がその所有権を護るという保障を得ているのと同様に、労働力=人的資本についても双方向の契約が成り立っているとみなすのだ。
重度の障碍者についても、テクノロジーの発展に伴って、何らかの労働になる可能性があるとみなす。
もちろん特殊な技能でもない限り、労働力=人的資本だけを頼りに国外に移住したりすることは不可能なので、国家に依存していることにかわりがないが、少なくとも国家と対等に向かい合うための論理的な基盤が確保できるのだ。
[ コメント ]
ちょっとまどろっこしいくらいの丁寧さで書かれているが、中身はかなり刺激的な本だ。
エピローグの、ロボットやテクノロジーの力で改変された「ポストヒューマン」の話もおもしろい。
【テキスト⑤】「「不自由」論 「何でも自己決定」の限界」(ちくま新書)仲正昌樹(著)

[ 内容 ]
グローバル化の進展につれて、何かにつけて「自己決定」が求められるようになってきた。
その背景には、人間は「自由な主体」であるという考え方がある。
しかし人間は、すべてを「主体的」に決められるわけではない。
実際、「自由な主体」同士の合意によって社会がつくられるという西欧近代の考えは、ほころび始めてきた。
こうした「ポスト・モダン」状況にあって我々は、どう振る舞えばいいのか?
そもそも「自由な主体」という人間観は、どう形成されたのか?
こうした問いを深く追究した本書は、近代社会の前提を根底から問い直す、新しい思想の試みだ。
[ 目次 ]
第1章 「人間は自由だ」という虚構(現代思想における「人間」 よき人間と悪しき人間 ほか)
第2章 こうして人間は作られた(人間的コミュニケーションの習得 コミュニケーションの「普遍性」と「特殊性」 ほか)
第3章 教育の「自由」の不自由(「人間性」教育としての「生きる力」論 「ゆとり」から「主体性」は生まれるか? ほか)
第4章 「気短な人間」はやめよう(主流派としての「リベラリズム」 挟撃される普遍主義 ほか)
[ 問題提起 ]
私たちの多くは、「自分のことは自分で決めなさい」「自分のやりたいことをやりなさい」と言われて育てられてきた。
そこにあるのは人間は生まれながらに「主体性」を持っていて、自身の「主体性」によって「自己決定」できるという近代的な人間観である。
著者はその人間観の成り立ちから、その限界を明らかにしていく。
[ 結論 ]
自身の「状況」とか「コンテクスト」とか「関係性」等が全く考慮されない自由な「主体性」というのあり得ない。
ワタシたちが「主体性」と呼ぶものの多くは、「気短さ(short-temperedness)」である。
つまり、周囲の状況や関係性を余り考えずに、迅速に決断できるということが、他人の影響から自由に「自己決定」できるということになる。
これは、回転効率を重視する資本主義に適した考え方であるし、逆に言えば、ワタシたちは、そうした自由に見える「主体的」な「自己決定」を強いられているとも言える。
また、最後に著者が言っているように、「思考」と「実践」は分けて考えた方が良いというのにはワタシも激しく同意する。
[ コメント ]
多くの思想家が登場して、新書とはいえ割と難解な本。
しかし社会思想に関心がある人や哲学っぽさが好きな人にはオススメしたい骨太の一冊。
【テキスト⑥】「ヨーロッパとイスラーム 共生は可能か」(岩波新書)内藤正典(著)

[ 内容 ]
ヨーロッパ先進諸国に定住するムスリム人口は、二世、三世を含め今や一五〇〇万以上といわれている。
増加と共に目立つようになってきた受け入れ国社会との摩擦は、何に由来するのだろうか。
各国でのフィールドワークを踏まえて、公教育の場でのスカーフ着用をめぐる軋轢などの現状を報告し、異なった文明が共生するための可能性を探る。
[ 目次 ]
序章 ヨーロッパ移民社会と文明の相克
1章 内と外を隔てる壁とはなにか―ドイツ(リトル・イスタンブルの人びと 移民たちにとってのヨーロッパ 隣人としてのムスリムへのまなざし)
2章 多文化主義の光と影―オランダ(世界都市に生きるムスリム 寛容とはなにか ムスリムはヨーロッパに何を見たか)
3章 隣人から見た「自由・平等・博愛」―フランス(なぜ「郊外」は嫌われるのか 啓蒙と同化のあいだ―踏絵としての世俗主義 「ヨーロッパ」とはいったい何であったか)
4章 ヨーロッパとイスラームの共生―文明の「力」を自覚することはできるか(イスラーム世界の現状認識とジハード ヨーロッパは何を誤認したのか)
[ 問題提起 ]
ドイツ・オランダ・フランスそれぞれの社会におけるムスリム移民の状況の考察を通して本書はイスラーム的規範と西洋文明的規範との考え方のズレを浮き彫りにする。
ドイツの社会習慣を理解してビジネスを成功させてもドイツ人にはなれないと述懐するトルコ人実業家が紹介されている。
移民はいつまでたってもガストアルバイター扱いで、同じ社会の一員とみなす発想は希薄だという。
疎外感からムスリムとしての覚醒をする動きが現れる。
衛星放送のパラボラアンテナが林立しているのを見て、母国トルコとの距離は近づいたものの、トルコ系移民とドイツ社会との心理的・文化的距離は逆に遠くなってしまったという指摘が印象に残った。
[ 結論 ]
ベネディクト・アンダーソンが示した“ポータブル・ナショナリズム”というキーワードを思い出した。
ドイツでは政治への参加資格として国家への帰属を求めるのに対し、もともと商業国家として成立してきたオランダの場合、納税を重視する。
スペイン・ハプスブルク家によるカトリック押し付け政策に対して独立戦争を戦ったという歴史的経緯があるためなのか、文化的多元主義をとり、宗教面でも列柱的共存が図られている。
それは他者の権利を認めるが、同時に相手への無関心をも意味する。
男女関係の乱れ、伝統的家族像の崩壊、麻薬に寛容な社会風潮などへの違和感から、保守的なムスリムとキリスト教政党が道徳感情のレベルで近いというのが興味深い。
フランスでの政治参加の要件はフランス語である。
また、周知の通り、フランスは国家と宗教とを厳格に分離する世俗主義(ライシテ、laicite)を徹底させている。
その背景については、下記の新書を参照のこと。
「宗教VS.国家 フランス<政教分離>と市民の誕生」(講談社現代新書)工藤庸子(著)

それは公的領域と私的領域とを分け、宗教はあくまでも個人の心の問題として認められ、パブリックな場面では一切表に出してはいけないとされる。
しかし、イスラームには聖俗分離という発想そのものがない。
つまり、内面において信仰心を持つだけでなく、教えに定められた行為を日々の生活の中で実践し、その積み重ねがあってはじめてムスリムといえる。
この点で摩擦が起こってしまう。
[ コメント ]
社会的同化を求める右派がイスラームに不寛容なのは理解しやすいにしても、リベラリズムに立脚する左派もまた、イスラームは人権抑圧的・反民主的・女性蔑視的として批判的なのは難しい問題だ。
フランスの世俗主義・啓蒙主義の“普遍性”に疑問を向けることすらしない点を本書は批判する。
また、これはキリスト教とイスラームとの対立というよりも、キリスト教と決別した世俗主義とイスラームとの衝突として把握する視点に関心を持った。
【テキスト⑦】「ネオリベラリズムの精神分析 なぜ伝統や文化が求められるのか」(光文社新書)樫村愛子(著)

[ 内容 ]
市場至上主義、雇用の流動化、社会保障の縮小、ワーキングプア、格差、貧困、自己責任社会―。
グローバル化経済のもと、多くの人々の生活が不安定化(プレカリテ)していくなかで、どのように個人のアイデンティティを保ち、社会を維持していけばいいのか?
自分探し、心理学、お笑い、オタク文化、メディア・スピリチュアリズム、リアリティ・ショーの隆盛はいったい何を意味するのか?
ラカン派社会学の立場から、現代社会、あるいは現代の人々がぶつかっている難問を記述し、処方箋の一端を示す。
[ 目次 ]
第1章 プレカリテとは何か?
第2章 再帰性のもつ問題
第3章 なぜ恒常性が必要なのか?
第4章 共同性を維持する現代の社会現象
第5章 電子メディアと解離的人格システム
第6章 文化の役割
[ 問題提起 ]
単行本「「心理学化する社会」の臨床社会学」がなかなか面白かった、樫村愛子初の新書。
「「心理学化する社会」の臨床社会学」(愛知大学文學会叢書)樫村愛子(著)

ただ、いくらなんでもこの本は詰め込みすぎだと思う。
[ 結論 ]
内容を箇条書きで紹介すると、
「プレカリテ」(=不安定性)というフランスで使われだした言葉をキーワードにしてネオリベラリズムのもたらす問題点を指摘し、それに対抗する思想をフランス社会に探る。
このへんは下記の新書の主張と少し被る。
「日本とフランス 二つの民主主義~不平等か、不自由か~」(光文社新書)薬師院仁志(著)

その問題をギデンズの「再帰性」の考えでもって社会学的に位置づけ、安定した生活には「再帰性」と、社会の安定を示す「恒常性」の2つが必要だということを述べる。
「恒常性」がなくなり、歪んだ「再帰性」が幅を利かせる現代社会を分析し、それに抵抗できるものとして精神分析の有効性を主張。
そういった社会観と精神分析の道具をもとに、ニューエイジやスピリチュアリズム、オタク文化、お笑い、電子メディアなどを分析。
さらに部分部分に安倍内閣の政治(この本の中でのネーミングは「安倍原理主義」)や東浩紀の「動物化」の議論を批判。
という盛りだくさんの内容でして、これを320ページほどの新書で書こうとしているわけですが、読んだ感想としてはやはり厳しい。
フランスでもサルコジ政権が誕生したことで、著者がネオリベラリズムの広がりに危機感を持っているというのはわかるのだが、政治と文化の両面から批判するのではなく、著者が得意な文化批評を中心に据えた方がまとまったものになったと思う。
【参考記事】
新自由主義(ネオリベラリズム)への大誤解と言いがかり
日本人が知らない自由主義の歴史~後編(3)ネオリベラリズムの登場と誤解
戦後復興を実現した「ネオリベラリズム」がなぜ悪口に?
日本人が知らない自由主義の歴史~後編(4)戦後復興と「ネオリベラリズム」
また、ここからは少し専門的なことになるが、そもそも著者が依拠するラカンの理論と「再帰性」の概念は両立しないのではないか、という疑問がある。
著者は「再帰性」を「自分自身の行為を振り返り、その結果をもとに自己をコントロールする能力」という形で捉えているわけであるが、「人間の欲望は<他者>の欲望である」と言い切るラカンにとって、「再帰性」のような考えは幻想以外の何ものでもないのではないか?
著者はイマジナリーな領域(つまり「想像界」)の重要視しているが、それは「想像界」だけがコントロール可能、つまり「再帰性」の概念と衝突しないからなのであろう。
けれども、そのぶん特に「象徴界」の重要性を無視してしまっていると思う。
[ コメント ]
ただ、内容の薄い新書が多い中で、ここまで内容が濃い新書というのも珍しいかもしれない。
著者の考えに素直に賛成することはできないが、読み応えのある本であることは確かである。
【テキスト⑧】「市場主義の終焉 日本経済をどうするのか」(岩波新書)佐和隆光(著)
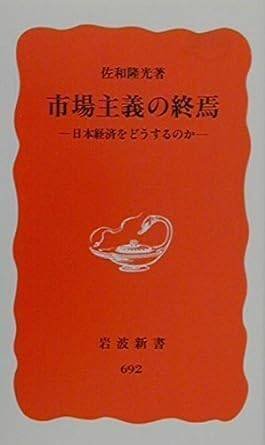
[ 内容 ]
長期不況下で閉塞感に覆われた日本。
旧来の制度・慣行の非効率を正すのに「市場」の役割は不可欠だが、万能視はできない。
格差・不平等をどう問い直すか、IT革命にどう対応するか、二〇世紀型産業文明からどう脱却していくのか。
「市場の暴走」を制御しながら、効率的で公正なシステムの構築をめざす確固たる指針を示す。
[ 目次 ]
序章 市場主義の来し方ゆく末
第1章 相対化の時代が始まった
第2章 進化するリベラリズム
第3章 日本型システムのアメリカ化は必要なのか
第4章 「第三の道」への歩み
第5章 グローバリゼーションの光と影
[ 問題提起 ]
著者の佐和隆光は、計量経済学、環境経済学を専門としている京都大学経済研究所教授であり、日本で最も著名な経済学者の一人。
それが証拠に本書も江湖に広く迎えられた。
[ 結論 ]
1979年、イギリスに誕生したサッチャー政権は、81年に発足したアメリカのレーガン政権と相呼応しつつ、積極果敢な市場主義改革を断行した。
わが国に目をやると87年から90年にかけてのバブル経済期、日本人の精神面での劣化=拝金主義が進み、私利私欲の追求にうつつを抜かすやからが、わが物顔で巷を横行闊歩するようになった。
89年のベルリンの壁崩壊、91年のソビエト連邦解体は、社会主義への幻滅を駄目押ししたのみならず、グローバルな市場経済化へ向けての怒涛の大波の堰を切った。
こうして80年代から90年代前半にかけて、市場主義という復古思想は、日本を、そして世界をすみずみまで浸しきったのである。
この市場主義に対して著者は、「終焉」を宣する。
その理由は本書で縷々述べられいるが、要は20世紀末から21世紀初頭にかけて起きた様々な「変化」に対して、市場主義改革だけでは「適応」しきれないと説くのである。
市場主義社会を超える革新的な社会経済システムが、したがって市場主義をこえる革新的な社会思想が、いま再び求められていると。
ケインズ経済学がそのまま復権するわけでも無論ない。
イギリスのブレア首相のいう「第3の道」―一言に要約すれば、市場主義と反市場主義を止揚(良いところどり)する体制 ―がそれに近いという。
今世紀に入り今後、世界を、そして何よりも日本を震撼させる、予想もしない「変化」が次々と起こるとで。
そうした「変化」への「適応」こそが、新しい社会経済システムを生む源泉となるはず。
にもかかわらず、日本のエコノミストの多くは、時代文脈のダイナミックな「変化」を読み解くことを怠り、かつては日本型制度・慣行の優位をとなえ、いまではその劣位をあげつらい、市場主義改革の必要性を唱えることのかまびすしいことといったらなかった。
そこで、佐和は断言する。
市場改革の積み重ねにより、この国の構造をアメリカ型に作り変えてみても、21世紀初頭の時代文脈にふさわしくはない、と。
なすべきことは、時代文脈の「変化」を先取りして、「変化」への「適応」を首尾よく成し遂げることにより、21世紀初頭の時代文脈に適合する、革新的な社会経済システムを創造することなのでる。
では、20世紀末期にいたり不振にあえいでしまった日本経済を、どう改革すればよかったのか。
この難問に対するエコノミストの答えは多くの場合、「日本型システムのアメリカ化」と「市場主義改革の断行」のふたつに要約されていた。
市場主義改革は、「必要」ではあるが「十分」ではない。
では、「必要」にして「十分」な改革とはなんなのかについての私見を、佐和は本書で提示する。
[ コメント ]
以上の記述で本書に御興味を持たれた方は、是非じかにあたることをお奨めする。
ラーメン一杯の値段で購入できるのですから、決して損はしないと思う。
【テキスト⑨】「公共哲学とは何か」(ちくま新書)山脇直司(著)

[ 内容 ]
人びとの間に広まるシニシズムや無力感、モラルなき政治家や経済人、やたらと軍事力を行使したがる大国―こうした大小さまざまの事態に直面して、いま「公共性」の回復が切実に希求されている。
だがそれは、個人を犠牲にして国家に尽くした滅私奉公の時代に逆戻りすることなく、実現可能なものだろうか?
本書は、「個人を活かしつつ公共性を開花させる道筋」を根源から問う公共哲学の世界に読者をいざなう試みである。
近年とみに注目を集める「知の実践」への入門書決定版。
滅私奉公の世に逆戻りすることなく私たちの社会に公共性を取り戻すことは可能か?
個人を活かしながら公共性を開花させる道筋を根源から問う知の実践への招待。
[ 目次 ]
第1章 公共哲学は何を論じ、何を批判し、何をめざすのか
第2章 古典的公共哲学の知的遺産
第3章 日本の近・現代史を読みなおす
第4章 公共世界の構成原理
第5章 公共哲学の学問的射程
第6章 グローカルは公共哲学へ向けて
[ 問題提起 ]
本書は「公共哲学」という新しい学問領域を提唱するものである。
「公共哲学」とは何か。
それは文字どおり、「公共性や公共的という概念を哲学的に探求すること」(17頁)である。
しかしそれだけではない。
山脇直司は「公共哲学」には上記の主題に加えて、批判の標的と目指すべき目標を含んでいるという。
[ 結論 ]
まとめると以下のようになる(第1章)。
【目指すべき目標 ← 批判の標的】
「活私開公」 ← 「滅私奉公」「滅公奉私」
「政府の公/民(人々)の公共/私的領域」 ← 公私二元論
学問横断的な知 ← タコツボ的学問状況
理想主義的現実主義・現実的理想主義 ← 理想主義、実証主義
「ある」「あるべき」「できる」の統合的論考 ← 「ある」、「あるべき」
「自己―他者―公共世界」
以下、本書は「公共哲学」の立場から、アリストテレス、ホッブス、ロック、ルソー、ヒューム、アダム・スミス、カント、フィヒテ、ヘーゲル、儒教、中江藤樹、荻生徂徠、横井小楠(以上、第2章)、植木枝盛、中江兆民、福沢諭吉、田中正造、吉野作造、福田徳三、南原繁、丸山真男(以上、第3章)、らの議論を再解釈する。
そして第4章では「公共世界の構成原理」としてコミュニケーション、正義(公正)、人権・徳・責任、福祉、平和、公共善を検証、第5章では「公共哲学」が政治社会、経済社会、社会組織、科学技術・環境問題、教育、宗教などの領域とどのように関わるかが論じられる。
最後に第6章で、それまでの記述を踏まえながら、山脇直司が現代社会に必要と思われる公共哲学のあり方を「グローカル公共哲学」として展開する。
このような新しい学問の提唱というのはなかなかできることではない。
したがって山脇直司の意気込みは評価したい。
しかし、私が本書を読んで「公共哲学」という学問が必要だという議論に納得させられたかというと、そうではない。
なお、形式的なことを言うと、本書では「公共哲学」の客観的説明と山脇直司の個人的見解の区別が明確でない。
これはこれで問題だと思われるが、以下、本書で述べられていることは、筆者の考え(207頁)と明記されている第6章以外は「公共哲学」の説明と解する。
まず、本書で展開される個々の議論は決して目新しいものではない。
「活私開公」は共同体主義や共和主義の議論として捉えられるし、理想主義と現実主義の相補性については例えば既にE.H.カーが「危機の二十年」で指摘している。
「危機の二十年――理想と現実」(岩波文庫)E.H.カー(著),原彬久(訳)

もっとも、カーはメタ論的に、学問は理想主義と現実主義が交互に表れるという動態的相補的関係に捉える。
後述参照。
「学問横断的な知」も、「総合政策」や「総合文化」などの学部学科や、平和学、国際関係論といった一つの専門を超えた学問領域を考えれば、まったく新しい試みだとは言えない。
こうして個々の論点を見ると、どれも既成の学問分野で既に触れられていることだという気がする。
また、「公共哲学」が扱う領域を見ても、「社会哲学」や(広義の)「社会学」、「政治思想」、あるいはもっと広く「社会思想」と呼ばれるものとどう異なるのかがはっきりしない。
そうだとすると敢えて「公共哲学」という新しい学問を提唱する意義がどこにあるのか。
それが本書からは見えてこなかった。
次に、「公共哲学」は新しい「学問」と称していいのかという疑問が残る。
上で、「公共哲学」は社会思想や社会哲学とどう異なるのかという疑問を呈したが、本書には、「公共哲学」と社会学理論(ただしここでは政治学や経済学とは区別された狭義の社会学)との区別として次のような説明がある。
すなわち、20世紀後半の社会理論が「システム」か「生活世界」を根本概念としていたのに対し、「公共哲学」は(中間団体を含めた)「公共世界」を分析対象とする(128頁以下、184頁以下)、と。
しかしこれは学問領域の相違というよりも、アプローチ方法の問題である。
そしてもしアプローチ方法の違いであるとすれば、それはマルクス主義、リベラリズム、共同体主義などと同様、(「~学」ではなく、「~主義」「~学派」と称するべきものではないか。
本書で言う「公共哲学」が「学問」なのかという疑問の根拠は他にもある。
本書では例えば、「反公共哲学的」という言葉が散見される(53頁、63頁、95頁など)。
しかし、法学でも政治学でも歴史学でも経済学でも文学でも物理学でもいいが、「反法学」とか「反政治学」というような説明のある入門書があるだろうか。
レトリックとして「反経済学」、「反哲学」と言ったりはするが。
恐らくないであろう。
なぜなら「学問」というのは「問い」を共有する知識・方法の体系だからである。
学問それ自体に善い悪いはなく、有用かそうでないかだけだ。
それなのに本書では「公共哲学的」な考えと「反公共哲学的」な考えが明確に区別されている。
「公共とは何か」という「問い」に対する開かれた「答え」の体系であるならば、「公共哲学」は「学問」と言えよう。
しかし、初めから「反公共哲学的」というように「悪い答え」が決められている(つまり、「答え」が開放的でない)「公共哲学」が「学問」と言えるのだろうか。
国際政治学・国際関係論の父と言われるE.H.カーの代表的著作『危機の二十年』は「新しい学問のはじまり」という章ではじまる。
もちろん「新しい学問」とは「国際政治学」を指す。
カーはそこで新しい学問のはじまり方をこう分析している。
まず目的(理想)が分析に先行した「ユートピア的」段階がある。
しかし理想と現実の格差を感じた時、反動として分析に力点を置く「リアリズム」の段階に移る。
それ以降は、リアリズムの不毛性にユートピアニズムが呼び出され、ユートピアニズムの生き過ぎをリアリズムが抑える、というサイクルが続く。
そしてカーはこう述べている。
「どのような学問も、全能を自負することのない謙譲の域に入り、めざすことへの願望と実在するものについての分析とを区別することのできる、きびしくつつましい在りようをとりうるまでは、学の名をうけるに値しないのである。」(井上茂訳「危機の二十年」岩波文庫、32-3頁)
私はカーの意見に賛成である。
そしてもし学の名をうける条件がカーの言うとおりであるとすれば、「公共哲学」はまだ「学問」とは言えないと思う。
上述のように、目指すべきことへの願望が強く押し出されており、それと実在するものについての分析との区別が明確でないと感じるからだ。
しかし他方で、あらゆる新しい学問はユートピア的段階ではじまるという点に注目すれば、「公共哲学」は「学門」への途上とも考えられる。
この点は今後の発展を見守るしかない。
実は、山脇直司自身も本書で、「学問」についてではないが、「学問の世界」について次のように語っている。
「そもそも学問の世界は、「それまでの蓄積をもとに批判と創造によって不断に更新されていくべき公共知」が主に追求されなければなりません。
しかし、そのようなダイナミックな公共知が展開されず、同業者仲間のピアレビュー(仲間うちの評価)やネポティズム(縁者びいき)によって、学問がなかば「私化」されていくような状態は、学界の業界化にほかならないでしょう。」(121頁)
私もその通りだと思う。
そしてこれは「公共哲学」にも当然該当するであろう。
例えば、本書は山脇直司自身が編集委員を務める「公共哲学」シリーズ(東京大学出版会)からの引用が多く、ピアレビューやネポティズムと見られかねない。
さらには、「公共哲学」はまだ「学問分野」としての歴史が浅く、批判と創造のサイクルの蓄積も十分にない。
カーの学問論も、山脇直司のあるべき「学問の世界」論も、学問の条件として相応の蓄積を挙げている。
ということは「公共哲学」が「学問」であるかどうかは、今後の研究・議論の蓄積如何に関わっていると言えよう。
以上、本書の感想を「新しいか?」「学問か?」に注目して批判的に記してきた。
ただし、私は本書で示されている個々の論点には一般論としては賛成である。
上で述べたようにそれらが新しいものだとは思わないが。
特に、共同体主義(コミュニタリアン)の考えに共感する私としては、佐伯啓思のような国家主義でない共同体論が新書レベルで展開されているというのも嬉しい。
国家のみが共同体でないのは明らかだからだ。
[ コメント ]
「公共哲学」の動きが契機となって日本でも共同体主義の議論が活発になることを期待したい。
【テキスト⑩】「アメリカの宗教右派」(中公新書ラクレ)飯山雅史(著)

[ 内容 ]
アメリカ宗教右派は、大規模な草の根保守主義運動の展開で、アメリカの政治にインパクトを与えてきた。
現代史におけるそのダイナミックな動きを、コンパクトにまとめたのが本書である。
大規模な草の根保守主義運動の展開で、同時代のアメリカ政治にインパクトを与え続けてきた宗教右派。
現代史におけるそのダイナミックな動きを、コンパクトにまとめたのが本書である。
どうして巨大な勢力に成長できたのか。
宗教右派を支持してきたのは、どのような人たちなのか。
彼らが求めてきたものはなにか。
これらを知らなければ、今のアメリカを理解することは難しい。
本書では歴史を遡りながら、基礎知識としてのアメリカ宗教問題を説く。
[ 目次 ]
第1章 プロテスタントとアメリカ
第2章 プロテスタント大分裂
第3章 リベラルの時代
第4章 宗教右派は何を求めているのか
第5章 宗教右派の勃興とモラル・マジョリティー
第6章 確立した宗教右派運動とキリスト教連合
第7章 ブッシュ政権と宗教右派の絶頂期
第8章 21世紀アメリカの宗教勢力地図
第9章 宗教右派の停滞と福音派の影響力
[ 問題提起 ]
本書の冒頭には、こんな数字が紹介されている。
アメリカではダーウィンの進化論を信じている人は、国民の約4分の1にしかすぎず、一方、神による天地創造説を信じている人は4割にものぼる。
日本人にはにわかに信じがたいこの数字は、アメリカが現在なお、宗教国家であり続けていることを示しているようだ。
したがって、
「米国はピューリタンの移民の時代から、基本的には宗教国家と言ってもいい。
欧州でも日本でも、近代化が進むと社会から宗教の影響が薄れて世俗的になってきたが、アメリカはそうではない」
と著者が語るように、宗教という視点を欠いたアメリカ論は、ニコチン抜きのタバコ、カフェイン抜きのコーヒーと同じで、ほとんど「論」の体をなさないはずだ。
本書は、アメリカの政治や社会を理解するうえで、最低限知っておきたいアメリカの宗教事情を「宗教右派」という視角から概説したものである。
[ 結論 ]
具体的には、アメリカのプロテスタントの動向を辿りながら、宗教右派の勃興から現在までの運動史やその主張内容がコンパクトにまとめられている。
読後感は歴史の教科書のそれに近く、もっぱら初学者に向けて知識の整理に徹した本であるため、著者独自の論や主張はほとんどない。
新書としてはやや知識を詰め込みすぎたきらいもあるが、本書を読むことで、アメリカ政治を見るパースペクティブはずいぶんと広がるはずだ。
著者の説明によれば、そもそも「宗教右派」という言葉に厳密な定義はなく、〈意味するところは、中絶や同性愛結婚の禁止などを主張して共和党を支援する宗教系の団体のことである〉という。
では、宗教右派の運動はいつごろから勃興したのか。
私のような門外漢にとっては意外なことに、それは1970年代後半以降のことだそうだ。
それまでのアメリカ政治は、1930年代のニューディール政策以来、リベラルの時代が長く続いていた。
現代のアメリカで「リベラル」や「リベラリズム」は、「大きな政府」寄りの思想で、弱者の保護や手厚い福祉政策を支持する立場を指す。
宗教の世界も、この構図とほとんど合致する。
アメリカのプロテスタントは、20世紀の初頭に、進化論など近代科学を受け入れる近代主義と、それを拒否して聖書を字句通りに解釈する原理主義とに大分裂したものの、1920~30年代には、近代主義者の勝利でほぼ決着がついた。
近代主義者たちは、プロテスタント主流派として、政治や社会に積極的に関わっていき、公民権運動やベトナム反戦運動で大きな成果を収めることになった。
つまり、70年代までのアメリカは、リベラルの時代であり、プロテスタント主流派(=近代主義)の時代だったわけだ。
「そうした状況が変わって、福音派と原理主義者が再び政治に目覚め、アメリカ政治を揺さぶり始めるのが1970年代から80年代だった」
「福音派」とは原理主義者ほど厳格ではないが、聖書を歴史的な事実と考えているグループである。
彼らは、「成長してから自分の信仰心を確認するボーン・アゲイン(回心)の体験を重視し」ており、この「ボーン・アゲイン」こそ福音派かどうかを分けるポイントだという。
60~70年代のアメリカは、ほぼリベラル一色で、黒人差別撤廃、女性解放運動、同性愛者の解放運動など、差別撤廃に明け暮れた時代だった。
こうしたリベラルな空気は政治だけにとどまらない。
「ヒッピーたちは髪を伸ばし、マリファナやコカインを使用して瞑想にふけったり、物質主義に反抗して山奥で共同生活をおくったりし、性の解放を主張してフリー・セックスの風潮も広まった」
こうしたチャラチャラした風潮は、厳格な性倫理や家族の価値を重んじる原理主義者や福音派にとっては許しがたいものだ。
彼らの不満に目を付けたのがニュー・ライトの政治活動家であるポール・ワイリックという人物だった。
本書からの孫引きになるが、ワイリックは突然、次のような戦略が閃いたという。
「ちょっと待てよ。
この連中(福音派)はものすごい数がいるけれど、誰も組織化していなくて、手が付いていない。
そうだ、彼らを(保守主義陣営に)呼び込もう。
彼らを組織化して、投票させよう。
その結果、どうなるかは、見てのお楽しみだ」
ワイリックの目論見はズバリ的中。
彼がカリスマ的なテレビ伝道師のジェリー・ファルウェルを擁して作った政治団体「モラル・マジョリティー」は、発足から2年のあいだで7万人の聖職者と350万人の信徒を組織化することに成功し、80年の大統領選挙では共和党のレーガン支持を訴えて扇情的な選挙キャンペーンを展開した。
このころからアメリカのメディアは、モラル・マジョリティーなどのグループを「宗教右派」と呼ぶようになったという。
宗教右派の中核である福音派は、もともと民主党支持者が多かっただけに、彼らが保守陣営に回ったことは「大事件」なのである。
80年代以降、宗教右派の運動は、交流と衰退を繰り返しながらも、徐々に政治的影響力を強めていった。
宗教右派は、極めて明確で具体的なテーマを掲げて、政治運動を展開した。
主たるものは、人工妊娠中絶の禁止、同性愛結婚の禁止、公教育での宗教教育の強化である。
これらのテーマは、次第に共和党政治家の「踏み絵」となっていく。
たとえば、共和党の大統領選挙候補に選ばれるためには、人工妊娠中絶への態度が厳しく問われるのだ。
「宗教右派は四半世紀も前から、(中略)共和党候補に踏み絵を踏ませてきた。
アメリカの指導者を決める時に、人工妊娠中絶に関する立場の表明が、第一の関門なのである」
著者は、ブッシュ大統領が再選を果たした2004年を宗教右派の絶頂の年、福音派の勝利の年と位置づけている。
この大統領選では、白人福音派の8 割がブッシュに投票し、ブッシュが獲得した票のうち、40%が白人福音派の票だったという。
まさにベッタリの蜜月関係がブッシュと宗教右派の間に築かれたわけだ。
「しかも、投票所を出た有権者に候補選択の基準を尋ねたところ、「倫理的な価値(中絶問題や同性愛問題などを包括して言う時に使われる言葉)」と答えた人が22%と最高で、「経済・雇用」の20%、「テロリズム」の19%よりも多かった〉
それにしても、「宗教右派」と彼らの主張に共感する「宗教保守層」がここまで拡大したのはなぜか。
著者は、いくつかの理論を紹介しながらも、「ポピュリズムの反乱」という見方が実態を反映したものだと述べている。
広範な宗教保守層は、ごく普通の市民たちである。
彼らは、50年代後半のリベラルが急進化していった時代に、「自分の娘が十代で妊娠したり、同性愛を描いた本が学校の推薦図書になったりして、それまで自分が信じてきた価値観の崩壊に強い不満を抱いてきたのである」と。
しかし、甘い蜜月関係はそうそう長くは続かない。
イラク戦争の泥沼化によって、ブッシュ支持率が急降下するのにあわせて、宗教右派運動も現在は停滞期に入っているのだとか。
その象徴として著者は、ジョン・マケインが共和党の大統領候補に選ばれたことを挙げている。
マケインは、かつて宗教右派を「分断と中傷を政治に持ち込む、不寛容の輩」とまで罵った人物だ。
「宗教右派のドンたちの腕力は衰えを見せてきていて、2008年の大統領選挙では、宗教右派が忌み嫌うジョン・マケイン上院議員が共和党候補に選出されるという失態も演じている」
宗教右派内部で亀裂があったり、カトリックの存在感が強まったりという状況もあり、今後、宗教右派がさらに下降線を辿るのか、再び盛り上がるのかを予測するのはなかなか難しいようだ。
[ コメント ]
本書を読みながら思い当たったのだけど、宗教という要素は欠いているものの、日本でも草の根保守がメディアを騒がせた時期があった。
「新しい歴史教科書をつくる会」が作った市販版の教科書がベストセラーとなったのは、2001年のことだ。
この会を調査・分析した「「〈癒し〉のナショナリズム―草の根保守運動の実証研究」によれば、その支持者たちも、現状に不満を抱くごく普通の市民たちだった。
「〈癒し〉のナショナリズム―草の根保守運動の実証研究」小熊英二/上野陽子(著)

アメリカの草の根保守を支えた宗教右派も、リベラルやプロテスタント主流派に疲れた人々に〈癒し〉を差し出したのかもしれない。
とはいえ、日本もアメリカも、保守や右派の〈癒し〉の賞味期限は切れかけている。
気分屋さんのポピュリズムは、次の〈癒し〉を何に求めるだろうか。
【テキスト⑪】「イスラムの怒り」(集英社新書)内藤正典(著)(集英社新書)

[ 内容 ]
06年サッカー・ワールドカップ決勝戦で、ジダンは何に激怒してマテラッツィに頭突きをしたのか。
この問いかけから、イスラム教徒(ムスリム)は、何に怒っているのか、そして我々のイスラム理解はいかに間違っているか、なぜ西欧はイスラムを執拗に嫌うのか、をわかりやすく解きほぐす。
ムスリムに対してしてはいけないこと、そしてそれはなぜいけないか、なども豊富な実例つきで解説。
異文化交流への道を探る。
[ 目次 ]
序章 ジダンは何に激怒したのか
第1章 「テロとの戦い」の失敗
第2章 隣人としてのムスリム
第3章 西欧は、なぜイスラムを嫌うのか
第4章 すれ違いの相互理解
終章 ムスリムは何に怒るのか
[ 問題提起 ]
2006年、サッカーW杯ドイツ大会。
フランス対イタリアの決勝戦、フランス代表のジネディーヌ・ジダンは試合終了間際にイタリア代表のマルコ・マテラッツィに頭突きを浴びせ、退場となった。
ジダンの家系がアルジェリア出身のムスリム(イスラム教徒)であることから、「テロリスト」と罵倒されたとの憶測が飛んだが、本書の著者は、ムスリムがテロリスト扱いされることも9.11以降は珍しくないと指摘した上で、こういう。
「考えられるのは、母親、姉妹、妻などの女性親族に対する侮辱、それも性的な意味合いを含んだ侮辱しかない」
なぜなら、その類いの侮蔑に「暴力も辞さないのは、ムスリムに共通の反応」だからだという。
西洋社会において、「ファック」などの性にまつわる罵倒はありきたりなことだが、ムスリムにはタブーだ。
「私たちが知っておくべきは、彼らの規範には私たちと異なる、越えてはならない一線がある」
この言明自体は正しい。
だが、教条的に理解しては、イスラム教は自分たちの規範に合わないことに対し、簡単に暴力を振るう宗教だと捉えてしまうだろう。
実際、私たちは9.11以降、パレスチナやアフガニスタン、イラクで起きた武装闘争や暴力事件を一絡げに「イスラム原理主義」や「テロリスト」といった文言で説明する報道を大量に聞いた。
「いつでも、自分のように(暴力的に)反応した者が罰せられる。
だが、悪意の挑発をした者は罰せられない。
それは不公正だ」
ジダンはテレビに出演した際、こう述べた。
本書は、こうしたイスラムの怒りが何に起因しているのか、とりわけヨーロッパ社会とイスラムとの軋轢を通じて示そうとする。
[ 結論 ]
05年秋、パリをはじめとする都市郊外で移民の若者による暴動が起きた。
多くの移民は所得が低く、ジダンのような社会的地位も望めず、家賃の安い地域に住まざるをえない。
失業率は高く、治安も悪いため、警察と内務省が暴力的に取り締まる。
前途に絶望していた若者らの鬱積していた不満が爆発した。
彼らは「理由があるから不満を抱いた」わけだが、国家は〈「治安」を掲げて取り締まりを強化する〉だけで、「差別」や「悪意の挑発」について改善することはなかった。
「悪意の挑発」とは、たとえば当時内相だったサルコジの「社会のクズ」「ごろつき」といった発言があるだろう。
問題は「差別」だ。
この場合はたんに「外国人であるための差別」として括れない難しさがあるからだ。
「自由・平等・博愛」というフランスの国是を忠実に守ることで生まれる排除の論理も働いている。
フランスが近代的な国民国家の嚆矢となったのは、革命によって「国家を絶対的な存在とし、教会を国家から切り離してしまった」ことによる。
国家が宗教に対し、中立を保つことを世俗主義という。
世俗主義における国家の統治は、個人が社会と契約を結び、自由・平等・博愛を旨とする国民によって行われる。
つまり、国民国家のメンバーとなるには、宗教から袂を分かった世俗主義をとるほかない。
だが、イスラムには聖俗分離の観念が存在しない。
公的領域からイスラム色を排除した世俗主義をとるトルコであっても、ムスリムの棄教は許されない。
ヨーロッパの世俗主義について著者がより詳細に述べた「ヨーロッパとイスラーム」によれば、
「ヨーロッパとイスラーム」(岩波新書)内藤正典(著)

イスラム教は、「「信じる」だけでは成り立たない。定められた「行為」を実践すること、あるいは禁じられた行為をしないことが求められる」と。
規範は礼拝に始まり食事、性生活、遺産相続、ビジネスにまで及ぶ。
したがって「ムスリムが信仰に則った行為をすればするほど、厳格な世俗主義を採るフランスの原則と衝突してしまう」。
本書に話を戻すと、象徴的なのが2004年に制定された「宗教シンボル禁止法」だ。
著者曰く、同法の「狙いがムスリムの女子学生のスカーフやヴェールだったことは間違いない」。
フランスに限らず、ドイツでもスカーフとヴェールは社会問題となっており、政教分離の徹底という側面だけで、クローズアップされているわけではなさそうだ。
近代的で先進的な国家に住むようになれば、移民もヨーロッパ文明に同化し、国家に統合されていくはずだ。
評者が思うに、そういう期待に沿わないムスリムへの苛立ちが根底にありそうだ。
イスラム教では女性の髪を「性的部位として認識」しており、羞恥心を覚える女性はスカーフとヴェールをつける。
それがヨーロッパの世俗主義や人権感覚からすれば、自由を抑圧する宗教的規範の表れに見える。
すなわち「男性が女性をヴェールで覆い隠し、女性の自由を奪っている」という非難となる。
むろんスカーフとヴェールをつけることに抑圧を感じる女性もいるだろうが、「スカーフを外せば女性が解放される」わけでもなく、髪の毛を露にしたからといって「西欧風に世俗化したわけでもない」というところに、この論争の難しさがある。
「先にイスラムへの嫌悪があり、なんとしてでもフランス固有の原則に従わせるために、結果としてムスリム女性がスケープゴートになってしまった感は否めない」
著者はこう総括するのだが、国民国家の原理である世俗化への要請が、ただちにイスラム嫌悪につながると解してよいものか。
ただ、スカーフやヴェールが「女性解放と文明化」の文脈で語られている以上、ムスリムをヨーロッパ文明に同化させるべき対象と見なす論があるのは確かだ。
イギリスでも、2005年のロンドンで起きたテロ以降、「寛容な多文化主義」がテロを招来させたとして、「ムスリム移民に対する「寛容な」政策を見直すことを宣言した」。
それに呼応するかのようにヨーロッパ各国も移民への居住許可に際し、「統合テスト」を導入するようになる。
表面上は語学試験だが、「ヨーロッパの文化や価値観に関する質問」を盛り込んでいるという。
著者はこうした動きについて警鐘を鳴らす。
「イスラムという宗教は、リベラリズムに反するから排斥しなければならないという方向に、世論も政府も急激に傾斜したのである」
「イスラム」とは、「神(アッラー)への全面的な預託」を意味する。
アッラーとは全知全能の唯一の存在である。
唯一であるとは、それ以上に分割しようのない真実の存在であるということだ。
したがって、
「日々の生活をどう過ごすか、人生をどう生きるか、についての規範は神の定めに従わなければならない。
人間が自分や社会を律するためのルールをつくることは、原理的にできないことになる」
と。
イスラムにおいて棄教はイスラム法学上、死刑である。
現代的な感覚からすれば、信仰の自由を認めないということになるが、唯一絶対の神の被造物に過ぎない人間が聖から俗へ逸脱することは、彼らの世界ではそもそもあり得ない。
ムスリムであることは、選択の問題ではなく、人であることそのものに関わるからだ。
移民先のヨーロッパ社会に溶け込む努力をしていたムスリムは、スカーフを「過激な「イスラム原理主義」の象徴だと主張する傾向さえ強まった」というような、世俗国家における「寛容」概念の綻びに、平手打ちを不意に食らわされたような気分だろう。
「アイデンティティを否定されたも同然だから、闘争心を掻き立て、結果として西欧への反感を強める〉ことになる。」
反感と憎悪の連鎖への解決はいまだ見えず、ヨーロッパは模索よりは不寛容な社会に向けて歩んでいるように見える。
「郷に入りては郷に従え」と考える向きには、世俗化しないムスリムにむしろ頑なさを感じるかもしれないが、ヨーロッパ社会とて、キリスト教の絶対性を相対化するのに数百年を要した。
ムスリムに同じ土俵に乗るべく急変を求めるのも酷な話だ。
「大切なことは、考えることを放棄して、感情的なナショナリズムや排外主義に傾斜しないことである」
正論ではあるが、著者は、排外主義と一線を画す「自由・平等・博愛」という理念が不寛容さに傾く道筋を、本書で描き出している。
[ コメント ]
理想と現実の矛盾を一気に解決する手立ては早々見つかるものではない、ということだけは明らかだ。
【関連記事】
【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】クリスチャンリアリズム
https://note.com/bax36410/n/nacae111ee25b
【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】功利主義
https://note.com/bax36410/n/n8cfc4f589169
【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】プラグマティズム
https://note.com/bax36410/n/nd8eab49c931f
【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】リバタリアニズム
https://note.com/bax36410/n/nb7400429866e
【政治哲学で今後の生き方を学ぶ】コミュニタリアニズム
https://note.com/bax36410/n/n9db59c1ae0cc
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
