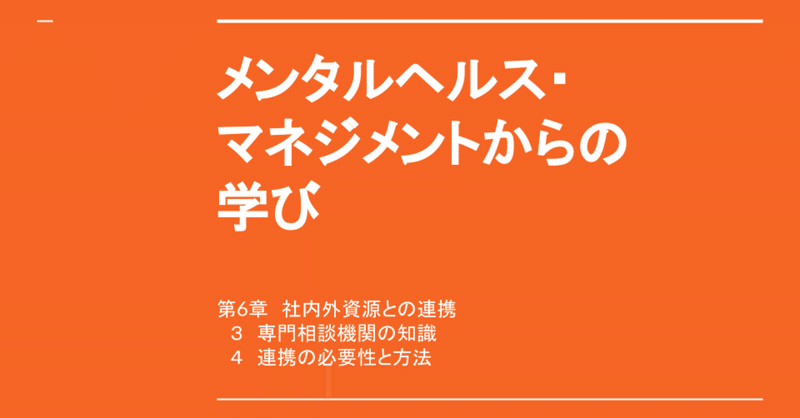
メンタルヘルスマネジメントからの学び#16
メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種を目指して、覚えたこと、感じたことなどをアウトプットしていくことで、記憶の定着と自分の考えの整理をしていきたいと思います。なお、内容については間違いなど普通にあると思います。これを見て落ちても責任は取れませんので悪しからず。
第16回目は、第6章のつづきで専門機関と連携についてです。知識の賞なので、サクッと読み解いていきましょう。前回はこちら。
第6章 社内外資源との連携
3 専門相談機関の知識
心にかかわる疾患を専門として扱っている医療機関いくつかありますが、パッと見よく分からないのが本音じゃないかと思います。心にかかわる疾患のうち、身体の症状・疾患(心身症)なのか、精神の症状・疾患(精神疾患)なのかで、かかる医療機関が異なるのですが、うつ病などの精神疾患であっても、身体症状がおこるものも少なくないので、どちらを受診するかは知っておいて損はありません。あとは、テスト的にはひっかけやすいところでもあるので、チェックしておく必要があります。

上記に、診療科と医師と疾患の関係をまとめました。守備範囲は概ねこのようになってはいますが、心療内科と精神科は守備範囲が重なる部分があります。また、精神科というより心療内科といったほうが受診するのに抵抗がないであろう等の理由から、精神科であっても心療内科と標榜することはあります。
どこを受診すべきか?については、今の自分の症状に近いと思われる診療科を受診して構いません。他の科が適切であると判断されれば、そちらをちゃんと紹介してくれます。ただ、大きな病院であれば科の移動は簡単ですが、クリニックなどに行った場合は、科の移動=病院の変更になりますので、初診料やカルテの共有などを考えると少し面倒です。なので、診療科を選ぶときは、そこで行われている治療の内容をよく確認しておくようにしましょう。私の場合ですが、睡眠時無呼吸症候群のときに睡眠外来を探しましたが、ネットで何となく検索するだけだと、精神科のほうが多かったイメージです。私は単純に無呼吸症候群の診察をしてほしかったので、精神科系の睡眠外来では、心の病で寝れない人向けにカウンセリングや睡眠薬とかを処方する感じになってしまいます。同じ睡眠外来でもやること全然違うので、その辺りは注意しましょう。
メンタルヘルスで受診をした場合、通院などが1回で終わることはありません。数回にわたって治療が行われるのが一般的です。そういう意味でも、病院に行くのか、街の診療所に行くのかは考えておいたほういいです。
病院と診療所の違い
病院
20人以上の患者を入院させるための施設を有する医療機関
診療所(クリニック)
19人以下の患者を入院させるための施設を有するか、
入院施設を有しない医療機関
病院と診療所の違いは上記の通りなので、大きい病院に行った方が良さそうではありません。ただ、病院でも診療所でも、開業をしている先生が主治医になってくれる場合は良いのですが、大学病院や総合病院では、同じ医師に診てもらうためには曜日指定があったり、転勤してしまったりが考えられます。信頼できる(した)先生による継続的な治療が受けられるかという視点も考慮して医療機関は考えるようにしましょう。
治療の実際
精神疾患を診断する場合、まず身体からくる精神症状でないことを確認します。別な疑わしい病気でないことを確認するために、血液検査などの検査を受けたり、いくつかの科を受診したりする場合もあります。調査票や心理テストの記入、現在の症状だけでなく、過去の病歴や成育歴、生活歴、家族の状況などの聴取、面接・診療を経て診断をされます。
そのうえで、以下の説明を受けます。
1)病気の説明
2)選択できる治療の方針と方法、その際の薬の副作用など、望ましくない効果などの説明
3)患者・家族・周囲のモノが守るべきこと
4)李朝の一般的な経過や今後の見通し
この説明を受け、自信が病気になっており、適切な治療で治るモノであることを理解することが正しい治療への第一歩となります。
テキストではうつ病についての一般的な治療方法が記載されています。第1に休養、第2に薬物療法、第3に心理療法・精神療法が用いられます。その他として環境調整が大切なこともあると書かれてます。また、職場が病気の要因になっている場合は職場と連携して対応することになります。
a)休養
エネルギーが枯渇した状態と例えられることがあるように、休養をしっかりとり、エネルギーを十分に蓄えることがまず必要です。休養の長さは症状により様々ですが、会社を休むということは同じです。休むことで他人の迷惑になる、休むことへの罪悪感、自分の居場所がなくなるのではないかという不安が休養への妨げとなります。管理監督者は不安を取り除き、休むことの必要性を説明しなければなりません。
b)薬物療法
うつ病や不安障害は単なる疲れや気持ちの問題でありません。脳の生理学的・機能的な不全状態、病気です。そのための薬であり、脳内の精神伝達物質の働きを回復させる効果がある薬が必要な病気なのです。周囲は不用意に「薬に頼るな」などと治療を妨げる行為をしないように正しい知識を持たなければなりません。
抗うつ剤、抗不安剤、睡眠剤、抗精神病薬、気分安定剤など多くの薬があります。特に抗うつ剤の部分がテスト的には重要です。抗うつ薬では、選択的セロトニン再取込阻害薬(SSRI)、セロトニン・ノルアドレナリン再取込阻害薬(SNRI)が第一選択剤となります。処方としては、2~4週間使用して効果があれば継続、なければ増量してさらに2~4週間継続使用、効果がなければ薬剤の変更などを行っていく流れとなります。三環系抗うつ薬、四環系抗うつ薬では睡眠や目のかすみ、のどの渇き、動機、便秘、排尿困難、立ちくらみなどの副作用がありますが、SSRI、SNRIは副作用が少なく使いやすいとされています(副作用がないわけではない)。他にも、スルピリドなどは少量では潰瘍の治療薬、大量では統合失調症の治療薬としても使われたりします。SSRIやSNRIをはじめ、他の抗うつ薬も、強迫性障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、摂食障害など、他の疾患にも用いられます。
これらの薬は医師の指示通りに飲んでいくことが大切です。効果の発現がゆっくりであること、再発防止の観点から、病気がよくなってからも半年~1年は投薬が必要とされています。
c)心理療法・精神療法
治療する人との人間関係を通じて、心にアプローチして、不調の改善をすべく、心理的な援助をしていきます。治療が継続できるように支えるという指示的な意味が強く、休養・薬で症状が落ち着いてからうつ病に対しての精神療法を行っていくと考えます。うつ病には、認知行動療法が用いられます。他には、問題解決技法(問題を明確化、たくさんの解決策検討、優先順位付けして実行)、精神分析、自律訓練法、交流分析、家族療法など様々な治療があります。
d)その他の治療
電撃療法、高照度光療法、断眠療法などそれぞれの病態に合わせて用いられることがあります。
治療形態はうつ病の多くの場合、外来治療で行われると思ってよいです。当初、1~2週間に1度の通院をしながら、まずは薬物の調整をしていきます。入院が必要な場合は以下のようなケースがあります。
医学的な意味で入院が必要な場合
・自殺の危険性が高い
・重度のうつ病で食事も十分にとれず身体的な管理が必要
・焦燥感・不安感が強く精神的に相当に不安定
社会的信頼を失う恐れがあるなどで入院が必要な場合
・統合失調症で幻覚妄想状態
・躁うつ病での躁状態がひどい
その他入院が必要な場合
・一人暮らしで生活リズムを保つことが困難
・投薬のルールや禁酒のルールを自分では守れない
・自宅で療養するのが家庭の状況で休養にならない
病気が重篤である場合だけではなく、総合的に判断して行われることを覚えておきましょう。
なお、職場復帰しても再発や再休職になることがしばしばあったため、職場復帰を目的としたリワーク・プログラムが行われるようになってきました。復帰後の就労継続期間を指標とした比較では、リワーク・プログラムを受けた人たちの予後が良好であるとされています。
リワーク・プログラムは大きく3つあります。医療リワーク、職リハリワーク、職場リワークです。1日800円程度が利用料の目安となっています。しかり、リワーク・プログラムが進むにつれて利用回数も増えてきて、利用料もう高額になってしまうので、リワークを利用する場合は、自立支援医療の申請をしておくとよいです。所得によりますが、月の利用料の上限が決まっていたりします。以下が詳しく載っています。利用を検討する場合は主治医に相談するとイイみたいです。
4 連携の必要性と方法
第6章の最後は、連携についてです。
どんな場面でどこと連携するかをまとめて終わりにしたいと思います。
1)メンタルヘルスに関する情報収集
メンタルヘルスに限らず、安全衛生に関する情報は、労働基準監督署、産業保健総合支援センター、中央労働災害防止協会、各地域の労働基準協会
メンタルヘルスに関する情報は、保健所や保健センター、精神保健福祉センターから情報を得ることができます。
2)メンタルヘルス教育を受ける
事業場内での教育の講師を地域の専門医療機関に依頼するとともに、講師の先生にも事業場の業務内容や環境といったものを理解してもらって、相談時や治療時に役立つようにできると良いです。外部EAP機関とこうした内容を含んだ契約をすることもできます。
3)ストレス状態や職場環境の評価や改善
職業性ストレスチェックの結果をもとに、外部専門家、ストレスチェック実施機関やEAP機関などの協力を得て、職場のストレス対策、環境改善を図ります。
4)メンタルヘルス不調の早期発見
面接などの結果、社内外資源に相談を進めます。産業保健スタッフや、EAP機関との契約があれば契約窓口への相談などを行います。このようなスタッフや契約がない場合は、精神科や心療内科の受診を検討します。
5)治療過程での連携
主治医との連携するためには本人同意が必要ですが、同意があれば、主治医と連携して的確な情報提供を行います。このことにより、業務上の配慮や、適切な治療と早期の病気改善につながると同時に、復職後の再発防止に役立つことが少なくありません。
外部との連携を行う際には、連携窓口は一本化するようにします。事業場内メンタルヘルス推進担当者などを活用して、事業場内の連携を確立して専門機関との連携をだれが継続して担当するかを決定します。事業場内の連携や本人との統一した対応を保つためにも、ここで得た情報は文章として保管しておくとよいです。費用についても事前に取り決めておくとスムーズな連携が可能となります。
まとめ
各所と連携しながら治療を進めていくとが重要なのですが、どのような機関があるか、守備範囲は?など知っておくと話がスムーズに進みます。費用についても、知らないと損をすることは多いと思います。リワーク・プログラムの自立支援医療だけでなく、会社員や公務員がもらえる健康保険の傷病手当金というのもあります。他には高額療養費制度や保険に入っている人は、保険から出ることもあるかもしれません。医師などに相談してみると色々な方法を教えてもらえます。
カスタマーサクセスの必要性と、トークンエコノミーな未来におけるコミュニティのあり方を考えます。ってだけではないですが、ざっくばらんに気になったことnoteします
