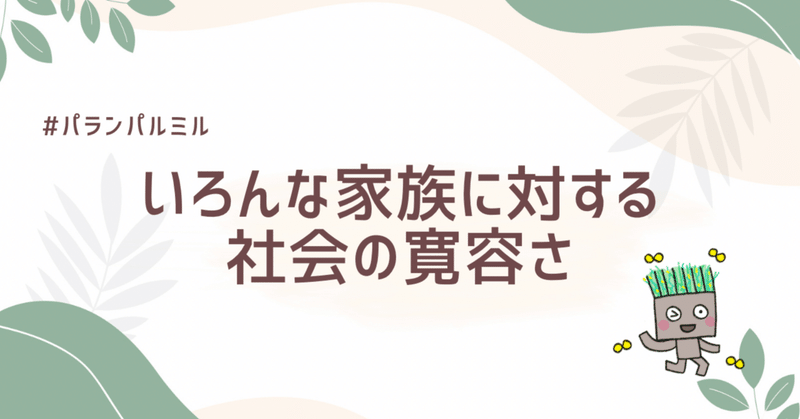
いろんな家族に対する社会の寛容さ
昨日のabema primeご覧いただいた皆様ありがとうございました!
子どもにとっての親の離婚というところに焦点をあてつつ、『離婚しづらい世の中がいいのか』『離婚をポジティブにすべきなのか』という問いがありました。

ようするに、もっといろんな家族の形に寛容な社会になってほしいという願いからだと思うのですが、『うまくいかなかったら離婚すればいいよね』という考え方に繋がると、それは寛容ではなく、大人が相互理解を諦めることの正当化のように感じてしまいます。
私は親が離婚をしたときに中2の思春期でひねくれていたことも相まって(笑)、「相互理解ができず、諦めるなら結婚するなよ」「相互理解ができず、諦めるなら子どもを産むなよ」と両親に対して思っていました。
ですが、そう考えることは同時に自分(=子ども)の存在否定につながるので、しんどさがマシマシになるわけです。
離婚を願って結婚する人はいないと思うので、しなくていい選択なら離婚はない方が良いのです。すすんで取られる選択肢ではないという意味では、離婚はネガティブな選択です。これを「離婚って恥ずかしいことではないよね」「3組に1組もいるなら、もう当たり前だよね」という風にポジティブにしようとすることには、私はNOを言いたいです。
ただし、離婚はポジティブにはなり得ないけれども、「(子どもにとっての)親の離婚」はそれ自体がマイナスではありません。
「離婚しても何の問題もないよね」ではなく「親が離婚しても子どもには何の問題もないよね」を目指していくという意味なら『離婚がネガティブに捉えられる社会を変えよう』というのもまだわかります。
ただ、実際子どもに降り注ぐ問題だらけなので、まずはそれが知られること、そして一つ一つ対処が与えられていくことが必要と思います。
・・・・・
私が21歳の時、妹が私立高校に進学するにあたって、お医者さんに健康診断をしてもらって、診断書を書いてもらわないといけないというのがあったんですね。
妹が高校進学するときは父は体調を崩していたので、受験の手続き、制服や教材の準備、中学の卒業式や高校の入学式の出席は私が全部やりました。お金面も、妹には私のような思いをさせないようにと思ってとにかく頑張りました。
それで、この健康診断の付き添いも私が一緒に行ったのですが、診察室に行った妹を待合室で待っていたところ、おばあちゃん先生が私のもとに来て『お母さん!どうしてあなたは子どもと一緒に来ないわけ!?親なんだからちゃんとしなさいよ!まったくこれだから若い人は・・・(ぶつぶつ)』と、まくしたてられたのです。
その勢いに私があっけにとられ、しばらく先生の話を聞いた後に『すみません、私、姉なんです』と言ったら『なんでもっとはやくいわないのよ!!!』と怒鳴られる始末・・・(笑)
いやいや、あなたが全然私にしゃべらせようとしなかったやん・・・と思ったのですが、『この人はうちが父子家庭で、お父さんが今動けなくて、姉の私が病院に付き添っているなんて思ってもみなかったんだろうな』と思いました。
子どもと一緒に病院に来る女の人は、お母さん。
男の人だったら、お父さん。
それが普通。
妹ととぼとぼ歩いた帰り道は今でも覚えています。
「頑張ってるね」って言ってくれたら、ちょっとは救われたのに。
そういう、悪気のない普通の概念が知らず知らず子どもを傷つけてきたのがこれまでの日本の社会です。
こういったことは親の離婚のみならず様々な要素を抱える人たちにおいて、起きているのではないでしょうか。
自分には自分の尺度で見た「普通」の概念があること。
そこにあてはまらないものを排除したり断罪する権利はどの人にもないこと。
このことに気づいていくことが「寛容さの高まり」だと感じます。
それは法律が変わったり、制度が増えたりするだけでおこなわれるのではなく、丁寧な対話によって仕組みを創っていく過程が叶えていくものであり、相互理解を諦めない大人が増えていくことこそが近道なのではないかと思っています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
