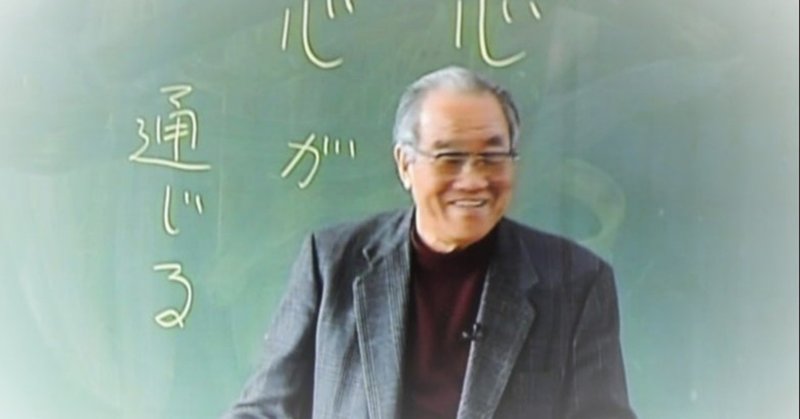
河合隼雄を学ぶ・12「これからの日本③」
(前号の続きです)
【日本の土を踏んだ神 ~遠藤周作の文学と宗教~】
ユング心理学というものは面白いが、これを日本に導入しようとする当初、河合隼雄はなかなかに苦労したという。
文化であれ、思想であれ、どこかの土、違う土を踏むということは大変なことであって、その土を踏んだ途端に変容するという性格を持っていると言ってもいいくらいであり、ユング心理学も、日本の土を踏んだ途端に、これはもう変容を始めるだろうと、河合隼雄は当時の本に書いたのだという。
そして、異国の土を踏むということがどんなに恐ろしいかということを書くために、遠藤周作の『沈黙』を取り上げたという。
ロドリゴという信心深い司祭が、日本の土を踏み、日本の塩魚を食べ、日本人と交流する。キリストは変わらないかもしれないが、このロドリゴの中のキリストは変わった。踏み絵を前にして、ロドリゴはキリストの声を聞くが、それは母国にいたときの天上からの声ではない。彼の足下、足の下から語る、日本の土の中から掘り出された、銅板に焼かれたキリストが「踏むがいい」と言ったのだ。
・・・ということを書こうとして、当時の編集者から「遠藤周作は手ごわい人だから、これはやめたほうがいい」と止められ、発表するのはやめたとのこと。しかし、その15年後、河合隼雄と遠藤周作は対談の機会を得、その後、何度も対談することになる。上記の原稿も、どこかのタイミングで見せたということである。
二人とも、お互いに共通に宗教ということを常に念頭に持っているという自覚があった。遠藤周作はカソリックであるが、河合隼雄は特定の宗教に入っているわけではない。しかし、お互いに宗教的なことを問題にしている。
それは、ルドルフ・オットーがいうところの『ヌミネーゼ』であると河合隼雄はいう。宗教というと、あれをしてはいけない、これをしてはいけない、これをしろ、こうしなきゃいけないとか、色々いうけれども、そんなことはみんな付け足しであって、そういうものをどんどん取り去っていって、宗教の最も本質的なところを見ていくと、『ヌミネーゼ』、なんとも言えない体験、完全に圧倒されるような凄い力、どうしようもなく引き付けられる抗いがたい魅力、そういうものにたどり着く。そういう途方もない、つかみどころのない体験を、慎重かつ良心的に観察しつづけることを宗教といったらいいんじゃないか、ということルドルフ・オットーは言った。
河合隼雄は心理療法の中で、そのような物凄い強烈な力に翻弄されるクライエントに対し、たじろがず慎重にそれを見続けていく、そしてクライエントとともにそれを体験する。その時に河合隼雄が体験し、感じ取ったことを、フィクションという形で他人に伝えることができるのが、作家である。
『沈黙』にしても、遠藤周作の凄い宗教体験がベースにあるのだが、それを自分のこととしてそのまま語るのではなく、『沈黙』という作品を通して我々に伝える。そして、作品というフィクションのほうがリアリティをもって我々に伝わるというところが、非常に面白いところなのだと河合隼雄はいうのである。
【日本人の倫理観】
日本人の倫理観というのは、自分と地人との「関係」の中に設定されている。自分と関係のある知り合いがいるかもしれないところ、すなわち「世間」の枠内では悪いことはしない。しかし海外にいったときは「世間」の枠外だと認識して、羽目を外したりする。ある意味では臨機応変な倫理感である。
一方、アメリカ人の倫理観というのは「神との契約」であるから、あくまで自分の内面にある。自分の町から遠く離れたからといって、自分の内面には常に神の目があるので、羽目を外したりしない。場所とか他人の目は関係ない。
日米の平均的な倫理観を比較した場合、アメリカのほうがより厳しく、徹底しているといえるだろう。
しかしその割に、日米の犯罪状況を比較した場合、アメリカのほうがより深刻で、犯罪発生件数も多い。銃が許可されているかの違いはあれど、それだけが理由ではないだろう。より厳しい倫理観を持っているはずのアメリカで、なぜ倫理観に反する犯罪に走る者が多いのか。
河合隼雄は、厳しい倫理観を持つ社会であるからこそ、そこから一度外れてしまったと自分で感じた人は、とことん倫理に反する生き方に走るしかなくなるのでないか、と考察している。そういう意味で、日米の倫理観について、どちらが良いとはいちがいには言い難い。
さて、アメリカの子どもは「親からモラル・サポートを得た」と話すという。アメリカの親は「何々してはいけない」「人間はこうでなくてはいけない」と、折に触れて、言葉で語るのだろう。つまり、モラルが明確な言葉の形をとっている。
いっぽう、日本人はどうか。モラルをひとつひとつ、明確な言葉で子どもに語って聞かせる親というのは、むしろ珍しいのではないか。日本の子どもはモラルをどこで学ぶかというと、大部分は、日常の生活の中で、ごく自然に身につくものである。モラルは、言葉ではなく、親の生き方からなんとなく伝わってくる。
宗教にしても、日本人は意識していないかもしれないが、宗教的なものが、日常生活全体に染み込んでいる。
例えば「もったいない」という心について、よく取り上げられる。「もったいない」という言葉は、英語で正確に置き換えることができないという。我々が、ごはん一粒でも「もったいない」と言って大切にしてきたのは、単にモノを浪費しない、という意味だけではない。モノそれ自体を尊ぶ、命であったものを尊ぶ、だから一粒たりとも粗末には扱わない。それが日本人にとっての宗教であり、倫理であり、モラルである。
河合隼雄は、数ある仏教経典の中でも、特に華厳経に「もったいない」の精神を感じるという。
華厳経の教理を特徴づけるのは「一即一切、重々無尽」すべての物と物、人と人は、一見区別がありながら、実はひとつに融合している、という考え方である。
ここにコップというものがあるが、本当はそんなものはない。ここに私という人間がいるが、本当はそんな人間はいない。人や物の区別は仮のものに過ぎず、本当に一切が重なり合っているのだ・・・おおむねそのような意味である。
華厳経にいう「私なんていうものはない」という感覚は、逆にいえば、「この世の一切が私である」ということでもある。
「私」という固定的な実体はないけれども、すべての人、すべての物との関係の中に、「私」は存在する。無限に続く全関係の総和こそが「私」である。
そして、そういう考え方が日本人の心の深層にあるからこそ、「もったいない」という意識も生まれてくる。ごはん一粒であっても、それは「私」を形作る「無限の関係」の一端をなすものであり、だからこそ粗末にできないのだ。
しかしながら、戦後、日本がどんどん物質的に豊かになるにつれて、この「もったいない」という感覚が薄れ、その根底にあった「すべてはつながっている」という感覚も薄れていった。
「すべての人や物が自分とつながっている」
「すべてのつながりの中で自分は生かされている」
この「関係性の感覚」をなくしてしまうと、私たちは、心の深層の拠りどころを失ってしまうのではないだろうか。
西洋の自然科学の「分析知」は、「すべてはつながっている」という考え方の対極にある。物を分けて分けて、これ以上分けられないところまで分けて研究する。そこから得られる知により、私たちは大変な恩恵を受けている。
しかし、ここにきて、西洋的な分析知の限界が見えてきてきているという。研究対象を総体的にみる、部分と部分の関係性をみることが重視されてきているという。生物にしても、細胞ひとつひとつはそれぞれ一個の生命体でもあるのだが、たくさんの細胞が、細胞同士の関係性の中で自分の動きを決めている。60兆個の細胞のシンフォニーが、私たちの身体をつくっている。生命とはそういうものだという。
「この世のすべては関係しあって存在している」
という仏教の考え方に、欧米でも非常に関心が高まっているらしい。欧米の知識人にとって、仏教の考え方は、最も強力かつ体系的なパラダイムを提供すると河合隼雄はいう。
日本人である私たちは、自分たちの心の深層にあるものを、いま一度立ち止まって見つめてみる必要があると、私も思う。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
