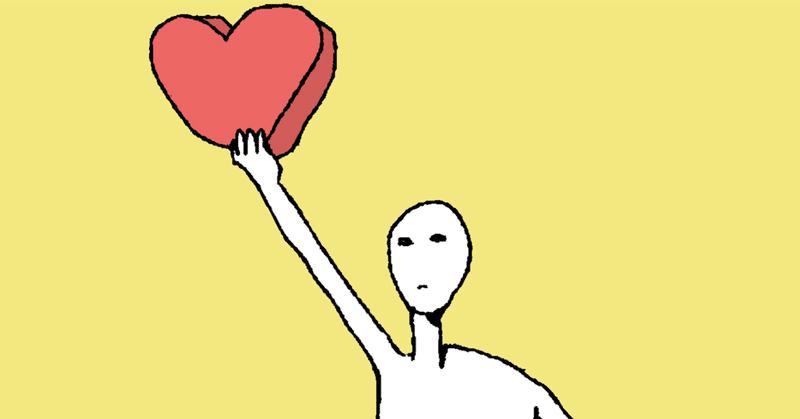
「自己決定」への探究の可能性(仮説)
昨日参加していた某会議のキーワードは「高校生の自己決定の担保と尊重」。自己決定・・・高校生は「できない(子が多い)」という前提ということだよなぁ・・・とぼんやりと考えながら帰宅したのだが、寝る前に思い至ったことがあった。
5年前に書いた、高校時代の「自由と自己責任」の話。
ウチの高校は制服もないし、校則もほぼナイ。入学式は校長先生の「学園は自由なれど責任は重し」というひとことから始まり、いろいろなシーンで、教員から「自己決定」を、ある意味「迫られる」(笑)ことが多かったような記憶が。教員に管理された記憶はいっさいない。自分で考え決めていくことがあたりまえの文化があったように思う。
これ、旧制中学だった長野県内の高校ではよくある話らしく、学力の高い学校ほど制服も校則もない傾向がある。先日、たまたま話を聞くことができた高校(県内でも屈指の進学校)でも、同じような話がでてきた。というか、ウチの高校に輪をかけて強烈な自主性を求める校風だった(笑)。それも伝統的に。あとから思い出したのだが、高校のときの担任、ここの学校の卒業生だったかもしらん。
ここで出た話のひとつが「学力が高い子たちだからできるという側面はある」という話。確かにそういう側面はあるだろう。そして、この話を裏返すと、「学力が低い子たちにはできない」ということになり、「学力の低い学校ほど制服もあって校則がきっちりしている」という実態があるのだと思う。
だがしかし、である。ここでひとつの疑問が出てくる。
「学力の低い子たちにはできない」は、本当なのだろうか?
「できないからやらない」では、いつまで経ってもできないままでは??
「生徒の学力が低いから」自己決定を求めることができないのではなく、「生徒の学力に合わせて自己決定をうながすアプローチがむずかしいから」できない、だったりしてないだろうか? もしそうだとしたら、これは生徒の学力の問題ではなく、大人側の問題。ただ、これは大人が手を抜いているというわけではなく、自己決定をうながることにつながるような「生徒の状況にあわせた効果的なアプローチ方法」を持てていないだけではないかとも考えられる。
だとしたら。
今回の学習指導要領改訂のキーワードのひとつである「探究」は、自己決定につながるアプローチのひとつになりそうな予感がしている。学力が高い学校じゃないと探究はむずかしいのではないかという話もあったけれど、いろいろな実践事例でこれも覆されてきている。ということは、アプローチの手段は、いろいろ見えてきているってことなんじゃなかろうか?
ここからは大人が生徒を信じて任せることができるか、だ。
松倉由紀
キャリア教育コーディネーター・教育研修プランナー。1975年長野県上田市生まれ。静岡大学人文学部卒業。地元での就職に失敗(4か月めで退職届!)ののち、大手通信教育会社、人材派遣会社、コンサルティングファームを経て現職。キャリア教育の領域で教育プログラム開発と「しくみ作り」をする「企画屋」「クリエイター」であり「風呂敷たたみ屋」。2016年4月個人事業主から法人成り(株)ax-factory(https://ax-factory.wixsite.com/corporate)を設立。2020年京都造形芸術大学通信教育部(グラフィックデザイン)を卒業。デザインで学びをおもしろくします。
☆学校を応援する大人のための教育マガジン無料配信中☆
登録はこちらから。
https://submitmail.jp/FrontReaders/add/4173
バックナンバーまとめ読みはこちらから。
https://note.mu/axfactory/m/m4a777303bd10
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
