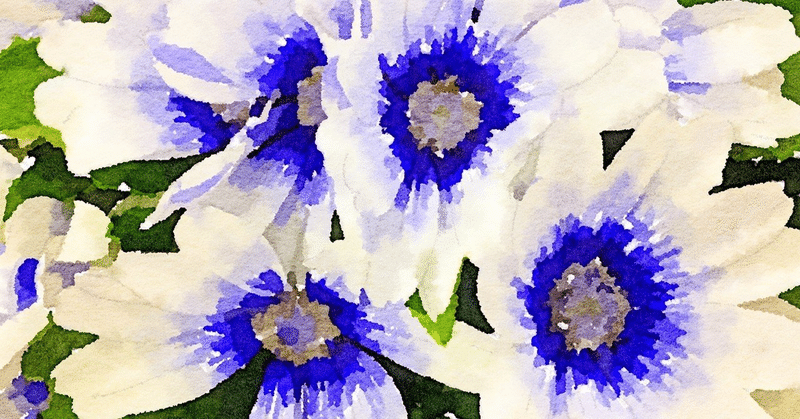
【書評】滝口悠生「死んでいない者」
【死んでいない者:滝口悠生:文藝春秋:2016:第154回芥川賞受賞作】
お通夜の話。
山間の旧街道沿いにある広い一軒家に、誰とも知れない親類縁者がわらわら集まって、二階に安置された故人の顔を覗いては去り、覗いては去る。近所の人が集まり出し、弔問客に振る舞う料理などを誰彼となく作り始める。遠方からの親類のためあちらこちらに布団が敷かれ、敷かれた布団の上には避難してきた猫が寝ている。まだ小さい子どもたちは自由に室内を走り回り、犬たちは柱に繋がれ悲しげに鳴いている。
大きな食卓を二つ並べてようやく収まるくらいの弔問客の一人一人の顔を眺めつつ、あれはどこの家の誰で、故人とどのような繋がりがあって、などということを詳しい者に聞いてはみるものの、その時点ですでに酒が入っており理性がおぼつかない。なんだかんだで旅行気分、自分はというと隙をみてちょっとサイクリングに出かけたりなどし、峠を超えて向こうの町まで観光する。その間も故人はドライアイスで冷やされ続け、焚きしめられた線香に燻されてゆく。
花輪の花の、主に菊の勝つ香り。出来合いのオードブルのぐにゃぐにゃに湿気った揚げ物の香り。そして線香の煙を凌駕する煙草の煙の香り。酒の香り。匂い立つ空間のなかで人々が思い思い、故人との思い出などを語ったり、語らなかったりしながら夜は更けてゆく。
――というのは自分の記憶から構成された数年前のお通夜の印象だが、印象だけで言うと本作についてもそれほど相違ない。
故人には五人の子がおり、その子から子の子までいるためかなり人数が多く、めいめいが自由に動いてゆく群像劇が展開される。その合間には、場に居る者はもちろん、わけあって列席していない者も含めた来し方がつらつらと語られてゆく。
先頃レビューした古川真人「背高泡立草」と印象が似ている。「背高泡立草」は親類が集まって草刈りをする話で、本作は親類が集まってお通夜をする話。語り口としても、三人称でありながら個々の人物の心裏まで分け入って、ある種シームレスに描いていくという点では似ている。似てはいるのだが本作のほうがシームレスの度合いは強く、地の文でそのまま作中人物の言葉を発したりする。
この語り口に独特なところがある。例として、
えー、なんであたしが、という返事は知花の頭のなかにすぐに浮かんできたけれど、それはごく一般的な応答の形として浮かぶものであって、知花が兄に返す言葉ではありえない。そんな返事はすまい、という自己陶酔めいた感慨をともなう否定のために浮かぶ。いいよ、と声を返し、内心で、いいよ、いいよ、お兄ちゃん、と歌うように繰り返す。兄のことが好きというより、兄のことを考えている時の自分が好きだ。でも、いつまでもこんなふうには思わない、思わなくなるのかもしれない。
(p50)
上記は故人と同居していたニートの兄、美之に「通夜ぶるまいの料理、少し持ってきてくんないか」と頼まれた時の妹、知花の描写である。知花の「心の声、内観、発言」がシームレスに記述されているのがわかる。最後の二文については、知花の考えなのか、三人称主体による俯瞰的な言明なのか、はっきりとしない。「――の自分が好きだ」は知花の心の声のようだが、「――思わなくなるのかもしれない」は三人称主体による評言のようでもある。この「主体の曖昧さ」ないし「主体の浸潤」が、作品全体に独特の印象を付加している。
一般的な小説における三人称主体というのは、場を俯瞰しながらも個々の主体に対しては一定の距離を置くものだが、本作の三人称主体はそれぞれの登場人物の意識までをも総覧して語る。通常人は他人の意識のなかまで覗くことはできないので、こうした描き方は不自然なようにも思われるのだが、意外にもそれほどの違和感なく読むことができた。
というのも、そもそも我々は他者とコミュニケーションを取るにあたって、少なくとも彼が私と同じように感覚したり考えたりする、いわば同型の存在と見なしている。「おはよう」と言えば「おはよう」と返すだろうし、「ばかあほどじまぬけ」と言ったら怒るだろうという「見込みの地盤」の上に初めてコミュニケーションが成立する。この地盤というのは主体の内面に自己と他者を同列の意識主体として位置づけることによって初めて構成されるものなので、結局のところ、他者は自己の内部で生きていることになる。
――と、多少強引に託けてみたが、ここで「死んでいない者」という本作のタイトルが示唆を帯びてくる。本作は死んだ者であるところの故人のもとに、死んでいない者であるところの親族が集まる話である。しかし故人は死んでいない者たちの内部で確かに息づいている。そして死んでいない者たち同士のなかにも、お互いにお互いが浸潤した形で息づいている。そうした一族の複雑に絡み合った関係性・想念の体系が、個々の人物の意識にまで分け入って詳述される独特な文体によって生々しく立ち上がってくる。
とはいえ語りとしては三人称なのだから、「そうして思ったり考えたりするところのあなたは誰?」という疑問は生じうる。「知花がそう思うこと」、あるいは「知花がそう思ったであろうという想像を美之がすること」、というのは作品世界内において許される。しかし、知花も美之も含めた全員の意識を覗くことができる三人称主体としての語り手はいったい何者なのだ、という疑問が生じなくもない。例えば、
それに結局松原の浜まで歩いていって何がしたかったのかは今なお思い出せないままだ。本当にそこには何も理由や経緯はなかったのかもしれず、幽霊みたいにふたり歩いていって、浜に腰を下ろし、波の音を聴いていたのかもしれない。そうだったらいい。
(p101)
以上は故人の幼馴染のはっちゃんが、故人との旅行の一幕を想起する場面である。最後の文の「そうだったらいい」が、どうにも語り手の声のように思われる。しかしそれは物語を白けさせるほどのものではなく、むしろ確信犯めいた作為として好意的に受け取ることもできる。
三人称の小説には時に、語り手(≒著者)の妄想の産物みたいな印象を受けることがある。特に本作はいわゆる「意識の流れ」的な手法で描かれているためそんな印象をより受けそうなところではあるが、意外にもその種の違和感はない。というのは単純に、それぞれの人物のキャラクター性だとか、情景だとか、出来事の進行だとかが、十分リアルに感じられるだけの描かれ方をしている、という点に依るのではないか。語りの主体そのものの個性というものを限りなく消尽しながら、人物、情景、出来事といった物語そのものをリアルに描いていくという姿勢の徹底が、「三人称主体の妄想」という印象を薄くし、物語としての成立を助けているのではないか。――と言ってみれば至極平凡な答えではあるが。
ここまで割と好意的な意見を述べてきたように思われるが、しかし上記した古川真人「背高泡立草」と同じような印象は本作でも抱かれた。「ならば自分の生活を注視するだけでこの所感は得られるのではないか(あるいはそれはすでに知られた所感ではないか)」「生々しい生活の印象など敢えてフィクションとして読むに足るものだろうか」という点である。先付けに記したように、近々にリアルお葬式、リアルお通夜に参列した身となれば自身の体験のほうが生々しい、というよりも生そのものである。確かに本作は単純にお通夜の話というだけではないものの、リアルお通夜も単純にお通夜だけというわけではなく、本作が示すように親族集まり様々な想念が渦巻くわけである。
それでも敢えて本作を読む意義はあるかどうか、というと。
個人的に本作最大の読みどころは、現実が異様な強度を帯びる瞬間の輝きを捉えた、以下のような抜き出しにある。
真っ先に浮かんでくるのは、横浜の家のリビングに美之と知花のふたりだけがいたある時のことだった。床に座って雑誌の付録かなにかを広げていた知花がふとソファに寝そべっていた美之を見ると、美之も知花のことを見ていた。その目が合った一瞬のあまりの短さゆえなのか、あるいはふたりの呼吸かなにかがぴったりと同調したのか、奇妙な、しかし確信に満ちた兄との一体感というか合一感に襲われた。今、ふたりは同じことを考えている。考えていることが同じなのではなくて、ふたりが一緒に、ふたりがかりでひとつのことを考えている。誰にそんなことを聞いたことがあるわけではなかったけれども、血のつながった兄妹というのはきっとどこもこういう瞬間があるものなのだ、とこの時知花は思った。美之は、目が合った一瞬のそのあとにはすぐに目を逸らし、天井の方に目を向けた。合一の感はすぐに消え去り、また別々の人間として部屋のなかで過ごしはじめた。
(p45)
こういうトリビアルかつ重大な出来事の描出というのは、とてもいい。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
