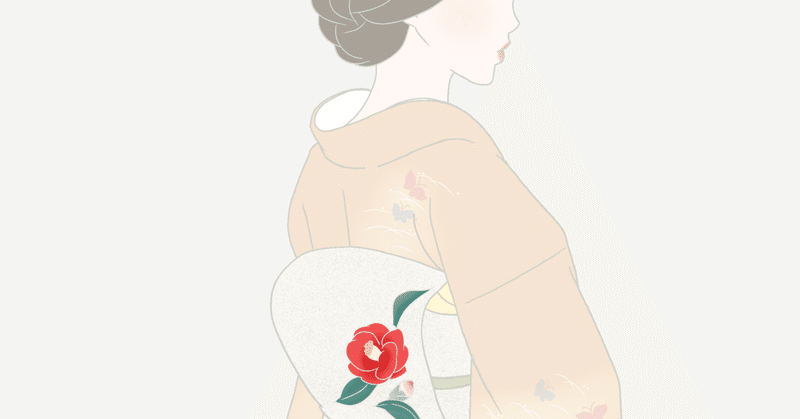
ぼくらが売っていたものは呉服ではなく。
ぼくが呉服屋に勤めて半年経った頃のことでした。
加藤さん(仮)という60代のお客様が、雪の降る日のある朝、お店に歩いてやってきたんです。
加藤さんはぼくの先輩のお客様で、つい2ヶ月ほど前に80万円ほどの呉服を買われたばかりでした。
「ぼうずはおるかい!」
加藤さんが怒っていらっしゃることは明らかでした。彼女の声と表情はとても強張っていました。
店内を見まわし、自分に着物を売った担当者がいないことがわかると、商談用の椅子に腰かけました。
「すみません、宮崎は外回りに出ていまして、もうちょっと待ってくださいね。」
ぼくはそう言い、加藤さんにお茶を出しました。
「おらんのかい。あのぼうずには言いたいことがたくさんあるんやって。まったく、どこをほっつき歩いてるんや!」
加藤さんの強い剣幕に押され、ぼくはおどおどしていましたが、このままだと他のお客様がいらっしゃったときに、店の雰囲気が悪くなってしまうので、しかたなく加藤さんの話し相手になることにしました。
すると、言葉が出てくる出てくる。加藤さんの不満はかなりのものでした。
行きたくないのに無理やり催事に連れて行かれた。
買いたくないのに高い呉服を買わされた。
だいたい、着ていくとこなんてない。
しまいには、「あんたら若いんやから、こんな仕事してたらあかんて」とお説教をいただく始末でした。
ぼくは「そうですね」と相槌を打っていましたが、内心では当の本人である先輩に腹が立ち始めていました。
(買う気のないお客さんに高額商品を売ってどうするんだよ。クレームになるだけじゃないか。大きな問題になったらどうするんだよ)
ぼくがそんなことを考えていたら、やっと先輩が帰ってきたのです。
店に入った先輩はすぐになにが起こっているのかわかったようです。
「あれー!加藤さん、どうしたの!来てくれたの?」
先輩の声が聞こえた瞬間、鬼のような形相をしていた加藤さんは、真夏の太陽で溶けたチョコレートのように表情をゆるませ、くるっと振り向きこう言いました。
「あんたを待ってたんやって。いいからこっちきんさい」
あんなに怒ってたのに、あんなにぼくにクレームを投げつけてきたのに、加藤さんは恋する10代の乙女のように頬を赤らめていました。
「あんたが全然うちにきいへんから来てやったんやって。なんやあんた、売りっぱなしで顔も見せんで。たまにはどうでした?やらなんや顔を見せんかいな。ほれ、これ漬物。これ食べんさいな。どうせ、たいしたもの食べてないんやろ。あんたそんなたぬきみたいな腹して、また毎日ラーメン食べてるんかいな」
加藤さんのおしゃべりは止まることなく続きました。
ぼくは席を立ち、バックヤードから見守っていましたが、クレームのクの字もなく、加藤さんは手作りの漬物を無理やり先輩に押し付けていました。
いったい、なんだったんだ……。あんなにぼくには文句ばかり言っていたのに、まるで恋人みたいじゃないか。
ぼくが呆然としていると、50代後半のベテラン女性販売員がぼくに近づきこう言いました。
「寂しかったんやって。加藤さんは。ただ、それだけよ」
「みんな色々文句を言うけどね。高いものを買わされた文句を言ってるんじゃないの。自分を大切にしてくれないことが寂しいのよ」
「あの人の娘さん。神戸に行ったきり、10年も帰ってきてないのよ」
あんたも気をつけんさいよ、と彼女はぼくの肩を叩き、タバコを吸いに外へ出ていきました。
今のぼくならよくわかるんです。
ぼくらが売っていたものは、呉服なんかじゃなかった。
ぼくらが扱っていたものは、日本の古き良き伝統なんかじゃなかった。
ぼくらは、孤独な人々の心の穴を埋めるなにかを売っていた。
思えば、お客様たちには孤独な人が多かった。
子どもが巣立ってしまい滅多に帰ってこない人々。
嫁との関係がうまくいっていない姑さん。
夫との関係がうまくいっていない女性。
恋人も友人もいない女性。
彼女たちには親密な人がそばにおらず、その代わりお金だけがあった。
彼女たちは使い道のないお金をぼくらに差し出し、ぼくらは彼女たちに親密性を提供していた。
誰からも優しい言葉をかけられることもなく、誰にも心を開けない彼女たちが自分をさらけ出せる唯一の場所が、あの店だったんだと思う。
呉服販売において、アフターフォローが重要視される理由もそこにある。
商品を売って終わりなのではなく、そこからお客様との関係が始まるからだ。
お客様にないがしろにされた気持ちを感じさせないために、孤独を感じさせないために、ぼくらは親密性を与え続ける。
だけど……。
彼女たちが日常生活のなかで、親密性を感じることができれば、何十万、何百万ものお金を使う必要はなかっただろうに。
夫、姑、友人、同僚。
身の回りの人々との関係性のなかに親密さを感じ、生きる喜びを感じられていれば、そんなことはなかっただろうに。
あれから20年近くが経ち、今ではそう思うんです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
