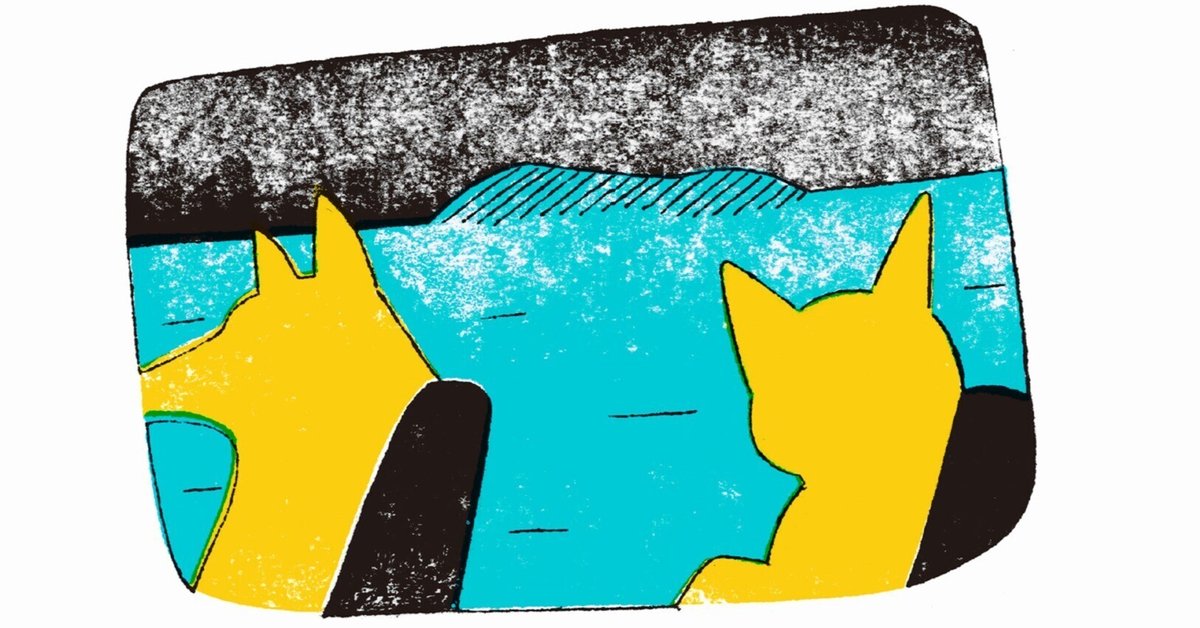
良寛のスケールと斎藤茂吉の新しさ 二人が詠んだ「母への思い」の味わい深さ
千年を経て愛される和歌と近現代の短歌。二首を比較しながら人々の変わらない心持ちや慣習に思いをはせ、三十一文字に詰まった小さくて大きな世界を鑑賞する『つながる短歌100 人々が心を燃やして詠んだ三十一文字』(あんの秀子著、朝日新聞出版)。特にガリ版で刷ったイラストは見ごたえ十分です。最終回は「母への思い」をお届けします。
江戸時代後期の禅僧・良寛は、名主の家柄に生まれましたが、幼い頃から字を書くのが好きで読書にのめりこみ、学問や思索を追求するタイプでした。風雅の道に生きて、早くに家督を息子(良寛の弟)に譲った父親との確執もあったようで、10人の子どもを育てる母の苦労を知りつつも、 良寛自身もまた自らの道のために家を捨てるという、「逸脱者」となったのです。

良寛26歳、母が死に瀕しているという知らせを聞いても、故郷には戻りませんでした。のちにふるさとの庵で、亡くなった母を思い出すとき、海の向こうに母の生地でもある佐渡が見えた。死に目に会えなかった母の形見が「佐渡の島べ」だというのですから、何ともスケールが大きい。と同時に、海に隔てられてすぐには行けないという孤絶感、 突き放した感じに、はっとさせられます。
『万葉集』を愛した良寛の詠みぶりは素直で、初句「たらちねの」は『万葉集』に多い枕詞。結句「見つるかも」の末尾「かも」も、万葉らしい詠嘆の調べです。
そしてアララギ派の近代歌人・斎藤茂吉の最初の歌集『赤光』に収められた「死にたまふ母」の連作。ここにも、『万葉集』への強く深い意識がちりばめられています。
山形県南村山郡金瓶村(現在の上山市金瓶)の農家に生まれた茂吉は、進学のために15歳で上京し、医院を開業する同郷の斎藤家のもとへ。やがて婿養子として斎藤家の次女・輝子と結婚することになります。

五十九首の「死にたまふ母」連作は、茂吉が医学部助手時代の31歳のとき、母危篤の報を受けたところから始まります。上野で夜汽車に乗り、母の臨終を看取って葬儀を行い、ふるさとの山々に包まれて湯に入り、蓴菜や若竹を食べるなどして母への思いを詠う、数日にわたるものです。
連作の中でも、この「みちのくの」は、ふるさと東北の地を意味する初句や、「一目みん」の繰り返しが強い印象を残します。故郷へと急ぐ気持ちが切実に伝わってくる歌でもあります。汽車に乗っていることからくる速度感や切迫感は、近代以前の歌にはないものです。
ぜひ連作としても味わってみてください。一首一首とその連なりが、そして連作全体が、さらには歌集自体が生きもののように迫ってきます。
1913(大正2)年に発表された『赤光』の茂吉と、それからおよそ100年前の江戸時代の良寛。ぷいっと詠んだような、作為のあまり感じられない良寛と比べると、茂吉には断然、短歌としての新しさを世に打ち出す気負いがあったでしょう。しかし、二人の間には『万葉集』という共通するものが、脈々と流れているのです。
