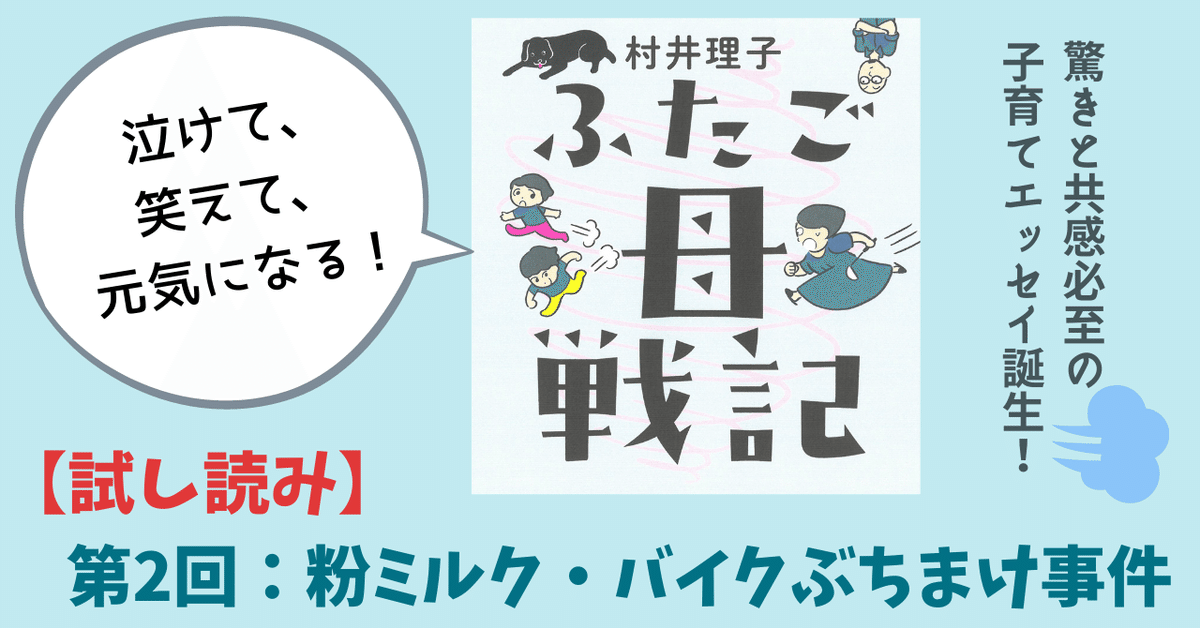
【試し読み】ワンオペふたご育児で追い詰められて…共感必至の子育てエッセイ!村井理子『ふたご母戦記』/粉ミルク・バイクぶちまけ事件
人気翻訳家・エッセイストの村井理子さんによる、初の子育てエッセイ『ふたご母戦記』。村井さんは琵琶湖のほとりに、夫と双子男児(16歳)、大型犬と暮らし、年間に何冊もの翻訳書やエッセイを出版、さらに義父母の介護も加わり、大忙しの日々を送っています。本書は、妊娠中から高校受験までの16年間を綴ったものです。
35歳で出産した双子の男の子が乳幼児だった頃、ほぼワンオペで子育てをしていました。今回は、孤独な育児で追いつめられた末に村井さんがブチギレた驚愕の出来事を記した、『粉ミルク・バイクぶちまけ事件』を特別公開いたします!
■第1回/自己紹介:初産で、双子で、高齢出産だ

粉ミルク・バイクぶちまけ事件
育児の何がそこまで大変なの? そもそも、大変だということはわかっていて、それでもあえて出産したのでしょう?と、私自身も何度か言われたことがある。そのたび、何も言い返せず、口ごもるだけだった。悲しい。
今だったら、育児の何がそこまで大変なのだと問われたら、「孤独」が一番辛いのだと大声でハキハキと答えることができる。大変だとわかって産んだのでしょう?と言われれば、それはもちろんわかっていたけれど、ここまで大変だとは夢にも思っていませんでした!と答える。特に、0歳から2歳頃の育児はどんなにタフな人でも苦労するのではないだろうか。
猛烈サラリーマンとワンオペ妻
いつの間にやら、世の中にイクメンという言葉が登場し、確かに、街には赤ちゃんを抱っこ紐で抱える若い父親たちの姿が増えたものの、自分の周りを見回すと、そんな人はあまりいなかったし、自分の夫もいわゆるイクメンタイプではなかった。私の数少ないママ友たちの夫は、ほぼ全員が今どきのイクメンのイメージからは遠く、どちらかというと、外でバリバリ働き、稼ぎ、育児は妻に完全に任せるタイプの人が多かった。しかし、そんな夫たちが悪い夫かというと、皆が気のいい、優しい人たちで、それぞれが幸せに暮らしているように見えた。それでもやはり、子育てを一手に任されたママ友たちは疲れ切って見えた。
わが家も似たような環境だった。私の夫はとても真面目なサラリーマンだ。休まず働き、双子が赤ちゃんの頃は猛烈に残業をしていた。朝、7時に京都の職場へと向かい、琵琶湖北西部のわが家に戻るのは、ほぼ深夜になることも多かった。疲れて家に戻り、食事をして、風呂に入って、寝るのが精一杯の生活。そして、数時間寝て、また職場に戻る。家にいるよりも、職場にいるほうが長いような毎日だった。
双子と一緒に家から一歩も出られず、ほぼ眠ることができないような暮らしをしていた私は、そんな疲れ切った夫の帰りを今か今かと待って、毎日をどうにかしてやり過ごしていた。双子はひっきりなしに泣き続けた。1人がようやく眠れば、もう1人は目を覚ました。1人が風邪を引けば、もう1人も必ず風邪を引いた。とにかく誰かがつきっきりで面倒を見なくてはいけない。その誰かは、ほとんど私だった。夫が戻れば、30分でも育児を代わってもらうことができる。その間に自分の好きなことができる。
今となっては夫も大変だったに違いないと思うけれど、私自身も辛い時期を過ごしていた。そんなギリギリな日々は、今にして思えば、完全な悪循環のはじまりだった。
双子を連れて外出するのは至難の業
なにせ、双子育児は買い物さえ難しい。双子用ベビーカーには、縦型と横型があるが、横型に乗せるとスーパーの通路を歩くことができないし、縦型に乗せると、通路の角を曲がるとき、曲がった先に何があるのか見ることができない。横型も縦型も、2人を乗せたらカゴを持つことができない。まさか、カゴを載せたカートとベビーカーを同時に押すこともできない(腕が3本あったら可能かもしれないが)。
横型も縦型も、危なくてエレベーターを使うことはできなかった。横型だと、エレベーターに入る瞬間に必ずどこかがドアに引っかかるし、縦型の場合、入っていく最中にドアが閉まるのではという恐怖が先立って挑戦したこともない。それに、何人も乗っているエレベーターに、双子用の大きなベビーカーとともに乗り込むのは気が引けた。周りの視線が怖かった。
たとえば近所の公園に行ったとしても、2人を同時に遊ばせるのは至難の業だ。1人が右に行けば、もう1人は必ず左に行くのが双子というもの。睡眠不足の状態では公園に行くのでさえ、気が重い。重いのは気持ちだけじゃなくて、どんどん成長する双子は実際に重かった。双子の移動には、大人が2人は必要なのだ。そういう理由もあって、昼間、私は引っ越したばかりの家のなかで、双子につきっきりの日々を過ごしていた。そして、今か今かと夫の帰りを待っていたというわけだ。
引っ越したばかりの田舎町で、相談相手も多くはなかった。乳児検診で出会ったお母さんたちと話すことはあったけれど、双子の成長について保健師さんに何を言われるのかと不安で、会話の内容なんて記憶に残らなかった。ああ、なんて恐ろしいことだ……。
「育児」の脇役になろうとする夫
私の夫は確かにイクメンというタイプではないけれど、それでも育児の手助けはしてくれた。頼まずとも、おむつを替え、ミルクを作り、私が双子のどちらかにかかりきりになっていると、残りの2人の面倒を見てくれた。その点はとてもよい父親だった。
しかし、1点だけ彼に難癖をつけるとしたら、彼のなかには、「育児は母親がすべてやるべきもの」という考えが根強くあったことだ。つまり、彼が手助けをするときは、それは彼の好意からであり、彼自身は育児を自分の責任で行うべきものだと捉えてはいなかったと思う。それよりなにより、仕事だった。仕事をしっかりとすることが、父親の役目だと信じていたと思うし、育児は私の方が得意だろうと漠然と感じていたのだと思う。そんな夫は、育児というステージに立つと、突然、脇役になろうとした。私からすると、ちょっと待って、この舞台で主役は2人だよ?という気持ちが常にあったのだ。
脇役としての育児が辛くなると夫は、必ず別の脇役を舞台に送り込んできた。わが家から車で20分程度の距離に住む義母だ。夫は自分が困ると必ず、「母さんに頼めばいいじゃないか」とか、「おふくろだったら、たぶんこうする」なんていうタブーを口にした。私からすれば、夫の口から最も聞きたくない言葉だ。私たちの舞台に、突然そんな個性派俳優を送り込まれてもという気分だし、実際、義母はキャラクターの強い人で、数々の神話を信じる人でもあった。その神話とは、母乳神話であるし、3歳児神話であるし、手作り神話だ。そのすべてを全力で否定したい私とは、あらゆる点で意見が異なった。そして義母は、脇役というよりは、主役を張りたいタイプの人だった。
夫の両親には、様々な形で育児を支援してもらった。双子が2人とも発熱すれば、小児科の受診に付き合ってくれ、私が疲れているときは食事のしたくなども率先してやってくれた。もちろん感謝はしているが、心に1ミリも余裕のなかった私は、彼らの手助けさえも受け入れることができないほどに追いつめられていた。
避難部屋に籠もる夫
追いつめられていたのは、夫も同じだっただろう。子どもと妻のためにと必死に働いて家に戻れば、泣き続ける双子と疲れ切った妻が虚ろな表情で待っていたとしたら、悪夢のようだ。そのうえ、妻は苛立ち、部屋は荒れ果て、洗濯もロクにできていない状態だったとしたら? 私が逆の立場でも音を上げそうだ。
残業が続く日々には、夫は双子とは別の部屋で眠るようになり、早く家に戻った日も、双子と時間を過ごすことなく、いつもの避難部屋(と、私は呼んでいた)に籠もり、テレビを見るようになった。「頼むから、たまには休ませてくれよ」と夫は言った。その台詞は私のものだと思いつつも、言い争う気力もなかった私は夫の言葉を受け入れ、夫が残業から戻った日は、彼の好きなようにさせていた。そしてますます追いつめられた。
夫はいきいきと仕事に邁進するようになり、私は孤独を感じるようになった。私はこの広い世界で、たった1人でこの双子を育てているのだと考えるようになり、たとえ家のなかに誰かがいたとしても、私は1人なのだと信じ込み、双子を育てあげなければ、絶対に失敗してはならないと、決意を固くした。そう考えるようになった途端に夫への執着が薄れ、夫が「今日は残業」とメールを寄こせば、「がんばって」と答え、「今日は送別会」と言われれば、「了解」と返すようになった。
夫が家にいようがいまいが、まったくこだわることもなくなったし、むしろ、夫の手から育児を取り上げるようになっていった。なぜなら、この育児は私1人が完璧にやり遂げなければならないものだと、私がぎりぎりの精神状態で、自分を追い込んだからだ。
両腕にミルク缶を抱えて……
そんな恐ろしいある日のこと、夫がいつものように、「ごめん、今日は送別会!」とメールを送ってきた。双子の面倒を見ながら、いつものように「了解」と返事を出した。そして、ようやく眠りはじめた双子に添い寝して、私も、うとうととしはじめた。30分ほど経ったときだろうか、メールの着信を知らせる音が携帯から鳴った。夫からだった。今から帰るというメッセージとともに、ラーメン店で同僚とラーメンを食べ、笑顔でピースサインをする夫の写真が添付されていた。それを見た瞬間、私のなかで何かがはじけた。ふらふらと立ち上がった私は、両腕に育児用粉ミルク缶を抱えて、ガレージまで歩いて行った。
ガレージに行き、夫が大切にしていたバイクの前に立ち、ミルク缶の蓋を開けた。そして、中身をすべてバイクにぶちまけた。1缶が終わり、そして2缶目もすっかり空にした。そして、空になったミルク缶を渾身の力でガレージの壁に叩きつけ、バイクを思い切り蹴り、静かに双子の寝ている部屋に戻って、私も眠ったのだった。
この日以降、夫は徐々に変わり、育児に積極的に関わるようになった。私は夫の助けを徐々に受け入れるようになり、安心して育児を夫に任せるようになった。私も夫も、バイクの話は口にしなかったし、夫はガレージのミルクの粉をきれいに片付け、何ごともなかったかのようにバイクを磨いて、そのまま乗り続けた。
この大事件から数年経過したある日、外出から戻った夫が、「バイクで信号待ちしてたら、ハンドルのあたりから粉ミルクが落ちてきたわ」と愉快そうに言った。今となってはわが家の定番の笑い話になっているが、当時はそれほどまでに追いつめられていたのだと、ふと恐ろしくなることがある。
