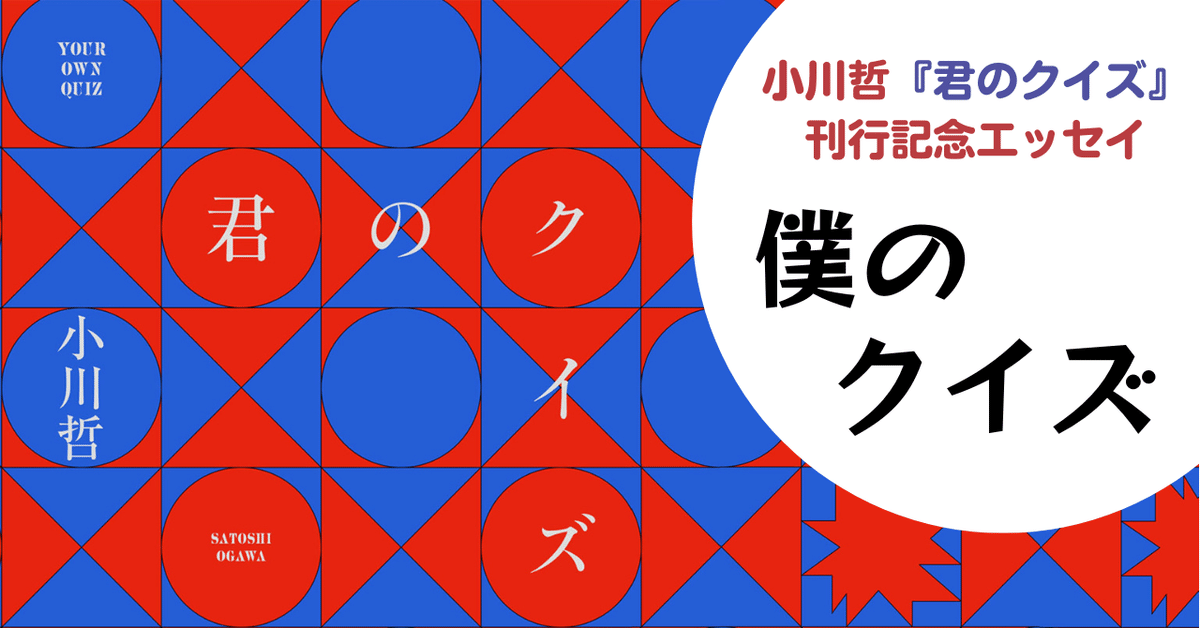
まるで「クイズ」を体験するような新しい小説の誕生! 小川哲『君のクイズ』刊行記念エッセイを特別公開
10月7日、小川哲さんの『君のクイズ』がついに発売となります! 本作は競技クイズのプレイヤーを主人公に、まるで自分自身が“クイズ”と対峙しているような没頭感と、頭がフルで回転するような感覚を味わえる、まったく新しい小説といえます。「小説トリッパー」2022年夏季号に掲載後、各紙文芸時評、書籍紹介ブログやYouTube、SNSなどで編集部も驚くほど異例の大反響を呼んだ作品になります。
刊行記念として、朝日新聞出版PR誌「一冊の本」2022年10月号に掲載された著者・小川哲さんによるエッセイを特別に公開します。

僕のクイズ
作家・小川哲(Ogawa Satoshi)
人生において、僕たちはさまざまなクイズと出会う。面接官に「志望動機は?」と聞かれ、準備していた答えを口にする。食卓に置かれたカレーの「隠し味は何だと思う?」と質問され、もう一度じっくり味わってみる。自宅で、職場で、学校で、僕たちはよくクイズを出題される。
クイズプレイヤーたちは、クイズが好きで得意な人たちだ。彼らが得意としているのは「競技クイズ」という種目で、広義のクイズとは多少異なっている。「競技クイズ」で出題されるクイズには基本的に答えが存在していて、その答えが正しいことを何らかの手段で証明することができる。「競技クイズ」には早押しクイズや多答クイズなどの形式が存在し、勝ち抜けのために必要なポイントなどが定められている。「競技クイズ」とは、客観的な基準によってクイズに正解する能力を競う種目である。
僕が「競技クイズ」とはじめて出会ったのは高校2年生のときだ。もっともそのときは競技クイズという言葉も、概念も知らなかった。当時たまたま見ていたテレビで高校生クイズをやっていて、ちょうど決勝ラウンドの早押しクイズだった。
敗色濃厚だった栄光学園チームの一人が「チャージかけるか?」とチームメイトに問いかけ、他のみんなが「かけよう」とうなずいた。「チャージ」が何を意味するかわからなかった。結局、「チャージ」後の栄光学園は誰よりも早くボタンを押し続け、何問も連続で正解し、最終的に逆転優勝した。
テレビの前の僕は、栄光学園の劇的な逆転に感動した上で、率直にこう思った。「それなら最初からチャージをかければいいのでは?」
翌日、高校生クイズを視聴していたクラスメイトたちと「チャージ」の話題で盛りあがった。それまでほとんど正解できていなかった栄光学園が「チャージ」によって別人のように連続正解したこと。最初から「チャージ」をかければいいのに、と思ったこと。
その日から僕の高校で「チャージかけるか?」という言葉が流行した。使い方には幅があったが、主に本気を出すときや、窮地に追いこまれたときに口にする言葉だった。マラソン大会中に苦しくなったとき、トランプで遊んでいるとき、気になっていた女の子に連絡先を聞くとき、僕たちは高校生活の中で、幾度となく「チャージ」をかけた。
栄光学園の優勝から10年以上経ってから、小説家になった僕は、徳久倫康くんというクイズプレイヤーと知り合った。飲み会の場でクイズの話題になったとき、僕は自分の得意ジャンルから「サッカー選手であるハンダノビッチはどこのチームに所属しているか?」という稚拙なクイズを出した。徳久くんは「インテルのゴールキーパーですね」と即答した。僕は徳久くんの知識の広さに、そして徳久くんが別段サッカーが好きなわけではないことに、とても驚いた。それに加えて、大学の学科の後輩に田村正資くんというクイズプレイヤーもいた(田村くんはあの伊沢拓司さんとともに、高校生クイズで全国優勝をしている)。
それ以来、僕は「クイズの勉強」を始めた。純粋に、クイズプレイヤーのことを尊敬したし、彼らがどうやって様々な知識を得て、それを保存しているのか気になったからだ。
「クイズの勉強」と言っても、僕の勉強の仕方は特殊だった。一般的なクイズプレイヤーのように問題集を解いてクイズの実力を磨いたわけではない。彼らがどのように知識を集めているか。相手より先に早押しをするために何を考えているか。競技クイズの世界ではどのような実力が必要とされていて、どういうプレイヤーが大会に優勝するか。
僕はクイズそのものというよりも、クイズに魅入られた人々や、彼らの考え方に興味を持った。彼らがどのように自分の世界を広げていくのか、彼らは世界をどのように見ているのか――そんなことをよく考えた。僕は「クイズの勉強」ではなく、「クイズの勉強をする人々の勉強」をしたのだった(あえて自分を表現するのなら、戦術マニアのサッカーファンや、プロ棋士の対局の観戦を楽しむ「観る将」に近いのかもしれない)。
ちょうど、10数年前の僕が、たまたま高校生クイズの決勝戦を目にしたように、『君のクイズ』は、テレビのクイズ大会の決勝の場面から話が始まる。
クイズプレイヤーの本庄絆は、最終問題でまだ1文字も読まれていないクイズに正解し、大会で優勝する。対戦相手だった語り手の僕――三島玲央はヤラセだったのではないかと疑い、本庄絆がどうして読まれてもいないクイズに正解できたのかを探りはじめる。
そのクイズ大会はヤラセだったのか、本庄絆は魔法を使ったのか、それとも何か合理的な理由があって、1文字も読まれていないクイズに正解することができたのか――はたして三島玲央はどういう結論を導くのか、というのが主なストーリーだ。
この小説には、クイズの素人の僕が「神がかり的な早押しに対して純粋に驚く」気持ちと、「クイズの勉強」をした僕が「早押しには常に合理的な根拠がある」と考える気持ちの、両方が共存している。100年以上前、初めて電話に触れた人は、受話器から聞こえる声が幽霊だと感じたというが、10数年前に栄光学園の早押しを見た僕は、それがクイズプレイヤーしか使うことのできない魔法のように感じた。しかし、クイズプレイヤーや競技クイズについて学んでいく過程で、栄光学園の人々がどういう技術を使ったのか、「チャージ」とはいったい何だったのか、そのことがよくわかるようになってきた。早押しクイズでは、状況に応じてどの程度のリスクを許容するかが変わってくる。たとえば「『おい地獄さ行(え)ぐんだで!』という書き出しで始まる、小林多喜二の書いたプロレタリア文学の作品は何でしょう?」というクイズがあったとする。多くのクイズプレイヤーは「おい地獄――」まで聞いた時点で、答えが『蟹(かに)工船』であると考える。逆に言えば「おい地獄――」まで聞いてしまうと、ライバルに先を越される可能性が高くなる。相手に正解されるとマズい状況では「おい――」と聞こえた段階で押す。問い読みのイントネーションを確認し、「おい――」が「オイラー」や「及川光博」と続かないことを確認する。しかしそれでも「おい木村さん信さん――」(樋口一葉『にごりえ』)の可能性はある。そのリスクを承知しながら、「おい――」で押す。これが「チャージ」だ。
つまり、追いこまれた栄光学園のメンバーは、誤答するリスクを背負いながら、相手より先にボタンを押すことを優先することにした。彼らは魔法を使ったわけでもないし、前半で手加減をしていたわけでもない。「高校生クイズで優勝する」という目標のために、最善の戦術をとっていただけだ。
『君のクイズ』には、「クイズ」という形式を通じて見ることのできる世界を(成功しているかどうかは別にして)、可能なかぎり描いたつもりだ。「クイズ」は僕たちの世界が広がっていく過程や、「知る」という行為の美しさと難しさ、僕たちが経験してきたすべてのことを問いかけてくる。自分の本を「ぜひ読んでほしい」と言うのは気恥ずかしいので、僕の本を読まなくてもいいから「ぜひ競技クイズに注目してみてほしい」とだけ言わせてほしい。
*小川哲著『君のクイズ』は朝日新聞出版より10月7日発売予定
