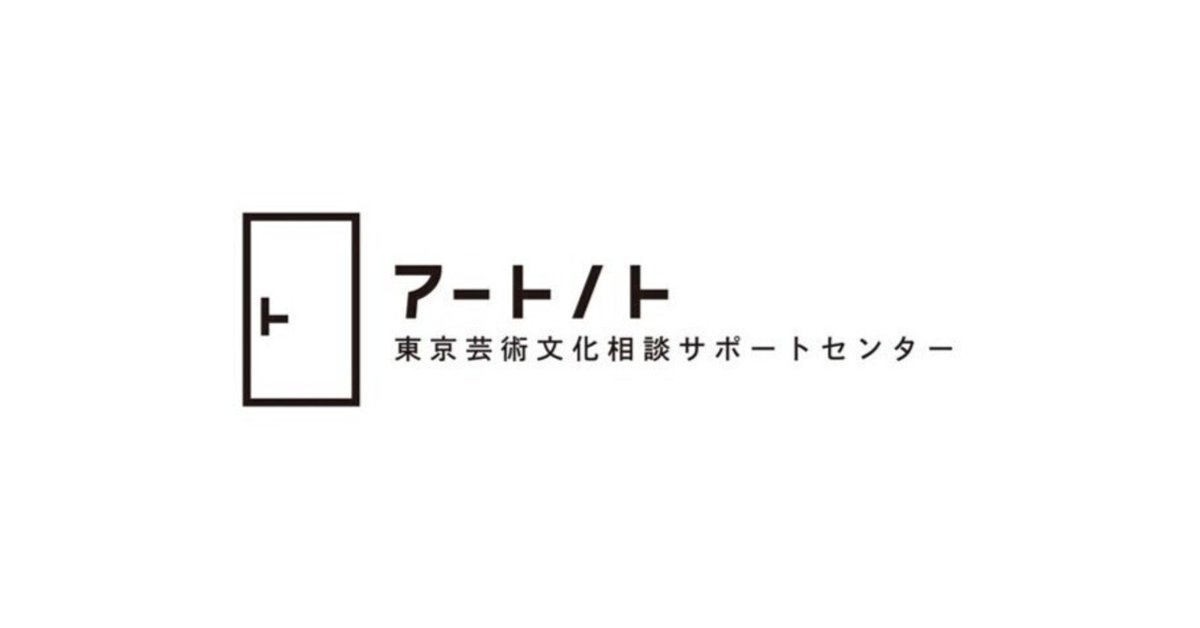
Q58 コンサート開催と観客の安全
エンターテインメント・ロイヤーズネットワーク編
エンターテインメント法務Q&A〔第3版〕
株式会社 民事法研究会 発行
より許諾を得て抜粋
協力:エンターテインメント・ロイヤーズ・ネットワーク
Question
コンサート開催中に事故が起こり、観客がけがをしてしまった場合、どのような対応が必要か。また、主催者は、コンサートにおける感染症の予防義務を負うか。
Point
① コンサート提供における主催者の義務
② 損害賠償責任の根拠規定
③ 賠償責任保険等による備え
Answer
1.コンサート主催者の義務
コンサート主催者は、コンサートの観客に対し、演奏等の提供を行うことが期待される。コンサート主催者の義務の主たるものは、コンサートの主題である演奏等の提供である。加えて、コンサート主催者は、観客らが、安全に演奏等の提供を受けられる場を提供するという「安全配慮義務」も付随的義務として当然に負っていると考えられる。
「安全配慮義務」は、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触関係にある当事者間の一方または双方が相手方に対して一般的に認められるべき信義則上の義務であり(最判昭和50・2・25民集29巻2号143頁など)、債務不履行責任の一つとして不法行為責任とは別異の責任として判例上認められている。
したがって、コンサート主催者は、演奏等を提供するのみならず、観客が安全にコンサートを楽しむことができるよう、観客らに対し、コンサートを楽しむうえで必要となるさまざまな注意(押し合わない、飛び跳ねない等)を喚起するとともに、警備員や会場整理係を適宜配置し、興奮した観客がステージ近くに殺到し、けがなどをすることのないように、使用する機材や演出により観客に危険が及ぶことのないように適切な配慮を行う必要がある。
また、コンサートにおいてけが人や病人が発生した場合、当然のことながら、コンサート主催者は、けが人や病人の介護に当たり、必要に応じて、コンサートを一時中止するなどの適切な措置をとることが求められる。興奮した観客が殺到したことなどによりけが人が発生したような場合、舞台装置に不具合が生じたような場合には、コンサートを即時中止し、新たなけが人等の発生を予防する措置も必要となる。
近時は、地震などの自然災害により、コンサート会場に危険が及ぶことも想定されるため、コンサート主催者としては、万が一の場合に備えて、緊急避難通路や救助の要請などについて確認をし、観客に対するアナウンスや避難誘導方法などについてもマニュアル化しておく必要もある。
また、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)等の感染症について、コンサート会場における感染の拡大が危惧される場合には、コンサート主催者は、観客、コンサート出演者、コンサートスタッフの安全確保のために、前記安全配慮義務として、感染防止対策を行うことが要求される。感染防止対策については、公益社団法人全国公立文化施設協会「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」、一般社団法人クラシック音楽公演運営推進協議会「クラシック音楽公演における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」、緊急事態舞台芸術ネットワーク「舞台芸術公演における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」などが参考になる。
2.損害賠償の根拠
コンサートにおいて、けが人や病人が出た場合の損害賠償請求は、コンサートという役務提供の債務不履行(民法415条)に根拠を求めるほかに、前述の安全配慮義務、コンサート主催者の過失による損害として不法行為(同法709条)に根拠を求めることができる。また、事故発生の直接の原因となった行為者に過失が認められる場合、当該行為者に不法行為責任を追及するとともに、当該行為者の使用者である会社等に使用者責任(同法715条)を請求することも考えられる。さらに、屋外でのイベントなどの場合、土地工作物責任(同法717条)による責任追及がなされる事例もある。
損害賠償請求を行う場合に、債務不履行と不法行為が併存し、それぞれの要件や時効過失相殺の有無など双方に差異が生じうる。安全配慮義務についても、もともとは不法行為時から3年で短期消滅時効にかかる不法行為に基づく損害賠償請求のみでは被害者の救済が不十分であることから、債務不履行責任の一つとして、不法行為の短期消滅時効後も責任追及を可能とし被害の救済を図るものである。しかし、ある一定の事象に対する損害賠償とし
て、債務不履行で請求するか不法行為で請求するかによって、その結論に大きな差が生じることは適切ではないという考え方から、判例上、双方の結論に大きな差が生じないような判断がなされており、実務上はいずれの構成によっても大きな差異が生じないとされている。また実際の裁判においても、予備的請求などにより、債務不履行と不法行為の双方を根拠として主張することが多いと考えられる。
3.コンサートの事故に関する判例
⑴ 観客が死亡した事例
イギリスの人気ロックバンドのコンサートにおいて、演奏開始直後、人気演奏家にできるだけ近づいて演奏を聴こうとした観客多数が一時にステージ前に殺到し、観客の1人が多数の観客の中で転倒し、他の観客がその上に倒れたり当該観客を踏みつけるなどした結果、観客が死亡した事案がある。裁判所は、日本でも20歳前後の男女を中心に高い人気を得ているロックバンドであり、しかもハードロックの演奏をすることを特徴としていたというのであるから、その演奏により観客が熱狂し、興奮した観客の中には席を離れてステージ前に近づこうとする者が現われることは当然予想されたとして、現場責任者に対し、不法行為責任(民法709条)の成立を認め、その使用者であるコンサート主催者に対し、使用者責任(同法715条)の成立を認めた(札幌地判昭和58・4・27判夕502号145頁)。
⑵ 出演者が負傷した事例
米国のベースギター演奏家が、ロック歌手のコンサートにバックバンドの一員として出演した際にホール舞台中央部のセリ穴から奈落に転落して負傷した事故において、関係者に対し、出演契約に基づく安全配慮義務違反による債務不履行責任、本件コンサートの舞台監督者の不法行為についての使用者責任、ホールの舞台設置の瑕疵に係る工作物責任を根拠に損害賠償請求を行った事案において、裁判所は、事前のリハーサルにおいてセリ穴の存在について十分な注意喚起が行われていたことなどを根拠に、損害賠償責任をいずれも否定した(東京地判平成7・6・26判夕904号166頁)。
⑶ 悪天候のためにコンサートが中止された事例
「雨天決行」とのチケットを販売していたにもかかわらず、悪天候のために野外コンサートを中止した主催者に対し、再演を求める請求を行った事案について、裁判所は、再演を求める請求は直接強制・代替執行・間接強制のいずれも許されず不適法であるとするとともに、悪天候のため野外コンサートの開催を中止した主催者に債務不履行につき責めに帰すべき事由はないと判断をしている(東京地判昭和63・5・12判事1282号133頁)。
4.賠償責任保険
コンサート主催者としては、コンサートの安全に配慮し、無事に観客らにコンサートを楽しんでもらうようにするとともに、イベントの賠償責任保険に加入し、万が一の場合に備えることが重要である。イベント関連の保険には、主として以下のようなものがある。
⑴ 施設賠償責任保険
入場者等第三者に身体障害・財物損壊を与えたことによる賠償責任損害を補償するものであり、会場施設そのものの構造上の欠陥や管理の不備、イベント運営上のミスにより、入場者等の第三者の身体・生命を害し、または財物を損壊したことに対する法律上の損害賠償責任を負担したことによって被る損害を補償する。対象となる事故としては、コンサート会場で火災が発生し、避難通路の不備により観客が逃げ遅れて負傷した場合などがある。
⑵ 損害保険
イベント出演者出場者、観客、スタッフ・アルバイト等イベント関係者がイベント中に急激かつ偶然な外来の事故により負傷したとき死亡・後遺障害保険金、入院保険金、手術保険金、通院保険金が支払われるものであり、コンサート開催中に観客が将棋倒しになって負傷した場合などに適用される。
⑶ 興行中止保険
不測かつ突発的な事由によりイベントが中止または延期した場合に、回収不能となった費用または喪失する収益を補償するものであり、たとえば、屋外コンサートが台風により中止された場合の会場設営費、広告宣伝費、チケット払戻手数料等について補償されるものである。
⑷ 小 括
以上のように、コンサート等のイベントで起こりうる事故等による損害については、一定程度保険によりカバーすることができるが、被保険者に故意または重大な過失がある場合や、直接の事故と関係のない医療事故、戦争、暴動(テロ行為を除く)、地震、噴火または津波などの不可抗力事由など、通常の保険と同様に、一定の免責事由があることに注意する必要がある。また、被害者に保険金が支払われる場合であっても、イベント主催者に故意・重過失がある場合や明らかな不法行為があった場合などには、保険会社からイベント主催者に対し別途求償がなされることもある。
5.コンサート開催における注意点
コンサート開催においては、演奏等を観客に楽しんでもらうために、演奏や演出を工夫するだけでなく、その前提となる観客、出演者、スタッフ等の安全を確保したうえで、コンサートを楽しんでもらうことが肝要である。
万一のためのマニュアルの作成や保険の付保、警備員の配備といったリスク管理のみならず、演出においても観客、出演者、スタッフ等の安全に配慮した工夫が必要である。興奮した観客が押し合うといったことのないよう、曲の演奏順を考えたり、出演者に「皆が楽しめるように(マナーを守ろう)」といった観客に対するメッセージを伝えさせるなど、エンターテインメントと安全とが両立するような形で、演出を行うことが考えられる。また、感染症が拡大しているときには、入場時の検温や、検温結果による入場拒否、座席移動の禁止や後日の連絡手段の確保など、安全確保のための手段をとることができるよう、チケット販売前から販売の条件やコンサートの開催条件を十分に準備しておく必要がある。エンターテインメントの面を重視するあまり、安全面を軽視し、事故が起こることのないよう気をつけたいものである。
執筆者:笠原智恵
東京芸術文化相談サポートセンター「アートノト」
アーティスト等の持続的な活動をサポートし、新たな活動につなげていくため、2023年10月に総合オープンしました。オンラインを中心に、弁護士や税理士といった外部の専門家等と連携しながら、相談窓口、情報提供、スクールの3つの機能によりアーティストや芸術文化の担い手を総合的にサポートします。
公式ウェブサイト https://artnoto.jp
