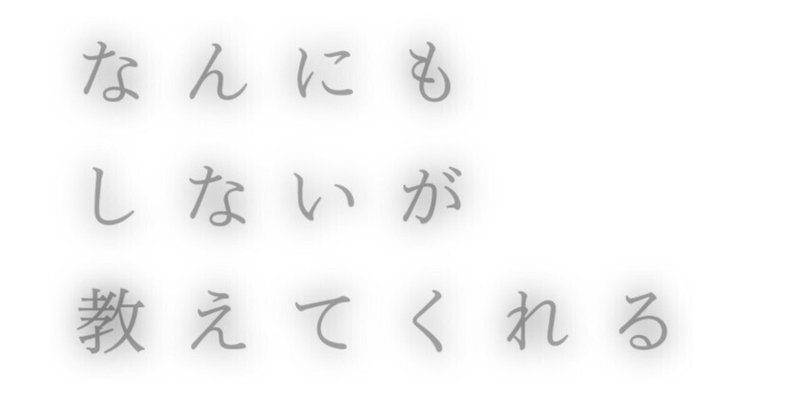
なんにもしないが教えてくれる。「はじめに」と「1章」を公開します。
新刊「なんにもしないが教えてくれる」
昨日、Kindleで出版しました。
この度、「はじめに」と、目次、それと一番最初の1章を公開します。ぜひ、雰囲気を感じていただき、参考にしてください。
なんにもしないが教えてくれる
はじめに
外国に旅に行くと、よく思うことがあります。それも、欧米のようないわゆる先進国ではなく、アジア圏の国がわかりやすいかもしれません。
有名な観光地や、現地のグルメを楽しむのもいいけれど、その国の、その街の人々の何気ない様子を観察することは、僕にとって一番の旅の醍醐味でもあります。
しばらく人々の様子を眺めていると、街のいたるところに〝なんにもしていない〟人がたくさんいることに気づきます。
日本で生活していると〝なんにもしていない人〟というのに出会うことはほぼ皆無です。みんな、常に「何かをしている」のが通常モードです。
仕事をしている、作業をしている、どこかに向かって移動している。つまり、常に何かの行為の最中にあるということです。
最近で言うと、一番典型的な例が「スマートフォン」でしょう。少しでも時間が空くと、スマホを開き、LINEをチェックし、SNSを見て、動画コンテンツを観たり、ゲームをしたりする。
電車に乗るとよくわかるけれど、ほとんど全員がスマホに視線を落とし、指を動かしています。
若い人はもちろん、中高年世代まですべからく、電車に乗ってスマホを観ているという状態です。
紙の本を読む人も、昔と比べて減っているような気がします。電子書籍があるし、ニュースもすべてスマホ。
もちろんスマートフォンはとても便利です。いつどこにいても調べ物ができる。コンパクトだし、とても使いやすい。昔は満員電車で新聞を読む人が煙たがられたものです。
スマートフォンの登場により、誰もが手のひらのなかで、世界中とつながれるようになりました。SNSを開けば、遠く離れた友人の近況を知ることもできるし、自分の近況もアップして、それに対して「いいね」などのリアクションをしてもらえることで、他者とのつながりを感じることもできる。
他にも、動画サイト、音声配信、映画やドラマを観ることもできます。われわれはスマートフォンのおかげで、日々「退屈」することなく、常に新鮮で、われわれを楽しませてくれる情報に接していられます。
それに合わせて、当然情報の速度は格段に上がりました。
おかげで、ぼけっとしていると世の中の流れにあっという間についていけなくなるくらいです。
SNSはもちろん、さまざまなインターネットのコンテンツがあふれかえり、人々は退屈どころか、立ち止まり息をつく暇すらない。
そう、暇がないのです。
ただでさえ勤勉でせっかちで「働きアリ」と揶揄された日本人なのに、スマートフォンの登場により、ますますわれわれには〝なんにもしない〟時間がなくなってしまった気がします。
就業後や、休憩中に一息つくときですら、その一息や一服はスマートフォンに思考を預けることと同義になっています。
時代の流れ、というものはあるので、今の社会に起きていることを否定はしたくないし、そんなことに意味はありません。でも、それらのシステムやプラットフォームそのものを制作した人たちというのは、案外その辺のデジタル機器や情報とのつきあい方は慎重であり、スマートフォンに思考を預けない時間を大切にしているのは事実です。
優秀な人たちほど休暇をしっかり取り、その際は緊急連絡以外は取らないというエリートは多いです。
そして世界のトップエリートたちが実践している「マインドフルネス」と呼ばれる〝瞑想〟も、そのひとつの典型だと思います。
マインドフルネスは、坐禅や、インドのヴィパッサナー瞑想などから、宗教的要素を取り除いた瞑想法。禅の要素もあるので、日本人から見れば逆輸入的なもので、昨今は国内でも始める人が増えています。
瞑想法にもいろいろな解釈や目指すゴールがありますが、基本的には〝なんにもしない〟をすることだと、僕は思っています。
だから、瞑想はとてもおすすめです。現代人が忘れてしまった感覚を取り戻すことができると僕は思っていますし、その効果は実証されていると言えるでしょう。
僕たちは子供のころからずっと「何かをする=生産性」と教えられてきました。
もちろんそうなのでしょう。その効率重視の資本経済社会を通して、われわれ日本人は確かに物質的には豊かになったのかもしれません。だけど、はたして日本人は幸福なのかと問われると、はなはだ疑問です。
毎年何万人にも上る自殺者。コロナ禍や世界的な物価高により、ますます経済的に追い詰められている中小企業。
では、この切羽詰まった状況で、われわれは何をすべきか? 何をすればよいのか?
本屋に足を運べば、悩み解決、成功法則、願望実現を謳うタイトルの書籍がごまんと並び、インターネット上にも膨大な量の情報があります。
しかし、それでも人々の悩みが尽きないのはなぜか? 次から次へと新しい方法論が生まれ続けるのはなぜか? 何かやり方が間違っているのでしょうか? 努力が足りていないのでしょうか?
いえ、きっとみんな努力していると思いますし、うまくいかない人のためにはまた別の方法が提示され、どんどん方法論だけが増えていったのではないでしょうか?
つまり、悩みを解決するためのやり方とか、そのための努力では、われわれが幸福になるためのアプローチとして何かがずれているのでは?
だったらいっそのこと、何かをして解決しようとするのではなく、〝なんにもしない〟を、やってみてはいかがでしょうか? という提案が本書の目的です。
悩みを解決したり、自己実現したりするための鍵が、実は何かをすることではなくて、〝なんにもしない〟こと。
われわれは何かをつけ足しすぎたのです。いろいろな法則や方法論にしがみつき、それに飽きるとまた次の方法論を求める。
しかし、これからの時代はそのあたりを変化させる必要があります。今までのやり方では通用しないと、多くの人が気づいています。
情報化社会と資本主義によって、われわれが本来持っていた「人間」とか「生命」というものの外側にたくさんひっつけてきたものを、取り外す必要があります。それが日本人として、人間としての、幸福へとつながることになると思います。
だから、この本は何かをするための方法論ややり方を伝えるのではなく、〝なんにもしない〟ための本です。
もちろん〝なんにもしない〟ので、この書籍に書かれたアイデアを実践するにあたり、コストは1円もかかりませんし、何も難しいことはありません。何か新しい技術を身につける必要もありません。
しかし、その〝なんにもしない〟時間が、心に余裕と余白を持たせ、豊かな精神性を取り戻し、それが新たな行動へのインスピレーションにつながり、結果としてわれわれの生命力と幸福感、そして自己実現への呼水になります。
本書では身近な例や、僕が体験し、日常にその要素を取り入れたさまざまな〝なんにもしない〟を題材にしながら、そのすばらしさを、あなたにも感じていただければと思います。
目次
1 〝なんにもしない〟の可能性
2 〝なんにもしない〟待ち合わせ
3 タバコを吸う人
4 歯磨きとマルチタスク
5 ただ食べる
6 水に浮かぶ
7 風邪のときは何をする?
8 木になる
9 内臓の〝なんにもしない〟
10 脳もファスティング
11 ニュースと原始時代
12 テレビと想像力
13 電車広告に奪われる意識
14 皿洗いの〝なんにもしない〟
15 お風呂の〝なんにもしない〟
16 洗濯機は〝なんにもしない〟?
17 発酵こそが、〝なんにもしない〟の極み
18 〝なんにもしない〟で話を聞く
19 出力する前に
20 感情をただ見守る
21 空間の〝なんにもしない〟
22 心の空間
23 瞑想との出会い
24 瞑想をやってみる
25 ただ座る ただ歩く ただ立つ
26 秩序と無秩序
おわりに
1 〝なんにもしない〟の可能性
あなたは1日に〝なんにもしない〟時間をどれほど持っているでしょう? 僕自身がそうなのですが、昔はけっこうぼんやりと過ごす時間がたくさんあったような気がします。
小さいころとか、10代のころとか、とにかくぼんやりと妄想にふけったり、そこから派生した雑念のような思考に反応して、考えごとをしたり、アイデアが生まれたりするのを楽しんでいました。
しかし、大人になり、退屈な時間は日々の生活に追われるようになり、携帯電話を持つようになり、パソコンとインターネットを手にして、ぼんやりと夢想にふける時間はどんどんなくなっていました。
空いた時間は、「ストレス解消」という名のもとに、今度は日々の忙しさで溜まったストレスという目に見えない心の澱を発散させるための行動をするようになりました。
スマートフォンを手にして、SNSを使いこなすようになってからというもの、わずかな空き時間ですら〝なんにもしない〟時間はなくなり、SNSを眺めていました。
つまり1日中、僕は何かをしている状態だったのです。
妄想に心遊ばせる時間や、自分の思考や内的な感情に食い込んで考え込む時間がほとんどなくなっていたと気づいたのです。
少し話を変えますが、「子供は天才」なんて言葉を聞いたことがあるかもしれません。その理由は、おそらく子供が遊びの天才であるからでしょう。
彼らは自分を楽しませ、満足させるために、新しい遊びを発明します。われわれ大人も、かつてはそんな天才でした。
しかし、その遊びとは「必要性」があるから生まれたのです。まさしく「必要は発明の母」ということで、これは発明家のエジソンから松下幸之助、幼稚園児まで変わりはないでしょう。
子供って退屈が嫌いです。退屈な時間を我慢できないから、それを解消すべく、自分にできる材料と能力を駆使して、新しい遊びを発明します。
しかし、常に目の前に退屈を紛らわせてくれるおもちゃがあったらどうでしょう?
いつも気を引く、気軽なコンテンツがあったら、先ほど述べた〝必要の母〟はその子のなかで生まれるでしょうか?
子供の前にいつもテレビがあって、さらに指先ひとつでさまざまな動画コンテンツが見放題のYouTubeがある時代になりました。
せわしない大人どころか、子供たちですら、今は〝なんにもしない〟時間が失われつつあり、その退屈のなかで生まれる天才的な発明やアイデアは、昔に比べてぐっと減っているような気がするのは僕だけでしょうか?
もちろん忙しい子育てのなかで、タブレットやテレビを子守がわりにしてしまうこともあると思います。わが家も子供が小さいころは共働きで、アニメのDVDなどに少なからず頼っていました。
もちろんそれらの動画コンテンツを観ることでその子の知識が増え、可能性が広がるということもあると思います。
しかし、新しい発明やアイデアを生み出したいなら、思考を外側に向けるのではなく、ときにぼんやり全体的に、ときに深く内向的にならないと、それは起きないのでは?
天才の子供ですらそうなのに、凡才の大人たちが今日もあくせくと過ごすのでは、自分の幸福についてのアイデアや、悩みを解決する発想の転換などは、なかなか生まれないと思います。
まずは思い出してみようではありませんか。仕事や義務に追われず、そして便利なコンテンツを持っていなかった子供時代の、ぼんやりと過ごした時間。思考や感情を解放する時間を。
**********
Kindle unlimitedなら読み放題です。ぜひ、日常に「なんにもしない」を取り入れて、豊かな人生を送るヒントにしてください。
サポートという「応援」。共感したり、感動したり、気づきを得たりした気持ちを、ぜひ応援へ!このサポートで、ケンスケの新たな活動へと繋げてまいります。よろしくお願いします。
