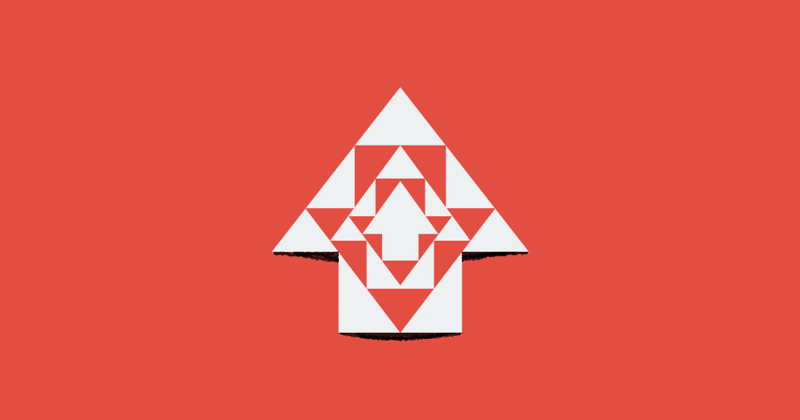
ベクトル量とスカラー量について
今月に入り2週間ぶりの理系記事。今後はもっと書きたい。そんなわけで、今回は「ベクトル量」と「スカラー量」について説明したい。
ベクトル自体は高校で習うはずだが、この分類をきちんと習うのは、大学に進学してからであろう。カテゴリー的には数学の話だが、実際は物理学で本領を発揮する用語である。
よく分かる一例 〜スイカ割り〜

この絵が例えとして分かりやすい。裏で画像検索していて、偶然見つけた。
よく言われるのが、大きさの情報だけ持つのが「スカラー量」であり、大きさと方向の情報を持つのが「ベクトル量」であるということ。
このスイカ割りの例で言うと、スイカまでの距離だけ言われても、どう進めば良いか分からない。右への距離なのか、左への距離なのか、方向が判断できないからである。これがスカラー量の考え方である。
一方で、スイカまでの方向と距離を言われれば、進み方も自ずと理解できる。これが大きさと方向のふたつを持つベクトル量の考え方である。
ベクトル量の例
物理学の話に置き換える。ベクトル量の代表例と言えるのが「力」である。ベクトル量なので、複数の方向(成分)に分けることができる。

前に紹介した「変位」・「速度」・「加速度」もベクトル量である(力と同じく方向単位に分解できる)。
スカラー量の例
スカラーの代表例を挙げるとすれば「仕事」になるだろう。中学校で出てくる「運動エネルギー」や「位置エネルギー」も仕事の一種である。

スカラー量は方向を持たないが、仕事(エネルギー)は大きさを比べることに意味がある物理量なので、スカラー量で問題ない。
上の図で説明すると、仕事は力(F)と変位(x)の掛け算である。
厳密に言うと、仕事はベクトル量である「力」と同じくベクトル量である「変位」の内積で求められる。この辺は大学の基礎教科で習う話である。
おわりに
今回は「ベクトル量」と「スカラー量」の違いについて解説してみた。
ちなみに、よくありがちなミスとして、スカラー量とベクトル量をきちんと判断せずに、定義上で成立しない演算してしまうことである。ベクトル量とスカラー量を足し算してしまうなどなど。
定義式を見る際には、ぜひこの辺も確認しながら理解してみると良いと思う。
-------------------------
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。ゆるりとほぼ毎日の更新で取り組んでいます。気まぐれ感はありますが、何卒よろしくお願いいたします。
-------------------------
⭐︎⭐︎⭐︎ 谷口シンのプロフィール ⭐︎⭐︎⭐︎
⭐︎⭐︎⭐︎ ブログのロードマップ ⭐︎⭐︎⭐︎
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
