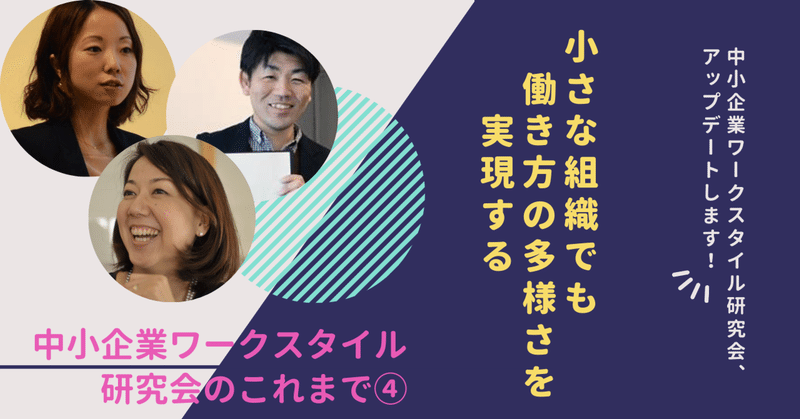
地域で働く働き方のこれから/中小企業ワークスタイル研究会のこれまで④
今から10年前の2014年5月30日。「地域で働く働き方のこれから」というテーマのもと、東京西側エリアで活躍している中小企業の3社をゲストをお招きし、地域で働くにおいてどのような意識があるか、どのような状況が取り巻いているのかを中心として、3社それぞれのプレゼンテーション、3社トークセッションを開催しました。
1.東京西側エリアで「働く」を創るスピーカー3名のご紹介
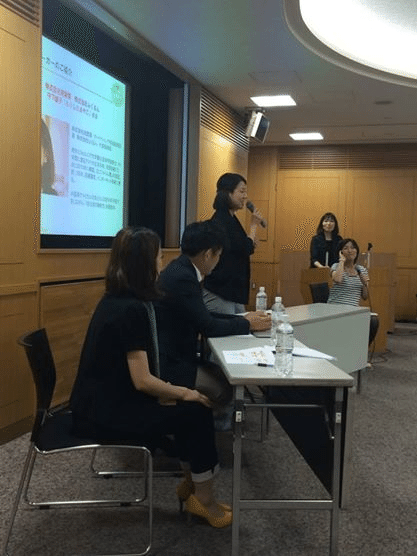
有限会社あきゅらいず美養品 人材環境研究所採用・育成担当 平野知実氏
(現:株式会社LIGUNA 当時東京都三鷹市に在していました。現在は東京都小平市に移転。また、平野氏は、現在株式会社musuhi 取締役CHRO)
「誰もが自分らしく生きていくことのできる日本をつくる」という夢を高校生から明確に持ち新卒で人材コンサル企業に就職。あきゅらいず美養品で人事を務め組織づくりに関わる。
株式会社たまらば(当時、東京都多摩市に在していました)
代表 浜田健史氏
2013年多摩大学総合研究所客員主任研究員に就任すると同時に株式会社たまらばを運営して地域の子育てしながら働く男性・女性達の「場作り」を実現する。
株式会社旭製菓 マーケティング担当取締役(東京都西東京市)
株式会社ふくるん 代表取締役
守下綾子氏
16年間に渡るアメリカ生活の後、家業を継ぐために2010年に帰国。主に「かりん糖」の製造、卸、OEM、店舗運営、インターネット事業に携る。中国系アメリカ人の夫と3人のこどもを育てながら「自分流の働き方」を模索中。
2.3社のプレゼンテーションの共通点
「地域で働くこと」という共通点をもち、独自のスタンスで「働くこと」に取り組んでいる企業の3者が集まりました。
3社に共通していると感じたのは、ワークライフバランスは企業と個人双方の課題であり、バランスの舵取りができてこそ仕事とライフに充実が生まれるということです。
①個人と企業のコミュニケーションが密接であること。
例として、社員をランダムに集め、交流会をはかり、そこでの秘密は参加メンバー内のみで守られるという独自の施策をとる企業がありました。自分の身体や心の変化もオープンに言える環境にあることが、会社の事業推進に繋がっていると考えているそうです。
②企業と個人、それぞれが考えるサポートとコミット
企業はそれぞれの社員のもつワークライフバランスのグラデーション(幅)を用意する必要性があるという話があがりました。一方で、企業・組織ばかりがサポートし続けるだけではなく、相互に理解と前進を繰り返していくために、個人は覚悟を持って選んだ道にコミットできるかが大切だという言葉もありました。
③「働く」「暮らす」の距離の近さ・ワークとライフのバランスを保つ
スピーカーのおひとりも元々仕事中心の生活を長らくおこなってきた当事者であったものの、「地域で働く」ということを自らが選択したことで、ワークとライフのバランスを保つ意識が一層高まっていると伝えていただきました。それによってご自身のパートナーとのコミュニケーションが深くなったというお話に対して会場からも深い頷きがありました。
朝早くに都心部へ移動し、長時間働き続け、夜帰宅してから暮らしが始まるという都心型のワークスタイルではなく、それぞれの「働く」と「暮らす」の距離が近くあること、だからこそどちらものバランスを考える機会があるという話がありました。
3.参加者それぞれの「地域で働く」想い
トークセッション後のワークショップは参加者全員で「地域で働くことへのメリット、デメリット」をテーマにワークショップを行いました。
メリットとして大きくあがったのは、衣食住のゆとりと地域コミュニティの情報獲得です。衣食住が隣接することは、女性だけでなく男性も、ワークライフバランスの充実につながると考えられます。
一方、メリットは認識しつつも地域を働く場所として選定できない一番の要因として、仕事の幅、量、収入面のダウンへの懸念があげられました。

しかし、その不安はそもそも地元企業を知らなかったり、現状の職業への固執から生まれているものもあることが参加者の発表より分かりました。終了後も参加者間で交流している様子が見られ、「地域で働くこと」への理解と課題が明確となった会となり、私達も多くのことを学ばせていただきました。
4. 2024年の今、ふりかえって
新型コロナウイルスの出現により「働き方」を変えざるを得なかった2020年以降。より一層「地域で働く」という言葉は真剣さを増したように感じています。東京から人口流出というニュースも流れていた数年でもありました。
“東京一極集中”に変化の兆し 人口移動のデータと移住の現場|地方潮流 | NHK政治マガジン
自分の「暮らし」「働く」をより身近に感じながらバランスをとっていきたいという想いの人が行動にうつした数年間でもあるように思います。
この当時でつかっていた「地域で働く」という言葉には、今後地域の社会課題と共にテクノロジーが組み入り、より一層「地域で働く」における多様さが生まれるようにも感じています。
この回の中小企業ワークスタイル研究会は、西武信用金庫様が地域の活動支援としておこなっている「第1回西武街づくりの活動助成金」を活用させていただきました。改めて、今回このような機会をいただいた西武信用金庫さま、ゲストスピーカーの皆様、ご参加いただいた皆様、有難うございました。
地域で働く。そのこれからを見つめる
個人の求める働き方が、組織を追い越した….。
そう感じるコロナ禍の働き方の変容があり、より一層働く場所・地域について考えた人も多いと思います。
小さな組織の働き方の多様さは東京以外のさまざまなエリアで、もっと模索を繰り返して、もっと先進的な、もっと工夫にあふれた、働き方の多様さを実現していると思います。
「小さな組織の働き方を学び合うコミュニティ」という場を通して、皆さんと共に、地域にあふれる小さな組織の多様な働き方を、その挑戦や模索や継続を学び合える場所を創っていきたいと思います。
小さな組織の働き方を学び合うコミュニティ CAMPFIREコミュニティ (camp-fire.jp)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
