
【シャニマス】『THE (CoMETIK) EPISODE』について【まとめ・感想】
本記事は「アイドルマスターシャイニーカラーズ」のイベントシナリオコミュ『THE (CoMETIK) EPISODE』についてのまとめ・感想記事です。ネタバレがあります。
記事概要
少し前のコミュになりますが、『THE (CoMETIK) EPISODE』がとても良いコミュでした。
まだ読んでいない人には興味を持ってもらえれば、もう読んだことがある人には、あらためて整理するきっかけにでもしてもらえればと思いまとめました。
コミュのまとめ
オープニング :「VIBES GROOVE」
CoMETIKのレッスンは順調である。彼女らが出演を予定しているライブイベントに、283プロダクションから追加でユニットが参加することが決まった。
ある日、コメティックはレッスンに取り組んでいるようです。
レッスンでは、斑鳩ルカが鈴木羽那と郁田はるきから手本を見せるようせがまれています。
そんな様子にトレーナーは「コメティックらしくなっている」と彼女らを評します。
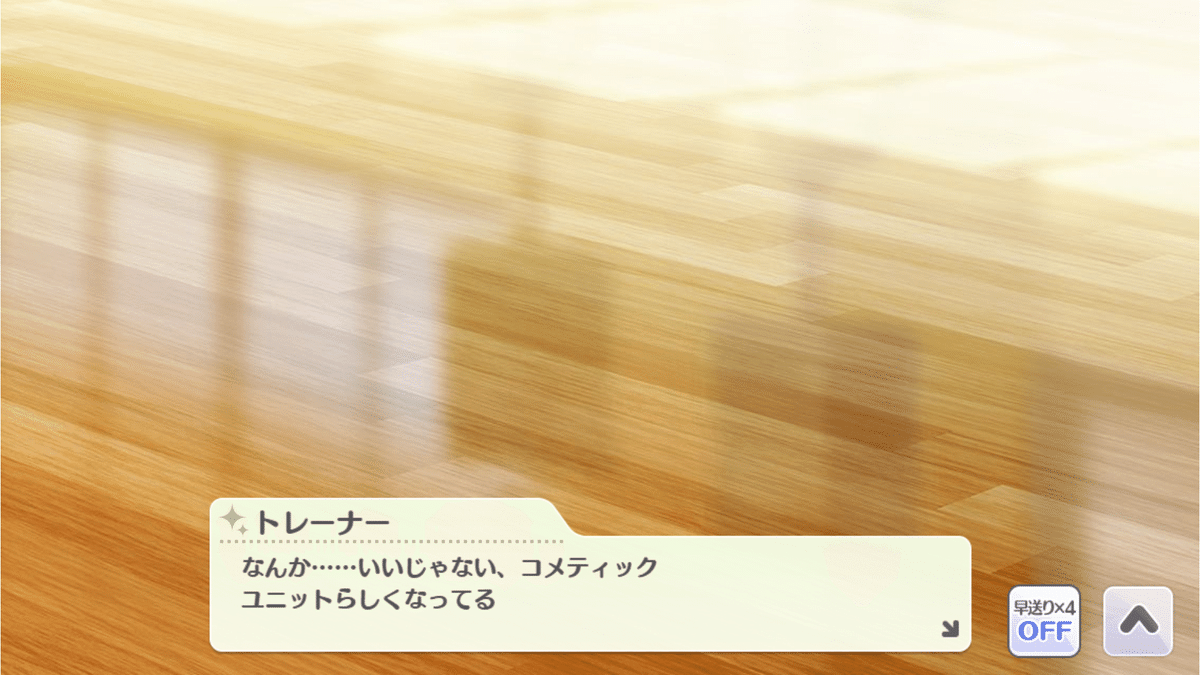
「らしさ」のことをトレーナーは「空気感」と言いもします。
曖昧なこの言葉について、鈴木羽那は「バイブス」といい、郁田はるきは「グルーヴ」と表しています。
単純に歌とダンスを練習しているだけでは生まれないらしい、この「空気感」というものの正確な定義は分からないようですが、慥かに、彼女らが「空気感」、「バイブス」、「グルーヴ」と、それぞれ示したもののイメージするところは分かる気がします。

事務所ではイベントのスタッフさんとプロデューサーが話していました。
CoMETIKの出演するイベントへの参加を辞退したグループがあり、彼はその代わりを探しているようです。

急遽舞い込んだ打診にプロデューサーは困ります。
先方もこの反応には予想がついていたようです。プロデューサーがいうには、本番だけならまだしも、出演するに当たってはそのためのレッスンなども必要らしい。
そんな会話の中、人数が増えるほど難しくなるだろうそうでしょうという相槌に、プロデューサーは思いつきました。

人数の少ない──二人組のユニットなら出られるかもしれない。

レッスンの風景を通してCoMETIKの「空気感」が醸成されてきたことが示される。この「空気感」というものは曖昧な言葉だが、彼女たちがいうところの「バイブス」、「グルーヴ」などのような雰囲気やニュアンスを示す言葉のように納得されている。
彼女たちがレッスンを受けているなか、彼女らが出演する予定のイベント主催者側とプロデューサーのやり取りが描かれる。
出演者を探す主催者との会話の中で、プロデューサーには心当たりがあった。
第1話 「2と1」
斑鳩ルカはレッスンを終えて事務所に戻るとプロデューサーの見ている番組に気が付く。鈴木羽那の冠番組が始まっていたらしい。初回放送では郁田はるきがゲストに招かれていた。放送後の二人は斑鳩ルカの出演も打診しようと話している。SHHisの緋田美琴はイベントへの出演を了承した。
夜までレッスンをしていたのであろう斑鳩ルカが事務所に戻ると、プロデューサーがテレビの画面を眺めていました。

画面に映っているのは鈴木羽那と郁田はるきが話している様子です。
鈴木羽那は「鈴木の部屋」という冠番組を始めることになったようです。
この番組はゲストを呼ぶ形式のトーク番組らしく、初回放送では郁田はるきが招かれています。

プロデューサーは、帰ってきたばかりの斑鳩ルカに、目の当たりにしたことの一つ一つを説明しようとします。

どうやらユニットメンバーが初めて持った、そして三人のうちの二人も出演するこの大切な番組について、斑鳩ルカはそれでも何一つ知らなかったふうに見えます。
仲間外れにされたように感じてつらい思いの一つもしそうなものですが、彼女はプロデューサーの説明を求めることもなければ、顔色を変えることすらありません。
説明を始めたプロデューサーには聞いていないと言っています。

二人のやりとりの間にも、番組は進行しています。
彼女らは「いつもの会話をしてるだけだ」と笑いあっていました。

プロデューサーの説明に興味がないことを伝えた斑鳩ルカに、彼はそれでも「鈴木の部屋」への出演を持ちかけます。
彼女には自分の出演する様子が想像もつかなかったようです。

番組の放送後に鈴木羽那と郁田はるきは通話で「鈴木の部屋」の話をしています。

番組の内容は彼女たちが言った通りの「いつもの会話」ではあったものの、テロップなどの編集で面白くなっていたそうです。
編集されているのであれば、配信というよりは収録されたものの放送なので、彼女たちの仕事自体はもう終わっていて、番組が放送された後で二人ともそれぞれの場所でそれを見てからしている会話らしい。

また、再生数が記録されているということで、「放送」というよりは「公開」というのがニュアンスにあっているのかもしれません。どうやらYouTubeのような公開と、いわゆるアーカイブが両立した形式の媒体が想像されます。

さて、上手くいった「鈴木の部屋」の初回放送でしたが、「これからも頑張って」という言葉を聞いて鈴木羽那は不安を口にします。
編集で面白くなった動画の内容や納得のいく再生数、たくさんのコメントといった成功は、もしかしたらいつもの楽しい会話、いつもいてくれている郁田はるきに依存したものであったのかもしれない……そうであればこれからの、郁田はるきの居ない「鈴木の部屋」は成功するか分かりません。
……どうすれば面白くなるのでしょうか。そもそもどうであれば成功なのでしょう。再生数が多ければそれで成功なのでしょうか。コメントの数もそうなのでしょうか。ほんなものはいわゆる炎上騒動でも増えるはずです。どうやって増やせば良いのかも分からなければ、どうすれば成功なのか、考えはじめると、とにかく何も分からない気がします。
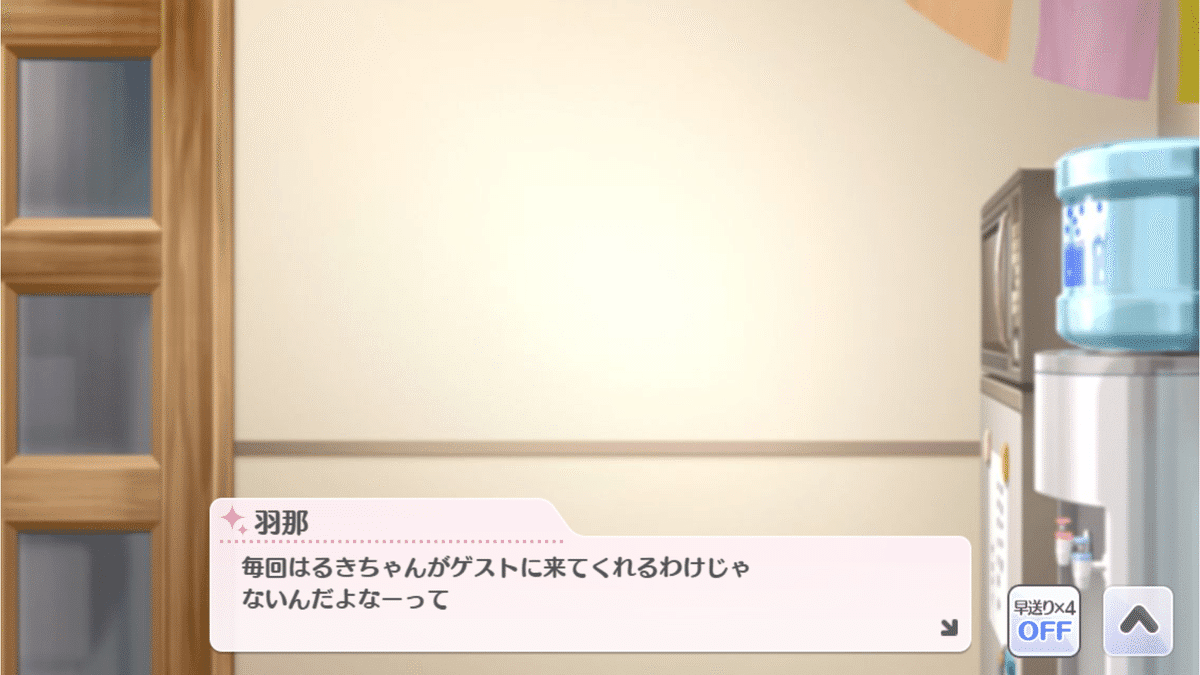
そこで郁田はるきは「鈴木羽那であれば大丈夫」であり、「鈴木羽那といろんな人のトーク」が見たいと伝えています。
「鈴木の部屋」初回の成功は、鈴木羽那がいたからだと強調するこの発言は、今の彼女に適切な励ましであるよう思われます。
電話越しに不安だといった鈴木羽那の言葉や、あるいは声色を聞いて、どんな思いをしているのかがよく分かっていたように感じます。

鈴木羽那は嬉しかったようです。
そして、郁田はるきが「いろんな人とのトークが見たい」と言ったことを受けて、斑鳩ルカをゲストとして呼んでみようか、という思い付きを口にします。

郁田はるきの「いろんな人とのトークが見たい」という発言は郁田はるき自身の謙譲を通して、初回放送の成功はゲストに依存しない鈴木羽那自身の魅力だったことを示したいものであるように思います。その目的は今後「鈴木の部屋」が上手くいくということに自信を持ってもらうことでしょう。
鈴木羽那の「ルカちゃんも、ゲストに呼んでみようかな」という鈴木羽那の「なんとなく」という雰囲気の発想は、郁田はるきの励ましに含まれた目的からは外れているようです。
ここでの郁田はるきの驚きは、鈴木羽那に自身の魅力に自信を持ってもらう目的がどこか曖昧な結果に終わりながらも、しかしながらその返答は望ましいものに思われたことの表れなのかもしれません。
斑鳩ルカが「鈴木の部屋」に出演することが、どのように望ましく思われたのかは分かりません。
鈴木羽那が初対面の相手と話すのを避けることで番組が成功しやすくなると思ったのか、そうすれば番組に慣れてくれると思ったのか、他にも何を思ったか……は分かりません。
とにかく彼女は「いいと思う」と期待を口にしています。

事務所ではプロデューサーも電話をしていました。
相手は緋田美琴です。

プロデューサーの受け答えの言葉しか示されてはいませんが、どうやら、彼女はかつて同じユニットに所属していた斑鳩ルカの出演するイベントに自らも参加することを了承したようです。
かつて同じユニットを組んでいた相手と、今とは異なるSHHisとしての参加を。プロデューサーはそういう心配をしたようで、しかしおそらくは共演の打診にも平然としていた緋田美琴の言葉や、声色を聞いて、「考えすぎだった」と判断したようです。
彼の想定したような、何かしらの出来事や関係はないようにも思われます。

そうしてプロデューサーは、緋田美琴がそうしてきたのであろう追い込みのレッスンを、いつも通りに戒めて──おそらくはこれも過剰な心配ですが──電話を終えています。

その後少し考えてから、プロデューサーは先方に連絡することにします。何を考えていたのかは分かりません。CoMETIKの出演するイベントにSHHisが出演する、それが決まったのです。予定に変更があるのはSHHisの彼女らであってCoMETIKではない。
アイドルとして活動している彼女たちは、いずれも仕事をしている一人の人間である。大人が仕事をしている、仕事を振られてそれを了承して仕事をする……必要十分な事柄以上に踏み込むのは、そんな一人前の大人であることができていないのではないかという疑いの表れであり、ともすれば無礼な振る舞いです。
それでも敢えて心配した何かは、ただの思い違いだったのだから、これ以上の追及は明確に必要以上のもので、失礼に当たるとも思います。
恬淡としてことに当たるのが普通であり、信頼であり、礼儀であり、仕事をすることらしい。
……もし仮に、斑鳩ルカにSHHisの出演を伝えたとして、その疑いが彼女に伝わらないことがあり得るでしょうか。もし仮に斑鳩ルカが嫌だと思ったとして、緋田美琴らのステージを奪うことができるのでしょうか。それができたとして、それで彼女の心は満ち足りるのでしょうか。……そうであるならば、主催者から代役を頼まれたとき、その場で提案を切り捨てるのが正しいと判断することはできたのでしょうか。そういう判断がSHHisの意に沿わない、先のない選択に見えたとしてそれは正しいのでしょうか。……思えば思うほどに、分からないことばかりです。
そうして、緋田美琴の了承を以って、プロデューサーは先方にSHHisの出演を伝えることとします。

斑鳩ルカの了承は待たなかったにしろ──心配、即ち全面的に信頼できないことが伝わらないように──、せめて直接話しておくべきだと思った理由も、最終的には明確な事柄の見つかることではないのかもしれません。
鈴木羽那と郁田はるきが「鈴木の部屋」のことを伝えられていなかったらしいことや、自分も斑鳩ルカも、それを知らなくても平静を装ったことや、そのときの斑鳩ルカの様子や、そんな雰囲気や、ニュアンスや、バイブスや、グルーブが、なんとなく彼にそう思わせたのかもしれません。

プロデューサーが視聴している様子を見て、初めて斑鳩ルカは「鈴木の部屋」の存在を知る。しかし斑鳩ルカは目立った反応を取らず傷付いているようにも見えなかった。
鈴木羽那と郁田はるきの通話では、成功における「空気感」などの存在が、混沌としているようにも見なされる複雑な構築の元にあり、その構成要件の喪失が与える影響が甚だしい可能性があること、また極めて複雑な構成要素を持つ未来の予見可能性は著しく低いこと、また成功を実現するに当たっての努力に不安を払拭することが必要であるらしいことなど、数多の印象が示される。
また、言葉それ自体がオブジェクトであることの有する機能的価値が示されている。
事務所での通話を通しては、会話する人間のみの描写で、確かに通話相手の表情や反応が予想できることを実証しつつ、社会活動における礼儀の要請がどのような態度や振る舞いを形作っているのかの示唆がある。
第2話 「212」
鈴木羽那と郁田はるきが楽屋で共演者にしつこく誘われた。彼女たちは対応に苦慮するが斑鳩ルカが通りかかったのを機に難を逃れる。その後、送迎の車内では、プロデューサーが次のライブイベントにSHHisが出演することになったことを伝えた。それを聞いた斑鳩ルカは苛立ち、車から降りる。偶然そこに緋田美琴が通りかかった。
ある日の楽屋で、郁田はるきが共演者の男たちから声をかけられました。
彼らは挨拶するなり、自分たちがサインをしたというCDを渡し、SNSでフォローをします。
語尾からうかがえるような性急な人間らしい。一方で、二人からフォローが返せるかには確認を取っています。

鈴木羽那は特に気にすることもなく嬉しそうな声をあげますが、郁田はるきは彼が確認したような事が気になるようです。

その返答には「はーい」と返事をしますが、もう一方の、自らのサイン入りCDを渡した方の男は、すぐさま「お酒だめなんだっけ?10代?」と畳みかけます。

慎重な郁田はるきも、少し押され気味に相槌を打つ形になりました。
これを待って、彼は「じゃあ飲みに誘ったら俺ら捕まるな」と相槌を打ち、二人は笑います。

ここで、「酒の場に誘うこと」や、話にのみであれ聞かれるその意味が思われてか、自分たちをよそに上がった笑い声でそれについて考える時間を与えられなかったことが思われてか、郁田はるきは困った顔をしていることしかできませんでした。
もっと深刻なことは、隣にいる鈴木羽那はこんなやり方について一切思うところのないような顔をしているところです。

そして、そのまま彼らは「ただの」と、今の郁田はるきが思うような一般的な警戒は誤解であると言外に強調しつつ食事に誘いに来ます。

……非常によく準備された、洗練されたやりとりです。
一方的に無下にできないCDを押し付け、軽率に返しにくいSNSのフォローを飛ばし、飲酒できない年齢を示すことで、相互関係および社会的地位における劣位を意識させています。罪悪感や劣等感といったものは感性を如実に下げます。
細部に関しても笑い声で印象を付与したり、指摘しにくい展開で言葉尻を誤魔化したり、強引に話を進められる人数編成を考えたり、積極的に声を掛ける役割と、もしかすると本当は善人なのかもしれないと思わせるための控えめな役割に分かれていたりします。
特に、未成年であれば相手を選ばないところが良くできている。彼らは常習犯であるに違いありません。
ここで、郁田はるきの反応はまさしく彼らのやり口の想定した通りのものでしょう。彼女は対応に苦慮しています。
誘いの言葉に対して彼女は慎重になりたがっていますが、隣の鈴木羽那が色よい反応をするのはほぼ間違いがなく、「これから共演する相手だから丁重に」という態度のみで無礼を咎められないままでいる彼女はこの場で断り切ることができないでしょう。
何かの口実をつけて後日の約束にできたとしても、一度受け入れたものを断るとお互いの名誉に傷が入るでしょうし、そうでなくても日常的にこんなことをしている彼らは、そのためだけに彼女達との仕事をしつこく持ちかける可能性すらあります。
さて、少し脱線しますが、考えてみましょう。
仕事相手であるとはいえ、一見不躾であるように見えようとも、郁田はるきは断ればよいのです。文言は何でもよく、立ち去るのであれば鈴木羽那も強引に連れて立ち去ればよい。強引であればあるほど強烈に拒絶の意思は示せます。ただ、その分だけ今日やそれ以降の仕事に支障をきたす可能性は大きくなります。
大多数の人にとってはそうではないが、ある種の人は、ここである種の決断が求められていることに気が付きます。
この決断とは、断るか、断らないかです。
この選択においては何かしらの合理性を確かめるにはあまりにも不確定要素が多く、どちらの選択にもリスクがある。生きること凡てがそうであるように、これもまた全人的な決断になります。
あなたはどう思いますか?
私は断るべきだと思います。
年端もいかない高校卒業後の未成年と高校生を遊びに誘う男がまともな人間であったというのは、私の経験上にないことであって、節操もなければ思いやりも常識も、何よりも、甲斐性もない者たちでした。
そもそも仕事の前に仕事相手にモーションをかける態度から先の暗さが透けている。男性アーティストである彼らのコンプライアンス意識の低さは自らの仕事であるアートに対する意識の低さだ。仕事での成長や成功もさして期待できない。
また、未成年に声をかけるようでは相手にしてくれそうな女の子と見れば誰彼構わずそうするのであろう、スタッフや他の共演者も出入りする楽屋での、彼らのような粗略な振る舞いは目に付きます。裏での評判もお察しだ。
彼らとの時間それ自体も退屈だろうし、関わることでスキャンダルのリスクもある。先に述べた通り彼らの仕事への態度を慮れば、スキャンダルが起きた後まで彼らが華々しく業界に残り続ける可能性も低く、価値のあるようなスキャンダルにはならないだろう。価値が低い。そういうわけで、彼らとの交流にかかるリソースは別の交流に充てたほうが良い。
以上のことから、断るべきだ。自分になびかなかった女に向けられた男の悪口ほど周りの目に惨めに映るものはないから、それに人間性への評価を醸成するであろう裏方も味方に付けられるだろうから、断る方法も、自らの振る舞いに必要以上の害意が露出しない範疇であれば雑で構わない。理想をいえば、人目の多い場所にさえ行けば問題なく逃げ切れるだろう。
……というのが、画面の前で他人事として好きに考えた結論です。
実際に私が当事者だったら、きっと時間も余裕も客観性もありませんから、もっと普通で単純な判断をします。
それは即ち、相手があまりにも無礼であるため取り合わない、という判断です。上記の将来性については、礼儀を弁えている時点で一定程度評価されますからそれで構いません。
礼儀はそういったリスク回避のためにも機能しています。またその不文律を理解するだけの感性を保っているのであれば一定程度に評価できます。
……郁田はるきは、すぐさま何かをすることをしませんでした。決断を迫られたことに気が付いたか否かは別として、とにかく彼女は断らなかった。
この時点ではそれが良い判断なのかは分かりませんが、少なくとも後手に回る対応ではあります。
あまりにもヒントが少ないとき、あるいはあまりにもそれらしいものが多いとき、何かを決断するのは困難です。だから、少なくとも今は問題がないということで現状に甘えてしまうことや、もっと悪ければ、自らの思いや考えそれ自体への疑いを抱いてしまうことがあります。
こうなったら相手としてはどのようにも利用できる、実に都合の良いただの対象です。
無礼者には相応の態度を取ればよいというのではなく、相応の態度を取るべきなのです。
高校生にしては聡いように見える郁田はるきですが、年相応に社交経験の乏しい、良くない対応を取ってしまったように思います。
さて、そんな局面でしたが、折よく斑鳩ルカが来てくれて助かりました。
件の男は、これまでの洗練された態度が嘘であったかのように口ごもります。
斑鳩ルカは、彼らが想定していたような真面目そうな子と、無邪気で素直な子の二人組というものから逸脱しており、初めからやりとりに参加しているわけでもなく、成人でもあります。

どうやら彼は機転の利く人間ではないようです。
先ほどの洗練された振る舞いこそ、そのまま他の場所に出せるような出来栄えですが、あくまでも数を撃って当たったものを選んだだけのものに過ぎないようです。
素の彼ら自身はあまり先行きが芳しくないように思われます。

少し間が開いて、気まずそうな顔をした男たちに斑鳩ルカが会話を促す言葉をかけます。
それが想定されるべき会話だったのであれば、自らの来訪に気を取られた相手にかけるにはごく自然な言葉です。それ故にそうでない場合にはその会話が想定されるべき、つまり望まれるものではなかったことを強調するものとして機能しています。
彼らは愛想笑いをしてその場を後にしました。

郁田はるきは「どういう風に接すればいいかわからなくって」と述べており、やはり距離を離す選択が思い浮かばなかったようです。

さて、斑鳩ルカは、郁田はるきが「助かった」と述べたことについて、「そういうつもり」ではなかったと応じています。
これは社交辞令としての謙遜なのでしょうか。それとも、気まずそうに見えた男たちの顔つきや、困った顔をした郁田はるきと無邪気に笑っている鈴木羽那を見渡して本当に何も思わなかったということなのでしょうか。彼女が会話を続けるように言ったのは本心からのことだったのかもしれません。
ともかく目を閉じて黙った彼女の表情からは窺い知ることができない。

しかし、郁田はるきはそれでも感謝を伝えています。
……今回の斑鳩ルカの行為が絶対的に肯定されるべき、善い行いであったのかは不明です。
もしかすると、この男たちは今後大成し、一世を風靡する大芸術家になり、その名声が彼女を押し上げるような可能性もあり得ます。未来時点の確かな予知はできません。
もしそんな未来があれば、誘いを断ったことに後悔を覚えるかもしれません。その過程で斑鳩ルカの出現を恨めしく思う可能性すらあります。
……さて、このような予想が立ってようやく私たちに礼儀の効用が果たされます。この場において、彼らの未来がどうあれ、自身の混乱した思考の本質がどうあれ、斑鳩ルカの本心がどうあれ、この場において受益があったのは確かです。
今後、斑鳩ルカや郁田はるきがこれを後悔するときが来たとして、ここでそれが喜ばしいことであったことを認める約束がここに、感謝の形式をもってなされています。

鈴木羽那は、このやりとりの渦中にいながら、その苦悩をもたらした何某かからは蚊帳の外というほどに無関係でした。
郁田はるきの苦慮した原因を探せば、鈴木羽那の脇の甘さが目立つようにも思われます。今をもってなお彼女は何が起きていたのか分かっていないように見えます。
けれど、彼女は郁田はるきが斑鳩ルカに感謝を伝えるのを見てただ微笑むだけのことを通して、何かの役割を果たしているようでもあります。

この現場での仕事が終わって、送迎にやってきたプロデューサーが今回の仕事が「どうだったか」を聞いています。

鈴木羽那は問題なく「よかった」としており、郁田はるきもパフォーマンスがよくできたと答えています。
しかし郁田はるきはトークについて今一つであったと答えています。先ほどの楽屋のやりとりの様子が思われます。

続いて、「みなさんに楽しんでもらえるようなお話」をしたいと、彼女自身がトークについて目指すところについて話しています。

鈴木羽那はよいトークができていたのにと驚いています。
斑鳩ルカに同意を求めるものの、彼女からは返答がありません。彼女がどう思っているのか、それとも何も思っていないのかは分かりません。

斑鳩ルカは何かしらの評価を口にしませんでしたが、代わりに、反省をした郁田はるきにプロデューサーが問題なさそうだと言っています。
これに対する褒めてばかりだと伸びないかもしれないという返答には、先の楽屋での失敗や危機感が含まれているようにも思われつつも、晴れやかな表情を踏まえると前向きな反省を終えたように感じられます。

これに鈴木羽那が笑い、斑鳩ルカが息をつき、一つの会話が終わりました。
ここで、プロデューサーは今度のイベントにシーズも出演することになったという報告を切り出します。
不要で、今思いついたはずのないのに口にされた「そうだ」という言葉には、やはりニュアンスがあります。例えば、これが偶然であるということです。偶然であるならば、この話が非常に重大であるというわけではないのです。
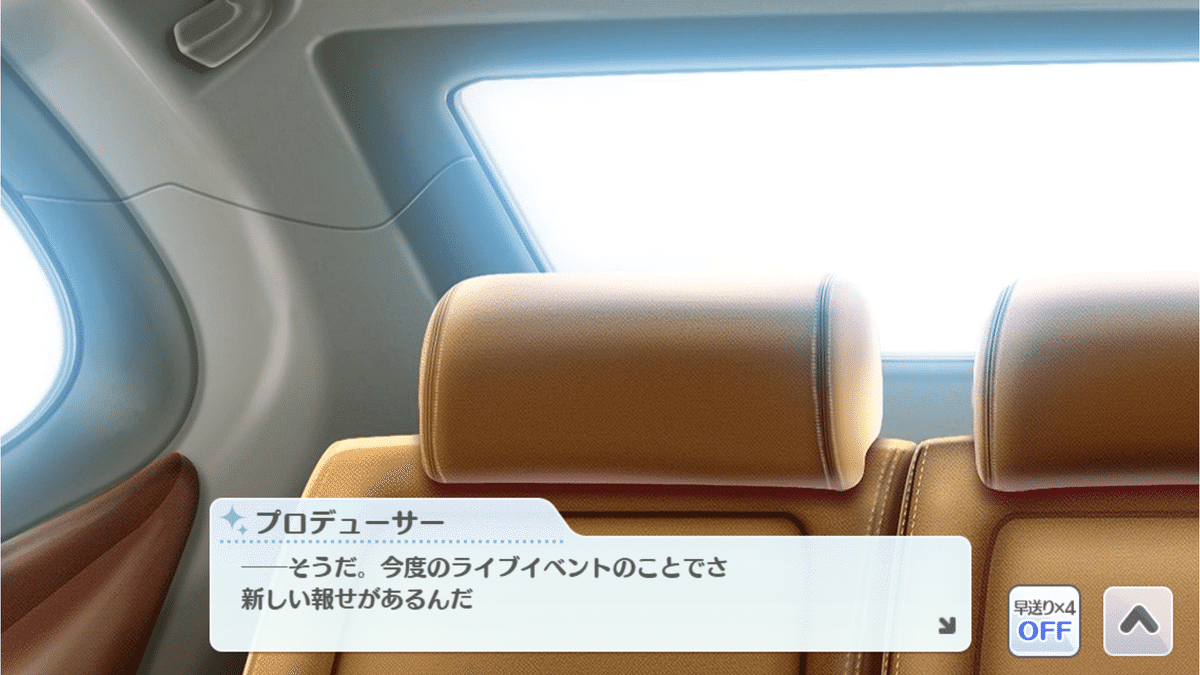
続いて彼はそうなった経緯についての前置きをします。必ずしもそれは定められたことではなく、必ずしもそうでなくてはならないわけでもなく、単に、そうただ単にそうなったというだけであることを示すための前置きです。
しかし、結果として次のライブイベントにSHHisも参加することになったという報告は、SHHisという言葉がいやに強調される倒置法で示されることになりました。
目的やアプローチは良いにしろ、「SHHis」というのが強調され、既にそれが彼女たちの中である程度重みのあることが共有されていたために、これまでの平然とした態度を強いた過程が逆説的に重大さを示してしまう……不器用で洗練されない振る舞いになりました。
これでは報告にその場所を選んだ目的、つまり斑鳩ルカの個人的な事情を鑑みて必要とされた個別の相談ではなく、職務上の必要十分な範囲での立ち入らない報告であるという形式を取った礼儀すら果たされません。

郁田はるきは当然ながらSHHisと斑鳩ルカの関係に思うところがあるようで固くなってしまいました。もしかするとプロデューサーの言葉遣いと深刻そうな態度が余計にそうさせたのかもしれません。
一方の鈴木羽那が至極純粋に強調されてしまったSHHisのことだけに注目しています。ここには挽回の余地がありそうに見えます。

これに便乗して、郁田はるきは、プロデューサーがこのような切り口を選ぶだけの気負う話題であるらしい「緋田美琴と斑鳩ルカの共演」を、「素晴らしいパフォーマンスをするユニットに対抗しなければいけない私たち」というニュアンスに塗り替えることを試みます。

場に静けさが戻ったところに、プロデューサーはもう一歩踏み込みます。
彼も郁田はるきに引き続き、「緋田美琴と斑鳩ルカ」ではなく、「シーズ」と比べられる私たちというイメージを強調しにかかっています。
また、あくまでも例としてですが、彼は「コラボ」といった企画について話しています。どうやら積極的に共演を望むよう期待を誘おうと考えているらしく思われます。

しかし斑鳩ルカはこれを激しく拒絶しました。

降りた先のどことも知れない場所で、斑鳩ルカは先ほどの言葉を思い返し苛立っています。
何も言わずに目を閉じているときの彼女も、やはり何か思うところがあったようです。

そんなところに、緋田美琴が通りかかりました。
プロデューサーがそう演出しようとしたのとは違う、自然そのものの顔立ちで。

ある番組に出演した彼女たちと共演者との楽屋での会話、そしてそれに対する困惑を通して、生きるという活動の難しさが示される。特に、何かを思うことについて制限し誘導する諸条件が存在すること、また洗練された振る舞いに関する示唆がある。また感謝という儀礼の行為が示されている。
送迎の車内では、プロデューサーがそれとなくSHHisのイベント出演を切り出すが失敗に終わっている。ここでは先の楽屋で示された、ある事象に対するその場における「空気感」、「バイブス」あるいは……を変更する試みを中心に、洗練されているかどうかの差異が示されている。
また、「空気感」……を変更することや、そういった仕草に気付くことなどを実現している理性の効用も示された。
第3話 「たがい」
斑鳩ルカは通りかかった緋田美琴と少しばかりの会話をした。緋田美琴はSHHisとしてライブイベントに出演することを気にしていないようだ。斑鳩ルカは彼女が手にしたレモンティーにさえ注意が向いてしまう。緋田美琴がその場を立ち去る。斑鳩ルカは孤独を感じた。
前話にて車を降りたところに緋田美琴が通りかかりました。急な出来事に斑鳩ルカは言葉に窮しています。

緋田美琴はライブイベントへの出演に際した挨拶を切り出しました。

自然な挨拶です。「よろしくね」という挨拶だけで伝わらなかった様子を受けて、自然に補われた「ライブイベント」という発言のニュアンス、そしてSHHisとしての出演になることを告げるまでに、一切の気負いを感じません。
言葉は倒置表現の体を取りましたが、前話のプロデューサーとは異なり伝えたい内容以上に言葉が強調されず、全体として過不足のない挨拶の範疇にあります。

緋田美琴による告知は彼女にとって理想的でしたが、それでも斑鳩ルカは「シーズ」という言葉が気に掛ったようです。

再び同じイベントのステージに立てることへの素朴なよろこびを伝えるための「同じステージ」という言葉にも異なる見解を抱いたようです。

続けて、イベントへの出演という文脈から合流した思考のもと、緋田美琴は自分がどういった状況にあるかを説明することになります。

ここでは今からどのような行動に出るのかを、つまり、今ここにいる斑鳩ルカと別れるに至る必然的な事情を伝えています。
またこのコミュニケーションでは礼儀の要請によって相手に内容を伝えるだけでなく、会話を通して自身の予定、即ち未来時点の自分のあるべき姿を確認しています。

こうしてあらためて予定を確認する過程で、緋田美琴は過去時点でのプロデューサーの発言を思い出し、さらに斑鳩ルカが目の前にいるという現在の状況を踏まえて、妥当性の高い推論を導いています。

一方で、斑鳩ルカは引き続き、一つの言葉に心を奪われていました。

そうしているうちに、斑鳩ルカは緋田美琴の手にあるレモンティーに気が付きました。彼女は見たものの名称をそのまま呟きました。

緋田美琴は相槌を打ちつつ、それがどういったものであるかを説明します。その上で斑鳩ルカに飲んだことがあるかと問いました。
通常、何の変哲もない市販の飲料に相手が関心を寄せたとき、概ねそれは相手もそれを飲んだことがあるという偶然の一致を喜ぶものだということが多いでしょう。
類推するにはやや限定的な規則ではありますが、記憶の参照が良好に行われる状態の私たちにとって、無意識にこのような予想を実現するのは難しいことではありません。

このときも斑鳩ルカは彼女とユニットを組んでいた頃の緋田美琴を思い返し、記憶に一致しない彼女の振る舞いに当惑しているばかりです。
彼女の返答は「さぁ」と曖昧で、意味をなしていません。

目も合わず、想像していたような反応もなく、斑鳩ルカは明らかに様子がおかしいのですが、緋田美琴は少し考えてから立ち去ることを選んでいます。
予定のために事務所に向かう、決められた時間に事務所で自分がプロデュサーと打ち合わせを行う、というあるべき姿に相応しい自分であるための行動です。
彼女は会話の成立しないことを咎めたりしていません。別れ際に掛けられた声は、礼儀の要請に応えつつもどこか優しく聞かれます。

「また今度」という別れの決まり文句にもまた、その形式のなかに再会の約束が含まれています。

緋田美琴が立ち去った後も、斑鳩ルカはその場に立ち尽くしていました。
「同じステージ」という言葉に彼女と同じ思いを抱いていない。
孤独というのはどこまでの分かちがたいもので、どこまでも個人のもので、孤独であるということは、いつでも、誰にとっても、堪え難いことであるように思います。

斑鳩ルカは、もはや輝かしい過去の再帰があり得ないことから目を背けていたことを認めます。しかし、まだそれでも、それを言葉にできないでいます。

一つ、彼女は何も思い返さないという不可能な試みから解き放たれ、あるいはそれを妨げていたのはその試み自体であったのかもしれません。
そのまま先ほどの緋田美琴がそうしたような類推を始めます。

しかしながら彼女の見つめる世界に映るものは何もない。
風が木々の葉を吹き散らし、車両は行き過ぎ、歩く人々は遠く、緋田美琴はそこにいない。いたてしても、かつての彼女は、そにあった輝かしい日々は、もはや戻らない。
風が吹いて、独りきり……足が止まった。
……過去ほど美しいものはなく、先刻の別れの挨拶に含まれた別れの言葉は彼女の心に何らかの意味を結ぶことができなかったようです。
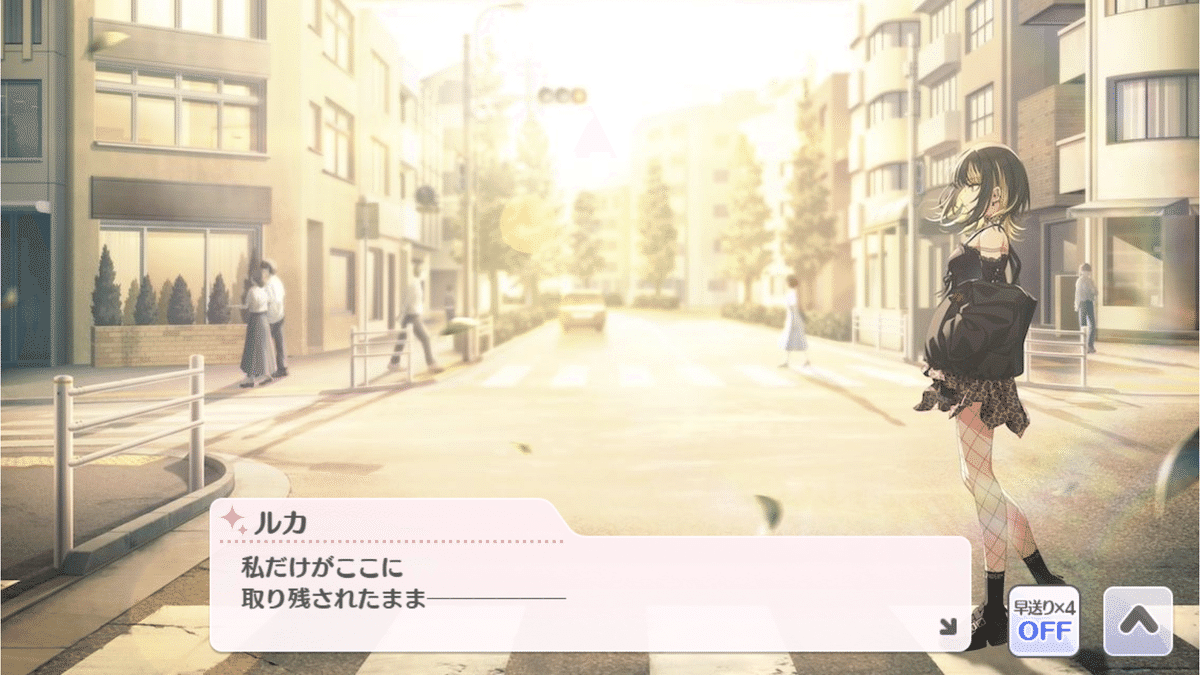
ここでは、健全な理知のはたらきの保たれている緋田美琴を通して、理知の機能と、それが会話という社会活動のなかでのその効用が発揮される様子、ならびにそれを扶ける礼儀や信頼を描いている。
斑鳩ルカは状態が悪く、目の前に起こる出来事や事物を総合することや文脈を掴んでおくだけの感性が十分に機能しておらず会話が成立しない。一方で、個々の単語や物品などへの、単純な知性は強烈に働いており彼女を苛んでいる。
緋田美琴が口にしたそれぞれのユニット名や持ち物から、過ぎ去った日々がもはや戻らないものであることを受け容れることで、最低限の活力を取り戻したものの、それでも孤独を自覚することのほかには役に立つことがなかった。
第4話 「下手くそな人人人人」
斑鳩ルカがレッスンを休んだことで、プロデューサーは自らの行為を後悔する。そこに郁田はるきから電話がある。彼女もまた斑鳩ルカを思っているらしい。斑鳩ルカが休んだCoMETIKのレッスンは上手くいかなかった。鈴木羽那の提案で斑鳩ルカに上手くいかなかったレッスンの様子を収めた動画を送信した。斑鳩ルカは「下手くそ」と呟いた。
前話のやり取りから日を改めて、斑鳩ルカは動くことができませんでした。
斑鳩ルカはただ「休む」とだけメッセージを送っています。

鈴木羽那、郁田はるきの両名がこれに反応しています。

プロデューサーはメッセージを受けて、事務的な内容で返信します。
郁田はるきが立ち入らないメッセージを送っている一方で、プロデューサーは欠席の原因として体調不良を積極的に支持する一言を添えてもいます。

その一方で、彼は先日の自身の発言とその後の斑鳩ルカの反応を思い返し、今日斑鳩ルカが欠席に至ったのは自らの行為の結果であると思ったようです。
しかしながら、前話を見たところ、斑鳩ルカが欠席するに至ったより直接的な要因は彼との諍いではなさそうです。彼女はそれから、偶然出会った緋田美琴との会話のなかで輝かしい日々を取り戻すことはできないということを改めて思い知り、そして、心を深く閉ざしたように思われます。

確かにプロデューサーが知るところに限れば、斑鳩ルカがその日に緋田美琴と出会ったことなどは知らなくても不思議ではありません。また、イベントの出演に関しても緋田美琴が気にも留めないのであれば斑鳩ルカに気を遣うのは必要以上のことです。そうであればこそ、やや危険性を認識しつつも礼儀の要請に応えることを優先する判断に至ったのでしょう。
そういうわけで、結果として、彼は自らの行為が不適切で失敗に終わったことを悔やみます。
そうしていると、郁田はるきから電話がかかってきました。

彼女はメッセージで済ませずに電話をかけてきています。
そのようにするときには様々な目的が考えられます。
例えばすぐに返答がほしいときなどがあります。他には声が聞きたいからというのもありますし、交換したい情報が多数あるときなども話した方が早くに済むでしょう。メッセージでのやりとりは取り繕う余裕があるから、直接話した方が実際の人となりが分かると女の子がいうのを聞いたこともあります。
メッセージと比較したとき、電話は否応なく相手に時間と手を取らせ、緊張を強いる手段であると言えます。彼女はそんな電話をかけてきました。
急な電話をかけるときのある種の一般的な挨拶として、謝罪し、郁田はるきは今の都合について確認しています。

プロデューサーもまたこの件については特に動じる素振りを見せません。「何かあったか」という返答は先ほどのメッセージを思えばやや察しの悪い言葉であるように思われます。

彼女はこれを受けて言葉に詰まりつつ、斑鳩ルカについての電話であることを伝えます。

彼女は自分に何かできることはないか考えていたこと、そして結果として明確な答えが見つからなかったことを伝えています。

この一連のやりとりは解釈の余地があるところだと思います。
私個人の経験としては、様々な形式で危機意識を抱いたことのある、つまり自意識の強い女の子が、庇護対象とみなした女の子を慮ることに正当性を見出している場合、そういった女の子たちは、庇護対象であるはずの女の子に対して、私が恬淡な態度の形式で礼儀を守った接遇を実践すると──積極的な慰め等の行為を明示的に行わないと──概ね苛立ちとともに疑いの目を向けてきたように思います。
そういうわけで、郁田はるきもまたそのように、プロデューサーの「体調不良かな」というメッセージの文字面に疑いを抱いたのではないかと思います。「まさか本当に体調不良だと思っているのではないか?」と。
明確にその疑いが意識の俎上に上がったのだとは思われませんが、それでも「昨日からずっと何かできることはないかと考えている」ほどに真剣な自分と比較して、気にも留めていないように思われるようなプロデューサーの文面に反感を抱くというのは、むしろ自然なことであるように感じます。
さて、そういった疑いを抱いたためにかけられた電話に対して、プロデューサーの応対は「(郁田はるきに)何かあったのか」と問うものでした。これはあくまでも型通りです。
彼のモノローグから思うに、彼は察しが悪くて、電話が斑鳩ルカについてののものであることが分かっていなかったように思われます。そのため、この応対もまた要件が不明である電話であったために行われた型通りの対応におさまるものだったのでしょう。
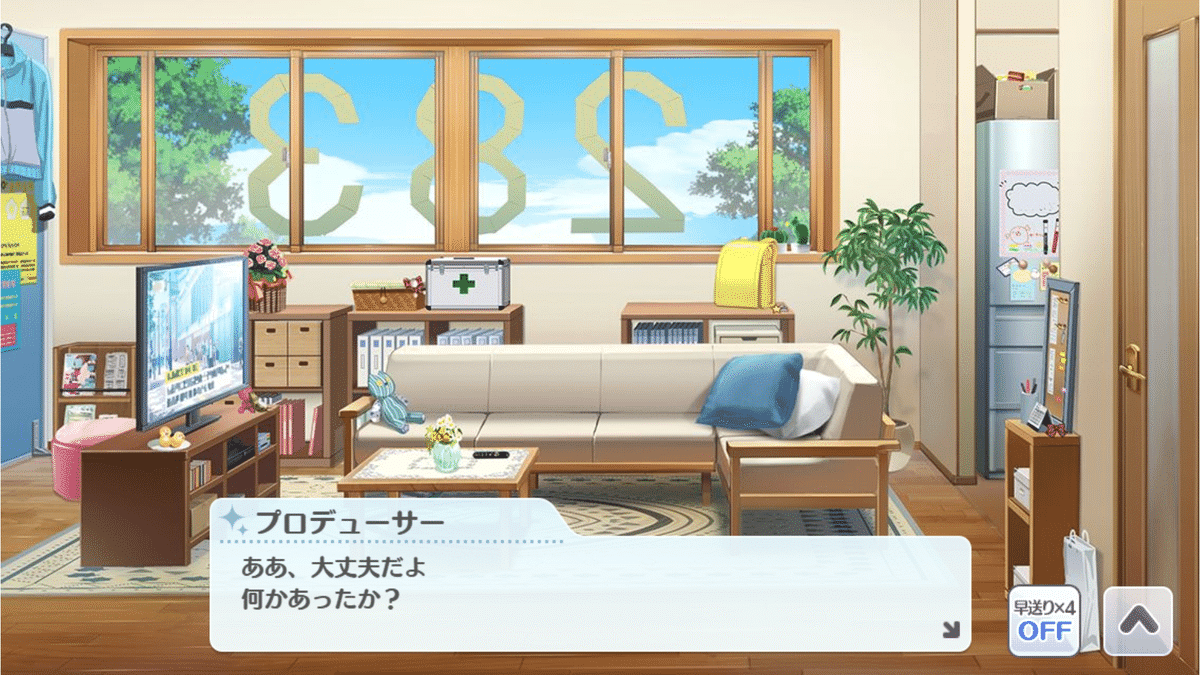
いつも通りのプロデューサーの振る舞いを受けて、郁田はるきは言葉に詰まります。
プロデューサーの応対は、郁田はるきに電話をかけさせるに至ったのと同じ、平気な態度の、形式的な振る舞いに違いありませんが、その言葉には確かに、彼女がその存在を疑ったのであろう真率に他者を慮るニュアンスが含まれています。
また、彼の変わらない振る舞いと、彼女自身の礼を失した大胆な行為が無意識に比較されたのかもしれません。
ここでの彼は信用に値するのかを問われようとしていましたが、これまで積み重ねてきた経験が知らず知らずのうちに、彼とアイドルとの信頼関係を守ったように思います。

要件を聞かれたことをきっかけに、彼女はここで自分が電話をかけた理由を考えはじめ、その過程で自身の思いを振り返っています。
自分にできることはないか昨日考え始めたことを思い浮かべ、斑鳩ルカにしてやれることが思いつかなかったのだといいます。ここで彼女は斑鳩ルカのあるべき姿を想定することができていません。私たちの行為における動機は一般に、あるべき姿の想定と、その理想からの逸脱を認識するところから始まります。
彼女が昨日からの数時間考えども思いつかなかったのは確かに自分のなすべきことですが、同時に、それは彼女にとっての斑鳩ルカの理想の姿でもあるのかもしれません。
もしかすると平素の彼女は斑鳩ルカに他の何らかの理想を重ねることなどなかったのかもしれません。そのままの彼女がそのままに理想だったのでしょうか。

彼女はここで自分の行動指針を定めることができませんでしたが、形式通りのやりとりを経て、電話をかけた自己の振る舞いに非があったことを認められる程度には落ち着くことができたようです。
またその上で、彼女が衝動に任せた行為における目標であった「プロデューサーの考えを聞く」という行動に結論しています。
当初の動機であった疑念によっても最終的にはプロデューサーの考えを聞くことにはなったのでしょうが、この会話で交わされた形式的な定型句、それにより生まれた客観性、そしてそれによる自己分析の試みによる動機の変化を経て、今の彼女には冷静で公平な態度があるようです。
その状態なら誰かの話を聞く価値が、そして誰かが彼女に話す価値がありそうです。

この言葉を受けてプロデューサーはまず初めに感謝を述べます。
──礼儀とは、それが及ぼす結果が本当のところで不明である行為、あるいは行動というものに対して、それがどういったものであったのかを確認する儀式です。それらは時に衝動的であり、予定調和には収まらず無軌道な変化を遂げることもあります。動機や理想の如何によらず、利益を得ることもあれば、不利益に繋がることもあります。関連する様々な心の動態があり、行為は、ほとんどの場合においてその主体に犠牲を強いるものです。
それ故に、感謝においては行為による利益を、謝罪においては行為による不利益を確認します。
この儀式は礼節という言葉が示す通り、その確認を終えたのであれば、その挨拶を以って節目とし、その行為については以後執着しない約束でもあります。
さて、プロデューサーは郁田はるきが斑鳩ルカについて心配して考えてくれたことにといって感謝を伝えます。また同時に電話をかけたことについてもその勇気が必要であったとして、感謝と配慮を示している。
彼が彼女の振る舞いからどれだけのことを洞察したのかは分かりません。私が彼女たちのやりとりを解釈せざるを得ないように、相手がどのような動機をもって行動したのかを完全に覚知することもまた、できるわけではありません。
感謝は、そういった不可知を背景にして、それでも確認できる感性の上での評価を行うところに美点があると言えるでしょう。
これらの挨拶はあくまでも両者が客観性をもって行える方法で、多くは言葉による表明として実行されています。

また、「電話をかけるのに勇気が必要だったよな」という配慮の言葉は非常に評価できる振る舞いです。
実際に彼女が電話をかけるという行為に踏み切るまでに勇気が要求されたのかは不明です。私であれば彼女の言動からそれが衝動的な振る舞いであり、勇気を感じるだけの畏れを抱くことができなかっただろうと予想するのですが、プロデューサーがどう思っていたのかは分かりません。
しかし少なくとも、社会活動を行うのに十分な人間は、相手の時間や手を取らせることへの畏れを持っています。だからこそ私たちは相手と関わるに当たっては恥ずかしくないだけの準備をします。例えば電話をかけるのであれば最低限要件だけは明らかにしているはずです。
そうであればこそ、アイドルという仕事に携わる郁田はるきにも、当然ながらそういった畏れが、そして行為に及んだのであればその畏れを乗り越えるだけの勇気が、存在するに違いないものであるはずです。
このときの彼女がそうであることができたとは私は思いませんし、プロデューサーにも本当のところでは分からなかったところなのだと思います。
それでも、彼は次の彼女がそんな誰かであるために、その扶けになるものであるのは、きっと彼女の行為は衝動による放埓なものではなく勇気を伴ったものであったのだと言っています。
何よりそこには、例えそれが間違っていたとしても、郁田はるきがその理想の存在であったことを信じるという態度が言外に示されていました。

そういった儀礼を経て、プロデューサーは彼女の問いに向き合いました。
彼は少し考えると、斑鳩ルカのことを信じるということを期待すると伝えています。そしてそれを期待する相手は郁田はるきだけでなく鈴木羽那でもあるといいます。
郁田はるきはおそらく具体的な行為を求めて質問しているため、抽象的な言葉に戸惑いますが、彼は特定の行為ではなく、そのままの自然な振る舞いを求めます。

彼女はどこか納得しかねる様子だったためか、プロデューサーは彼から見た彼女たちがどのような人かを伝えています。これもまた漠然とした、抽象的なイメージです。
そして、そういうイメージが斑鳩ルカを「いい方向に連れて行ってくれる」と思うのだと話しています。
郁田はるきに「斑鳩ルカにできること」が思いつかなかったのは、斑鳩ルカのあるべき姿が彼女には思い浮かばなかったからでもあるのだと思います。そういう意味で、彼女が斑鳩ルカにできることを探すのであれば、具体的な姿を想定し、それを実現するための目標を段階的に設定することが効果的でしょう。
そのように指示しないのは、目指すところがそうではないからかもしれません。
漠然として、目標も基準もなく、ただ自分の自然な振る舞いをする。具体的な命令など何もない、あるとすれば、それは自ら描く理想の姿であるのかもしれない。
……そうあることを彼は望むようです。

そして彼は求められた思考を、気持ちに変更して表明しています。
郁田はるきの要求は叶わなかったものの、電話をかけるに至った当初の疑いにはほぼ完全に応えることができているようです。

彼女もまたプロデューサーへの信頼を確認することができたようです。また、一つ悩みが解消して、気持ちを新たに活力を得ることもできました。
二人は最後にお互い挨拶をしてこのやり取りを終えました。

二人にそのままの自分でいてくれることを期待する一方で、プロデューサーは自らができることについて考えていました。

レッスンを終えて鈴木羽那と郁田はるきが話しています。
二人で言葉を継いでいけるくらいに彼女たちは仲が良いのですが、レッスンはそのように上手くいくわけではないようです。

理由を考えても分からないようです。二人は斑鳩ルカの不在に理由を求めますが正確なところは分かりません。
そんななか鈴木羽那は、斑鳩ルカにレッスンで撮影した動画を送ることを提案します。

郁田はるきはこれに驚き、体調不良ないしそれよりも状態の悪い相手に負担を強いるようなことをするのは如何なものかという考えを述べます。

鈴木羽那はこれに対して体調の良いときに見てくれたらよく、見てくれなくても構わないというように返答しています。

この返答を受けて郁田はるきは動画を送ることに賛成します。
ここで、郁田はるきには自らの行為に当たっての畏れが存在しています。動画を送信する行為を通して、斑鳩ルカには何らかの時間や体力を使わせることになりそうです。それでも、それに見合った効果や価値があるのかを考えることができています。
また、鈴木羽那は電話をかけた際の郁田はるきがそうであったように畏れを感じるところはなく、衝動的にレッスン動画を送るよう提案していますが、ここでは郁田はるきからの質問による検証の過程を踏んで、二人で出した結論としては期待するに足る行為となるように感じられます。
この判断にはプロデューサーが恬淡な態度を取ったことがかえって良い結果に繋がった経験に拠るところがあり、鈴木羽那の、斑鳩ルカの不安定な心情に頓着しない提案にもまた希望を見出したようにも思われます。

いざ動画を送ろうという段になって、文章を考え始めた郁田はるきですが、そんなときに鈴木羽那が先に送ってしまいました。

「アドバイスがあったらお願いします」という必要最低限の簡潔な文章です。ここでの平易さには、先刻のプロデューサーが勇気の存在を予想したような作為の痕跡はありません。
プロデューサーは恬淡とした態度を装っていましたが、彼女は本当に恬淡としているのかもしれません。
郁田はるきはプロデューサーの口にした鈴木羽那の「また違った思い切りのよさ」をそこに感じたようです。

斑鳩ルカは自室でメッセージが届いたのを見ました。
それは動画ファイルに、必要最低限のメッセージ、そしてそこに体調不良を慮る「お大事に」という定型句が付け足されたものでした。
私には、これがプロデューサーと鈴木羽那、郁田はるきの会話の賜物であるのを知っています。彼らがどれほどのものとして斑鳩ルカに届いたのかは分かりません。

それでも彼女は届いた動画を再生しました。
そして、「下手くそ」と呟いています。
彼女は知らず不完全な二人の様子に完成形を重ねて──完成された先の理想の姿を──予想しているようです。

行為とそれに伴う礼儀の要請を中心に郁田はるきの成長の過程を描いている。
理想の喪失に端を発する斑鳩ルカの抑鬱状態とそれに伴う欠席、それに対する微妙な礼儀の振る舞いから、郁田はるきはプロデューサーに電話をかける。
衝動的にかけた疑いの電話では、プロデューサーの恬淡な態度や信頼のポーズを経て彼女は認識を改めた。特に、斑鳩ルカに自分ができることがないかと悩む郁田はるきには、例えば自身のするものを含む何らかのアドバイス等で自らの感性を塞ぐことなく、自分らしく思い悩んで行動することを求めている。プロデューサーは斑鳩ルカにもそうあることを望んでいるようだ。
彼もまた自身にできることはないか思い悩んでいるようである。
斑鳩ルカを欠いたCoMETIKのレッスンは上手くいかなかった。そこで鈴木羽那の提案から不調である斑鳩ルカにアドバイスを求めることとなった。郁田はるきは躊躇いを覚えるが、プロデューサーとの会話の影響と鈴木羽那の態度から、結果として動画を送信することになった。
斑鳩ルカは動画を見て、そこに映る自らを欠いたCoMETIKの「下手くそ」なパフォーマンスの理想のなかに自らの姿を見出すことになった。
第5話 「ドーナツホール」
斑鳩ルカは不調から立ち直りレッスンにやってきている。鈴木羽那が彼女にパフォーマンスやドーナツの話をする。後日のレッスンは上手くいったようである。レッスンを終えるとSHHisの七草にちかとすれ違う。彼女の手には先日の緋田美琴と同じレモンティーがあった。イベント当日、楽屋に集合したが斑鳩ルカは現れない。プロデューサーは斑鳩ルカに連絡を取ろうとするが上手くいかなかった。やむを得ず家に訪問しようとするが躊躇いを覚える。そこに緋田美琴が通りかかった。
鈴木羽那は事務所にやってきた斑鳩ルカを見るなり挨拶をしています。続けざまに体調について聞くあたり、彼女はメンバーの不調の原因を聞いてはいけない類のものであるとは露とも思っていないようです。

斑鳩ルカは返事をしませんが、それに構わず心配はいらないように見えると言い、そのまま彼女が戻ってきたことへの喜びを口にします。
彼女のが黙っている様子など意に介さずに話し続ける鈴木羽那は何も考えていないように見えます。

ようやく言葉を発した斑鳩ルカは、彼女が戻ってきたことを喜ぶ鈴木羽那に対して、自身が必ずしも必要でないことを伝えています。
「お前らは二人でいい」と考えているようです。

この「お前ら二人」という言葉について、鈴木羽那はすぐに理解できず、確認のために聞き返しています。また、続けて「それでは『だぶるは』」だと口にしています。

斑鳩ルカは彼女が口にした珍奇な「だぶるは」という単純な言葉自体に注意が向いたようです。
さらにどうやら、斑鳩ルカは鈴木羽那と郁田はるきの二人がそう呼ばれていることを知らないように思われます。

そんな様子を気にも留めず、鈴木羽那はレッスンが上手くいかなかったこと、そしてその原因が斑鳩ルカの欠席に求められるという考えを口にしています。
斑鳩ルカは相変わらず何も言いませんでした。
何を思ったのか、そして何かを思ったのかどうかも、やはり分かりません。

そうしていると、鈴木羽那が突拍子もなくドーナツを食べるかを問います。

突拍子もないこの提案に斑鳩ルカは驚きました。
鈴木羽那は「今日のおやつ」──毎日いつも用意されているもの──が「ミセス・ドーナツ」であることを補足しました。生もので消費しきらないといけないから需要の予測も難しく、そのためか「早い者勝ち」とするような少数が用意されています。これを食べるに当たっては積極性、つまり行為を要求するようです。

少し間を空けて、斑鳩ルカはその共犯の誘いを無下にします。
誘うということ自体も実のところで紛れもなく行為です。誘いを持ちかかけるということ自体が成功の可否にも結果の是非にも心を左右される、つまり勇気の要る、行為というものの一つです。
誘いを断るというのは、それ自体が行為の主体に失敗の烙印を圧すことに他なりません。
そのため、人間からの誘いを断るに当たっては、より強大な理由による不幸として断ることとなっています。偉大なる世界の大いなる美しさに任せることなどがよくあり、乗り気ではない誘いがあったときの私たちにはほとんどの場合で他の予定が既に存在します。つまり、大いなる循環のなかにあるこの世界の、巡り合わせの不都合があります。要するに口実をでっちあげます。
このような振る舞いは少なくとも私たちの間では暗黙のうちにお互いに了解されており、ある程度まではもはや最低限度の気遣いだとも言ってしまえるでしょう。
斑鳩ルカはそれすらしていません。先日の楽屋で郁田はるきたちに持ち掛けられた誘いよりは、幾分も断る理由を探しやすいはずです。
例えば、アイドルなのだから、高カロリーの食事で体型や肌の状態を崩すべきではないと主張することなどは非常に尤もらしい口実になってくれるでしょうし、目の前にいる鈴木羽那も鈴木羽那で、ここまで考えて黙っているだけの時間を気にしていないくらい人の様子を気にしないようです。
それなのに斑鳩ルカはただ単に断わり、理由を述べません。にべもない態度は接触を避けるための機制が働いているためのものなのかもしれませんが、とはいえ社交においては明らかな瑕疵です。

しかし、やはり鈴木羽那は気にしていません。
レッスンの動画を送ろうと言ったときに郁田はるきに言ったような調子で、断られたとしてもそれならそれで、という態度を取っているようです。

少なくともそのようなことは考えていないのでしょう。
続いて、ほんの少し間を置いて、斑鳩ルカに「ミセス・ドーナツ」と「クリーミィ・クランキー・ドーナツ」のどちらが好きかを問うています。全く意図の読めない質問です。何のためにされたのか、何が理由なのか全く分かりません。ドーナツは既に用意されていて、ミセス・ドーナツだということが分かっています。
ここまでの彼女が何も考えていないように見えた通り、この質問も何かの考えの元に行われたものではないように思われます。

斑鳩ルカが黙った理由は本当のところで分からないところではありますが、鈴木羽那は「悩むよね」と嬉しそうにしていました。
もしかすると彼女は同じ質問に悩んで、そしてそれが当たり前のことだと思ったのかもしれません。斑鳩ルカにもそれは同じで、少なくとも彼女にはそう見えて、それが嬉しかったのかもしれません。

後日、例のライブイベントを翌日に控えたレッスンを終えたところで、以前の上手くいかなかったレッスンを振り返りながら、やはり3人でのやることが「バイブス」あるいは「グルーヴ」に繋がっていると話しています。
彼女たちの会話はきわめてハイコンテクストで、お互い話そうとする話題を言外に共有しており、その表現もまた以前に起きた出来事を共有しなくては分からない言葉が用いられています。そしてこの会話は、記号的な未知の情報交換というよりも、むしろ既に共有された事実に基づいた複雑な思考に近しいものとなっています。
斑鳩ルカはこの会話での発言こそありませんが、鈴木羽那が言葉を見つけられず言外に共有する対象として表現したものが、「バイブス」や「グルーヴ」と呼称することとそれに至る背景、そして二人だけでは「バイブス」や「グルーヴ」に欠けた「下手くそ」であったことは確かに共有しています。

そして鈴木羽那はCoMETIKのメンバーとして、明日のライブイベントが楽しみなものであるという気持ちをそのまま表明しています。

そうしてレッスン室を出ると、そこには七草にちかがいました。
同じく翌日に控えたライブイベントのためのレッスンをしにきたようです。
七草にちかは斑鳩ルカとの確執があり、以前に個人的に揉めたこともあります。誰も関知しないところでのことで、きちんと仲直りができているようには見えません。緊張は明らかであり、お互いに沈黙しています。

そうしたなか、鈴木羽那と郁田はるきによる挨拶を受けて、七草にちかは平静を取り戻します。

二人の応対に同じく挨拶を返した七草にちかをよそに、斑鳩ルカ押し黙っていました。

そうしていると、やはり唐突に鈴木羽那は七草にちかの持っているレモンティーに気が付きました。
かといってそれ自体には何の変哲もないレモンティーだから、結果として何が起きたとしても、その過程で彼女の行為に何らかの過ちがあったとは到底評価できません。

それは先日、緋田美琴の手にしていたのと同じレモンティーでした。それ自体が直接何かを語るわけではありませんが、それを持っていることが暗示するものや、それを誰かが持っていたという体験に紐づいた彼女の記憶思が思い返されてしまうようにも思われます。

ライブイベント当日、集合時間を過ぎても現れない斑鳩ルカにプロデューサーたちは驚きます。
二人はCoMETIKとして集合時間には既に過ぎていたため、斑鳩ルカは当然ながら来ている、そして来ているのいないのであれば、例えば未だ姿を見せないプロデューサーに連れ出されたものと推察していたらしい。

そうではなかったため、驚きつつもあらためて集合時間を確認しています。

集合時間を確認して、改めて斑鳩ルカが到着している信じていた前提が崩れたことで、不安な表情を浮かべています。

それを見たプロデューサーは同じく取り乱しつつも、トラブルが起きたときの当然の対応として連絡を試みます。当然に行動に帰着しようとすることで平静を装いつつ、そこに規定されるに値するだけの効果があることを不安に宛がうことができます。これは姑息策ではありますが、重要な効果があります。
また、彼はすぐに従うべき具体的な行動指針を提示しており、これもまた不安の緩和には有効です。良い対応ができているように思います。

それに返事をして、それでもなお、二人にとってこの不安は拭い去れるものではありませんでした。
先日の上手くいかなかったレッスンを思わずにはいられないのかもしれません。
不安を覚えるのも、恐ろしいのも、当たり前であるように思います。

プロデューサーはそれでも「大丈夫」であると口にしています。

大丈夫だと言ってみせた彼ですが、連絡がつかないような状態あること、しかし家にいるのであろうこと、そしてここまで来れる状態にはあるのであろうことを推察しています。
推しはかることのできないのはそうなった原因でしたが、それについても考えの及ぶところではないことを早くに見切りを付けています。良好な理知の機能が窺える良い判断だと思います。

しかし、失敗の過去を思い返すことで、彼は躊躇いを覚えました。
もしかすると、今から斑鳩ルカ呼びに行くことでより激しい失敗が待っているかもしれない。休んでもどうにかなる日にいることができていた彼女がしかし今この場にいることができないほどの状態に陥っていて、その原因が分からない以上は、家に行って彼女を連れ出そうとする行為が彼女を今よりも深く傷つけてしまうかもしれない。

そうであれば、ライブイベントを諦めるべきではないかとも思う。今から変更することのできないパフォーマンスを諦めて、ライブイベントの主催者には謝罪をする。主催者には迷惑をかけるが、彼らからの要望を受けて代役のSHHisが出演をしているから事務所としての縁が途切れる可能性は小さいのではないかとも思う。……しかし将来のクライアントたちが斑鳩ルカをこれまで以上に敬遠するようになってしまうのは避けられない。急な出演の取りやめが、かつてのユニットメンバーとの関係に下衆がそうするような噂や勘繰りを生むかもしれない。何が起きるのか分からない。でも何が起きるのか分からないのは、今から斑鳩ルカを呼びに行った場合でも変わらない。けれどそのときには致命的なリスクがあるのかもしれない。

──立ち尽くしていると、緋田美琴が通りかかった。

前話にて示された恬淡な態度の美徳から、鈴木羽那の疑わない素直さが示される。
全体に、彼女の会話はハイコンテクストであり、そのテクストを共有していない場合には理解が及ばず、本人もそのことに頓着していない様子から、やや突拍子もない振る舞いであるように見える。
翌日に本番を控えたレッスンを終えると、七草にちかがそこにいて、斑鳩ルカは彼女が持っていたレモンティーを見て衝撃を受ける。
本番当日、彼女は現れなかった。出番までの時間が迫るなか、不安を覚える二人を前に予定の通りに上手くいくことを信じるように伝え、事態の解決を試みるプロデューサーであったが、彼もまた不安な現実を前に立ち尽くしてしまった。
第6話 「If you don't know」
プロデューサーは緋田美琴と話す。その後に斑鳩ルカの家に着いた彼は扉越しに彼女との会話を試みた。斑鳩ルカはプロデューサーとともにライブイベントの会場へ向かうこととなった。
斑鳩ルカはプロデューサーの予想した通り部屋にいるようです。
レッスンの後に見た七草にちかが持ったレモンティーを思い出し、緋田美琴はもはやSHHisであることを何度目かも分かりませんが思い知らされて、そのことに彼女は心を囚われているようです。
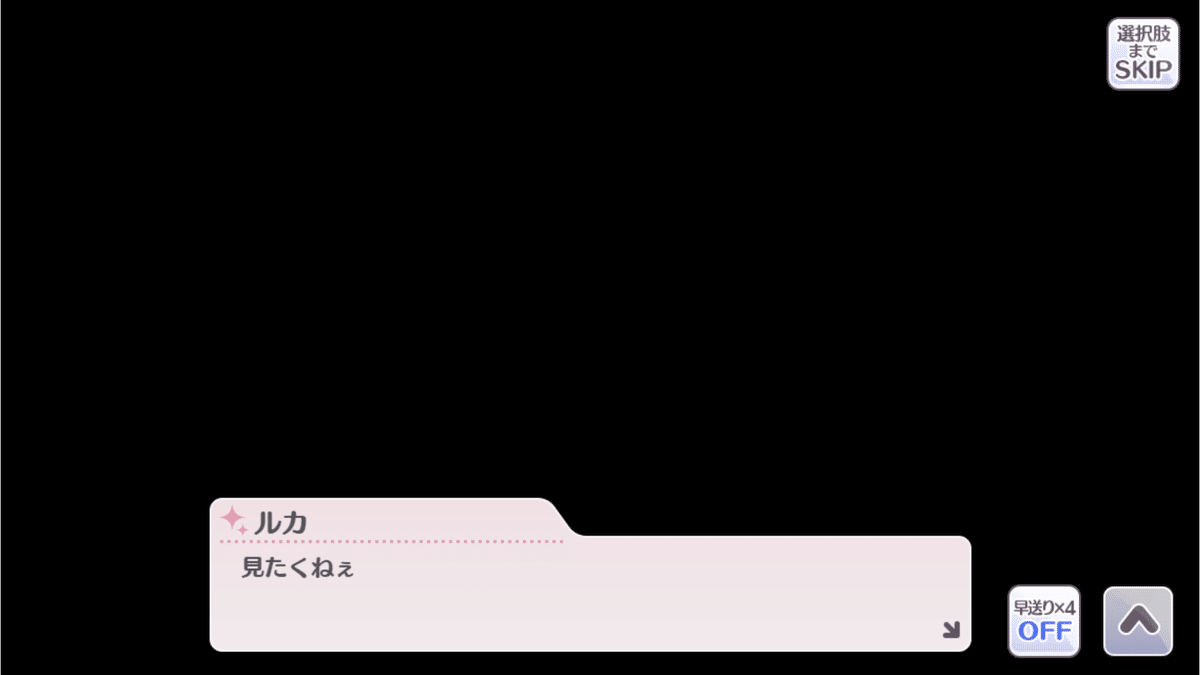

そのうち、彼女はステージに立つことをやめるのを思いつきます。思い出してみれば彼女が苦しんでいるのはアイドルをやっているからに違いありません。
そうでなければ、強いてSHHisに会うこともなく、そうすれば、苦しい思いをするきっかけだってない。そうすると、今目の前にある世界だけが全てで、そうであれば、そこには静かで穏やかだ世界だけがある。


それでも、これまで必死に練習をしてきたことを思い出してしまうらしい。そして練習をしてきたことを思い出すと一緒に練習していたもののことも思い出されるようです。
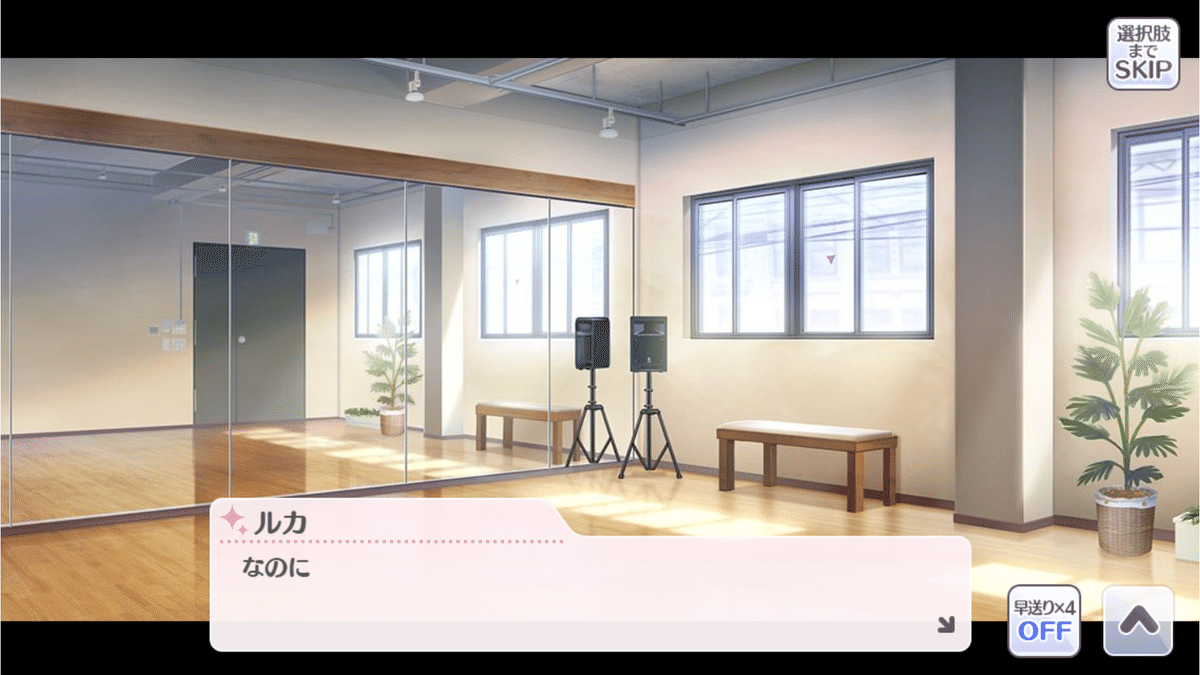


プロデューサーが通りかかった緋田美琴と話しています。
斑鳩ルカが現れないことを伝えると、彼女は事故や事件が第一に思い浮かべました。
彼にも思い浮かべたくないことはあるようで、「やめてくれよ」と述べています。

彼は心当たりとして自らが思うところについて話します。


彼は、斑鳩ルカにとってSHHisとの共演は受け容れがたいことだったのだと考えているようです。共演を拒むに至る具体的な理由については分からないにしても、何かしらの理由があるのかもしれません。
もしそうであれば緋田美琴にとっても言いにくいことだからでしょうか、彼は言葉を選び、歯切れの悪いもの言いをしています。

彼女は彼の質問の主旨を把握できずに聞き返しています。把握できなかったこと自体が、彼の懸念がある程度まで過剰なものであったことを暗示しています。

それでも彼は信じ切れずに、単に伝わらなかった可能性を思って補足をします。彼は網羅的に予想することの叶わない可能性の集積を前に、言葉を並べてしまいますが、彼女はごく端的に分からないということを認めます。



続いて分からない理由について、自身のスタンスについて、ごく単純な所信を説明します。
答えらしいものが得られず、やはり不安の解消されなかったプロデューサーはやや落胆の相槌を打ちました。
その様子を受けてかは知りませんが、平明な記憶から斑鳩ルカもそうであったことを思い出しています。


そしてそのまま自分がそうであるように、斑鳩ルカもステージに穴をあけてしまうことを望まないはずなのだという考えを口にしています。
これはそのまま彼に伝わる会話の形式を取りながら、実際には思考のように判断が行われています。
結論は、斑鳩ルカが欠席に至った理由は不明であるが、少なくとも彼女自身がそれを望んでいるわけではないだろうという推量の採択です。
過去の失敗と未来の巨きさを前に、客観性を保てないでいた彼は、これからとこれまでの実際の行為に及ぶ当事者ではない彼女によって客観的な推量を得ることができました。
──それにしても緋田美琴はこれまでずっと、斑鳩ルカがそうであることを疑わなかったようです。ステージに立つことを諦めない自分であろうとすることを、アイドルに相応しいアイドルであることを。

プロデューサーはそして感謝を伝えました。
斑鳩ルカがステージに立つのを拒んでいる、もう彼女が立ち上がるのを諦めてしまうのではないかという考え……そうしたことがない緋田美琴には、斑鳩ルカがもうアイドルではいられないのではないかと疑ってしまったことも、自分が最後まで彼女を信じていられなかったことも、それを彼に分からせてくれたことも、何も伝わりませんでした。
感謝はあくまでも行為による受益の確認することで、その礼儀の効用は節目とした挨拶を以って、その行為にいつもでも拘泥しない約束を交わすことです。それが計画も畏れもない単なる行動であったとしても、感謝は交わされます。



斑鳩ルカに信じていることを伝えに行くと言って、いつまでも感じ入ることなく、彼はすぐさまその場を後にしました。

斑鳩ルカの部屋の前で、プロデューサーは話し始めます。起き上がることができるからやはり体調が優れないというわけではなさそうです。

いるかも分からない彼女がいたことに安堵を覚えつつ、彼は初めに謝罪をしました。
斑鳩ルカはこの謝罪の理由に即座に反応するような心当たりがなく、思わず聞き返しています。もしそうであれば分かったはずであるから、この時点で、今まさに彼女が部屋を出られずにいることと彼の行為には、少なくとも彼女の意識の上での直接的な因果関係は否定されているように思われます。
この時点で、従前の彼の懸念は解消されていますが、これは彼の客観性を損なわせていた後悔にかたをつけるためのものでもあるのでしょう。


続けて、彼はこれまでに彼女に影響を与えてきたのであろう自身の行為を振り返り、その全てについて謝罪しています。また特に、彼にとっては以来己をを苛み続けている車中での諍いについて述べています。
ここには、過去を振り返り考え始めた彼にとって、思い出せる限りの全ての行動がどのように影響していたのかを確認することができなかったことが窺えます。これまでの彼らは、謝罪はさておき、感謝が形になっていなかったのでしょう。
厳密にいえば、ここでの謝罪はまず第一義に自身のために実行された礼儀であり、これから誰かと何かを話すにあたって、曖昧にするべきではない準備でもあります。
また、ここでは、彼女を説得するという目的の達成のためには、特に強い心当たりがある車中の出来事以外には言及しないのがよいように思われますが、彼は全てに触れてしまっています。



彼女は良くも悪くも、何も感じていないように見えます。

彼は沈黙したまま変わらない彼女の様子に、ただ謝りに来たわけではなかったのだと我に返りました。

そうして、自分の考えをまとめるように思いを言葉にしはじめました。
彼はずっと──きっとそれは彼が彼女のためにできることをしはじめた、283プロダクションのアイドルになる前からずっと──彼女がステージに立つことが幸せに繋がるのだと信じていたらしい。
それが正しいことであるのかは分かりません。時間を遡ることはできず違う未来を選んだ自分の姿を知ることもまたできない。だから彼はただそう信じています。
また、いつか郁田はるきからの電話では口にしなかった彼女たちのあるべき姿についての言及でもありました。あのとき、漠然とした言葉でしか表せずにいたものが「斑鳩ルカがステージに立つ」ということだけは確からしいものとして、これからの彼女の選び得る未来の全てにそうあることが決して異存ないものと信じて言葉にしているようです。


彼はその上で斑鳩ルカに問いかけました。

しかし彼女の反応には拒絶する意向があるのみで、何かが伝わった様子はありません。
……言葉は言葉に過ぎません。謝罪も、思いも、言葉で表されたならば言葉です。謝ればそれだけで許されるわけでらなく、言葉にすればそれだけで伝わるわけでもない。それが思いを代表していたとしても、言葉が伝わるためには言葉だけでは足りない。時や、場所や、時間や、巡り合わせや……あらゆるものが大切なのかもしれません。少なくとも、同じ何かに思い当たる、同じことを共有していることは大切なことらしい。けれど彼と彼女はそうではなかった。
ステージに立つことで彼女は幸せになれるという思いは、その言葉は、彼女には意識されたことの少ないことで……だから、彼女がステージに立ってきたのは、幸せになろうとしたからではなかったのかもしれません。彼がステージの幸せを信じていても彼女にとってはそうではないらしい。


諦めきれない様子のプロデューサーに彼女は話します。
もういいだろう、何回やったとしても同じようにいつかは苦しむことになる……だから、とそれでも口に出せないでいる諦めようとする彼女の言葉は、今まさに苦しむプロデューサーとの会話の形式を取った彼女自身の思考でもあります。
これまで彼や鈴木羽那や郁田はるきが希望を込めてそうしてきたような会話が、苦痛に満ちた状況のなかでは斑鳩ルカにもあり得た。


今の彼にこれほど伝わる思いもないでしょう。
……いつも、同じように苦しんでくれる誰かは見つかりません。不幸は本来的に個別のものです。小説が読まれるのは、もしかすると己の不幸が己だけのものではないと思いたいからなのかもしれない。
類稀な幸運によって彼女の不幸な夢が叶おうとしているように見えます。
──一人では追いかけずにはいられない希望の光からも、二人でなら目を背けていられるのだろうか。
膝を抱えて手を繋いでいられたなら、それだけで全てを諦められる……眩しい希望が暗闇の安寧を脅かしたとしても、繋いだ手を強く握り込めば、裏切りの恐怖からも背を向けていられるのかもしれません。
諦めた少女と彼女を諦めた青年として生きていく道もある。
美しい過去への憧れが、依然彼らを苛み続けようとも。

──力なく、けれど僅かに不機嫌な声に、彼の眼裏には、彼女の表情が思われていました。
そう、それはよく晴れた日のことだった。
彼らは公園にいた。何のためにそこにいたのかも、もう覚えていない。けれど、その時彼は既にプロデューサーで、彼女は彼の担当しているアイドルだった。
それは彼が思い返した謝罪するべき全ての過去の一つ……そしてそれは同時に、彼がステージに立つ彼女の幸せを信じた時間の一つ……そしてそのときから、彼は、紛れもない地続きの今を生きてきた。

彼は思い出し、それでも今に至るまでを信じること──諦めないことを確認したようです。
彼は彼の信じてきた今の連続を思い、彼女への同情を断ち切りました。


彼がのいう「今」は、そして「これまでのルカ」は283プロダクションに来てから、彼が信じてきた斑鳩ルカだった。
そして彼の信じる斑鳩ルカは、283プロダクションのアイドルで、CoMETIKとして彼らと時間を共にしてきたメンバーなのだと伝えている。
もはや時間をもってしか表現できない、あらゆる出来事や風物が、その全てをもって、彼や彼女が思い出し得るその全てが、彼の信じる幸せに繋がっていくのだと、そう信じている。
彼女が何度やっても同じだったのは過去のことであり、彼のいう今とは違うのだという。283プロダクションの彼女が、理想のアイドルがそうであるように理想を描くことを、思うことを諦めないことを信じている。


……彼の思いが伝わったのかは分かりません。
ただ緋田美琴の手にしたレモンティーを見つけたときのように、彼女の意識にはコメティックという言葉だけが意味を結んでいます。

プロデューサーは、自らの口にしたCoMETIKという言葉自体に、今置かれた状況が思い起こされ、立ち戻り、話を続けます。
彼は言葉を選び続けます。それは彼がこれまでしてきたように、どうなるか分からない畏れを抱き、それでもなされる一つ一つの行為であるらしい。
そしてそれを強いて見せないための緊張が、彼の語る速さを抑えているようだ。
彼は彼女が降板することによってCoMETIKが出演を辞退せざるを得ないことを口にします。
何かを伝えるというよりは、やはり彼自身の考えをたどるように、そしてそれが結論するところは変わらないというように、その理由を説明します。倒置するように述べる不自然は、何も強調するためではないようです。


彼はその論理的な思考の過程で爆発的に生まれ、その判断の困難を以って彼を圧倒してきた多数の可能性を思い、そして、そのなかから自らに強いて否定するべきものを、つまり斑鳩ルカを欠いた状態での出演、引いては彼女がいずれ脱退する未来を、確認しています。


高い水準で統合された思考と発話を実現していますが、会話の形式をとった思考は共有されていないのかもしれません。それが信頼性の高い言動であるのことが分かるのは、彼のこれまでを見知った私だからなのかもしれず、表面的な彼の物言いだけに注目すると、それは厳しくて狡猾であるようにも聞こえます。
彼の思いは、考えは、信じたものは伝わったのでしょうか。
斑鳩ルカは、レモンティーに緋田美琴の今を、そしてそれに暗喩される過去を、そしてもはやそこには戻れないことだけを思ったように、「CoMETIK」という言葉に、誰かがいつか彼女の行いを確認してきたことが、そしてまた別の誰かが、自分がその一員であることを信じて疑わずにいたことが思われたようです。
そして、そんな出来事を思い出すのは、その時々に彼女らがだぶるはの2人と斑鳩ルカであるのだと目を背けていながらも、知らずその瞬間の彼女たちがCoMETIKであることを疑うことなどできず、どうしようもなく信じていたらしい──。
思わない、感じない、信じない……不幸の果ての結論は、しかし撞着した夢の一つに過ぎなかったことを思い知ったのかもしれません。



交わされた些細なやりとりのことなど知るはずもなく、それが彼女の心に波を立てることなど分かるはずもなく、彼女が1人だったことやそれでも1人ではいられなかった悔しさになんて気付くこともなく、プロデューサーは彼の思考を続けます。

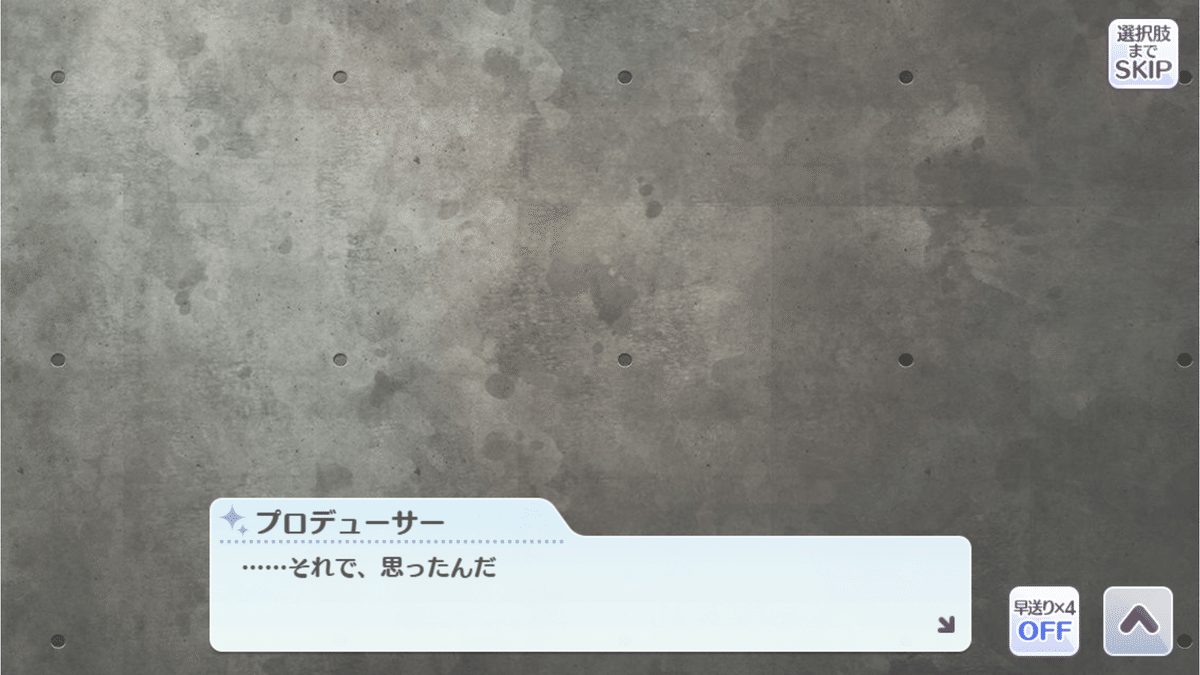
彼の思考は、しかしそれでも彼の信じてきた時間から彼女の心を推し量ります。その推量は正しいのか間違っているのか分かりません。


辿々しく、彼は自分の言葉を継いでいきます。
彼女は、何かを好きになることができるのだと、何かを好きになってしまうのだと、情け深いのだと彼は思ったらしい。

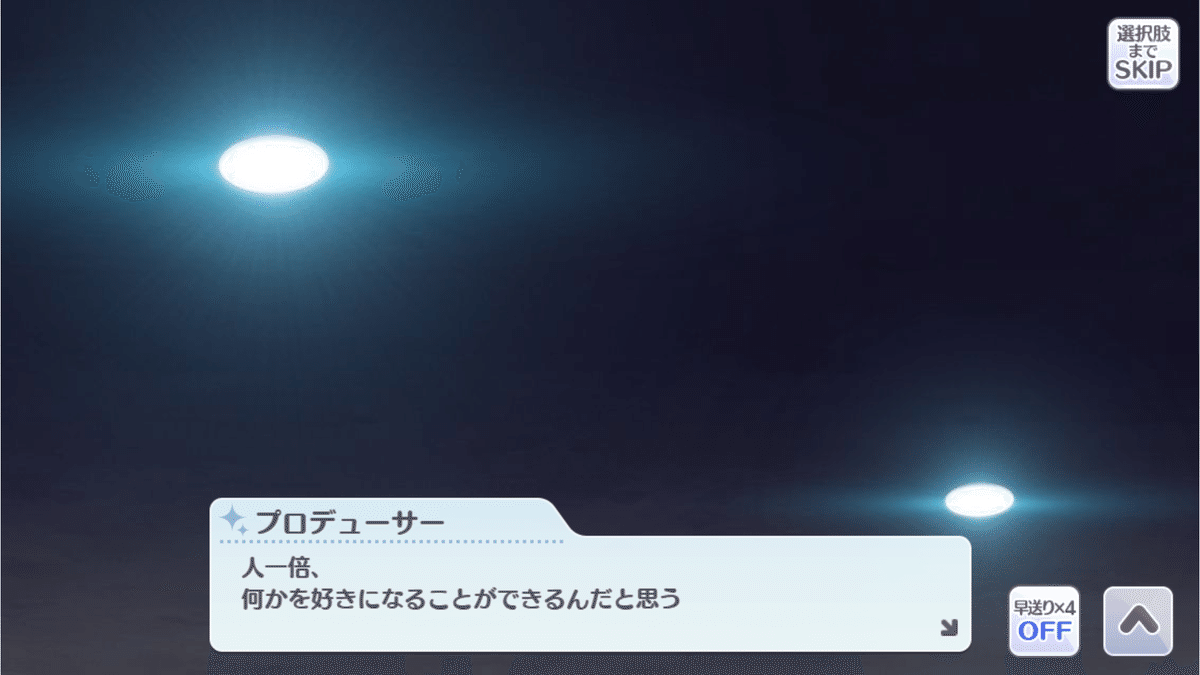
それが正しいのかは分かりません。
実際に彼女が、そうなのかも、そうでないのかも分かりません。
どうすればそんなこと思うのだろう。……自分の振る舞いを思い浮かべて、誰かの振る舞いを思い浮かべて、それからそれを比べて、色んなことを思い浮かべて、それが正しいのかを考えて、思い違いだっていくらでもあって……そうしてようやく初めて形になるようなことを、一体誰がするのだろう。一体、どれほど人を思えばそのようなことをしようと思うのだろう。
今の彼女は少なくとも、そんな風に考えたことはないのかもしれなくて、彼の思いや考えは、やはり彼女には何も伝えないのかもしれない。

その考えが正しいのか間違っているのか、その言葉が何かを伝えるのか伝えないのか、その行為が良い結果に繋がるのか悪い結果に終わるのか、扉を隔てた青年には、そして少女にすら分からないのかもしれない。
彼女の表情も、心のありようも、きっと本当はもっと複雑なのに、僕たちはそれでも感じたものからその全てを思い描こうとすることでしか分からない。
彼の考える彼女の思いは、彼女にとってはどうなのだろうか。今に至るまでを思い、描いた彼女の心は、やはり彼の思った彼女自身を嫌うようにも思われて、それは紛れもない彼自身の心に同じように思った過去があったことも暗示している。
傷付きやすい自分を憎む心に思いを寄せられたのならば、彼もまたそんな自分を憎むことがあったのかもしれないと思う。


それでも彼は、何かを思って、そのために傷付いて、何度もそれを繰り返して、それでも何かを思わずにはいられなかった彼女の今までを、素敵だと思ったのだ。
そんな姿に、ステージに立つアイドルの理想があることを信じたらしいのだ。



どうしても彼の思いはいつまでどうしても伝わらないらしかった。
彼の思いは伝わらなかったけれど、けれど、そうして彼女に理想を見出してくれた誰かがいたことばかりは思われてしまう。
レッスンやステージや、もしかしたら彼女が動けずにいるままのこの場所にだって、きっといたのだ。今彼女たちはきっと最後の一人を待っている。
目指す先、帰りつくところ、今この瞬間にいるべき場所は、美しい日々でも、何もない部屋のなかでもなかった。

プロデューサーは彼の思いを確かめて、彼がここまでただ一つ悩み続けたこと、斑鳩ルカの諦めようとする考えを否定する決断を表明します。


斑鳩ルカは彼の言葉を聞いて出てきました。
けれどそれは、彼の決断が心を搏ったわけでもなければ、彼の思考に思いを寄せたわけでもなく、ただ、その過程にあった彼の言葉に彼女が何かを思い、CoMETIKを思い出したからです。
彼女はCoMETIKだから、CoMETIKのステージに立つために出てきた。


だから、プロデューサーは連れ出したわけでもなく、説得したわけでもなく、彼女が言う通り、本当にただ騒いでいただけなのかもしれません。

もしかしたら、彼にとっては、彼女が出てきたのだから思いが伝わったはずで、そうであれば彼のように何かしらの苦しい顔をしていているものだったのかもしれません。
もっと感情的な言葉があると構えていたのに、投げかけられたのは常識的で世間並な──ここでは客観的な言葉で、平気そうに聞こえて意外だったのかもしれません。
いつか郁田はるきが勢い込んで電話をかけたときのように、客観的な彼女の様子に彼は自らの振る舞いを見つめて平静を取り戻し、そして改めて謝罪と感謝を伝えます。
彼女がどう思って出てきたのかは分かりません。本当に平気だったのかもしれない、平気であることを装っていたのかもしれない。
ただ一つ確かなのは、彼女が部屋から出て、プロデューサーには喜ばしく思われて、彼女が今からステージに立つことで、それには急ぐ必要があることでした。


格好はつきません。彼の感情的な言葉や振る舞いは最初から最後まで見当違いだったのかもしれません。
伝わったものだけを思えば、CoMETIKという言葉と、彼女は慕われてきたのだということだけで、それにしたって彼がそう伝えようとしたのではなく彼女が自分で気付いただけです。
しかし、動機や文脈はどうあれ、それでも彼はその言葉を口にして、彼女が何かを思う間を彼は意味を結ばない言葉で繋いでいて、そして彼女がステージに立とうとした今このときにその場にいる。
彼女はCoMETIKの彼女らのように彼女を慕うらしい、みっともない彼に敢えてそうすることはありませんでしたが、それだけで感謝を伝えるのには十分なことだったのかもしれません。


今話では、予測不可能な未来への恐怖と、思うことを嫌った末の無気力、行為の可能性を低減したものへの前提が決定的にすれ違っている、プロデューサーと斑鳩ルカの不器用な会話が行われる。
前話にて、斑鳩ルカを呼び戻しに行く足が竦んでしまったプロデューサーは、第三者である緋田美琴との会話のなかでステージに立とうとする斑鳩ルカを信じて疑わない様子に、自身のあるべき態度と客観的な視座を得て彼女を迎えに行った。
彼は扉越しに斑鳩ルカに話しかける。お互いの思うところを知るはずもない二人の会話は微妙に行き違い、最後まで噛み合わないながらも、それでもその過程にあった言葉だけは彼女の心に響いたようだ。
扉を開けた斑鳩ルカはCoMETIKの一人として立つべきステージを見据えている。
エンディング 「I didn't know that.」
斑鳩ルカはステージに間に合い、無事にパフォーマンスを終える。仕事を終えた帰り路、鈴木羽那はドーナツを食べようと提案した。後日「鈴木の部屋」の収録間近に迎えた斑鳩ルカは鈴木羽那と短い会話をした。
斑鳩ルカは出演に間に合ったらしい。予定の時刻を超過しても主催者たちは部屋やメイクスタッフを手配していてくれていた。ここでも誰かが彼女が来ることを信じていたらしい。

部屋に向かおうとすると出番を控えた緋田美琴と出会った。
彼女はCoMETIKのステージを生で見るのが初めてだと口にする。



彼女はいつかそうしていたように、彼女の衣装がSHHisのものであることにも、自身がCoMETIKであることにも、そうあること以上の注意を奪われないでいられたようだ。
緋田美琴の言葉が久しぶりの共演者のステージを楽しみにしていることや、その喜びを伝えようとしていることにも、思うところはあっても大きく心を揺さぶられることはない。
最低限度の返事をして、目下優先するべきステージに向けて彼女は先を急いだ。

そうした彼女の背中を見送って緋田美琴はどこか嬉しそうに見える。
以前、斑鳩ルカは自身と別のユニットを組んでいる緋田美琴に何とも思わないのかと思っていたが、彼女は彼女で、これまでに表舞台から身を引いた人たちを見てきた立場です。
そのなかにはきっとその時の斑鳩ルカのような者もいたのかもしれない。彼女が舞台に穴をあけることを望むはずがないと言ってみせた彼女にも、それでも帰ってこない未来は予感されていたのかもしれません。

改めて感謝を述べるプロデューサーに「わかっていたんじゃない?」と問いかける彼女の表情にも、そういう暗い可能性を否定する心の営みが覗かれるのかもしれません。


彼はやはり分かっていたわけではなかったと答えます。
彼はただ信じていたのだと言います。

彼は彼女がステージに立つことにどれだけの希望を見たのだろう。
ただそうかとだけ返した彼女はどれだけの時間を過ごしてきたのだろう。


斑鳩ルカの準備が整ったときには既にステージの脇に控えているような直前のことだったようです。スタッフたちは限界まで準備をしてくれたらしい。
出演時間に間に合ったことを喜ぶ郁田はるきでしたが、斑鳩ルカは集合時間に遅れたことを口に出すことで、言葉少なに謝罪しています。


初めてのことだったのでしょう、郁田はるきは驚きますが、すぐに何でもない普通のやりとりとして、気にしないでよい旨を示しています。


鈴木羽那はそんな様子にも特段の驚きはないようで、素直な喜びを表明しており、それはやはり彼女らしい。

斑鳩ルカは時間が迫るステージの袖で、二人を見つめていました。過去とは異なる何かではなく、ただそこにいる人間である彼女たちの目を見て、そういうふうに話すのは、もしかすると初めてことだったのかもしれません。

郁田はるきが感謝の言葉を伝えている。
ステージが終わったらしい。
郁田はるきはフェス形式に見合ったように宣伝を欠かさなくて、鈴木羽那は屈託のない喜びを伝えている。

ステージの上にあっても、斑鳩ルカは彼女たちの様子を眺めていた。自分が補うことのない、二人だけでもやっていけそうな二人に見える。
と、最後の言葉を残すとき二人が不意に間をあけた。
ステージは、少なくとも必要なことだけで作られているものではないらしかった。



帰り路、郁田はるきがSHHisのステージの感想を話す。
いつかそうしたのとは違って、その賛辞には切実な要求も、気負いもありません。
同調しつつ、鈴木羽那は自分たちのことも知りたがっています。素晴らしいステージにできたと思っているようだ。


それを聞いた彼女も嬉しそうです。評価は他人もするものですから結論とは言えないまでも、本人がそう信じることができるのは素晴らしいことです。

斑鳩ルカは会話に混ざらないながらも、彼女たちの話に今日のパフォーマンスを思い出していたようです。

すると、やや唐突に、鈴木羽那がドーナツが食べたいと言い出しました。
郁田はるきも、斑鳩ルカがきっとそう思っていたように、そんな彼女の振る舞いのことを急だと思っていたようです。


けれども、彼女は鈴木羽那にも同調します。
確かに、彼女たちは先ほどまで共に忙しない一日を過ごして、同じステージに立っていました。
複雑さのない単純な甘味を求める彼女たちの無意識には、今日の「頑張り」に来ないともしれない誰かを信じる心の営みも含まれていたことを示唆しているのかもしれません。
そうであればそれは斑鳩ルカには関りがないことです。

──ふと、郁田はるきが「どっちのドーナツ」がよいかを鈴木羽那に問いかけます。

彼女は少し間を置いて、何の話をしているのか分かったらしい。
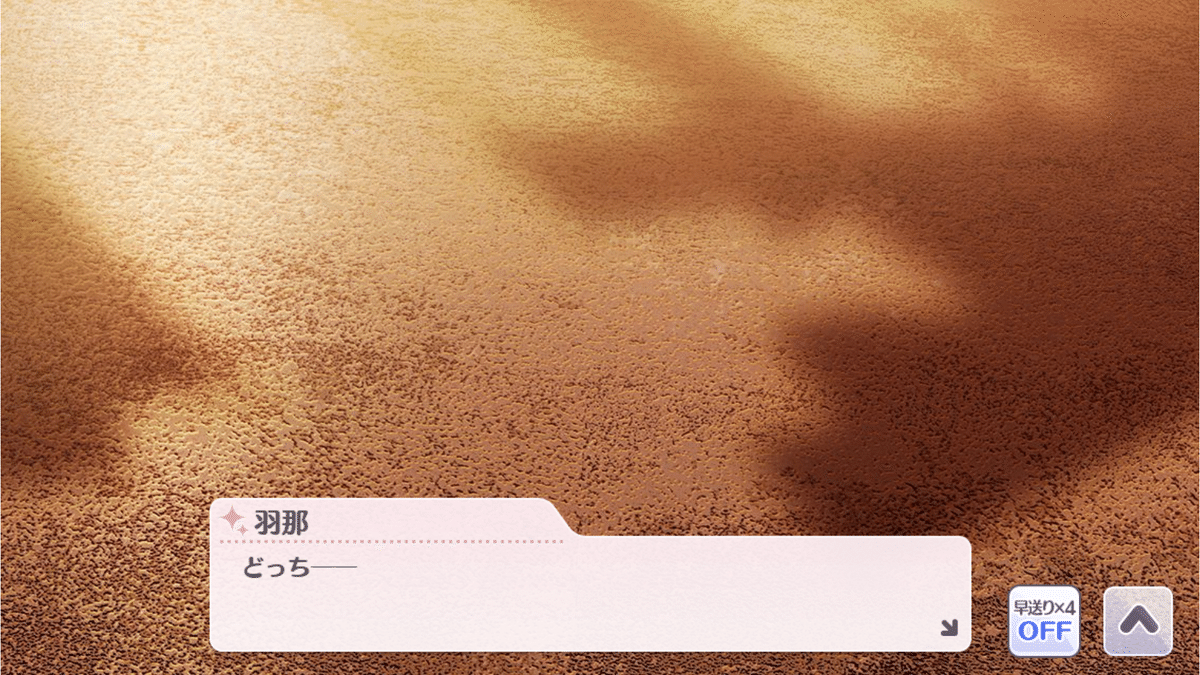

そして、そのまま斑鳩ルカにその質問を投げかけました。


鈴木羽那の示した選択肢を郁田はるきが引き継ぎます。


そして彼女たちは、斑鳩ルカがこの選択に参加することべきことを伝えています。

知った質問でした。
斑鳩ルカも、きっと、鈴木羽那が「ミセス・ドーナツ」と口にしたとき、郁田はるきがそうしたように「クリーミィ・クランキー・ドーナツ」を思い浮かべることができたのだと思います。
初めは知らないところで行われていても、しかし彼女の会話でもありました。
鈴木羽那は、「『どっちでもいい』はなし」だという。まるで、かつてそうしたかのように。

……あの時、鈴木羽那がドーナツを食べるか聞いてきた。
断ると、どうしてなのか、鈴木羽那も食べなかった。
……分からなかった。
きっと、同じだったのだ。彼女は斑鳩ルカを誘ったのではなかった。斑鳩ルカも一緒にと誘ったのではなく、郁田はるきはいないけれど、と誘っていたのだ。

どうしてドーナツには穴があるんだろう。初めは可愛らしいからだと感じた。話せる言葉が増えたころに持ちやすいようにするためだと思った。身体が大きくなり初めてから材料費を減らすためだとも考えた。
誰かから、その形の器具で熱を加えて作っていると聞いて、不思議な形は当然のものだったのだというのが分かった。熱が伝わりやすいようにしていたことや、過去に熱が伝わらなかった試作品があったことには自分で気がついた。
だからあの日、斑鳩ルカがドーナツを食べないなら鈴木羽那も食べなかったのだ。
知らなかっただけで、知ろうとしなかっただけで、もうそこにあったらしい。
彼女の感性は花開き、久しぶりの世界に向けられているようだ。
道路は先まで続いていて左に曲がっていき、強い風が青葉を散らして、疎らな人は行き過ぎて、そんな風景を切り取るレンズには、傾き始めた強い日差し映るだろう。光は、フレアとなって、きっとゴーストだって生まれる。レンズの上の私たちにはきっと影が落ちている、私は後ろを歩いていて、そして────
横断歩道の先には、二人が待っていました。

どうでもよいことだった。今、それが分かった。
ミセス・ドーナツもクリーミィ・クランキー・ドーナツも、そのもの自体はきっと本当はどうでもよいこと……レモンティーも、SHHisも……そして去りし日々も、きっと本当はそうだったのだ。

今そうでない何かがあるとすれば──あの日用意されていたのは、確か、ミセス・ドーナツだった。

いつか電話で話していたように、斑鳩ルカが「鈴木の部屋」にゲストとして出演することになったらしい。
様子はどうだと聞いて、それから自分の思いを言葉にする。初めに問いに答えて、その内容を言葉にしておく……もしかしたら私たちの会話には自然な気遣いのなかに生まれている思考の共有や確認の過程が含まれているのかもしれません。
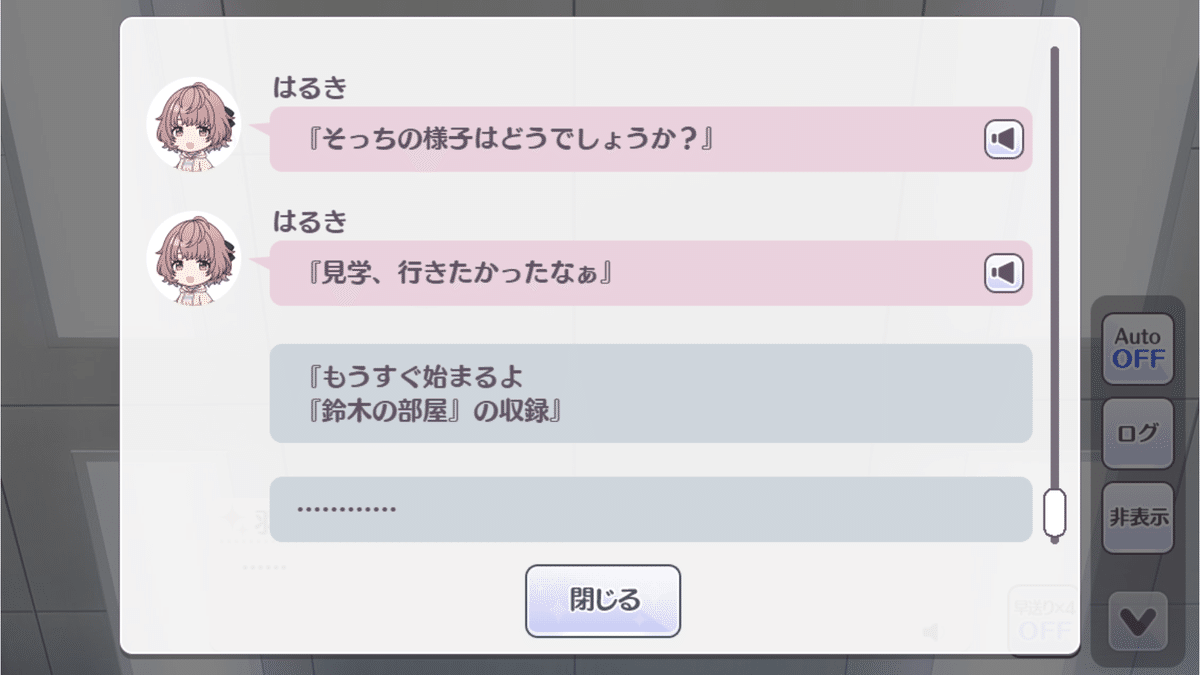
鈴木羽那が笑います。

何かを思い出したのか、変わったことがあったのか、分かりません。

斑鳩ルカの出演が嬉しいそうです。
きっと信じて、疑わずにいられるように見えます。

それでも気にしません。
仕事であれば当たり前で、普通で、平気だからです。


どうやら、約束の時間を忘れないでいられたようです。

『THE (CoMETIK) EPISODE』に寄せ
大切なものほど口にはできないらしい。
大切なものほど名状しがたい。
その理由は、それが大切であるがゆえにやはり名状しがたい。あまりにも複雑で、薄々そうでないことを知りながら、誰もが分かっているものとして話すだろう。話そうとも僕らにできるのは例を上げてみるくらいのことだった。
例えば、そこにはあらゆる要素が含まれている。
だから私たちは、時にそれを時間と呼び、時に言葉にせず、時に二重の敬語を使ってみたりした。
そうでなくても、大切な何かそれ自体を総て、示す言葉があるのなら幸運なことだが、それにしても、その言葉を口にするのはいつも畏れ多いことだった。
大切なものに限らずとも、世界は複雑だ。複雑だから未来のことも予想できずにいる。
この時代の科学はすごくて、どうして雨が降るのかも分かっているのに、それでもまだいつ雨が降るのかが分からない。
そんな調子だから、今目の前にいる人の心がどんなふうに移ろっていくのかが計算できるようになるのはきっとずっと先の話で、また、計算通りに彼の背中を押せるようになれる日は来ないのかもしれない。
だから悲劇は起きてきた。
僕たちはその理由を探そうとしたときに、いつも何を信じたらいいのか、何を信じなければいいのか分からずに、結局何も分からないことがよくあった。そうするうちにすぐそばに大きな原因があれば、それだけに全ての説明を任せてしまいたい気もした。
僕たちはそうして初めて、何かを残しておけば確かめていられただろうにと、そう思った。
そのためには分かたれぬものをそれでも分けるのが大切なのかもしれない。
礼儀……ありがとうだのごめんなさいだのと口に出すのが不思議だった。
有り難く思う、御免なさい、などという言葉が、どうしてそんなに使われていて、自分も使わないといけないのかが納得できなかった。落とし物を拾うのは当たり前のことだと思ったし、泣かせた相手に許されたいとも思わなかった。有り難くも、許すように言おうとも思わず、だから大人がその言葉を強いるのがいつも不満だった。
今、大人になって、仕事をして、後輩もできて、教育をすることもあって、色々なことに随分と慣れてきたものだが、それでも感謝や謝罪の言葉を口にしない日は決してない。
辛く苦しいことがあったとしても、お互いに美しくあることを目指す、そして変わらず、平気な顔をしている。
そんな美徳を守れる社会では、感謝や謝罪といった礼儀が織り重なって、ようやく大切なものを尊重してくれることを知っている。
そんなふうに美しい在り方を夢にも描けない人たちがいることだって、誰に言われなくても知っている。
思うということをするとき、思うことそれ自体がそうではなくても、思う先に苦痛があるなんてことは人並みの人生を送れば分かることだった。
思い、それを信じるというのは、もしかすると連絡のつかない恋人を待つようなことなのかもしれない。
来るべき人が来ない。けれど来るべきであるから、待ち合わせた場所から離れることはできない。どれだけ待てばよいのか、待っていてよいのかも分からない。
隣の者には待ち人が現れてその場を去り、また次の人も去り、新しい誰かが誰かを待ちはじめ、そして私より先に去っていく。
待ち続けるか諦めてしまうか、天秤に絶えず身を引かれながら、生の均衡に耐える時間……信じたものが眩しければ眩しいほど、信じて、信じ続けるのは苦しい。
本当は、もう諦めて、その場を立ち去ってしまうのがよいのかもしれない。同じように、思いを言葉にするのももうやめるべきなのかもしれない。
……でも、もしそれが叶うとしたら、どんな感謝や謝罪をさせてやろう。私はきっと平然としていやろう、今まさに待っていた私のためだけに。きっと相手も謝りきれずに苦しんで、平然とした顔で苦しい思いをするがよい。
それを私は次も懐かしもうと思う。今そうしているように。
感想
……そこにあるものに、気が付く。
感謝を覚える。
礼を言う。
──初めにそうした人間は、一体何歳だったんだろう。
面白いコミュだった。
色々な知見を踏まえた上で、技術的にも上手くて、『セヴン#ス』前後あたりからここまで描かれてきたエロティシズムの先、知性と、その一類型としての理性の有り様が描かれた。
特に本コミュでは、手段としての礼節や会話についてよく書かれていた。実用性が高い。
僕たちは一人で生きているわけではなくて──宗教やその類似物がそうするような、対象自身による自己の理性の援用を期待するものでないにしろ──生成された言葉等の物体を中心とした理解、即ち知性の機能を前提する個々に断絶した相互関係は至るところにあり得た。
僕たちは言葉を、誰かに思いを伝えるものとして、あるいは精々会話を通した思考の道具として使う程度だ。
意識するのもそれくらいだが、言葉の実態はもっと孤独なのだと思う。
お互いに何も伝えない孤独の中にも言葉は置かれていて、その言葉から何かを思い出すことがある。
本当のところで、それぞれの肌に隔たれた僕たちは、間に置いた言葉からそれぞれ何かを思い描いているに過ぎないのかもしれない。
扉を隔てたプロデューサーと斑鳩ルカのやりとりはそういった意味で美しい場面だった。
これまで283プロダクションのアイドルたちは色々な形で思いを伝えてきた。それは美しいことだった。
それでも、僕はそれだけが人間じゃないと思う。
僕自身がそういう交わりとはあまり縁がないからかもしれないが、それでもやはり、思いを伝えることだけが生きることではないと、思いを伝えることだけが言葉の全てではないと、そう思う。
本当は構成や表現、モチーフ、各々の美点と描写されたものの背景、演技や芝居についても、本当にもっと多くのことをもっと語りたいのだが、この辺りにしておきたい。
遅れましたが、良い作品でした。ありがとうございました。次も楽しみにしています。
ありれるれん
