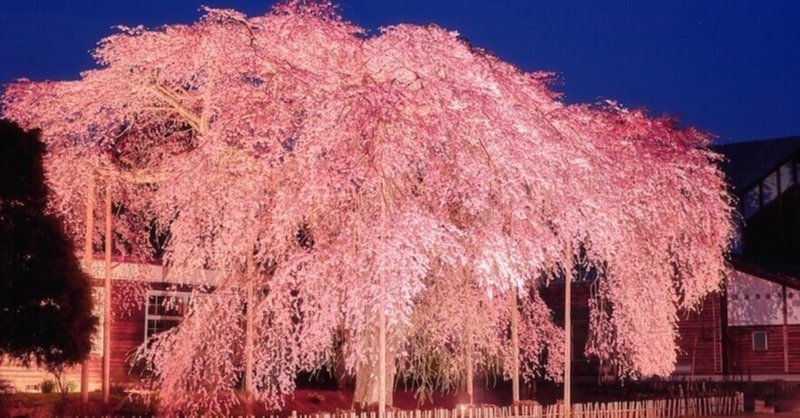
終活してたら学生時代の就活がよみがえった~44年前の採用合格通知書から
元気なうちに人生の最期に向けた準備をしておこうと、まず身の回りの書類の整理を思い立ちました。「終活」というほどではないのですが、生前整理で一歩を踏み出しました。
大学時代のマスコミ試験の資料を整理していたら、マスコミ以外で生まれ故郷に本社を置く鉄鋼商社の採用合格通知書が出てきました。江戸時代創業の老舗です。地元でホームセンターを経営し、東京では飲食店に進出するなど、消費者につながる業態もありました。
マスコミ志望だったため、その後、新聞社の内定をいただいたのでお断りすることになりました。40年以上も昔ですから、当時は「就活」などというコトバはなく、会社訪問とか就職活動とか言っていたように思います。
そして、いま「終活」です。
この終活という言葉は、「現代用語の基礎知識」にも登場し、すっかり一般に定着しています。内容まで深く考えたことはありませんでしたが、3月23日に私が所属するスタートアップ拠点、ナゴヤイノベーターズガレージ主催の「大人の学びなおし」(第3クール)の最終講義で終活の背景を知りました。
講師は佐藤啓介教授(上智大学大学院実践宗教学研究科)です。佐藤教授によると、終活の言葉が登場したのは2009年の週刊朝日「現代終活事情」だそうです。翌年、単行本になりました。副題は「わたしの葬式 自分のお墓」。つまり、当初は文字通りの人生の仕舞い方のマニュアル的なものだったようです。
佐藤教授によると終活をあつかった記事から読み取れる三つのキーワードがあるそうです。「自分らしさ」「美しく」「明るく」だそうです。
死生観を考えるといった深みに乏しく、いかに家族や他人に迷惑をかけず、エンディングノートなどに自分の希望を記し、死ぬまでは明るく生きようという傾向が強いようです。
私も書類の山を徐々に切り崩すだけではなく、自分なりの死生観を持ちたいものです。時代の変化とともに変わっていく葬式のやり方やお墓のことなど、あれこれと考えておいた方がいいのかもしれないと思い始めています。
「多死社会」です。1970年を境に自宅で亡くなる人と病院や施設で亡くなる人の数が逆転し、最近では8割が病院で最期を迎える時代です。
いろいろな葬送方法が出始めています。島根県には散骨できる島もあります。我がふるさとにも「アルプスが望める散骨場」といった新たな葬送の場ができても不思議ではないかもしれません。
願わくは花の下にて春死なんその如月の望月の頃
西行法師が詠んだ歌は、自分らしさや美しさが際立ち、西行自身、その後も長生きしています。いまでいうところの「終活」の走りだったのでしょうか。
見つかった採用合格通知書は、捨てずに残しています。この老舗企業はいま、ふるさとで介護施設も運営しています。これが役立つわけはありませんが、「願わくは…」。
(2022年3月24日)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
