
フィロソフィとかセオリーとか
こんにちは、こんばんは、Mariaです。
哲学者や心理学者の専門的知識や研究に裏付けされたお話とは別に、ご本人の経験や身の上をお話しする方がいらっしゃいますよね、私のようにw。
今日はそのことについて思ったことをお話しします。

私が心理学に興味を持ったのは、自分が幼少の頃から高校に入るまで、ところどころでいじめられたり、からかわれたりする対象になることが多かったので、いじめる人、いじめるターゲットを素早くキャッチする人のことが知りたい、と言うところがきっかけでした。中学生2年生でした。
さらに、
私は子供の時も、さてまた大人になっても「教師」と言う職業の人々に嫌われるキャラらしく、教師ぐるみの、又は教師扇動のいじめも経験しました。
そんな日々の中、大学で受けた児童心理、教育心理は、さまざまな実践の現場で自分にも、教えるという立場でも役立ちました。
そして、自分の苦い経験は、今でも止まることがなく生徒や外を歩いている普通の子どもたちにも起きていることに気づきました。
そして、大人はどのくらい、いじめや虐待の被害者、加害者、どっちでもない子たちの状況や彼らが見る背景に近づくことができるものなのか、を知人やブロガー方の育児経験談をテーマとし日々考えるようになりました。
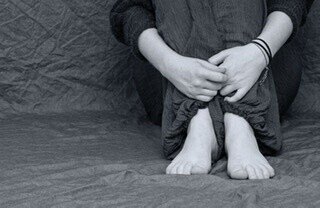
子供のいじめの根底には、孤独がある、と言うセオリーは昔からよく聞かれるものです。家庭で家族と交わり、日々を共にすることは生存において基本の基本です。
そして、小さい時から、自分が愛されているのか否かを判断するのは、親や兄姉そして友達や地域の人々が話しかける言葉とその頻度、と言うことも語られています。
この夏、私たち夫婦は、モンゴメリーの「赤毛のアン」を基に脚本が書かれたテレビシリーズを観ました。
私は、原作のファンで、アンシリーズは全て読み20代後半まで何度も繰り返し読みました。

ところが、アンのトラウマへの葛藤や彼女を取り巻く人々の日々の悩みやコンプレックスを如実に表現するこのテレビシリーズを観てショックを受けました。
原作を読んでいた頃は、孤児経験を持つアンの深層心理に目を向けることなく、ただモンゴメリーが描く、引き取られてからのアンの幸せ溢れる人生ばかりを愛でていたことに気づいたのです。
アンに出会った私は当時すでに孤独であり、過去のいじめをうまく昇華できない大人になっていました。
そして、心理学という鎧で自分を守っていたにもかかわらず、アンの苦悩や裏のアンの顔を描いたドラマには幸福感が見られないと不平を漏らし、アンはいつも大袈裟すぎて違和感すら感じたのでした。
当時の孤児院がどんなに劣悪環境下は想像できました。が、それゆえに対人関係に悩むアンや過剰に人に関わろうとする性癖を微塵も想像できず、原作以上に過剰なアンの妄想癖に辟易すら感じたのでした。
その時の私は完璧にアンを孤児院でいじめた側の心理になっていたのです。
あらためてこのドラマでの「赤毛のアン」に注目してから私はこう考えました。

人を作る要素には原因があり、原因による環境を気質や知識、知恵でどう選択するかで将来が決まるのだな、と。
どうしても避けて通れない悪影響や事故により、人生が人とは異なるものになることはよくあります。
良い選択をしてこなかった、無知なために選択を誤ったことを恥と感じ、心の中で無かったことにしようとする人ほど同じことを繰り返します。それしか方法を知らない、もしくは軌道修正は面倒なことだと考えるからです。
もし沼にハマったとして、前進しさらに沈みそうなところ、手をガシッと掴んでくれる人が現れたら?
その手を振り解くか、それとも助けに頼って沼から抜けようとするか。

沼にこれ以上いたら自分はどうなるか、という想像力、ここに気づけばおおかたどうすべきかが見えてくるのですが、この「想像力」を咄嗟に捻り出すことが一番難しいのではないか、とも考えます。
沼に落ちても気持ち良さを感じることだってありますから。。
哲学は、いろんな状況下を見据えてどう切り抜けるか、まるで知恵の輪を解いたり、迷路を抜け出そうとすることに似ているように見えます。
そして、考えて考えた末に出たなんらかの答えがその人のセオリーになっていくのだと感じます。

良い1日を。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
