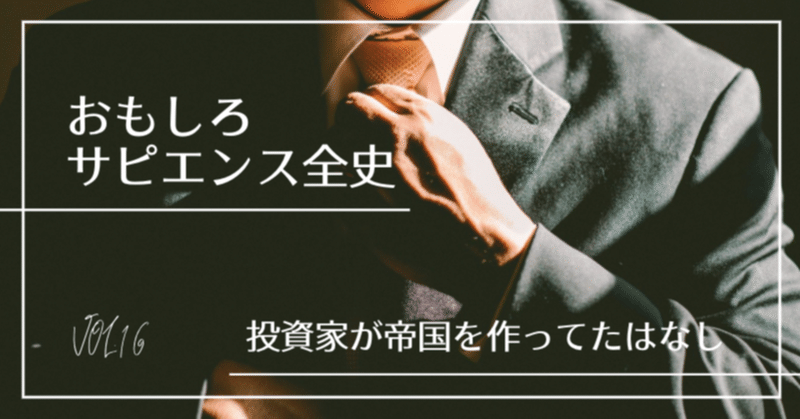
サピエンス全史をかる〜い感じでまとめてみました(第16章)
こんにちはー すっかり世界の歴史にハマったわたしです^^
歴史って、「うわ!こんな所でこれが繋がってるんだー!」みたいな感動だったり、バタフライエフェクト的な「もしこの時こうしなかったら...」という想像するとゾクゾクしちゃうところが好きです。
あと私はストレングスファインダーで「学習欲」「収集性」があります。
「もっと知りたい!もっと歴史の話くれ!(o'ω')ノ」とわたしの知識欲を煽ってくるのがサピエンス全史。どんどん勉強したくなるんですよね。
さて、前回は科学と帝国のずぶすぶな関係についてでしたが、
帝国と資本主義もやんごとなき関係でした。
内容が盛り沢山でまとめるのめっちゃ大変でした(;▽;)
第16章 拡大するパイという資本主義のマジック
『パイ』とは、お菓子のパイからきていますが、マーケティング業界では市場規模におけるシェアの事です。
パイといえばチェリーパイか市場のパイか。です(何が)
===============
意外とわかってない銀行の仕組み
===============
お金の動きと銀行残高のカラクリを、ベーカリー経営のマクドーナッツ夫人と、投資家のストーン氏、そしてストーン氏の銀行を例にストーリー形式で説明しています。

銀行は100万ドルの現金があれば1000万ドル貸付ができるのです。
私たちの銀行口座に記された金額の合計9割は、実際の紙幣や硬貨の形で銀行に収まっているわけではないということだ。
それゆえ、銀行の預金者全員が全額引き出したいと言い出したら、銀行は払い出せません。
あぁ、なんか改めて説明されると確かにそうだよね...(つД-`)
うすうす感じていても、銀行に毎月せっせとお給料を振り込む私ときたら、銀行を信用しているから、なんですね。

この信用という考え方と仕組みは、私たちの将来の資力が、現在の資力とは比べ物にならないくらい豊かになるという想定の上で成り立っています。
これは近代以降に登場した仕組みです。
===============
かつて、パイは拡大しなかった
===============
それまでは将来は現在よりも良くなるとは信じていなかったのであまり信用供与を行うことをしませんでした。
富の総量は限られていると信じられていたので、Aベーカリーが儲かればBパン屋が儲からなくて潰れるという発想だったのです。
パイの切り方はいろいろあっても、パイ全体が大きくなることはありえなかったということ。
大金を稼ぐことが悪だとみなされたのもそのためです。
キリスト教的道徳において、裕福な人はその悪行に対する贖罪のため、余った富は慈善事業に寄付しなければなりませんでした。

信用とは【明日のパイの大きさ】ー【今日のパイの大きさ】です。
パイの大きさが変わらないのなら信用が生まれる余地はなく、近代以前は融資をうけることはほとんど不可能でした。
こんな調子で新規事業の資金調達は困難で、もちろん経済は成長しないので人々も「経済は成長しないものだ」と思い込むという悪循環に陥っていったのです。
===============
金持ちは善だと言った『国富論』
===============
科学革命は「無知を認め、研究に投資することで物事が改善する」という進歩という考え方が登場した出来事でした。
政治家たちが研究に投資するのは、テクノロジーが何か解決してくれるという期待があったからです。これが14章のフィードバックループ。
この考え方が、経済にも取り入れられることにより、富の総量は増やせると人々は考えられるようになったのです。

この考えを世に広めたのは「経済学の父」と呼ばれるアダム・スミスです。
彼は『国富論』で個人起業家の利益が増すことが、全体の富の増加と繁栄の基本であると主張しました。
これは「自分の利益を増やしたい」という人間の利己的な衝動が全体の豊かさになるという、近代以前ではありえない斬新な考えでした。
スミスは経済は富と道徳は矛盾するという従来の考えを否定し、金持ちに対して天国の門を開いた。
経済成長の歯車を回す金持ちが、社会の中で最も慈悲深い存在だってこと。うん、私も金持ちになりたい。
しかし、勘違いしちゃいけないのは、利益は非生産的な活動に投資するのではなく、経済を拡大させるための再投資がマストだということです。
資本→生産に投資されるお金や資源
富→非生産的な活動に浪費される
近代以前は、何をしようと生産が大幅に増えることがないと信じられていたので、中世の貴族は収入を贅沢や戦争、慈善事業などに消費していました。
近代では貴族に代わって株式売買人や実業家などの新しいエリートたちが登場します。彼らは中世の貴族より金持ちですが、非生産的な消費への関心はずっと低いです。

いつも同じシンプルな服を着ていたスティーブ・ジョブズを思い出しました。
===============
経済成長は幸せを維持できるか?
===============
資本主義は単なる経済学説を超え、今や倫理体系にすらなっています。
正義や自由や幸福など、すべてが経済成長に左右される、いわば宗教のような存在になっているのです。
また、科学へ投資する際は、まず「経済成長を生み出すか否か?」が問われるように、近代科学の発展にも資本主義は多大な影響があります。
逆に近代科学の進歩なくして資本主義の信念を語ることもできません。
限りある資源のなか、近代で経済が飛躍的な成長を遂げたのは、科学者が価値ある発見をしてきたからです。
現在ではどうかといえば…
経済危機が経済の成長を止めてしまうのではないかという不安のなか、各国の政府や銀行は紙幣を濫発しています。
これは科学者や技術者がなんとか一発逆転ホームランをかましてくれるのではないかという期待によるものです。
果たして科学者たちは、政府がリーマンショック以降に発行してきた何兆ドルもの「見せかけの」お金を支えてくれるのでしょうか?ぞくっとしますね。

===============
商人たちが帝国をつくっていた
===============
18世紀後半までは、アジアが世界経済に大きな影響を持っていました。
そんなアジアでの資金調達といえば税金か略奪で、信用制度に負うところなどほとんどないと言ったところ。
一方、ヨーロッパでは、国王や将軍が商業的な思考をするようになり、資金調達は税金よりも信用を通じて行われるようになります。
それにつれて、商人や銀行家がエリート支配層となっていきます。
商人たちが築いた帝国は、国王や貴族たちが築いた帝国より圧倒的にうまくいっていました。
誰も税金は払いたくないが、投資なら喜んでする。
…というわけです。
起業家に投資することで国が繁栄したエピソードといえば、かの有名なコロンブスのはなしです。
最初のうちコロンブスは、東アジアへの新たな貿易ルートを開拓しようと各所に資金援助を求めますが、断られてしまいます。
散々苦労しましたがやっとのことでスペインのイザベル女王を説得して投資してもらったんですって。
コロンブスがアメリカ大陸を発見し、スペインも投資が大当たりして巨万の富を手に入れたわけですが、
100年後には君主や銀行家たちが探検の将来性に大きな信頼を寄せるようになります。
信用に基づく投資が新たな土地を発見し、それを植民地にすることで利益を生み、さらなる信用をゲットするという帝国資本主義の魔法の循環のできあがりです。

とはいえ、探検には危険がつきもの。帰ってこない探検家も多く、やはり冒険家への融資は投資家にとってリスキーなものでした。
そこで株式会社が大勢の投資家から資金を集めることで、ローリスクながらハイリターンを期待できるようになりました。
===============
オランダとスペインの信用の差
===============
16世紀、弱小国扱いだったオランダはグローバル巨大帝国スペインから独立を果たします。そればかりかスペイン・ポストガルに代わって海洋路の覇者となりヨーロッパで最も豊かな国になりました。
そんなオランダの成功の秘密は、そう。信用です。
オランダ人は当時急速に発展していたヨーロッパ金融制度の信用を勝ち取り、スペイン帝国よりたやすく軍事遠征の資金を調達できたのです。
具体的にオランダが行ったことは、
・貸付に対する期限内全額返済した
・個人の権利、特に私有財産の権利を保護した
上記2点でした。
個人とその財産を守らないような暴君的な国家に投資なんてできません。
それを証明するかのようにスペイン国王は約束を守らず、投資家たちから信用を損ね、敗北の道を辿ることとなります。
=================
「東インド会社」って色々あるんだね
=================
言うたら投資家が大金を投資したのは、スペイン王でもオランダ政府でもなく、株を売って資金を調達しようとしたオランダの株式会社だったんですけどもね。
こういった会社の株式取引のために、ヨーロッパの主要都市に証券取引所が設立されます。
オランダ東インド会社(VOC)は最古の株式会社と言われていますが、最終的にインドネシアを征服しました。
…「征服した」って「商業で天下取った」みたいなハラリの比喩かな?´д` ;
と思ったら、最初こそ商業的な目的でインドネシアに上陸した東インド会社ですが、関税を釣り上げる地元の支配者と戦うため、傭兵を雇って会戦や包囲戦を行っていたそうです。
近代前期では民間会社が帝国をぶち上げるのは普通のことだったそうです。現在でいうグローバル企業みたいな感覚ですよね。
ちなみにVOCが200年近く支配したインドネシアは1800年にオランダ政府が支配を引き継ぎ国の植民地にします。
ちなみにオランダ西インド会社(WIC)というのもあって、大西洋に進出しニューアムステルダムという入植地を建設しますが、イギリスに奪われニューヨークという名前になります。
ニューヨークのウォール街は、WICが入植地をイギリスや原住民の攻撃から守るために築かれた防壁が由来なんだとさ。
さてさて、そんな経済大国オランダはのちに、その地位をイギリスに奪われることになるのですが、
その際にイギリスはライバルのフランスにこれまた「金融界の信用」の差で圧勝します。
イギリスは南海泡沫事件、フランスはミシシッピバブルという同時期の財政危機の際の対応で差がついてしまったんですね。⬇️
フランスはミシシッピバブルがきっかけでフランス革命が起こります。
こうやって歴史の流れをみていると、資本主義と帝国は常につながりがあったことがよくわかります。
マルクスを始め、当時の社会を批判する人々が痛烈に皮肉を言っていたように、西洋の政府は資本主義の手下になり下がりつつあった。
政府が大資本の手下になり下がった例として、アヘン戦争があります。
イギリス東インド会社がアヘンを中国に輸出してぼろ儲けし、輸入を禁止した中国政府にイギリスは「自由貿易」という大義名分のもとに宣戦布告します。
すでにぼろぼろだった中国が敵うわけもなく、アヘン商人に有利な講和条約を結ぶこととなります。結果中国総人口の1割もの人々をシャブ漬けにするという、ただただ商人の利益のためだけの戦争でした。
商魂逞しいイギリスが戦争自体を商品としてしまったのがギリシア独立戦争でした。
オスマン帝国の支配下だったギリシアが反乱を起こした際に、ロンドンの資本家たちはギリシアに債権の発行を持ちかけます。
ギリシア軍が勝てば債権保有者がもうかるように仕組んだわけですが、トルコ軍が優勢になってしまい、このままだと大損してしまうイギリスは、多国籍艦隊でオスマン帝国を倒します。
ギリシアは独立を果たしますが、その後何十年も巨額の債務に苦しむことになります。
そんなことがあったとは。(ーдー;)イギリスこっわ。
===============
自由市場は正しいのか?
===============
資本と政治は影響し合うものだと大体わかりましたが、熱心な資本主義者は政治は市場に介入すべきではないと主張します。
政府は課税や規制を最低限にして、市場を自由にさせたほうがうまくいくという考え方です。
ですが、政治的な偏見がない市場などありえないので、この考えは無邪気すぎるとハラリは言います。
国が規制することで市場を守り信頼を確保できないと、信頼が消滅し不況になることはミシシッピバブルやリーマンショックで証明されているのです。

また、なんの抑制もない市場原理は労働者を守れず、奴隷制度などの悲劇を引き起こします。
奴隷貿易はどこの国家や政府も管理していない、純粋な営利事業であり、需要と供給の法則に則って自由市場が運営・出資していました。
18世紀を通じて、奴隷貿易への投資の2利回りは年率約6%だった。現代のコンサルタントなら誰もが、抜群に儲けが大きいと認めるところだろう。
利益と生産を増やすことに取り憑かれ、倫理的な考慮というリミッターを解除してしまい大惨事を起こすのが、自由市場資本主義の重大な欠点なのです。
今でこそ資本主義者の強欲ぶりは多少おさまっていますが、格差は以前として存在します。
経済のパイは大きくなっていますが、その分配はあまりに不平等です。グローバル経済は発展する一方で、農民や労働者はさらに多くのひとが飢えや貧困に苦しみ、1日働いても手にする食料は500年前の祖先より少ないのです。
農業革命のように近代成長も大掛かりな詐欺だった、ということになりかねない
第5章でサピエンスが小麦に翻弄される話がありました。
とはいえどんなに批判しても、私たちはもう資本主義なしでは生きていきません。
また、パイの分け前に多少の不平等はありますが、現代の生活水準は改善しているし、「楽園すぐそこ。もう少しの辛抱だ」と資本主義者は言います。
ほんとですかね??
第5章でも農耕民族は、前より一生懸命働けば、以前より良い暮らしができると信じてせっせと小麦の世話をしていましたよね。
現代人も資本主義に飼い慣らされちまったのかな(≡ε≡;)
次回は、地球の原材料とエネルギーは無限にあるのか?という話です。
サポートしていただけるととても嬉しいです! サポート金額は、しばらく眺めます。
