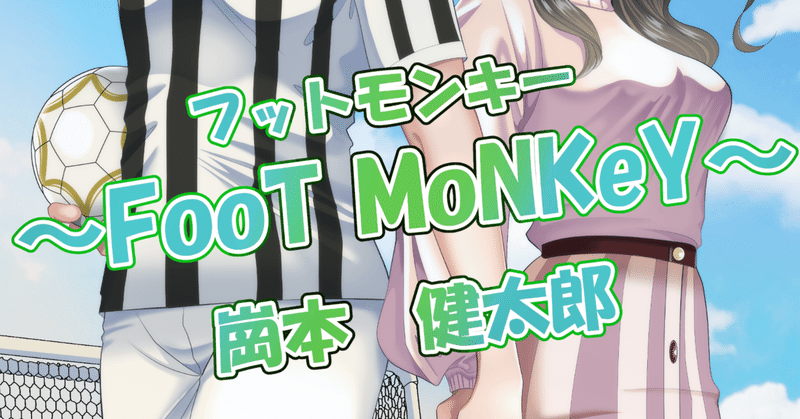
【漫画原作】フットモンキー ~ FooT MoNKeY ~ 第14回
#創作大賞2024 #漫画原作部門 #小説 #連載小説 #ラブコメ
静岡リーグ最終試合、県内最強チームである、静岡チャンピオンズとの対戦を前に、先日の気まずさから友達の家を転々としていた昴であったが、遂に瑞希との話し合いが持たれた。ここでは保がその責任感の強さを遺憾なく発揮し、丁寧に話を切り出した。
「お前ら本音で話し合ったのか?よそ行きの一張羅ばっか着てよ。そんなんで恋人って言えんのか?かっこ悪くても、自分のこと分かってもらおうって、相手のこと分かってあげようって、それが恋愛なんじゃねえのか?」悔しいけど、その通りだった。
「蓮はどう思う?」勘九郎が不意に話を振る。
「う~ん。僕は昴さんみたいに経験多くはないですけど、彼女の前では弱い所見せてると思いますよ。まあもともと、強い人ではないんですけどね」
それを聞いて、友助も素直な気持ちを吐露する。
「俺は昴さんが羨ましいですよ。選抜に行くかどうか決められて、行きたいと言えば、AFCにも出られて。人間は失って初めて、その大切さに気付くんです。贅沢ですよ、そんな人生」それを受けて、当の昴もそう感じていたようだ。
「そうだよな。一人っ子で、小さい頃から欲しい物はなんでも買ってもらえてさ。我儘言っても怒られる事なんかなかったし。それって案外不幸なことなのかもな。いつでも手に入るって、変わりはいくらでもあるって、そう思って、いろんなものを大事にして来なかったんだ。そのバチが今当たってんのかもな」
「そうですよ。人生どっかで、帳尻が合うようになってるんです。誰も楽に生きることなんてできないんですよ。今は自分自身を見つめ直す時期なんだと思います」
「そうだよな。きっと人間ってのは、苦労して手に入れるからこそ、大切にするんだ。簡単に手に入っちまうと、有難みってもんがねえんだ。だから感謝を忘れる。自業自得なんだよ」
「乗り越えましょうよ、昴さんならできる筈です。悲しい過去なら塗り替えましょう。都大会決勝でのあの出来事、辛いけど乗り越えられるはずです」
それを聞いた昴は少し遠い目をした後、ゆっくりと重い口を開いた。
「入ってた筈だった。自分なら絶対に決められた場面だった。けど、臆病風に吹かれて、自分かわいさに、チームを犠牲にしてしまったんだ」
「責められたことは、もういいんじゃないですか?悔やんでも何も始まりませんよ」
昴は小さく首を振った。
「誰も責めなかったよ。けど、逆にそれが辛かったんだ。なんであの時、自分を信じて勇気が出せなかったんだろうって。ずっと思い悩んで、あれから何点取っても、素直に喜べなくなったんだ。あの試合を最後にサッカーを引退した仲間もいる。大好きだったサッカーが、日に日に嫌いになりそうになるんだ」
「昴さんーー」
「けど何度辛いことがあっても、どんなに苦しくても、どうしても嫌いになれなかった。結局大切なものなんて、最初から分かり切ってたってのに」
昴はゆっくりと瑞希の方に歩み寄ると、真っ直ぐにその目を見つめた。
「俺、やっぱり瑞希が好きだ。いっぱい泣かせて、傷つけてしまったけど、瑞希のこと諦めきれないんだ」
「うん――私も」
「俺のこと許してくれるのか?」
「あれから考えたんだけど、私には昴くんしか居ないかなって。どれだけ泣いても、
やっぱり好きなんだなって。だけど、条件付きでね」
「――条件って?」
瑞希は昴の手を握って、しっかりとその目を見つめた。
「ねえ――プロになってよ」
「えっ!?」
「ここまで私を泣かせたんだから、もう一回カッコイイとこ見せてよ」
「瑞希――」
「私、信じてるよ。昴くんだったらできるって、またもう一回やれるって」
「――分かった。俺、絶対プロになってみせるよ!!」
「もう私のこと泣かさないでよ」
「ああ、約束する」
昴は男として、瑞希とのこの約束だけは、絶対に守り通そうと心に決めた。
それから一週間ほど経ったある日、瑞希と昴は休みが合ったことで愛犬ピクルスくんと遊んでいた。二人がピクルスと暮らし始めて、それなりの日数が経っていたのだが、瑞希には、ちょっとした悩みがあったようだ。
「なんか最近ピクルスが言うこと聞いてくれなくってさ」
「そうなの?俺的には、そんなことないと思うけどな」
「呼んでも来ないんだよねー。ピクルス~、おいで~」
そう言って瑞希が呼んだものの、ピクルスはそっぽを向いて無視してしまった。
「ほら~。私、嫌われちゃってるのかな?」
「なんで来ないんだろ?ピクルス~」
昴が呼ぶと、ピクルスはしっぽを振りながら、嬉しそうにに近づいてきた。
「ああっ、やっぱり~。嫌いなんだ~」
瑞希は少し不貞腐れたようにそう言った。
「信頼関係が築けてないんじゃね?ちょっと撫でてみて」
「う~ん、撫でさせてくれるかな~」
ピクルスは瑞希が触ろうとすると、背中や腹は撫でさせてくれるものの、頭や足は
嫌がって離れようとした。
「愛情が足りないのかな~」
瑞希はそう言うと、ゆっくりとピクルスの口に自分の口を近づけた。
「あっ、ストップ!無暗にキスとかは、しちゃダメだね。感染症とかでペットとの触れ合いは、リスクが伴うものだから、過度のスキンシップはご法度なんだ。これだけは、飼い始めた時に言っとけばよかったな」
動物から人へと感染する『ズーノーシス』は、口腔内の細菌が移るパスツレラ症、
排泄物から回虫の卵が経口感染するトキソカラ症、下痢が引き起されるアメーバ赤痢と犬を飼う時には、あくまでも人と動物であるということに留意しておくべきだ。
「そっかー。動物だもんね。これからは止めとこっと」
そう言うと瑞希は、側にあった固形のエサをピクルスにあげようとした。
「あっ、何もないのに食べさせちゃダメだよ!」
「えっ!?なんで。だってお腹空いてるんだよ」
「そうなんだけど、それだと言うことを聞かなくなっちゃうんだ」
「そうなんだ!なんでなの?」
「そうすると、自分が上だと思っちゃうからだね」
「上とか下とかなんか嫌だな。ペットは家族でしょ?」
「そうなんだけど、元は狼だからね。群れのボスには絶対服従ってのが犬なんだよ」
「そっかー、やっぱ詳しいんだね。それで、どうやって関係を構築するの?」
「主従関係を築くには、要求を受け入れないことと、飼い主の指示に従わせることだね」
「ふんふん、それでそれで?」
「あとは常に平常心で居ることかな。頼りになる所を見せないとね」
「へえ~っ、そうなんだー。そういうとこなのかな?昴くんて頼りになるもんね」
「そうかな?ありがとう、それは素直に嬉しいよ」
昴は少し照れたように、頭の後ろを掻いた。
「なあ、今日公園行かない?ピクルスとボール遊びしたいんだ」
「いいね、そうしよっか」
二人はさっそくピクルスを連れて、近所の公園へ行って芝生の上で遊び始めた。
「ここでも何か気を付けることってあるの?」
「あるよ!ここでのポイントは必ず犬を勝たせずに最後にボールを取り上げて終わるってこと。あとは指示を出す時のアイコンタクトと、マズルコントロールかな」
「アイコンタクトか~。マズルコントロールってどうやるの?」
「口を手で覆うようにするんだ。信頼関係を築けてるかのチェックだね」
そう言うと昴は、ピクルスの目をじっと見つめて口を抑えた。
「ほ~ら、ピクルス~」
昴が抱えて転がすと、ピクルスは嬉しそうにお腹を上に向け無防備な体勢になった。
「おお~!私にはそんな恰好することなかったのに」
「要は接し方なんだよ。原理が理解できれば従うようになるよ」
女の子と一緒だよと言おうかとも思ったが、余計なことは言わないことにした。
「こんなにも違うものなんだね」
「これができてないと『アルファシンドローム』って言って、犬の方が上だと思って
言うことを聞かなくなっちゃうんだ。接し方を学ぶのは人でも犬でも大事なんだよ」
それから二人は家に帰ると一緒に夕飯を作り、ピクルスより先に食事を済ませた。
「必ず飼い主の方が先に食べること。リーダーであることを理解させるんだ」
そう言うと昴はお座りと言って、ピクルスを撫でた後でエサを与えた。
「あと、チョコとかタマネギは、中毒症状を引き起こすから食べさせちゃダメなんだ」
「そっか。そう言えばレーズンとか、キシリトールもダメって聞いたことある」
「そうそう。買う前に、食べられるかどうかの確認は必須だね」
「毎日の歯磨きはどうするの?」
「歯磨きシートとかガムを使うといいかな。ガムは硬すぎなくて繊維質で嗜好性が高いものでないとね。上顎の奥の、前から4本目の歯を狙って噛ませるのがコツだね」
「そうなんだ~。なんか昴くん、博識じゃん」
「まあ結構勉強したからね。じゃちょっと上級編行ってみようか。ピクルス、伏せ!」
ピクルスは昴の指示を受けると、それから10分ほどその姿勢を保ち続けた。
「ちょっと長いんじゃない?辛くないのかなピクルス」
「犬はコレ大丈夫なものなんだ。もう10分したらOKだね」
それからピクルスは伏せの姿勢で待ち、昴の合図で姿勢を解き、ご褒美を貰った。
「おお~っ。すごい、完璧だね」
「あとは、1日1回コレを続ければ大丈夫だね。簡単だろ?」
「うん。接し方が分かると、案外悩むほどでもないのかもしれないね」
その後で二人は一緒に風呂に入って、犬用のシャンプーでピクルスを洗ってあげた。
「お風呂から上がったら、耳に入った水は、綿棒かタオルで出してあげるようにして、ドライヤーを当てる時には、温風と冷風を交互に当てるんだ。自然乾燥だと湿気を好むマラセチア菌が繁殖して、皮膚の痒みとか臭いの原因になるから注意しないとね」
「よくそんなに知ってるね。どうやって調べたの?」
「トリマーの友達から習ったんだ。やっぱ人から習った方が早いよね。あとビーグルはシングルコートだから、ドライングする時には、特に注意しないといけないな」
「おおっ!なんか専門的だね。他にはどんな犬が居るの?」
「オーバーコートだけなのがシングルコートの犬で、アンダーコートと両方あるのが
ダブルコートの犬だね。春と秋に新しい毛に生え変わる換毛期があるのが特徴だよ」
「それも全然知らなかったな。ねえ、ノートに書いてよ!」
「え~っ。めんどくさいな~」
「いいじゃん。お願い、ねっ」
そう言って顔の前で手を合わせる瑞希を見て、昴は観念したようだ。
「分かったよ。今回だけだかんな」
「やったー。流石は昴くん」
それから二人は歯磨きをしてベッドに行き、寝る準備を始めた。
「は~い、一緒に寝ましょうね~」
「あっ、それもダメだよ」
昴は瑞希がピクルスを布団に引き入れようとしたので、慌てて止めに入った。
「なんで?ちゃんとお風呂に入ってキレイにしたんだからいいじゃん!」
「それだと同等と見做しちゃうんだ。辛いかもしれないけど、ハウスに寝かせよう」
「う~ん、そっかー。分かった、そうするね。他にダメなことってある?」
「あとはソファで寝かすのもダメだね。これも同じ理由で寝ちゃったら優しく起こして、ハウスに移動させてあげた方がいいな。仔犬の頃にしっかり躾とかないとね」
「そうなんだ~。流石は飼ってただけのことはあるね」
「だろ?最初が肝心なんだよな、犬って」
一般的に犬を飼っている男の方がモテることが多いのは、この関係性の構築ができているからだと言える。女の子は自分より下だと認識した男とは『絶対に』付き合わないものなので、不用意に遠慮したり、下手に出たりするのは今すぐ止めるべきである。
それから昴は棚を見て思い出したのか、自らの行為を振り返って愚痴ってみせた。
「あああ~捨てなけりゃ良かったな~トロフィー。やっぱ思い入れあったんだよな~」
「それなんだけど――」瑞希は少し遠慮がちに話し始めた。
「実は後でそう言い出すかもしれないと思って、捨てずに取っといたんだ」
「えっ、マジで!?ありがとう!!さすがは瑞希ちゃん、頼りになるわ~」
「ふふっ。そうでしょ~」
この頃になると、二人は以前までには信じられないほど、穏やかになっていた。もうつまらないことでは喧嘩しない。そういった『信頼』が二人の間には存在していた。
12月23日のチャンピオンズとの試合の日、アップをしていた昴は目頭が熱くなる思いであった。『継続は力なり』昴は細々とではあるが、今日までサッカーを辞めずに続けてきてよかったと思えた。もし途中で辞めてしまっていたら、もしサッカーが嫌いになってしまっていたら、またこうして三人でプレーすることはできなかっただろう。
そう思うと感謝の念でいっぱいだった。
「頼むぞ勘九郎」
「ああ、任せとけよ。俺はもう、あの頃とは違うんだ」
そう言った勘九郎は、やけに自信ありげな表情を見せた。
静岡チャンピオンズは緑色のユニフォームが精粋なチームで、とにかく気性が荒く、キャプテンの林でなければこの陽気な問題児軍団を纏めることはできなかった。人型のディフェンダーパネルを用いたフリーキックや、マーカーコーンを並べてのドリブル等道具を使った練習を好み、運動神経はいいが、泳ぎが嫌いで体の固い選手が多い。
試合が開始されると、その洗練されたスタイルに昴から思わず本音が漏れる。
「やっぱきついな――」
静岡リーグは今回で1シーズン目で歴史が浅く、まだ発展途上であった。そのため、この『ゾーンディフェンス』を敷いてくるチームはチャンピオンズ以外になかった。
試合前からに練習して想定していたとは言え、不慣れなスタイルに、バランサーズは四苦八苦していた。だが、この状況を打開しようと、勘九郎が得意のフェイクからの
突破でチャンピオンズゴールに猛威を振るう。
勘九郎のこの『マシューズ』は、足首のスナップを利かせてボールの横側を蹴って、体のイン、アウトの順に転がして抜き去るという技で、初代バロンドールを獲得した
スタンリー・マシューズが使用していた技である。
「おおっ。マシューズ!!しっかしすげえな。キレっキレだな」
華麗なフェイクを目の当たりにした林は嬉しそうにそう言った。当の勘九郎は、アラの桜木を抜き去ってシュートを放つが、これは惜しくも枠を外れてしまった。そして、強烈なインパクトを残した攻撃に、チャンピオンズサイドは少々揉めている。
「おい、しっかり守れよ桜木」
「なんだ、梅津?お前の範囲だろ?」
「喧嘩すんなって」
「お前もだよ。松崎」
「なんだと、コラ」
「うるせえ、オラ」
“なんであんな仲悪りいのに、攻守ともにバッチリ連携とれてんだよ”
友助はこの三人の不思議な関係性に、疑問を抱かずにはいられなかった。
暫く聞いていると、しびれを切らしたように、林が会話に加わった。
「おい、外されたいのか?三人とも」
「い、いえ」
「そりゃねえっすよ、林さん」
「すません、ちゃんとやります」
“流石はボス。見事なマウンティングだな”
友助は先程まであれほどモメていた三人が、林の鶴の一声で難なくその場が収まったことに対して感服した。そしてこのことで引き締まったチャンピオンズは、林と桜木でディフェンスをかき回し、一段下げてフィクソの梅津が出した絶妙のクロスに対して、ピヴォの松崎がヘッドで合わせ鮮やかに先制点を彩った。これには林もご満悦だ。
「いいぞ、二人とも。この調子でガンガン行こうぜ!」
「はい、ありがとうございます」
「よっしゃ!俄然やる気になったぜ」
バランサーズにとっては手痛い失点となったが、前年に比べ友助、勘九郎を要する
今のチームにとっては、焦りを感じるほどのことではなくなっていた。そしてここで
昴と勘九郎は、アイコンタクトで往年のスクリーンを試みる。勘九郎が、梅津と昴との間に体を入れ、フリーになった昴が友助からボール受けてミドルシュートを放った。
ドライブが掛かったそのシュートはゴレイロ森川の手に当たるが、そのまますり抜け、見事チャンピオンズゴールへと吸い込まれて行った。点が決まると昴、友助、勘九郎の三人は一ヶ所に集まって喜びを爆発させる。
「流石だな勘九郎、まだ覚えてたとは」
「まあな。これは現役の時によくやってたからな」
「凄くやりやすかったですよ。初めてやったとは思えないくらい」
このスクリーンは『エントラリーニャ』と呼ばれる体を使わないスクリーンのことで、ディフェンスの間に入ることで受け渡しミスを誘発するプレーである。この連携プレーの輝きは、今後のバランサーズの活躍を予感させるものでもあった。
そしてこの同点弾によって奮起したチャンピオンズが猛攻を仕掛けて来たのに対し、バランサーズは、ここでも冷静に対処できていた。強固なディフェンスを崩せずに業を煮やした梅津が、撃たされるような形で放ったシュートを蓮が危なげなく弾き返す。
こぼれ球を拾った友助が、ルーレットで即座に桜木を躱してフィードを出し、これを勘九郎が流し込んで得点とした。
確かな手応えを感じたバランサーズの選手たちではあったが、チャンピオンズは全く動じることなく、林の個人技で、強引にでもチャンスを演出する。放たれたシュートはゴールへと突き刺さり、あっさり2対2の同点とされてしまった。なんとも惜しい場面であるが、林のダブルタッチを前に、流石の勘九郎も不覚を取ってしまった。
その後、試合は動くことなく前半を終え、先程の興奮冷めやらぬままハーフタイムに入ったバランサーズは、保、昴、友助、勘九郎、蓮、瑞希、莉子、美奈が、それぞれの思いを吐露した。
「いいぞみんな同点なら上出来だ。チャンピオンズの不敗神話を塗り替えてやろう」
「そうだよね。俺たちここまでやって来れたんだ。絶対に勝とうぜ!」
「あと一息ですね。勝ってこれまでのチームの嫌な流れを断ち切りましょう!」
「練習の時から感じていたが、連携の取れたいいチームだ。これは行けるかもな」
「ぼ「いつもより安心して守れてますよ。盤石な体制ですね」
「いい感じで形になってるよね。このまま後半まで乗り切ろう!」
「前半2本多くシュートしてるよ!同点でも押してるのは断然ウチの方だよね」
「勝てない相手じゃないよね。今の私たちなら、なんか行ける気がする!」
一方のチャンピオンズは、和気藹々と話すバランサーズの選手たちに対し、一ヶ所に固まって終始、林が話すのを全員が一方的に聞いているという展開であった。
「これは生き残った者が勝ちの生存競争だ。抗うことはできない、何人(なんぴと)たりともね」
「勝てるかどうかは運じゃない。これまでどれほど歯を食いしばって来たかだ」
「経験に勝る方が栄光を掴むんだ。俺たちには培ってきた確かな実績がある」
「戦なんだ。殺す気で行くぞ。甘ったれてるヤツは今すぐピッチから去れ」
一見非効率にも思える行為だが、チャンピオンズはこの方式で、今期の静岡リーグの試合を『ただの一度も』落としたことはないのであった。
後半に入ってもバランサーズは乗りに乗っており、ゾーンディフェンスに対し切り札にしていた『オーバーロード』での対策を講じた。これは、片側のエリアに人数を集中させ、寄せた反対側に攻撃を振ることで打開するという戦術だ。
そして、ディフェンスの統率は保に任せて、昴、友助、勘九郎でメッシ、スアレス、ネイマールのMSNの如くシュートを乱発して行く。チャンピオンズは、そんな彼らを前に形振り構っていられないといった様子であり、最終戦でのプレッシャーによって、本来の荒々しさを取り戻しつつあった。
そんな中で一際やる気をみせるプレーヤーが居た。チャンピオンズゴレイロの森川である。彼はボールを持つと、積極的に上がってきてプレッシャーをかけ、5対4の数的有利の状況を作るプレーヤーであった。
このパワープレーの後にでもゾーンで引くことができる為、一見ブレイクが頻発するように予想されるのだが、チャンピオンズはわりと余裕を持って、後半のゴールを守り切っているのであった。そうやって時折チャンピオンズは、執拗にバランサーズゴールを脅かそうと猛威を振るっていた。その狡猾さに、友助は特にこれを警戒していた。
“!!“
ここで森川が撃った4度目のシュートを蓮が跳ね返し、それを更に桜木が蹴り込んで得点となった。綺麗にゴールが決まりはしたのだが、なぜか多少の違和感を覚えるようなプレーであった。それを見ていた昴は、溜まりかねたのか声を荒げる。
「おい審判!今ユニ引いてたじゃねえか。なんで見てないんだよ!」
指摘を受けた審判は、困ったようにたじろいでいたが、梅津が友助のユニフォームを引っぱったかどうかは既に確認のしようがないため、流すしかなかったようだ。
だがそんな事は物ともせず、勘九郎はマシューズからの切り返しで緩徐にフィードを出し長めのクロスを送った。友助はこれをワントラップで華麗に切り返してみせ、焦る桜木を鷹揚に躱すと、豪快なミドルをチャンピオンズゴールに叩き込んだ。
「いいぞ、友助!いつでも連動してくれてるから、パスが出しやすいぜ」
「ありがとうございます。勘九郎さんのパスは受けやすくて、愛がありますからね」
この二人は実戦で共闘するのは初めてだが、その実力から長年連れ添った夫婦のような理解度であった。そんな中、チャンピオンズのポニョ柳は、桜木と交代で、ピッチへ立つと、一つの決心を胸に秘めていたのであった。緊張しながらも、ゆっくりと友助に忍び寄ると、猛烈に体をぶつけて来た。
「イテっ。なんだよ?最終戦だからって、ファウルでもなんでもお構いなしかよ」
こういったプレーは『マランダージ』と言えるものであり、その意味合いとしては、乱暴なプレーを指し、悪質な反則と訳されるようなものでもあった。
この暴挙で、友助が押しのけられてスペースができた所に、透かさず林が走り込んでボールを受け、強烈なミドルシュートを放ってきた。あわや得点かと思われたが、この挙動を見抜いていた蓮が、間一髪の所で弾いて見せ、なんとか事なきを得た。
このファインセーブで、首の皮一枚繋がったバランサーズは、ここから一気に士気を高めることができ、流れを引き寄せて行った。そして試合終盤、友助がルーレットから繰り出したアーリークロスに、勘九郎が合わせて華麗にゴールに流し込み5対4とした。「ナイス、勘九郎!!」この値千金の得点に一番喜んでいたのは中だった。
その後バランサーズの選手たちはベンチ内外で盛り上がり、完全に優位に立っているにも関わらず、全く攻撃の手を緩めなかった。
後半ラスト4分。歓喜に湧くバランサーズの選手たちとは対照的に、落胆の色を隠し切れないといったチャンピオンズの選手たちは、焦りを募らせながらも懸命にプレーを続けて行った。だが無情にも時間は流れ続け、遂にはタイムアップとなった。
試合後に林は茫然自失となり、周りの声にも全く応じていなかった。
昴はAFCで共に戦った仲間であるため心配ではあったものの、敗者となった相手に情けを掛けるのはプライドの高い林の心を逆に傷つけてしまうのではないかと考えて、そっとしておくことにした。バランサーズの選手たちは、あの静岡最強とされていた
チャンピオンズに勝利し、東海大会出場の切符を手にしたことに対し喜びを爆発させる。
そしてここで勘九郎は、約束を忘れてはいなかったとばかりに切り出した。
「これで昴は辞めなくてよくなったわけだ。だが、約束はちゃんと果たさないとな」
その言葉を受けてバランサーズの選手たちは、誰を殴るかの指定は特にないのだが、マネージャーも含め、全員で昴を一発ずつ殴って行った。殆どが形式的に殴る素振りを見せるというものだったが、友助と保だけはわりと本気で殴っているように感じられた。一通り終わった後、保は殴ることを渋っている蓮に対して、行動を促した。
「ほら、お前も殴っとけって」
「えっ!?でも俺は別に何の恨みもないんですけど――」
「いいから、せっかくなんだからよ」
「う~ん、じゃあ一発だけ」
そう言って繰り出されたパンチは思いのほか威力があり、当たり所が悪かったのか『ゴキッ』という鈍い音を立てた。これが済んだところで、勘九郎が話し始める。
「どうだ昴、身に染みたろ?」
「ああ、これでやっと分かったよ。俺は『身勝手』だった」
「で、お前は誰を殴るんだ?」
勘九郎にそう言われると、昴は無言で自分の頬を叩いた。
「よし、これで全員が殴り終わったな。どうだ、結構痛かったろ?」
「そうだね。正直、蓮のやつが一番痛かったけどな」
「はは、意外と恨みを買ってるのかもな」
勘九郎にそう言われ、蓮は慌てて釈明する。
「い、いえ。そんなことはーー」
「分かってるって、冗談だろ」
昴がそう言うと、昔のチームの雰囲気を取り戻したように小さな笑いが起こった。
チャンピオンズ戦が終わって一週間ほど経ったある日、バランサーズの選手たちが
東海大会に向けて練習を行っていた所、莉子が瑞希に悩みを打ち明けていた。
「最近、新之助くんの暴力が酷くなってきてさー」
「ああ、あの問題児の彼氏ね。ほんと困ったもんだよね」
すると側でそれを聞いていた勘九郎が、少し表情を変えると二人に話し掛けて来た。
「莉子、その彼氏ってもしかして、荒木 新之助か?」
「そうだけど、なんで苗字知ってんの?」
勘九郎の言葉に、莉子は少し怪訝な表情を浮かべた。
「俺の苗字、荒木って言うんだ」
「えっーー!?あ、そう言えば、ちょっと雰囲気が違うけど似てるようなーー」
「そっか、莉子の彼氏って勘九郎くんの弟だったんだ!」
「莉子。よかったらその話、あとで詳しく聞かせてくれないか」
「あ、うん。分かった。今日のこのミーティングが終わったらね」
勘九郎はやはり気になったのだろう。先程の話を確認したい旨を莉子に伝える。
一方で他の選手たちは、保が持って来た、静岡リーグの結果に夢中になっていた。
「最終的なランキングは勝ち点ごとにチャンピオンズが21点で優勝、ウチが17点で準優勝、テクニシャンズが15点で3位、スコアラーズが14点で4位、ブロッカーズが11点で5位、ソウルフラーズが10点で6位、フェインターズが6点で7位か~、ランナーズが5点で8位、ブレイカーズが3点で9位と。それにしても勿体ねえよな。ランナーズはフルでリーグに出てたら、上位に入ってたかもしんねえってのによ」
その隣で蓮が、ベスト5が書いてあるページを眺めていた。
「ピヴォがランナーズの金さんで、アラがフェインターズの暇さんと、ソウルフラーズの凝さん、フィクソがテクニシャンズの港さんで、ゴレイロがブロッカーズの硯さん、ポニョが――中さん!で、得点王がスコアラーズの焔さんと、それから、ーー栄えある
MVPに輝いたのが、チャンピオンズの林さんか。まあ、これなら妥当な内訳だな」
それを聞いて、友助が会話に割って入る。
「まあ俺の見立てでは、凝さんより勘九郎さんの方が上手いっすけどね」
「そう言ってもらえると嬉しいよ、仲間から認められるのは名誉なことだしな」
勘九郎は素直に嬉しそうだ。それを聞いて気を遣ってか、保が話し始める。
「おい昴。また拗ねてんじゃねーだろうな?もしリーグ序盤からジンガがあったらとかそんなこと」
「もう、そんなことはねーよ。俺が選ばれなかったのは、チームに貢献出来てなかったからだ。一人相撲でプレーしてた俺には、ベスト5に選ばれる資格なんてねーよ。そうだろ、勘九郎?」
「昴、お前――大人になったな。嬉しいよ。それでこそ俺がこのチームに入った甲斐がある」
「勘九郎――ありがとう」
思わず泣き出してしまった昴を冷かしながらも、バランサーズの選手たちもそれぞれ涙目になっていた。
