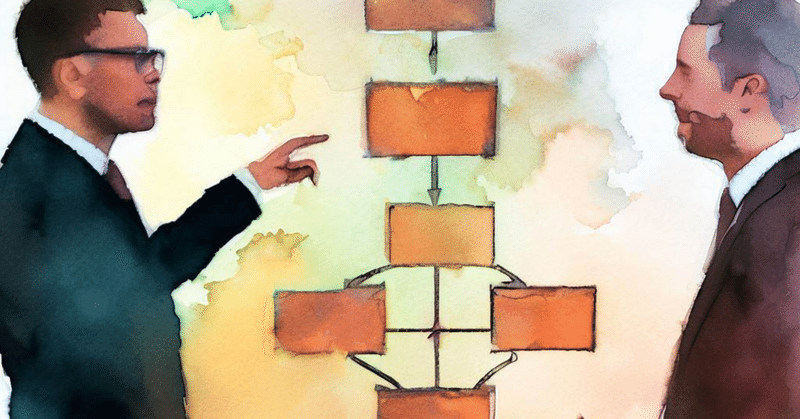
上司の7割はダメ上司
このnoteをご覧になっているのが管理職の方とは限らないというご指摘を受け、直近、管理職、経営目線のnoteが多かったことを反省し、ちょっと別の観点のことを記載します。
このnoteに記載していることは、あちこちで聞いたり読んだりした言葉が起点になっていることが多いのですが、これは私のオリジナルの言葉になります。「上司の7割はダメ上司」、自分で言うのもなんですが下品な言葉です 苦笑。はっきりいって、私以外の人は思っていても言わないと思います。
気骨の人事!!とか勇ましいことを書いた次が、これかい、という方もいらっしゃるかもしれませんが、これは現実の話。当たり前の話ですが、人材には限りがあり、どこに誰をはめるのか、人事を考える側は大変頭を悩ませるわけです。すべてができる立派な人がいないわけではないですが、そんなのはごく一握り、Aさんはこれができるけど、ここがダメ、Bさんはここまではいけるが、この点に課題がある、、、そんなことを思いながら、誰を昇格させようかとか、なんやかんやと悩んでいるわけです。
戦略的に作ることになったポジションがあったり、定年を含めて退職や異動で空席になったポジションは埋めていかないといけない。その時には、上記のようにいろいろと頭を悩ませながら、あーでもない、こーでもない、って体制を決めていきます。部下受けがいい人事もあれば、上司受けがいい人事もある、いろいろな要素があります。まだちょっと足りないところがあるけど、うまく伸ばしていこうという抜擢人事もあり得ます。経験こそ人を育てる最大の栄養源でもありますから。あるいは、今はこれがベストだけど1年これを経験させた後のCさんだったら、こうはめられるはず、みたいなこともあります。この時間をかけた育成、組織の拡充というのは組織運営の醍醐味でもありますね。
私にとっては、こうした検討の結果が、組織体制です。ある意味、今いる人員で現状のビジネスを考えたときに最適(と思われる)体制、ということです。だから「こんなにもダメなところがあるのに、なぜこんな人が管理職になっているのか」と思われるのは当たり前です。課題があるのはわかっていてもその人に託していく、そういう判断でやっているわけなので、「カンペキな上司ではないと思うけど許してね」という言い訳の言葉が冒頭の「上司の7割は、、、」です。もちろん、カンペキな上司ではない上司の中に、私も入ると思っていますけど。
逆に人事を考えなければいけない側は、いくつか考えていかないといけないことがあります。まずは、時間軸。いつまでにこの人にこういう経験をさせて、次の段階でこうする、とか時間軸は頭に置いておく必要があります。変更は当然発生するにしても、半年後、1年後、さらにその先の人事構想はあるべきです。
そして、抜擢。上述のように機会を与えることで伸びる人材というのは必ずいます。あるいは、元々できる人材を若いからという理由だけで権限を与えないのはもったいないことと言えるかもしれません。
最後に妥協。冒頭の言葉に戻りますが、全てを兼ね備えた人材がふんだんにいることはありません。その中で、最善を考え、いくつもの妥協を経て人事はできていきます。そこは苦いものとして飲み込むしかないということです。7割の上司はダメ上司、、、、ってホントひどい言葉ですけど。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
