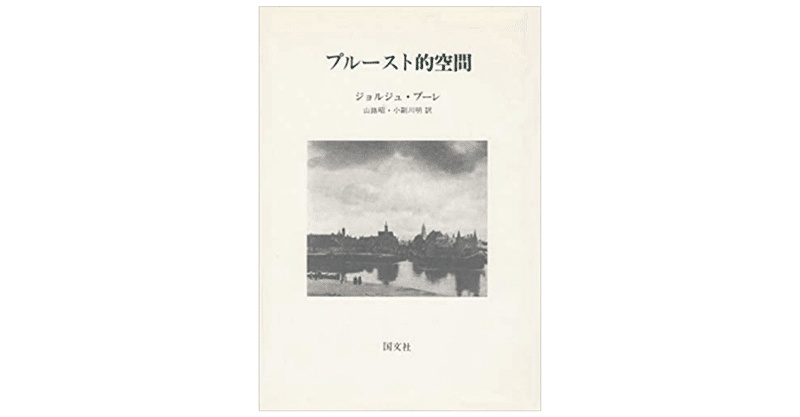
ベルグソンの時間論からライプニッツの空間論への『失われた時を求めて』
『プルースト的空間』ジョルジュ・プーレ , 山路 昭, 小副川 明 (翻訳)1963年
古本市で、ジョルジュ・ブーレ『プルースト的空間』という本を手に入れた。プーレって誰?となるが50,60年代に活躍したフランスの文芸批評家(ジュネーブ派とか)。今では古くなっているのか、よくわからないけど、おもしろかった。
プルースト的空間
それまでのベルグソンの時間論解釈からライプニッツの空間論解釈。『失われた時を求めて』の登場人物が場所を背景として描かれていると。アルベルチーヌだったら、バルベックの海辺。だからパリで出会うと以前のように魅力を感じないで戸惑う。スキー場でナンパされて東京に戻ったらイモ兄ちゃんだったというのと同じなのかも。
それで貴族は場所の名前とつながっているので存在感(居場所がある)があるのだが、語り手はそういう場所を持たない。だから観念があっち行ったりこっち行ったり彷徨うということ。自我が彷徨い自己が出来ていない。
語り手の居場所のなさというのが滑稽に描かれるのは、貴族もそうなのだが見栄にある。その場所場所で己を大きく見せようと背伸びしつつスノッブに振る舞う。語り手の記憶は、ある部分絵画や芸術作品に負っている。それは彼の背景としてステンドグラスのように併置されたモナドということらしい。旅の移動は空白で幕間だとすればある部分映画的なのかもしれない。走馬灯のような記憶なのだが時間論として見るのではなく、空間論としてそのモナドを開示していく創造力なのかもしれない。ワンシーン(エピソード)がセット(芸術作品)によって形作られるみたいな。
補遺──ベルグソン
そもそもベルグソンの時間論もよくわからないのだけど補遺にベルグソンについて語っている。死ぬ間際に一気に過去を回想してしまう瀕死者の生還話について。よく聞く話だけど夢か現か、文学者のテーマとしても多い。
夢想者、芸術家、瞑想者はすべて、多かれ少なかれ瀕死者と同じように、現実から解脱した《幻視者》である。かれらは、現世や彼ら自身にたいして、行動する人間の狭い眼を注ぐことはせずに、「事物と(かれらの精神)をその本源的な純粋性のうちに認知する」のであり、
すなわち、これが純粋持続と呼ばれる意識であるから、瀕死者の幻像は欠如を埋めるための想像力として受動的態度ととる。だから自我がライプニッツのモナドのように分散する場を自己によってまとめる意思の力が生ある人間として行動をせしめる。直感として生の躍動(受動の精神ではなく行動の身体)として動き始める。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
