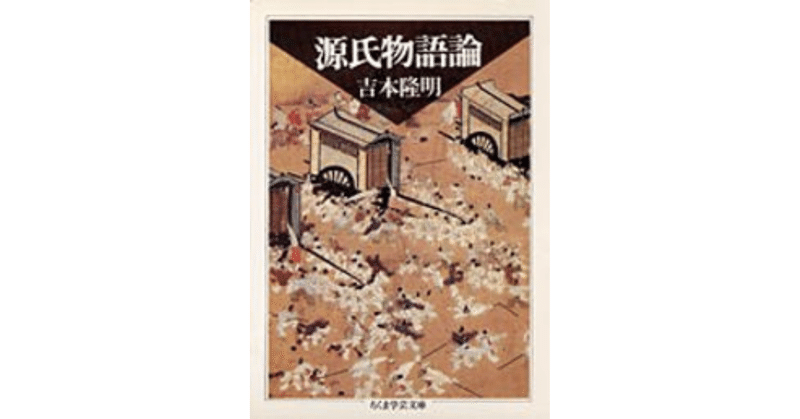
『源氏物語』の物の怪は「愛の亡霊」なのか?
『源氏物語論』吉本隆明
『源氏物語』をひとつの小説作品として自由に読みとくと、その世界はどのように立ち現れてくるのか。作品をつらぬく無意識としての〈自然〉、霊異に対する人々の心のありよう、また歴史物語『大鏡』や『栄花物語』とのトポロジカルな同型性に着目し、作品の構造と深層を浮き彫りにする創見と洞察にみちた画期的論考。
第1部 母型論
第2部 異和論
第3部 厭離論
第4部 環界論
附録 わが『源氏』
『源氏物語』の解説本というよりも吉本隆明が『源氏物語』を通して文学をどう読むのかという本であり、あとがきに古典の学者に細かいところを突かれていた。それは吉本が、原典主義者でもなく、また登場人物のモデル探しもしないというように、あくまでも『源氏物語』は文学として読むのであり、『源氏物語』を語りながら彼は文学を語っているのだ。
例えば『源氏物語』を勧めるのなら手に入り安い与謝野源氏が誤訳もあるがいいという。それは与謝野源氏が彼女の『源氏物語』を構築出来ているからだと思うのだ。ウェイリー版でも橋本治版でも『源氏物語』は文学として楽しめる。それは彼らの中に『源氏物語』という文学世界(空間)が構築出来ているからだ。
それで吉本源氏はどんな世界だろうとかというと、藤壺が影響を与える昼の世界と六条御息所が影響を与える夜の世界に分類する。その原型として桐壺の更衣が光源氏が記憶にない母というイメージで存在しているのだ。そこに母性という光源氏が手にしたい世界があるのだ。しかし、それは母ではあるが愛人としての近親相姦であり、それが天皇の妻であるからなおさらタブーである行為なのだ。
近親相姦的愛の物語は神話的なのか、藤壺の物語はそうなのだが(第1部 母型論は藤壺が昼の母なら、六条御息所は夜の母として光源氏と関係する)、(第2部 異和論)次第に現実的な愛の物語になっていく。それは様々な女の物語なのだが、その変化は作者である紫式部の宮廷内の変化であるという。
しかし光源氏も女たちも年を取ることで現実の欲望世界から(第3部 厭離論)最終的にはそれらから解脱していこうとする仏教思想に傾いていく。当時の女性は愛人としての役割が終わったら出家するしか無かった。あとは末摘花のように待つ女に徹するか?
(第4部 環界論)は影響関係にある『栄花物語』との比較の一覧が面白い。それは現実の様々なモデルがいただろうが、『源氏物語』はその一部でしかありえず、その雅な世界は紫式部の創作なのだ。うるさい古典学者が『栄花物語』の筋が違うと言ってきたが、そこを綿密にあきらかにしない。また『源氏物語』の訳は吉本自身が訳しているのだが、口語と文語が混じっているとか、そういう繊細な解釈は『源氏物語』おたくがやればいいのであって、吉本はまず文学を楽しんでいるのだ。
『源氏物語』も『栄花物語』も文学として吉本の文学空間の中で構築されるのだ。そこに吉本が学んできた文学というもの、それは古典文学だけではないもので構築されているのである。その中で「物の怪」の重要性は、それまでの権力(天皇の呪いとしての物の怪)機構ではなく、女性の愛の物の怪、それはフロイト理論のようなヒステリーとしての「物の怪」として読む、そこが紫式部の現代的な感性なのだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
